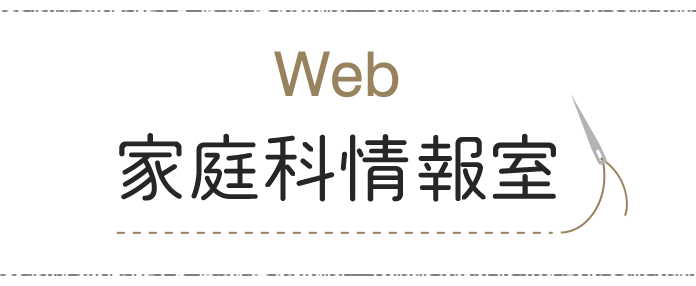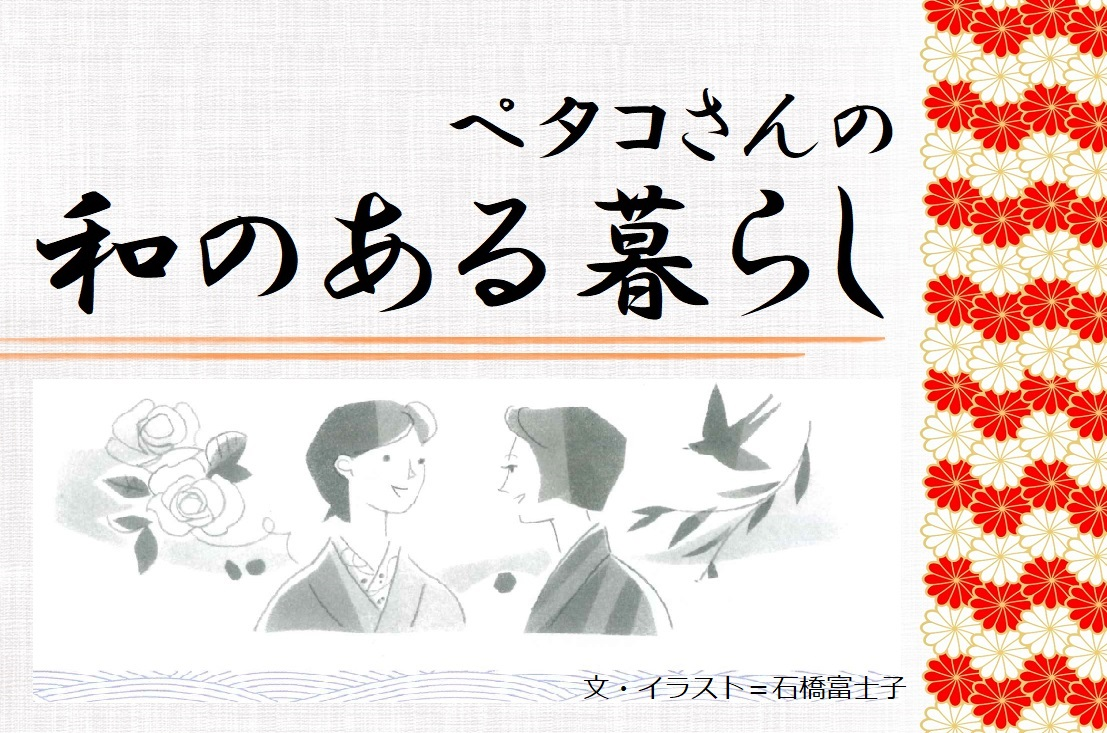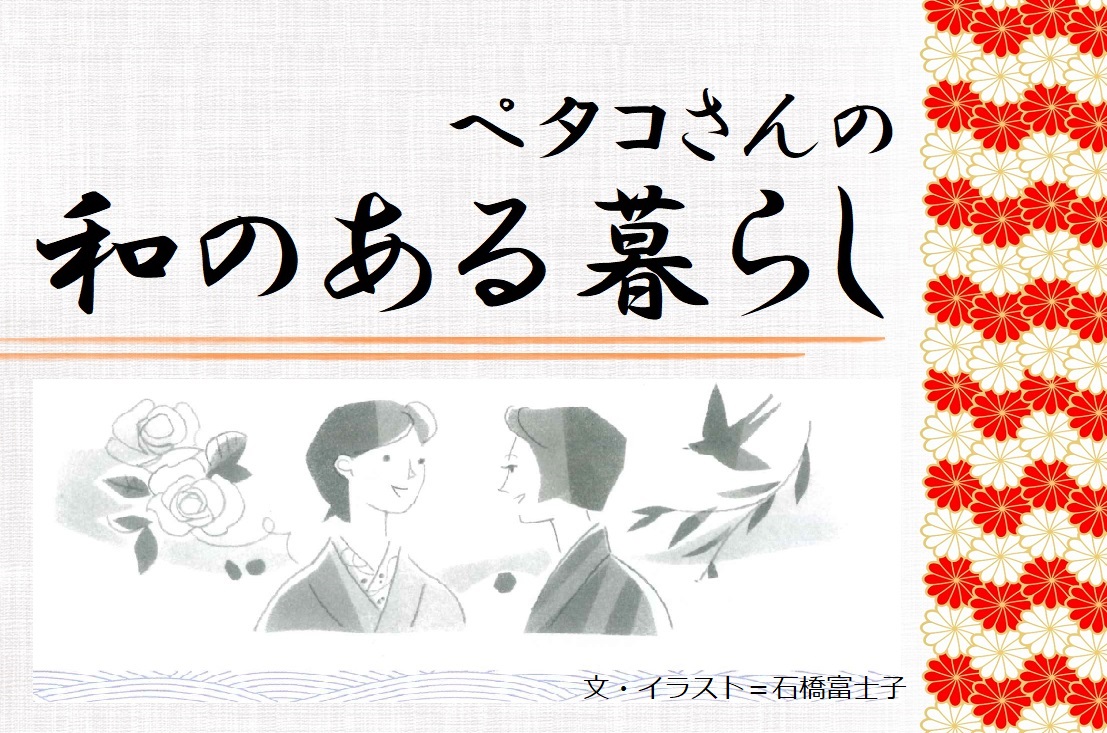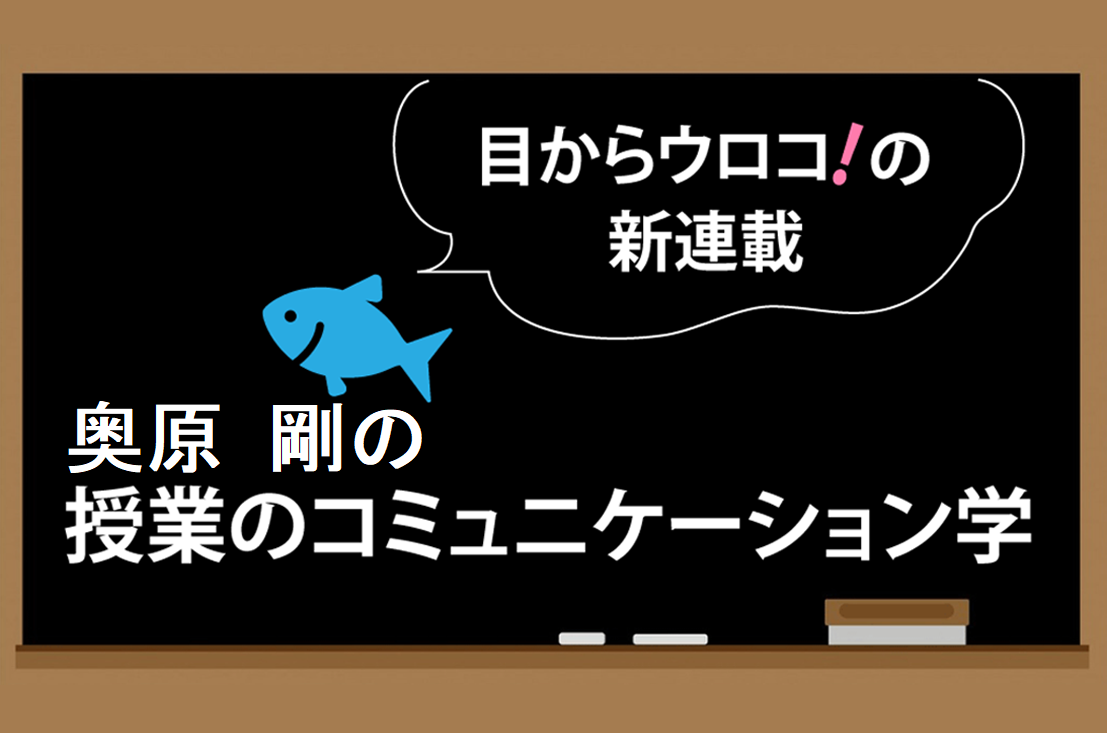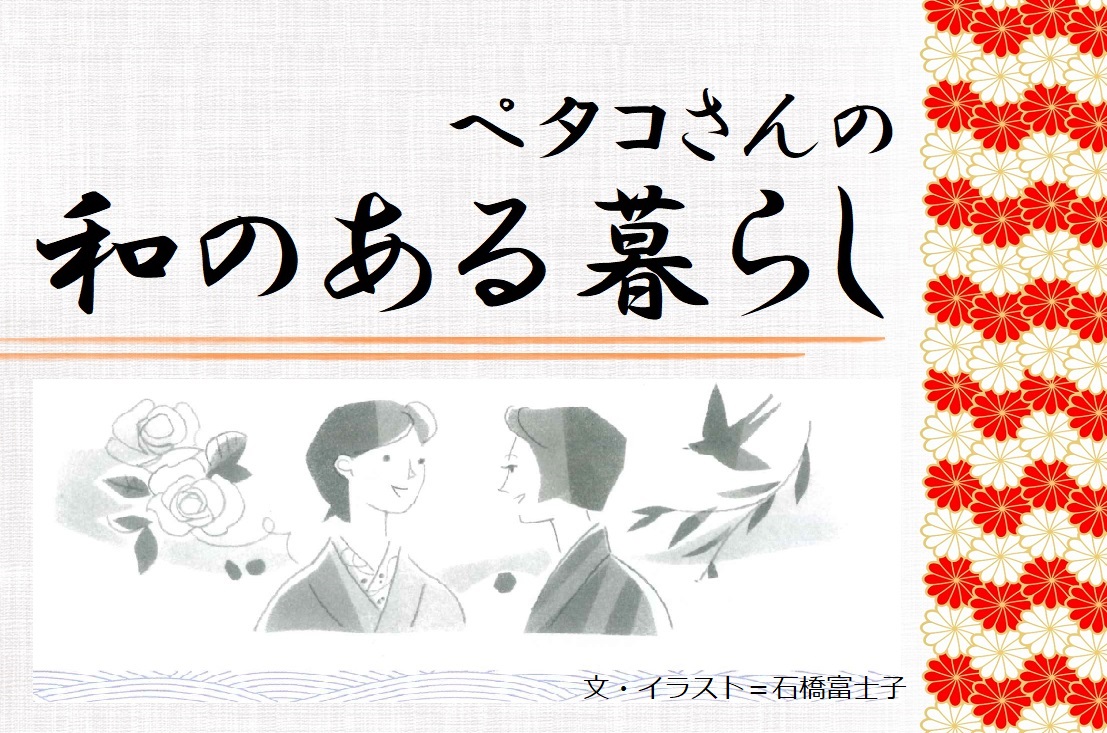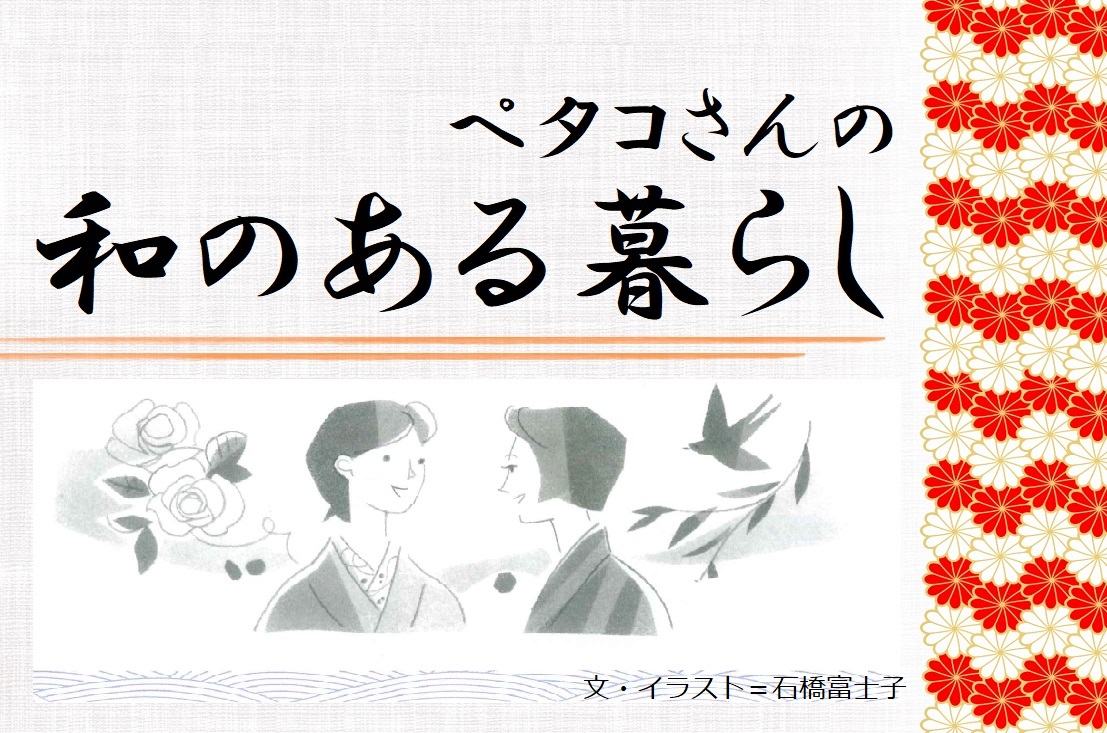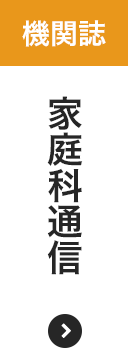ペタコさんの 和のある暮らし
[第3回]炭のある暮らし
石橋富士子
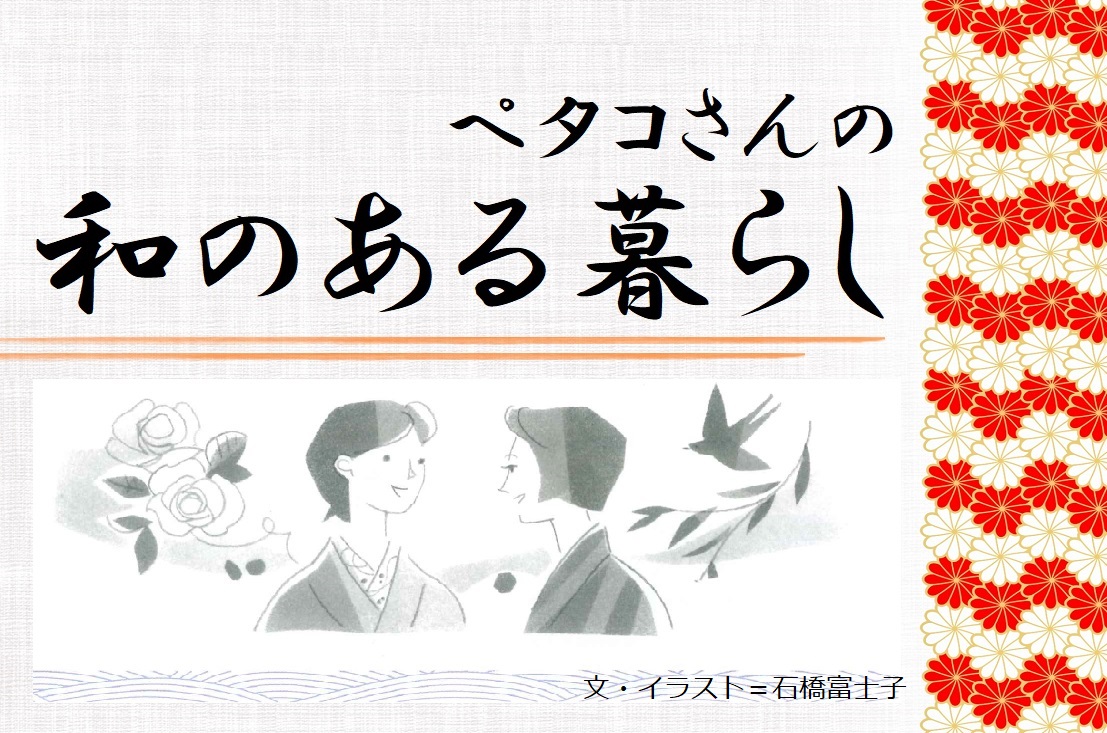
秋の夕日は釣瓶落し。夜のとばりが降りると少し肌寒い季節です。
この季節になると始まる生活習慣が炭の準備です。夕飯の支度といっしょに炭をおこします。
火消し壷から炭を幾つか火おこしにいれて弱火にかけると,10分ほどで黒い炭の端にオレンジ色に光ってきます。手あぶりの灰をならして炭を並べ,様子を見ながら火が落ち着くのを待ちます。
風の抜け道を作るように炭を配置するのがコツで,これがなかなか難しいものです。うまくいくときもあれば途中で火が消えてしまうこともあり,きれいに燃え始めるとちょっとした達成感を味わえます。
これに五徳と鉄瓶を乗せれば完成。小さな手あぶりですが赤外線の効果か,見た目以上に暖かいものです。部屋の隅に扇風機を置いて空気を循環させればエアコンなど使わなくても暖かです。
この手あぶりは暖かいだけではなく,網を置いて椎茸やめざし,油揚げを炙り,銀杏を炒るのも楽し。湯豆腐,お酒の付けなど,秋の夜長をゆっくりとすごす演出をしてくれる調理器具です。時々炭を足して配置を整える作業も魅力的です。たき火を前にすると皆無口になってしまうのに似て,小さな炭火も心穏やかにしてくれます。
食後,鉄瓶のお湯でいれるお茶はまろやか。傍らでおやきや大福を温めていただきます。
夜も更け,余ったお湯は湯たんぽに。寝るときは火消し壷に炭を入れて火の始末をします。消し炭は火がつけやすいので,これを明日火種として使います。
炭はとても経済的。秋に一包み買うと,春先まで毎日使っても,少し余るほど。余った炭は缶に入れ非常用として保存します。地震など万が一の時,ガスなどが使えなかったり家以外の避難先であっても,炭があれば湯を沸かし,煮炊きが出来,暖がとれる。これはとても心強いこと。皆さんにお勧めしたいくらいです。
気を付けなくちゃいけないことがひとつ! 炭を使うときは換気に注意。時折窓を開け,部屋の換気をお忘れなく。
(2011年10月25日発行 家庭科通信46号掲載)
著者プロフィール
石橋 富士子(いしばし ふじこ)
毎日を着物で暮らすイラストレーター。教科書,絵本などの他,和小物製作デザインやオリジナル落雁の型を使った落雁作りワークショップなどを開催。「家庭科通信」の表紙も創刊時から手がけている。著書に「知識ゼロからの着物と暮らす・入門」「知識ゼロからの着物と遊ぶ」(幻冬舎)。着物をもっと楽しむための刺繍和小物をつくる富士商会を2015年設立。https://fujipeta.com/
一覧に戻る