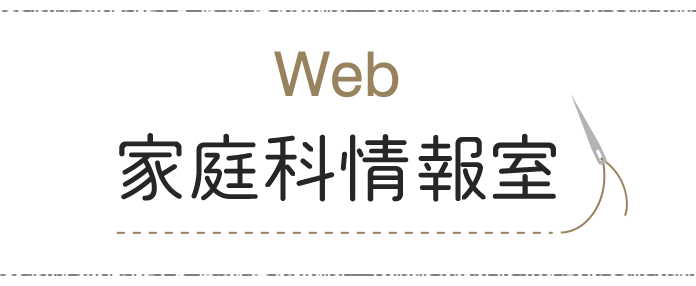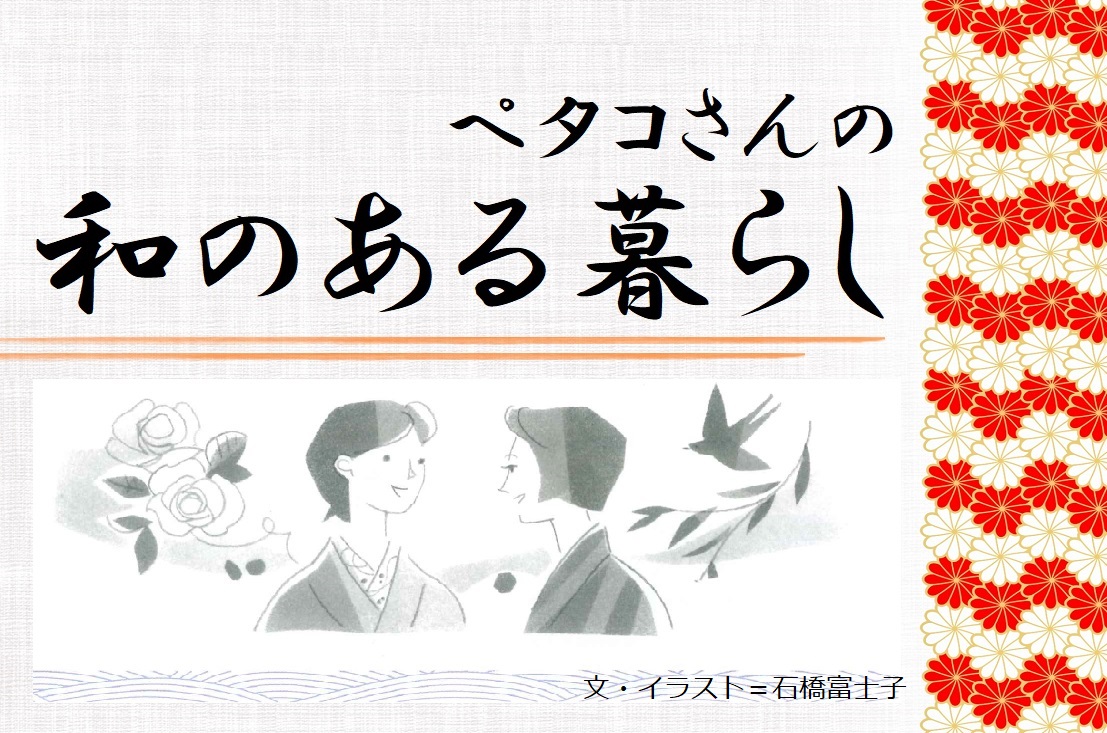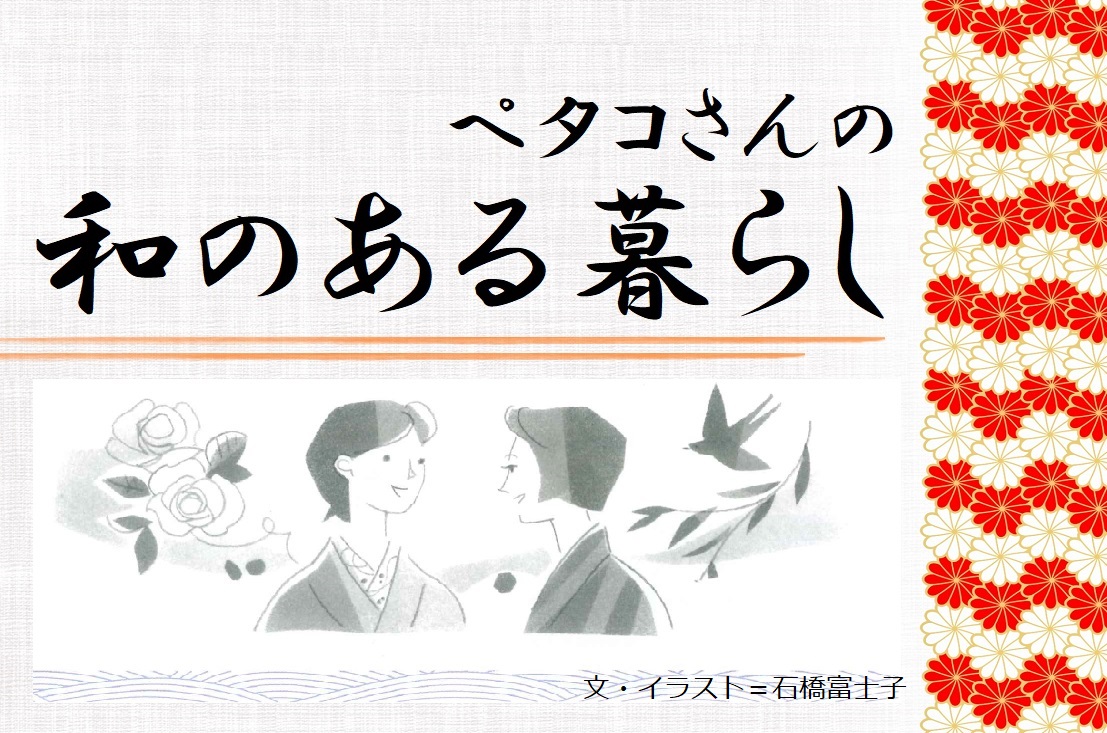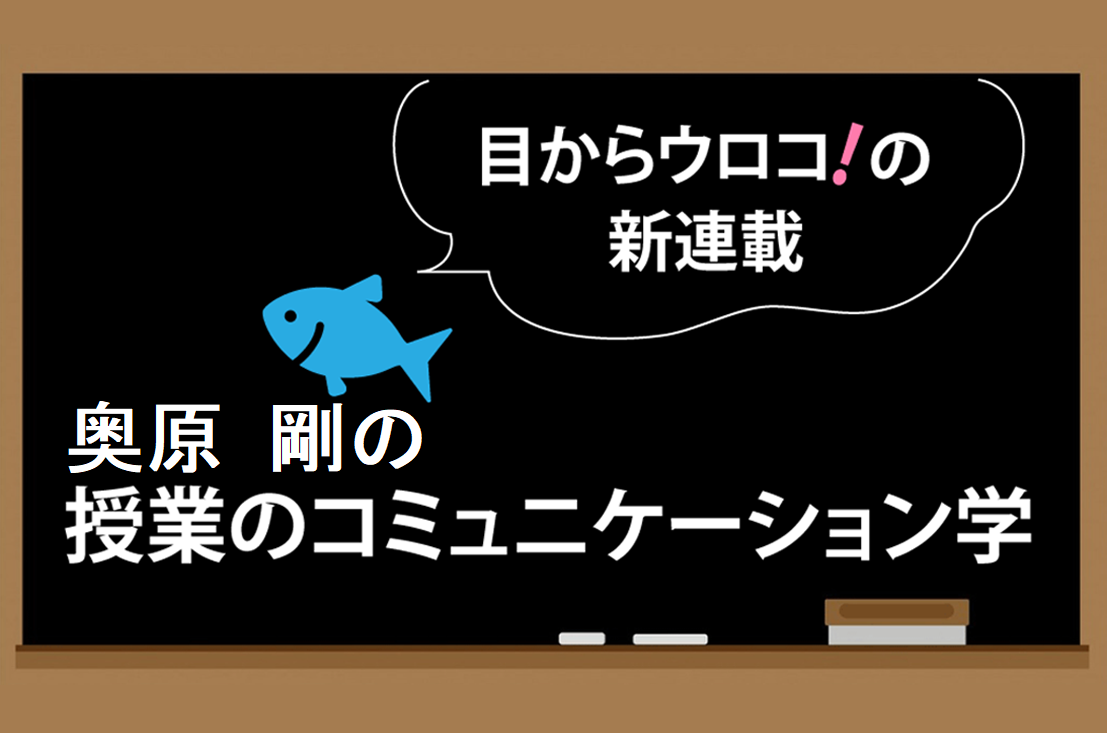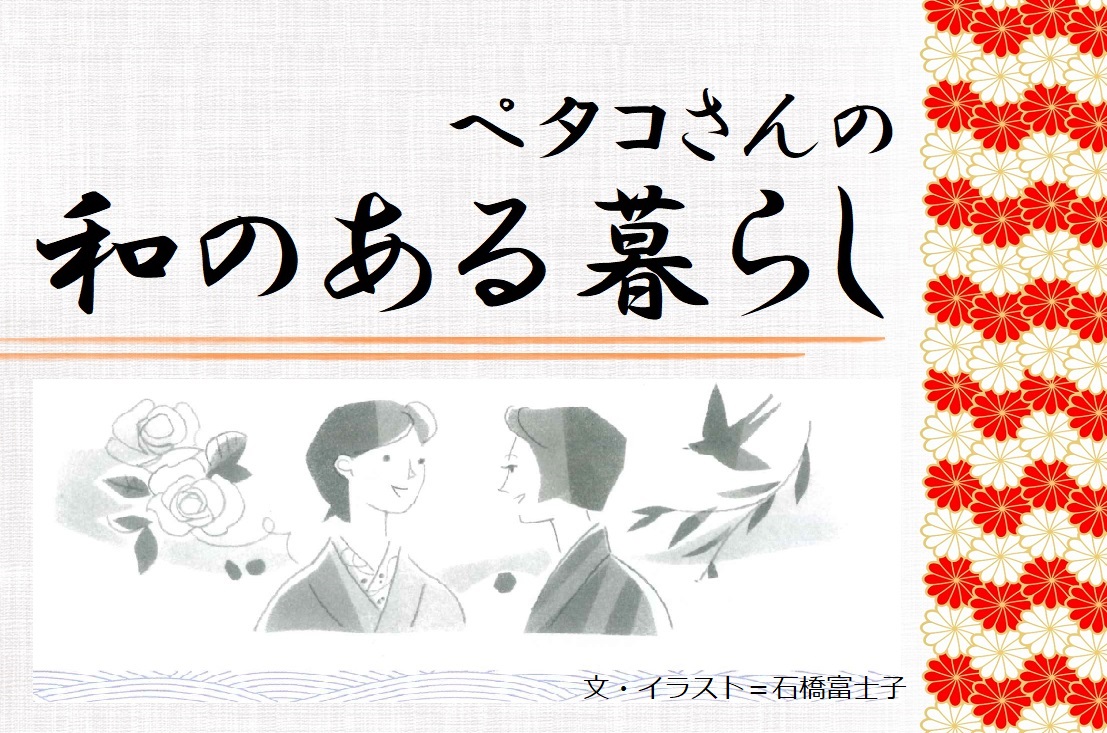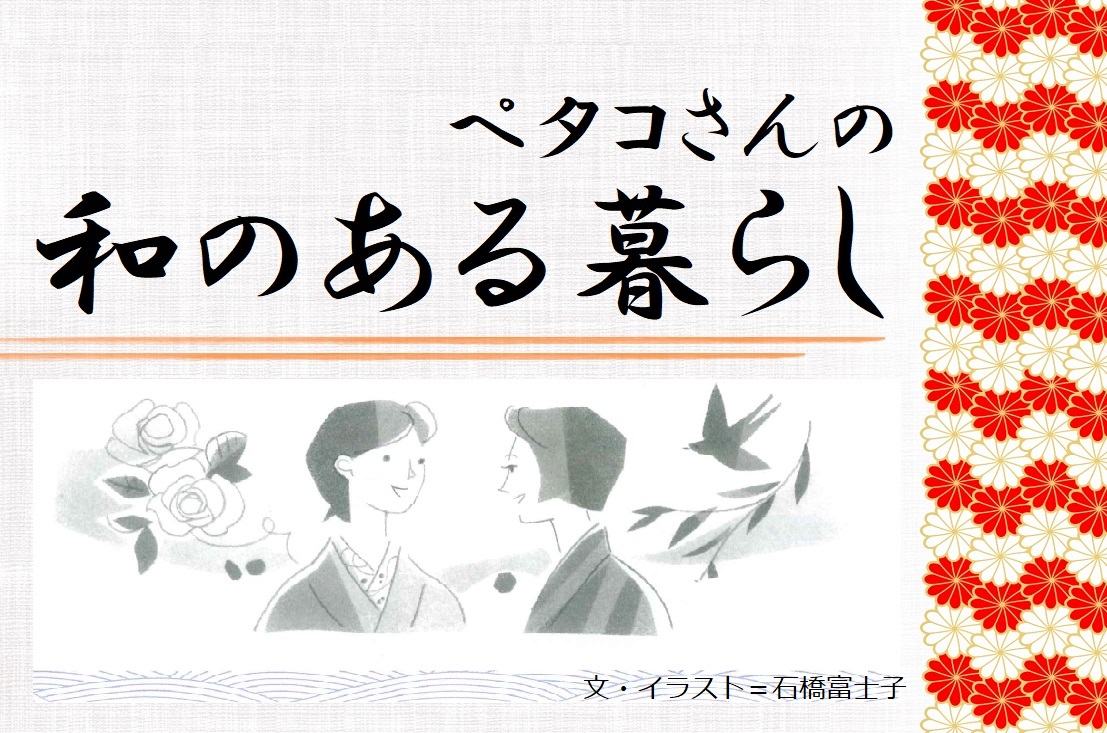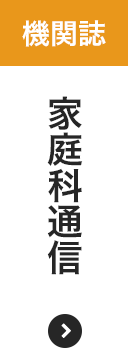ペタコさんの 和のある暮らし
[第4回]手づくりの縁起物
石橋富士子
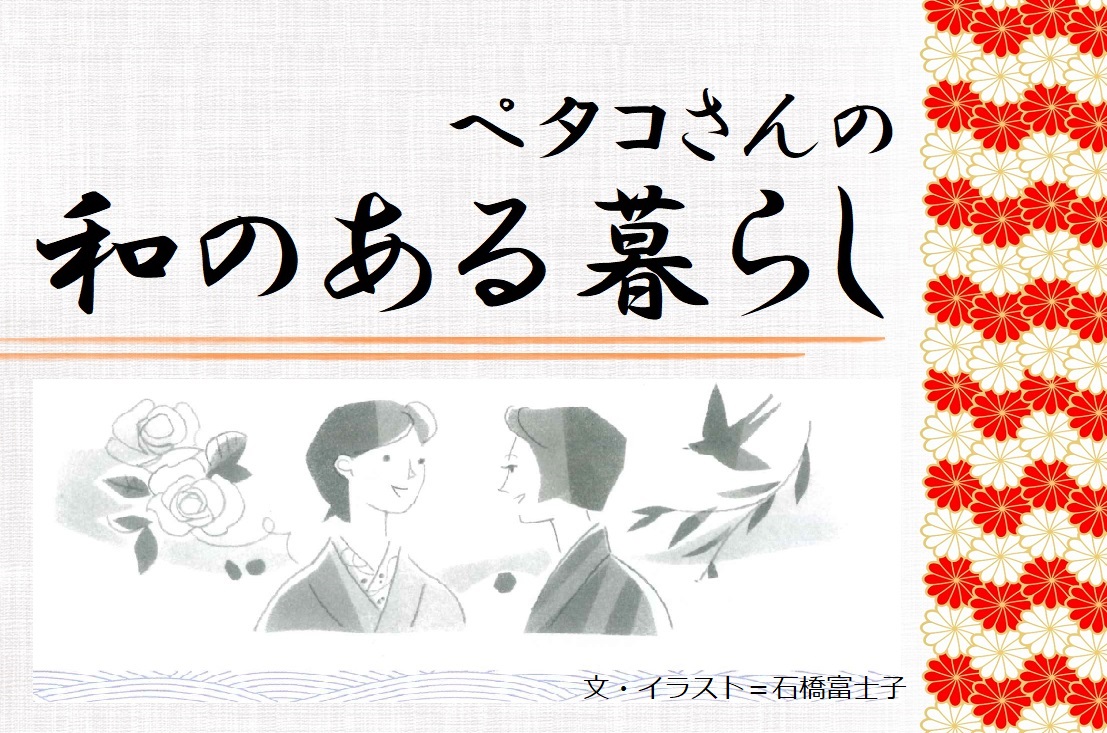
東京は,さまざまなシーンで江戸時代が息づいているのを感じます。どんなに街並みが変わっても,空が狭くなっても,神社やお寺や鎮守の森があり,季節の行事がおこなわれています。
たとえば雑司ヶ谷の鬼子母神,冨士神社の冨士講,大鳥神社の酉の市,穴八幡の一陽来復など。お参りのときの楽しみは,手づくりの素朴なお供え物やお土産物です。
山開きの日に冨士神社に行くと,藁のヘビが売られています。赤い口を開いたヘビは,厄よけ水あたり,火防の縁起物で台所や蛇口に飾ります。
大鳥神社の酉の市で入手できる熊手ですが,私が好きなのは一番小さな竹と稲穂でつくられたもの。簪として日本髪に飾りたくなるような,シンプルで美しいアート作品です。
豊島区雑司ヶ谷の鬼子母神のお会式大祭に売られる「すすきみみずく」はススキを束ねてつくってあります。ふっくらとした形が美しく,私も見よう見まね,子どものころ近くの原っぱのススキを刈ってつくったことがありました。ミミズクを一つつくるのには,ススキが20本ほど必要でした。
このミミズクには伝説があります。200年ほど前,病弱な母の看病をしながら暮らしている貧乏な娘が,薬も買うことができず,毎日鬼子母神にお祈りしていました。ある日,娘の夢枕に蝶の姿の鬼子母神があらわれ,「すすきみみずく」のつくりかたを教え,これを売るようにと告げます。娘はさっそく「すすきみみずく」をつくり,門前で売ると飛ぶように売れ,薬も買え,しだいに母の病気もよくなったといいます。
先日新聞にこんな記事が載っていました。
ミミズクをつくる職人の方が高齢になり,つくるのをやめたとのこと。後継者もなく,それではミミズクのつくり手がなくなってしまうと心配した地元の人たちが,自分たちで伝承していこうと活動を始めたそうです。
各地で同じような問題が起こっているのではないかと心配します。なんとか絶やさず地元の有志で伝え続けてほしいと願っています。
(2010年10月25日発行 家庭科通信43号掲載)
著者プロフィール
石橋 富士子(いしばし ふじこ)
毎日を着物で暮らすイラストレーター。教科書,絵本などの他,和小物製作デザインやオリジナル落雁の型を使った落雁作りワークショップなどを開催。「家庭科通信」の表紙も創刊時から手がけている。著書に「知識ゼロからの着物と暮らす・入門」「知識ゼロからの着物と遊ぶ」(幻冬舎)。着物をもっと楽しむための刺繍和小物をつくる富士商会を2015年設立。https://fujipeta.com/
一覧に戻る