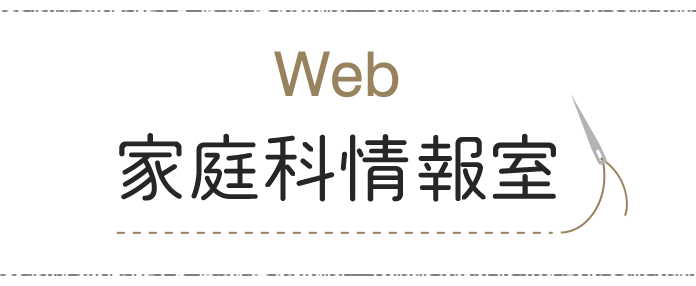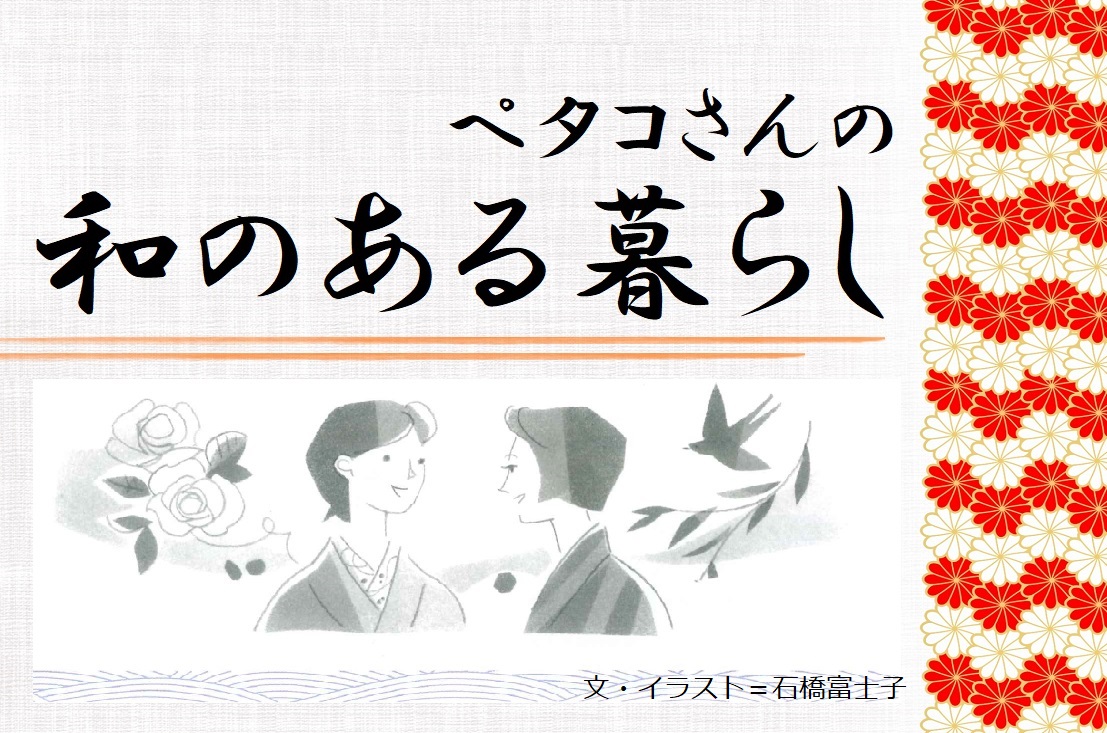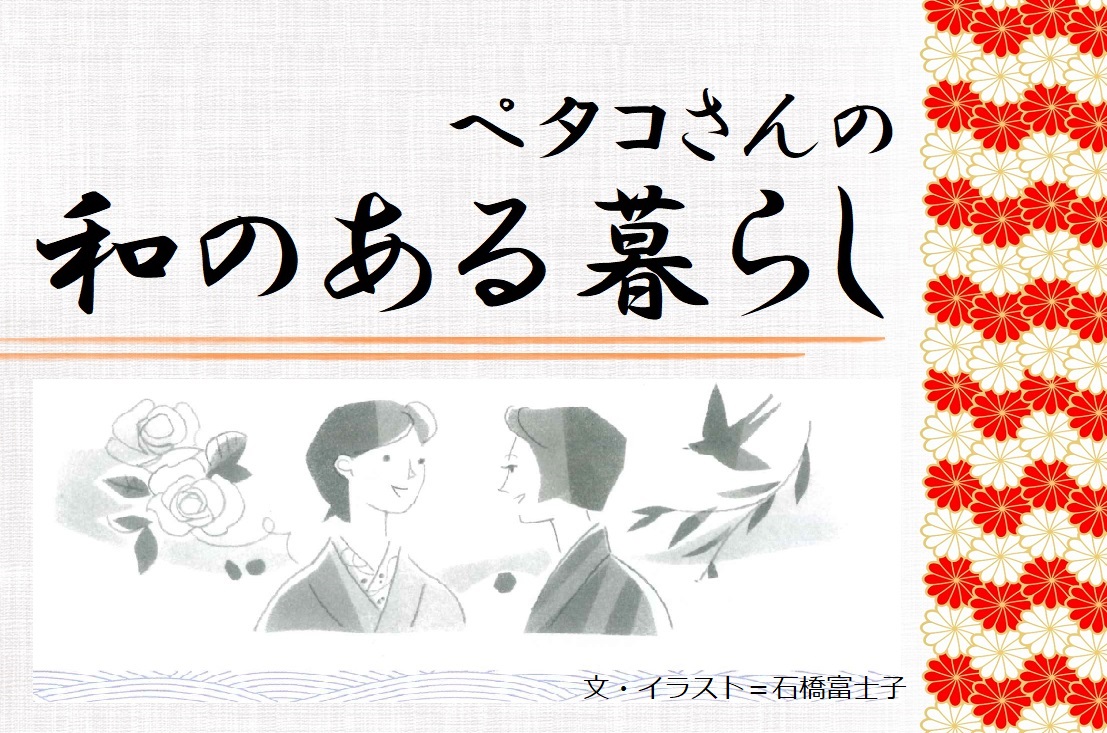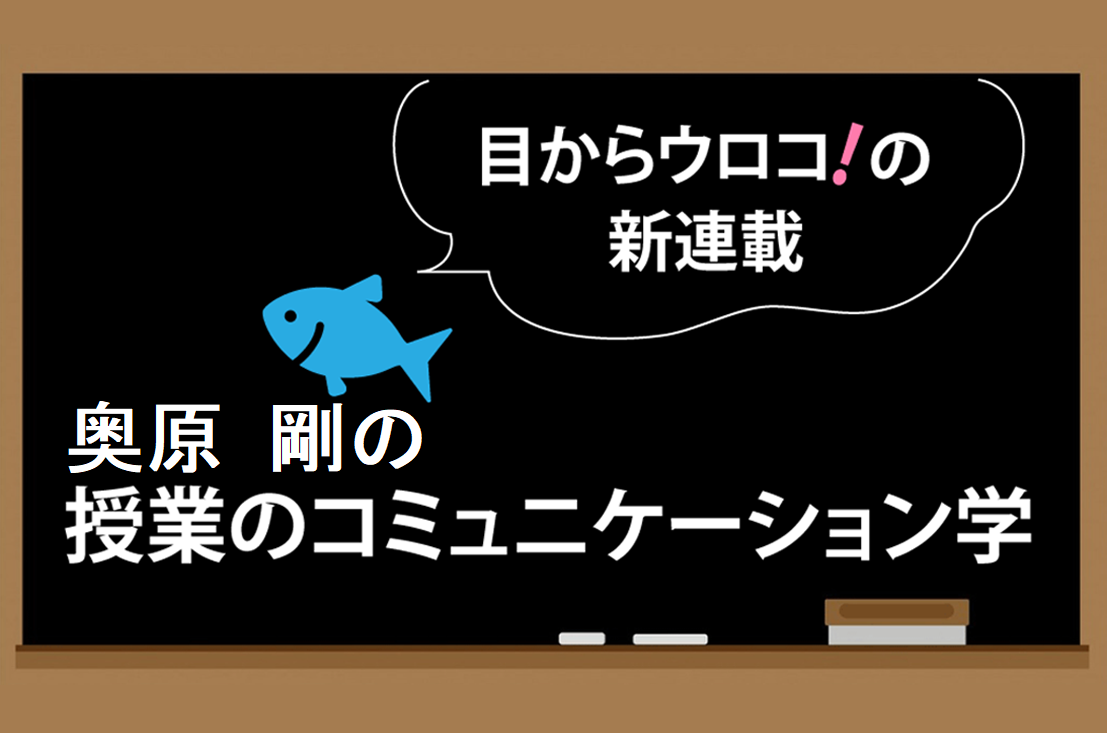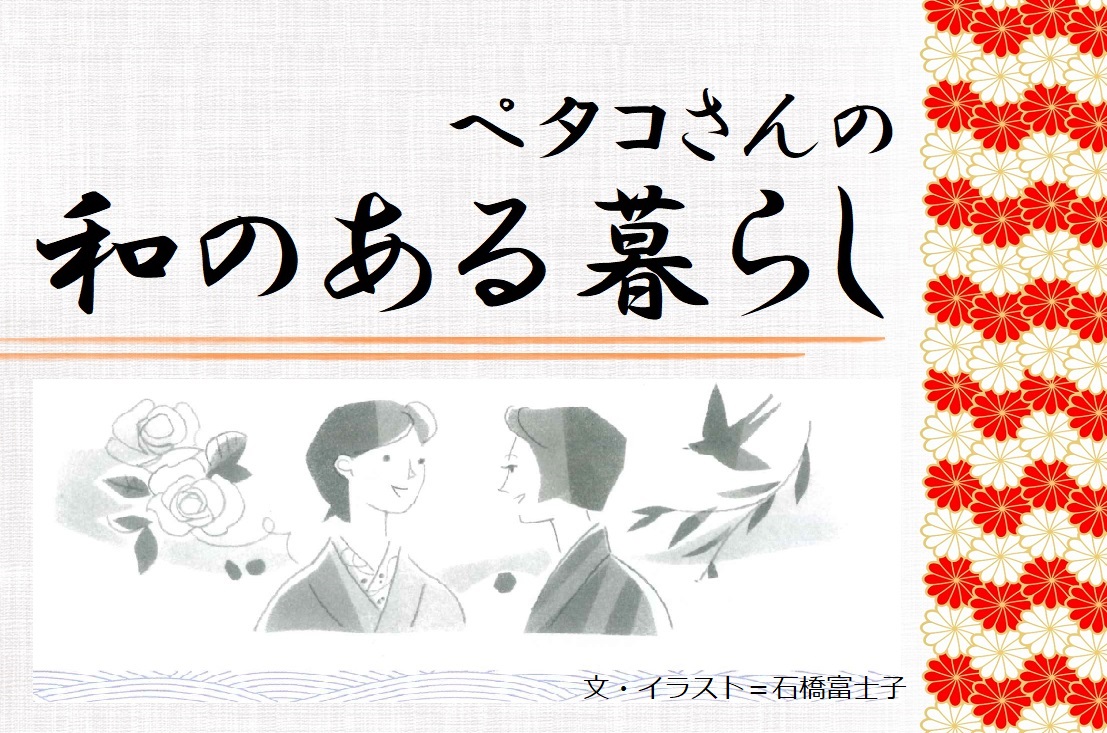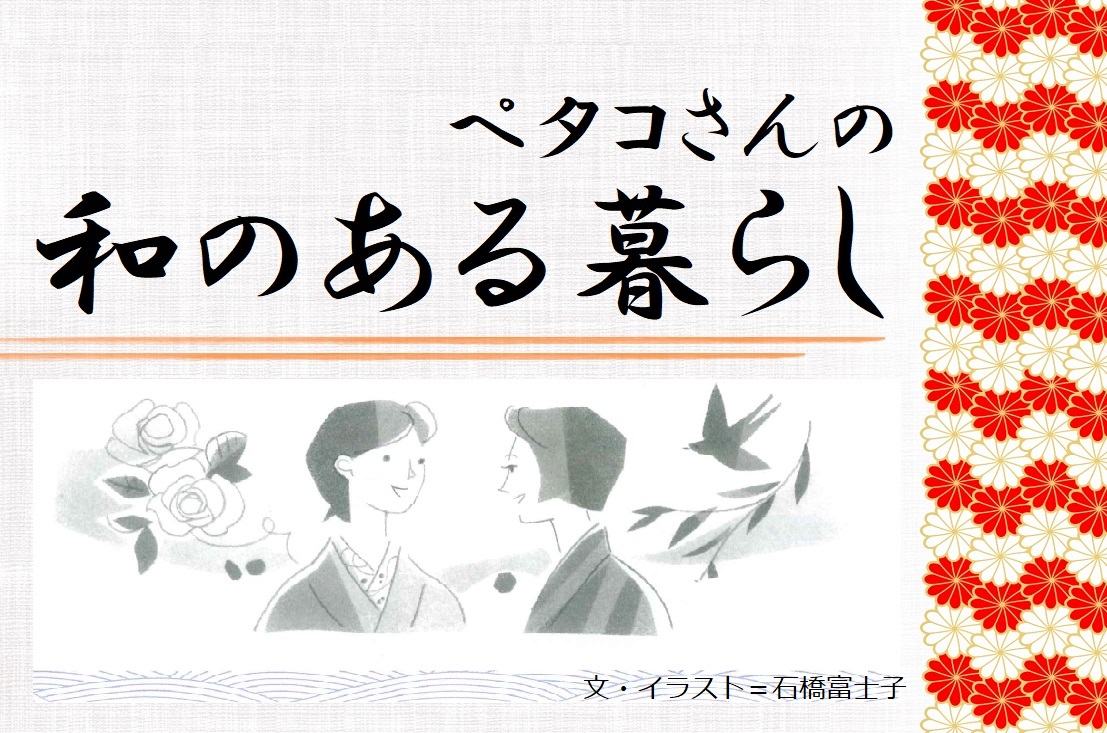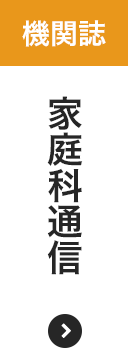ペタコさんの 和のある暮らし
[第11回]育て,食べる楽しみ
石橋富士子
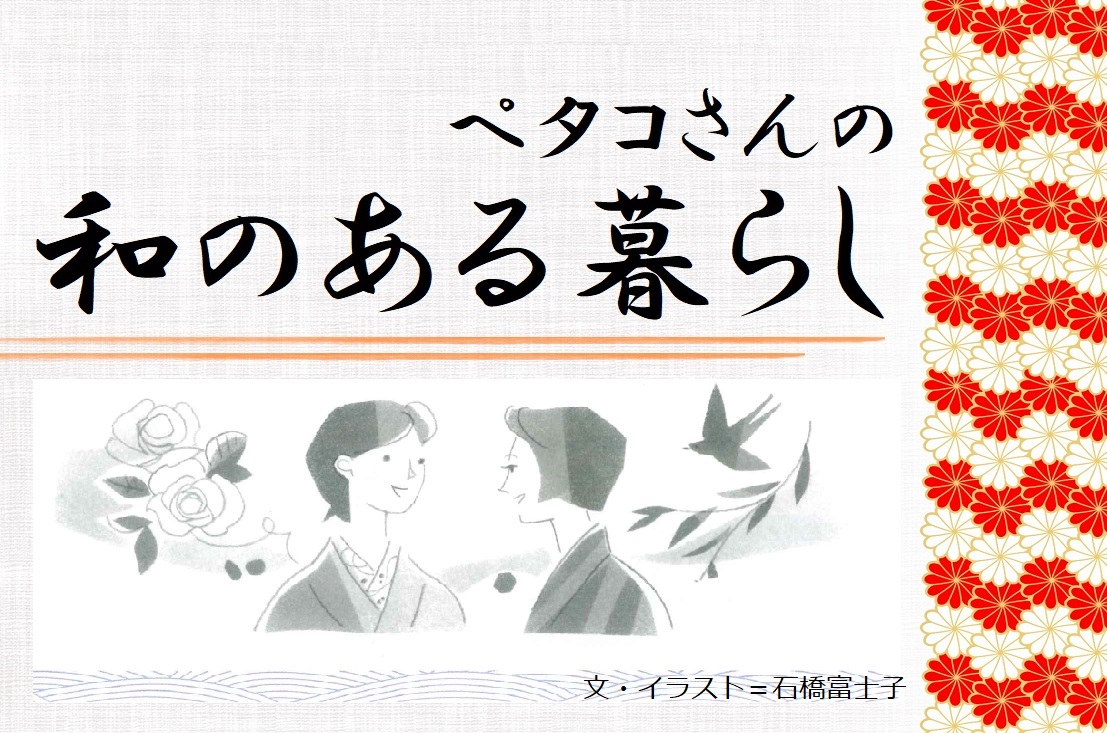
家庭菜園がブームです。花の寄せ植え「コンテナガーデン」の流行の後,今は「野菜栽培」が注目を集めています。
我が家でも小さな庭と,コンテナなども動員し,所狭しと野菜と花が同居しています。
梅,無花果,山椒,葡萄,サルナシ,ラズベリー,ブラックベリーなどの果樹,そして野菜はサラダ用の各種葉物,トマトやオクラ,茗荷,インゲンやニンニクまで,思いつくままにごちゃごちゃと育てています。
2月,寒い寒いとばかり思っている頃,枯れたような葡萄の枝先がぽっちりと膨らむと,春の予感を感じ,つややかな山椒の新芽は,寒さですっかり縮まった背筋をシャンとさせてくれます。
山椒や茗荷,大葉などはちょっと添えるとお料理がぐっと引き立つ日本のハーブ。使うときは少量なので,コンテナや路地植えなどにしておくと新鮮なものを使えてオススメです。
その代わり手をかけてあげないといけません。
夏場は毎日セッセと水やり。ちょっとでも怠ると,とたんにしっぺ返しがきますので,枯らさないように朝夕水を運びます。
野菜の花後,サヤや実が段々大きくなり色づいて,やがて収穫となります。野菜を育てる一番の醍醐味は,なんといってもこの瞬間です。
採れるものは野菜の気分次第,カゴ一杯の収穫物は思わず写真を撮って,ブログにアップしたくなるような達成感を与えてくれます。
かつて,江戸の人々は園芸や野菜作りにいそしんでいたようです。苗売りの行商が行き交い,長屋の脇や入り口横,垣根などを利用して野菜などを育てていました。
空き地などで見かけることの多いドクダミは,利尿作用,動脈硬化の予防,湿疹,かぶれによいとされる薬草です。単に繁殖力が強いだけではなく,積極的に増やしていたのだと聞きました。
歌舞伎の「夏祭り浪花鏡」の舞台には井戸端の垣根に実る南瓜の実が,夏の暑さを見事に演出し,とても印象的でした。
今年は南瓜を育ててみようかな。
(2012年5月25日発行 家庭科通信48号掲載)
著者プロフィール
石橋 富士子(いしばし ふじこ)
毎日を着物で暮らすイラストレーター。教科書,絵本などの他,和小物製作デザインやオリジナル落雁の型を使った落雁作りワークショップなどを開催。「家庭科通信」の表紙も創刊時から手がけている。著書に「知識ゼロからの着物と暮らす・入門」「知識ゼロからの着物と遊ぶ」(幻冬舎)。着物をもっと楽しむための刺繍和小物をつくる富士商会を2015年設立。https://fujipeta.com/
一覧に戻る