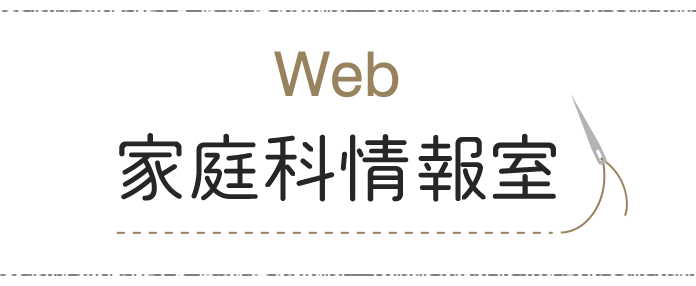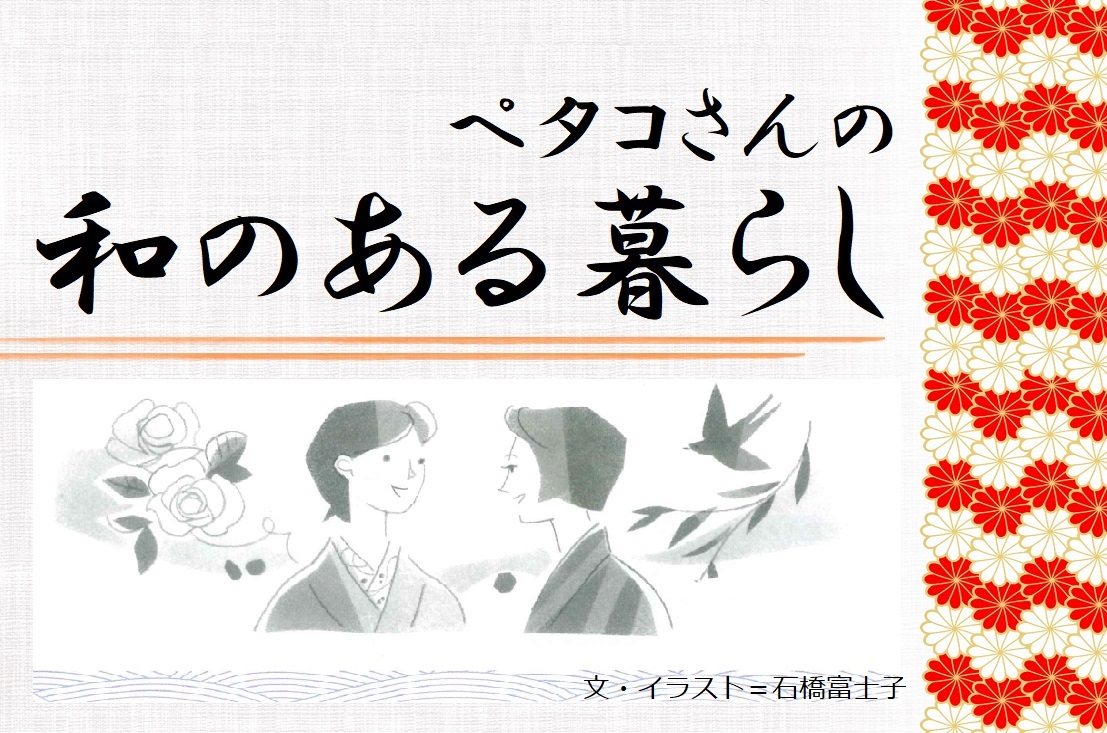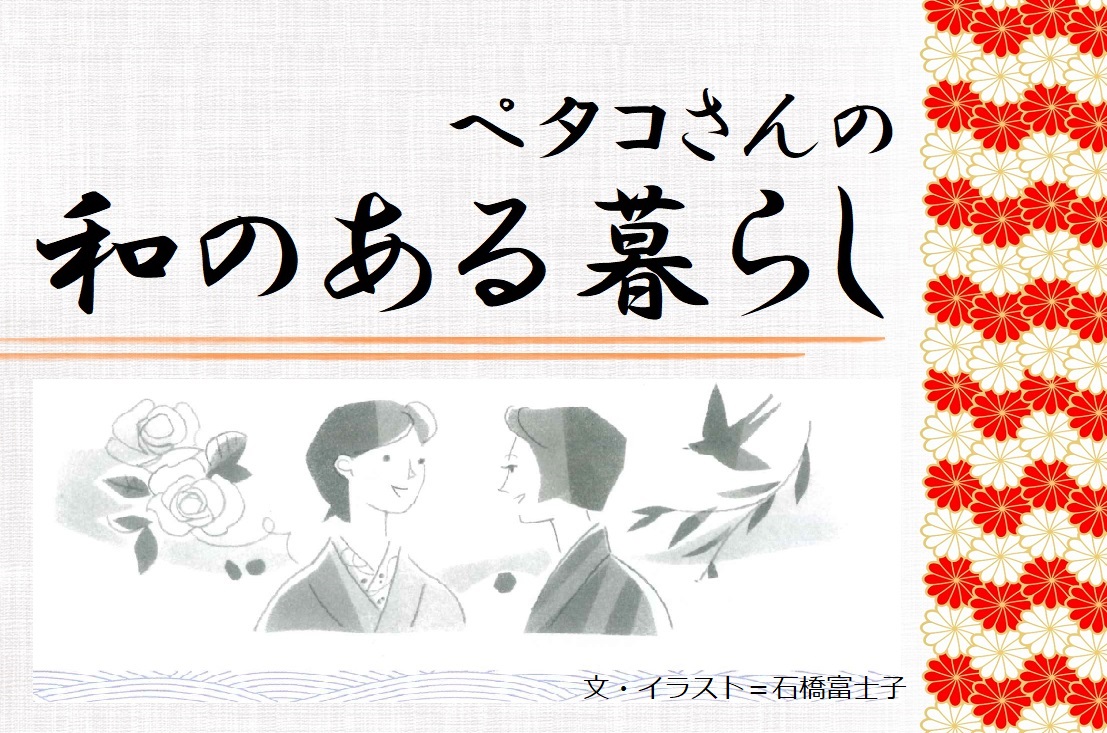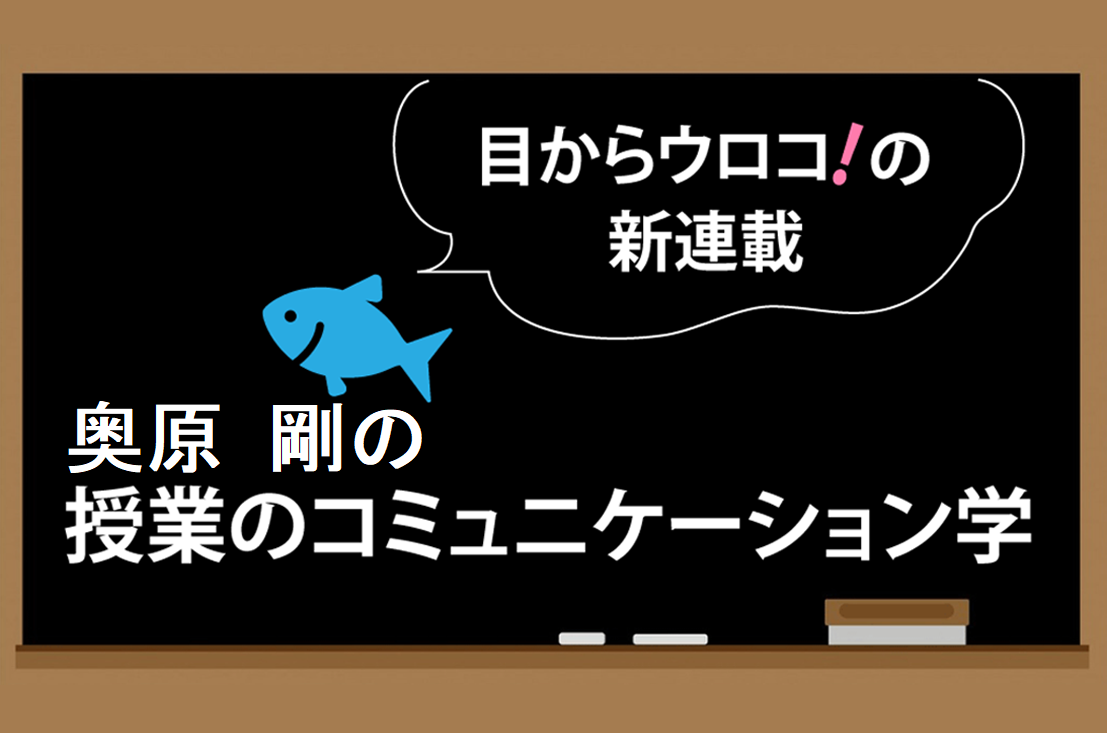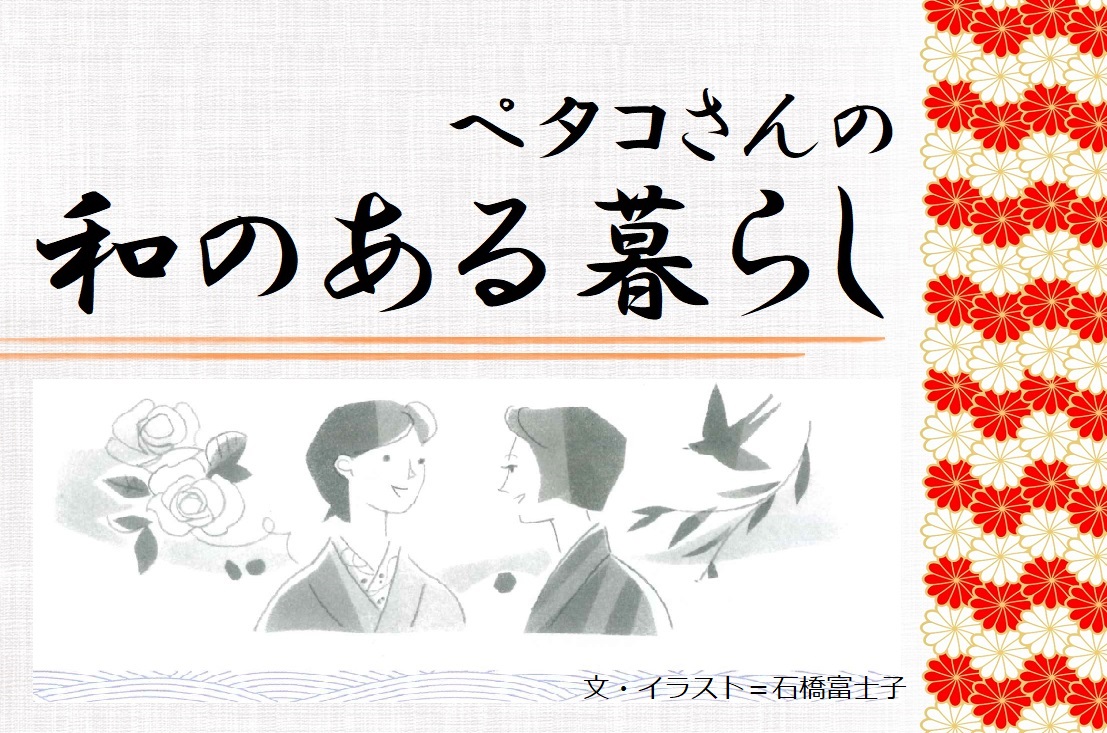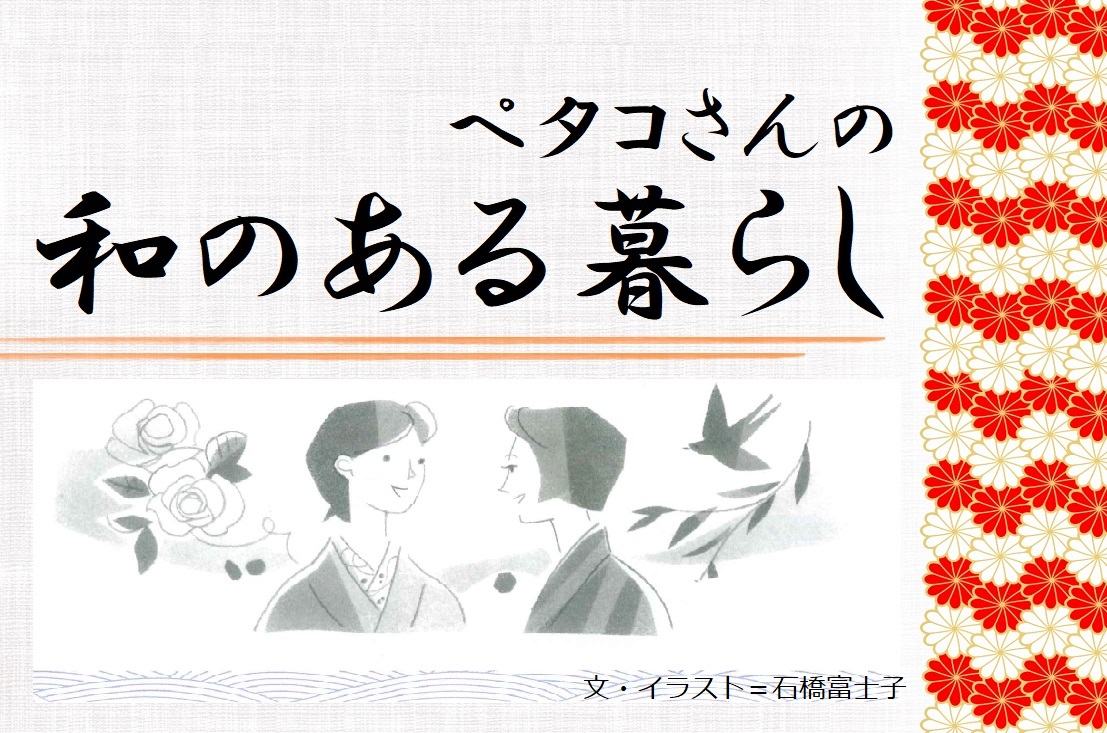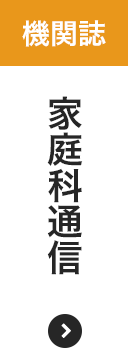ペタコさんの 和のある暮らし
[第16回]着物と気候
石橋富士子
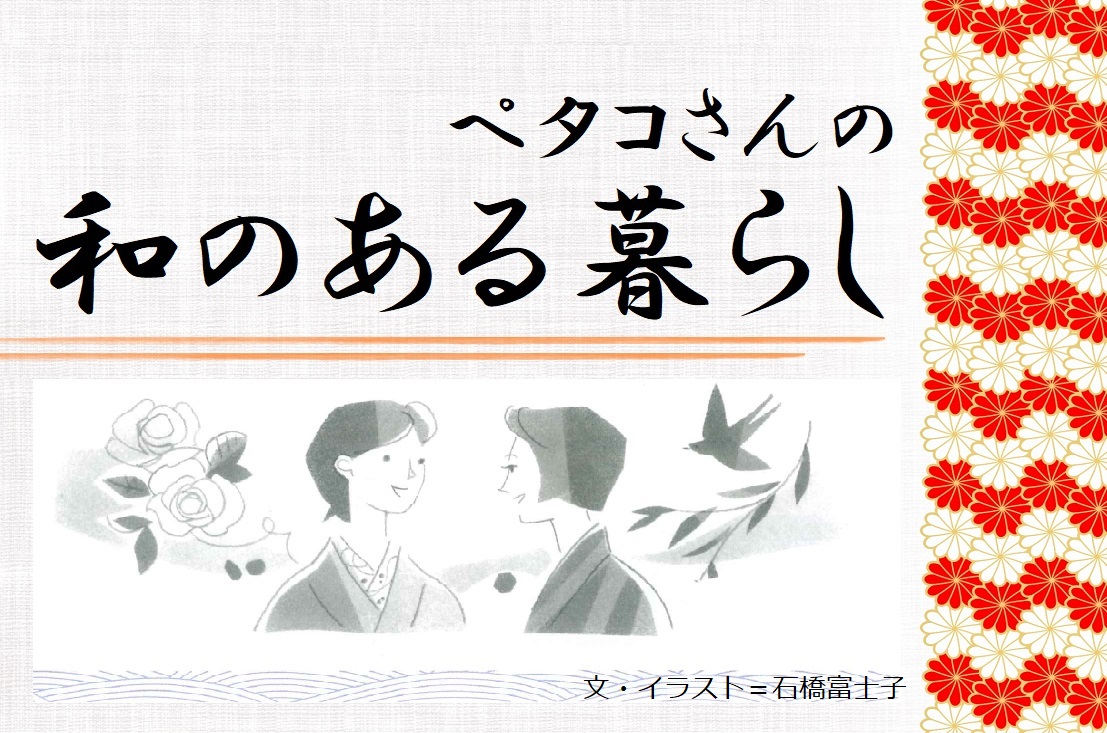
10月は衣替えの季節です。平安時代に始まったといわれる衣替えの行事は,6月と10月の年二回,来たるべき季節の衣類を出し,それまでのものは風を通し,点検し,ほころびや汚れがあれば繕い,きれいに整えて衣装箱に収めます。
私が子どもの頃には,暑さ寒さの到来は季節とほぼ合致して,すんなりと衣替えを完了でき,季節を移せたように思いますが,近年は温暖化のせいか季節外れの異常気象ともいうべき気候に出会うこともあって,いったんしまった着物をひっぱり出したり,と悩ましいことが多くなりました。
そういったことに出会うたびに古くからの習慣と,このところの自然とがずれてしまっているように感じます。
習慣と気候との不一致,ずれは,毎日を着物で暮らす私の生活に,少なからず不自由を感じさせることになります。
たとえば夏の暑さ。今までにはなかったような高い気温と,寒さを覚えるほど冷房が効いた室内の温度差,扇子とショールが欠かせません。街を歩けば階段の昇り降りで汗がふき出てきますし,突然の雷雨も気がかり。急な雨が心配で,薄色の着物を選ぶ機会がすっかり減ってきました。
また仕事の打ち合わせなどで洋装の方とお会いすることも多いので,着物を着ている自分だけが浮いて,先様に違和感を感じさせてしまわぬような工夫も必要になるなど,ささやかながら気を遣います。
いろいろな気苦労はありますが,それでも着物を着ていてよかった,と思うことは両手にあまるほどたくさん。
季節を映す多彩な柄や色に出会うたびに,日本の自然の豊富な彩りを感じ,夏のさらりとした麻の肌触りや冬のざっくりした織物の感触に嬉しさを覚えます。そしてそう感じるたびに,なんと着物での暮らしは自分を豊かにしてくれているのだろう,と思うのです。
気候の変化への対応や必要となる工夫は,ときに大変ですが,だからこそそんな変化もさらりと受け流し,これからも着物で暮らし続けていくために,これからの暮らしと自分の年齢に合わせた着物とのつきあいかたをつねに再点検する必要があると感じる今日この頃です。
(2016年10月25日発行 家庭科通信59号掲載)
著者プロフィール
石橋 富士子(いしばし ふじこ)
毎日を着物で暮らすイラストレーター。教科書,絵本などの他,和小物製作デザインやオリジナル落雁の型を使った落雁作りワークショップなどを開催。「家庭科通信」の表紙も創刊時から手がけている。著書に「知識ゼロからの着物と暮らす・入門」「知識ゼロからの着物と遊ぶ」(幻冬舎)。着物をもっと楽しむための刺繍和小物をつくる富士商会を2015年設立。https://fujipeta.com/
一覧に戻る