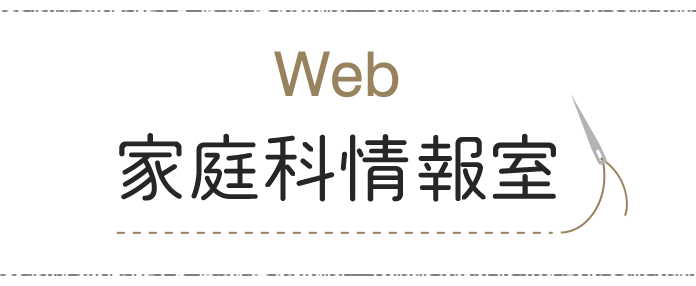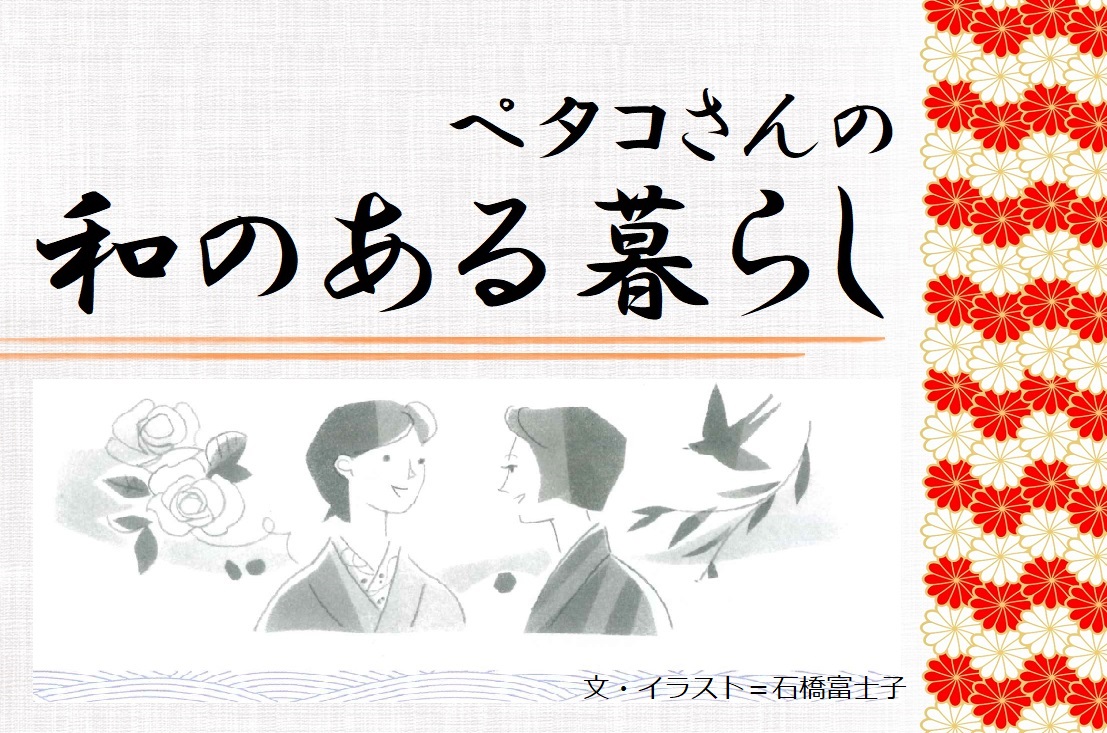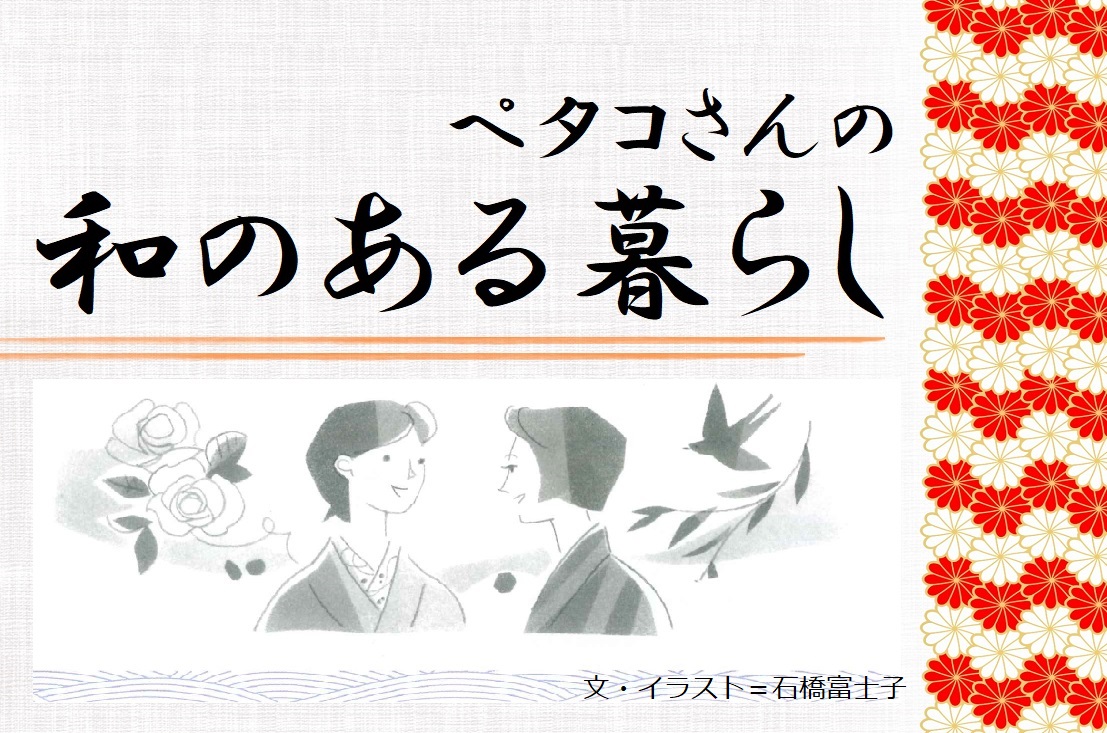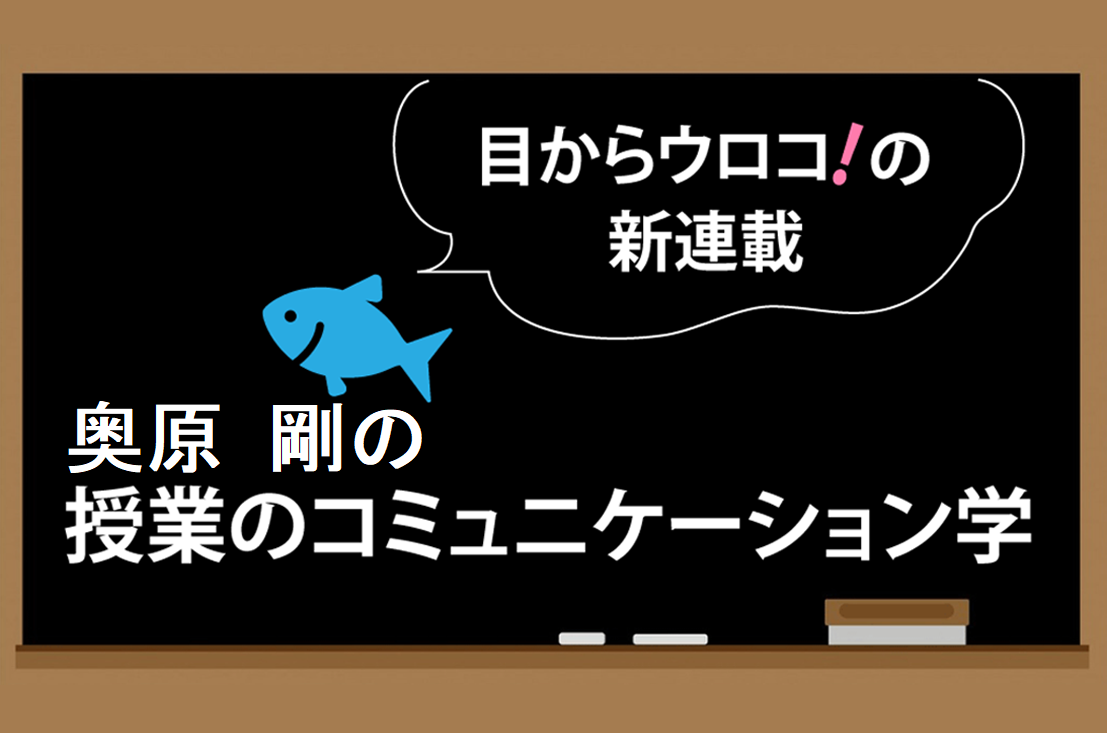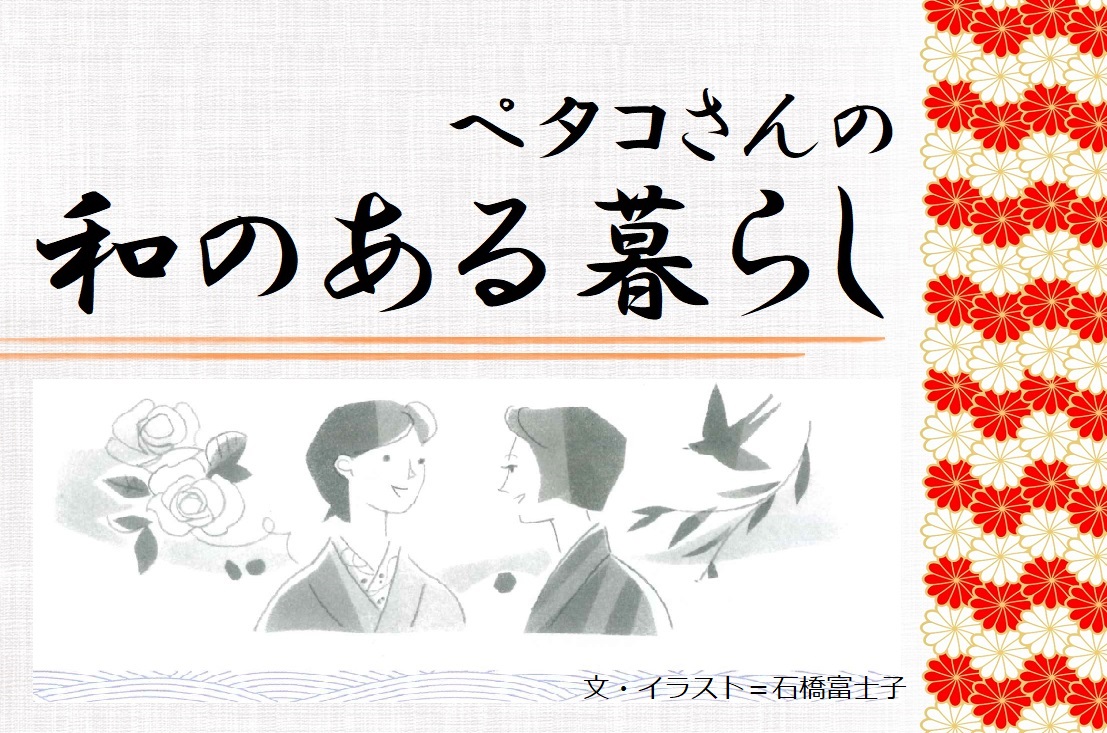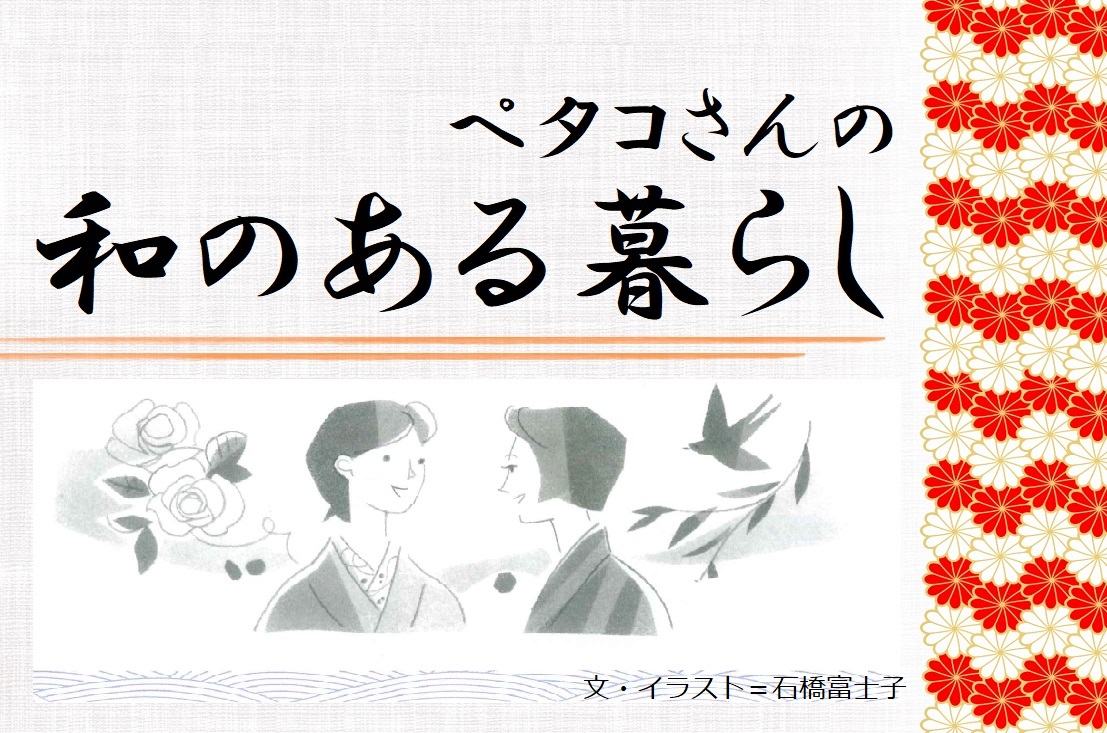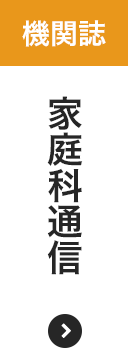ペタコさんの 和のある暮らし
[第18回]明かりを楽しむ
石橋富士子
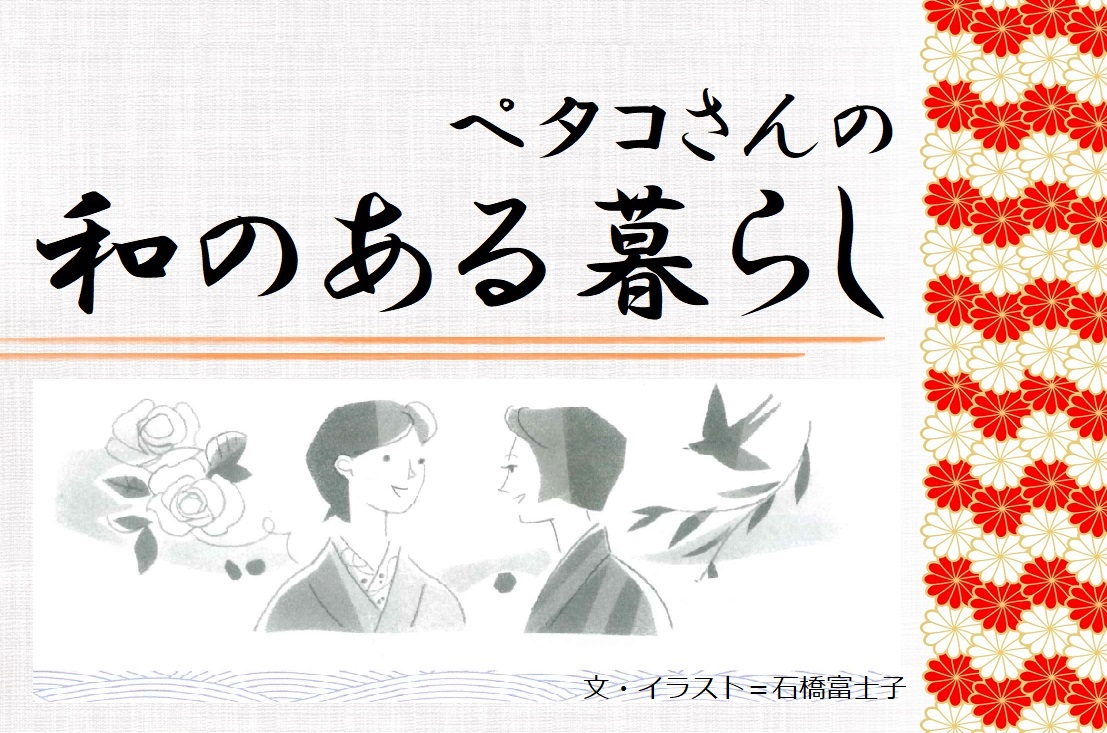
静かな夜を楽しみたい季節。上からの照明は消して,スタンド,ろうそくや間接照明がおすすめです。
照明器具の光度や角度,ライトの色を変えると,リビングや仕事場がレストランやバー,カフェのように柔らかく,リラックスできる雰囲気に変わります。
明かりを置く位置を低くして,人に直接ではなく壁やテーブルなどに光を当てると部屋に奥行きが生まれます。
観葉植物の鉢にクリップで取り付け,ライトを下から天井に向けて植物の葉をライトアップするのも素敵です。
江戸時代,明かりはろうそくや植物油など高価な貴重品でしたから,一般庶民はまだ明るさの残る夕方に食事や風呂,用事をすませ,さっさと寝てしまったようです。おかみさんが仕立てなど内職する時はあんどんをともし,手元を明るくするため片側の窓を引き上げて針仕事。そんな浮世絵を見たことがあります。
植物油が買えない家では安価な魚の油をともしますが,とても生臭かったようです。ここから猫が夜中にあんどんの油をなめる,という化け猫話が生まれたのかもしれませんね。
ろうそくの明かりは素敵ですが,小さくても火,油断はできません。目を離すのが心配です。
電池でともるろうそくが便利です。ちゃんと時折炎がゆらいでいるように見えます。
火を使わないのでいろいろ面白い工夫が出来ます。切り絵をシェードに貼ったり,レースのコースターをかぶせても素敵です。
寒い季節,忘れてはならないもう一つのローカルな明かりは手あぶりです。炭の赤い炎の色は見ているだけで心が温かくなってきます。手あぶりは暖房と煮炊きを兼ねた明かり,夕方熾した炭火を深夜寝るまで上手に保ち続けるのもちょっとしたゲームみたいで楽しい仕事です。
古い木造の我が家では家の中に暖かいところと寒いところ,ほの暗いところと少し明るいところがありますが,照明も暖房も部屋全体均一ではない方が,豊かな気持ちになれるような気がします。
(2013年10月25日発行 家庭科通信52号掲載)
著者プロフィール
石橋 富士子(いしばし ふじこ)
毎日を着物で暮らすイラストレーター。教科書,絵本などの他,和小物製作デザインやオリジナル落雁の型を使った落雁作りワークショップなどを開催。「家庭科通信」の表紙も創刊時から手がけている。著書に「知識ゼロからの着物と暮らす・入門」「知識ゼロからの着物と遊ぶ」(幻冬舎)。着物をもっと楽しむための刺繍和小物をつくる富士商会を2015年設立。https://fujipeta.com/
一覧に戻る