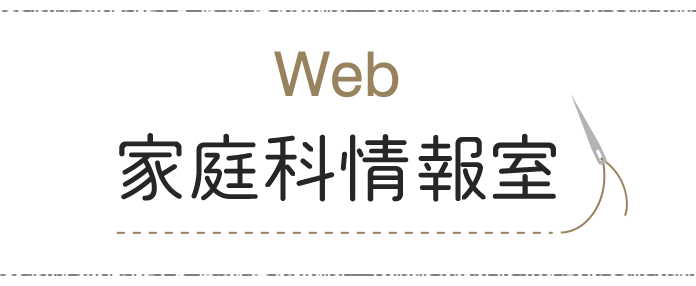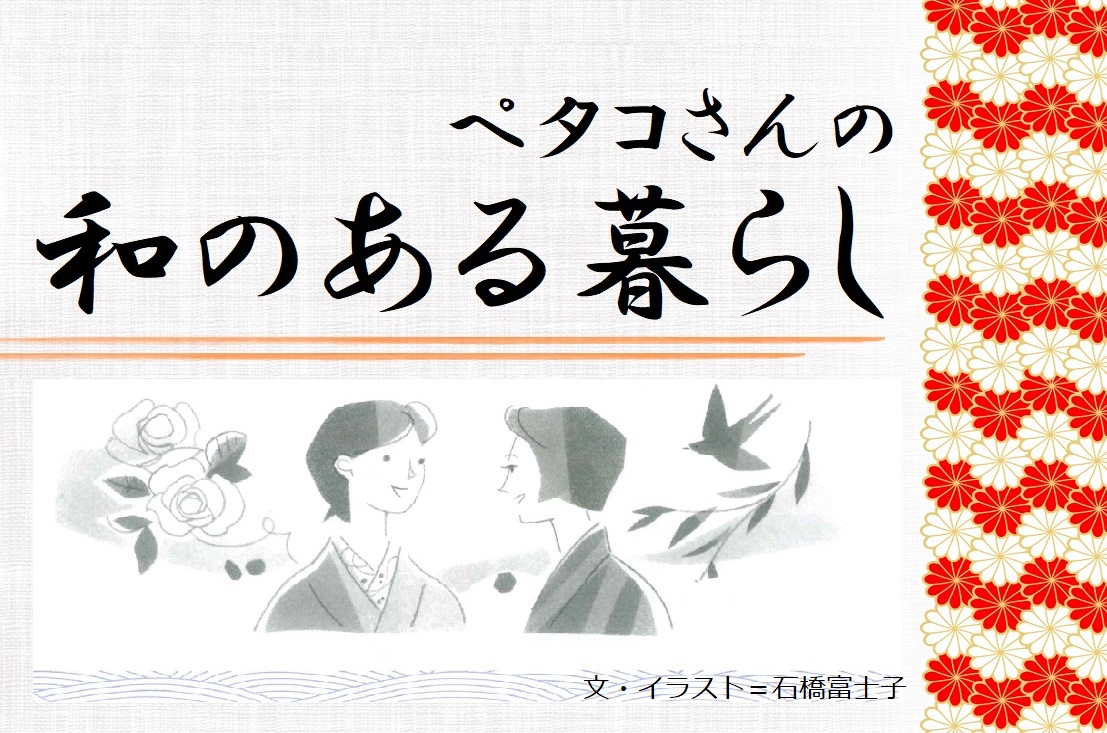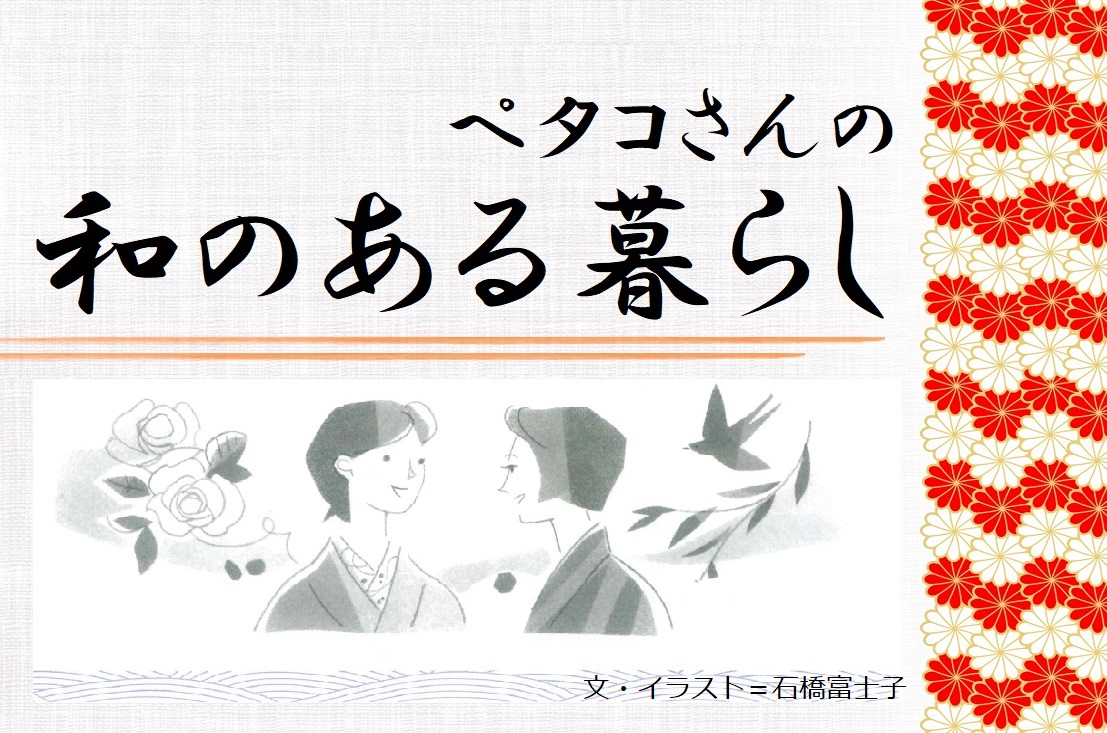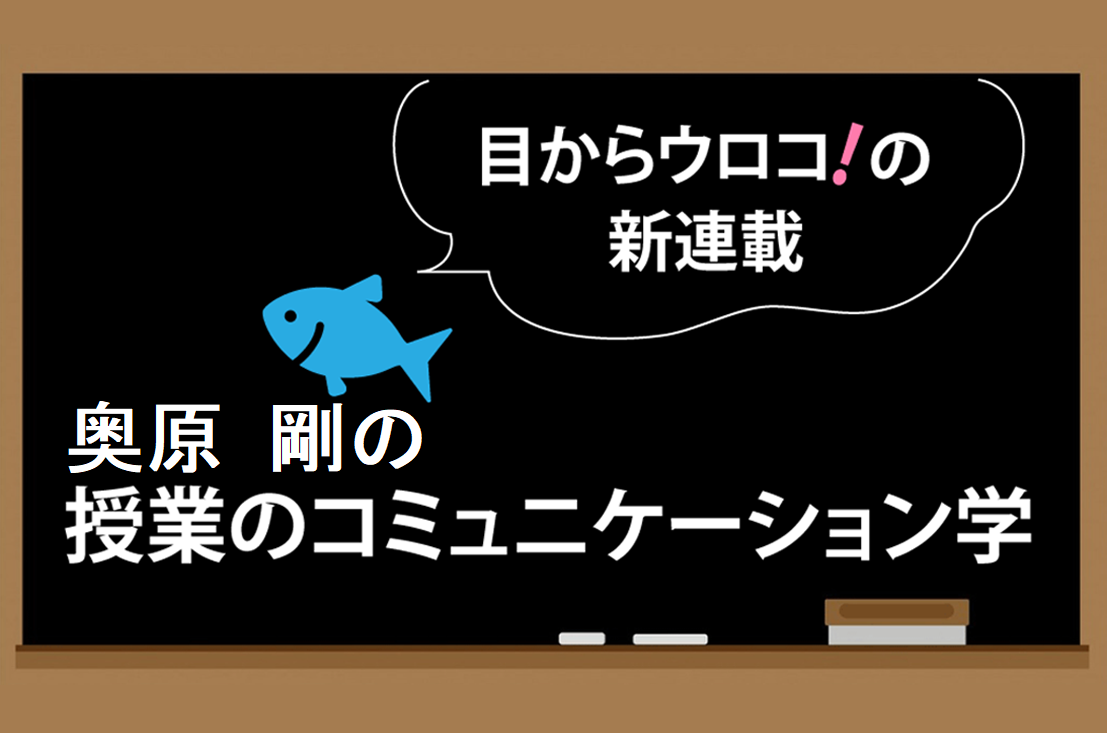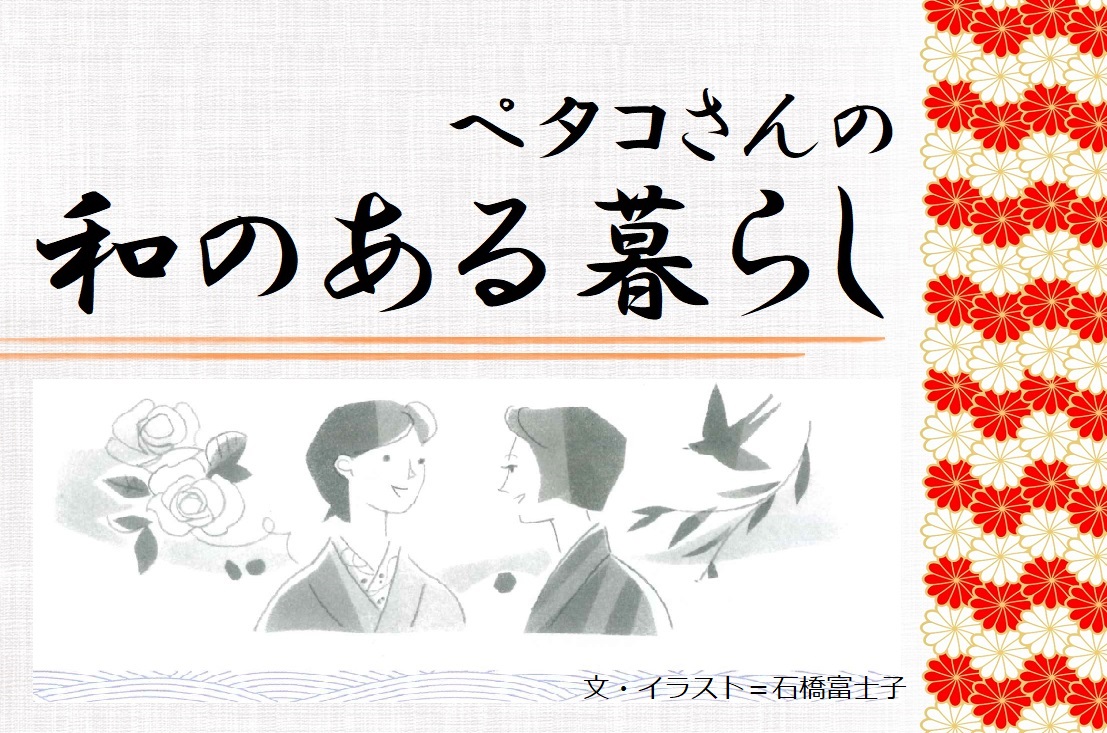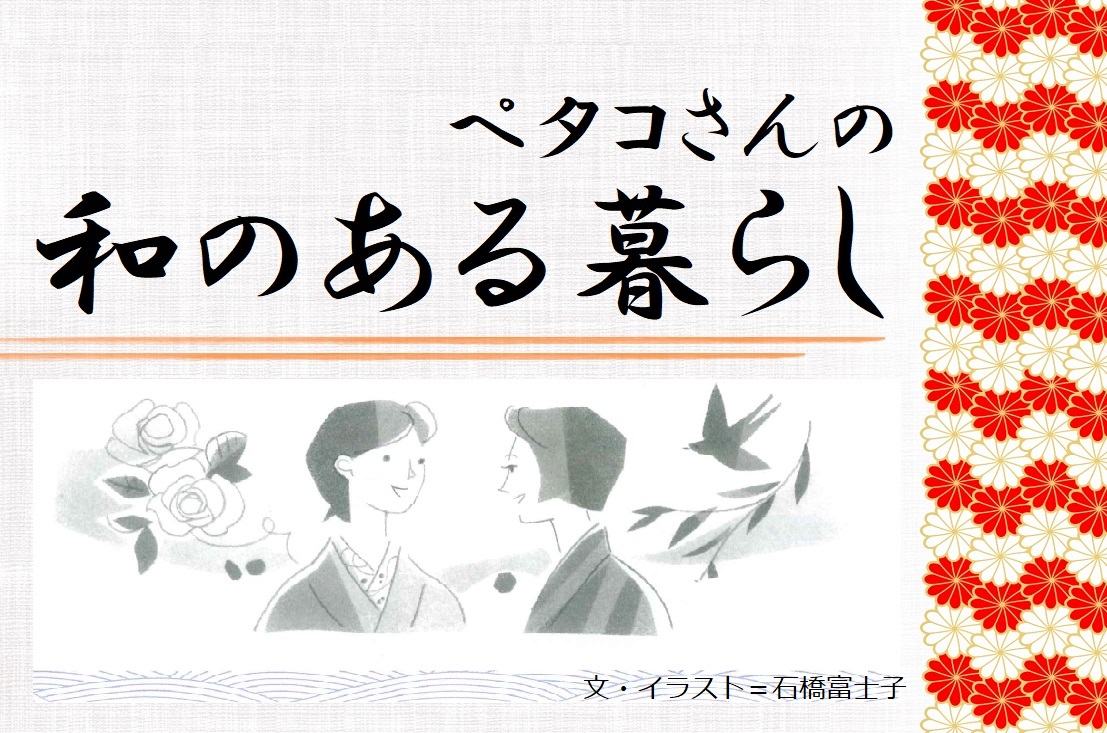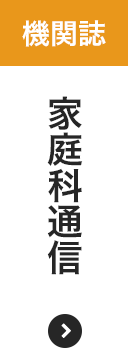ペタコさんの 和のある暮らし
[第21回]節句の飾り
石橋富士子
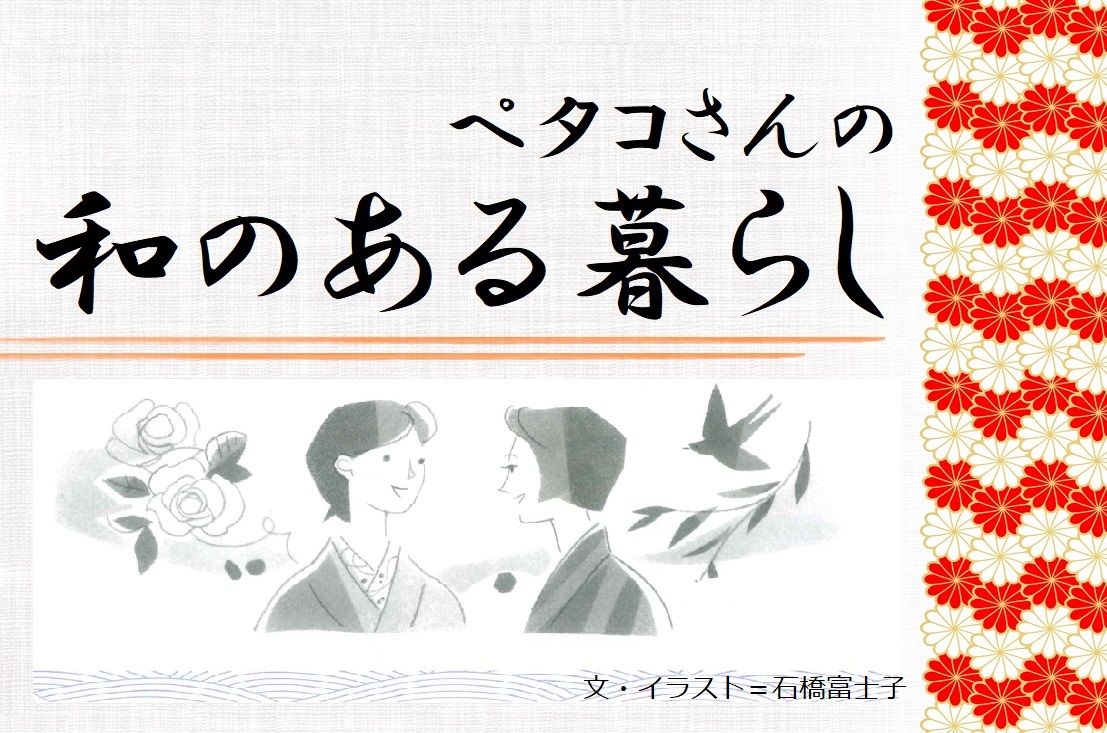
寒い季節が別れを告げ,ほっこりと花が咲き始める日々を彩る,雛祭りと端午の節句。
幼い日に,雛人形といっしょに桃の花や菜の花などを飾ったことを懐かしく思い出します。
天気の良い日に押し入れの奥から木箱を出して,中から布にくるんだお雛様を確かめるように眺め飾っていきます。私の雛人形はガラスのケースに入った小さな段飾り。一番好きなのは女雛や男雛ではなく三人官女の御神酒を持った人。白い着物と赤の袴がシンプルながら美しいと思ったのかもしれません。おいしいとは思えなかった白酒も,ピンクや黄緑色が綺麗で好きだった雛あられや菱餅も今では懐かしく思い出します。
雛人形は,節句が過ぎていつまでも出しておくと縁遠くなるといわれ,翌日にはすぐに押し入れの奥にしまわれます。
次に飾るのは端午……ですが,女ばかりの我が家では,金太郎などの人形も鯉のぼりも飾らず,菖蒲湯や柏餅で端午を祝いました。
子どもが手を離れた年齢になって,自分のためにお雛様を飾る女性が増えていると聞きました。孫がいるような年配の女性たちも,今度は自分のために雛人形を求めるそうです。シンプルで小さな雛人形を,お花といっしょにちょっとしたコーナーに飾るのも素敵。小さくて愛らしいお雛様は,幼い日の楽しい思い出を呼び起こしてくれそうです。
雛祭りや端午の他にも節句があり,年5つの節句があります。起源は古代中国から日本に伝わった陰陽五行とか。
1月7日の七草の節句(人日・じんじつ),3月3日の桃の節句(上巳・じょうし),5月5日の菖蒲の節句(端午・たんご),7月7日の七夕の節句(七夕・しちせき),9月9日の菊の節句(重陽・ちょうよう)です。
七夕には笹に短冊を飾り,重陽には菊を飾るのもいいですね。節句が近づくとその雰囲気にあったはがきなども店に並びます。どなたかに送ったり,壁に貼って飾るだけで季節感が出ます。住空間や環境の中に季節を感じることが少なくなりましたので,季節の節句を飾ることは単調になりがちな毎日に,季節のリズムや活力を与えてくれるような気がします。
(2014年3月25日発行 家庭科通信53号掲載)
著者プロフィール
石橋 富士子(いしばし ふじこ)
毎日を着物で暮らすイラストレーター。教科書,絵本などの他,和小物製作デザインやオリジナル落雁の型を使った落雁作りワークショップなどを開催。「家庭科通信」の表紙も創刊時から手がけている。著書に「知識ゼロからの着物と暮らす・入門」「知識ゼロからの着物と遊ぶ」(幻冬舎)。着物をもっと楽しむための刺繍和小物をつくる富士商会を2015年設立。https://fujipeta.com/
一覧に戻る