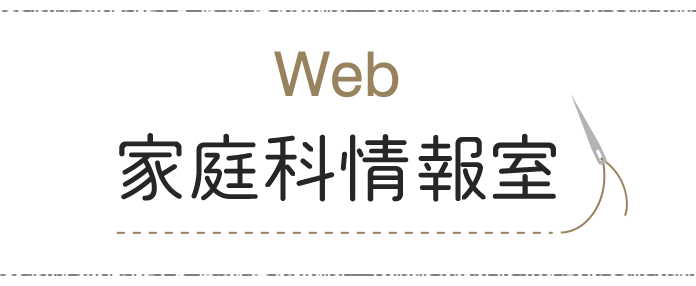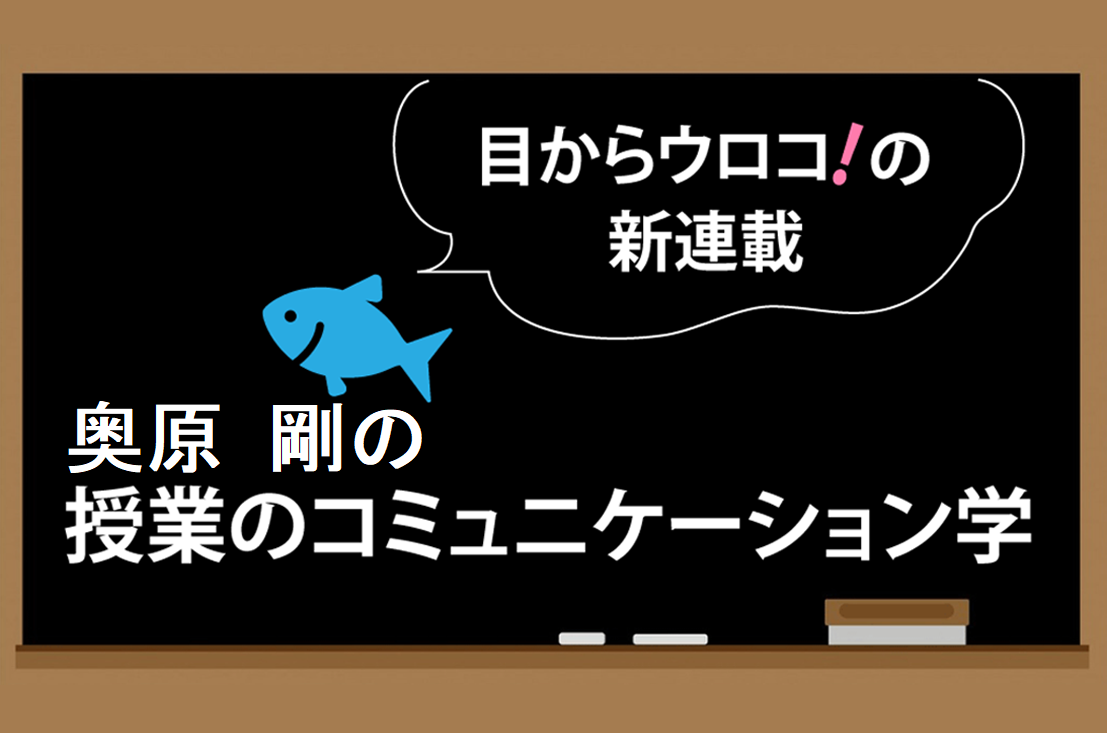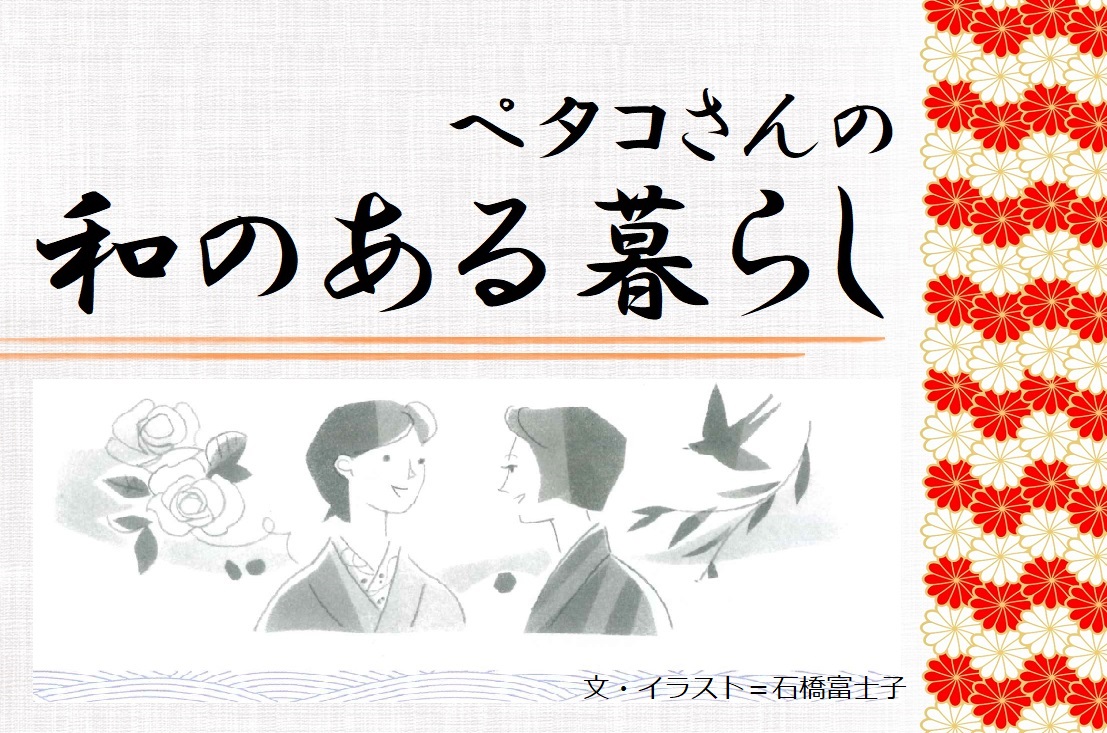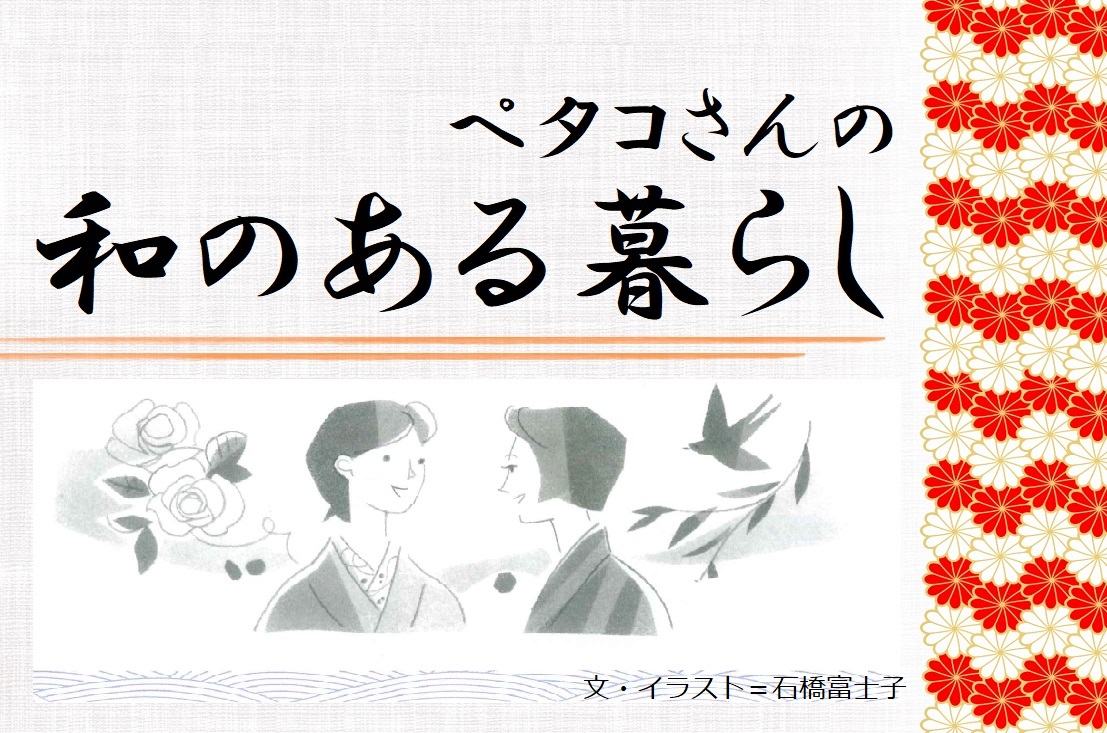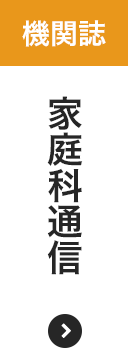ペタコさんの 和のある暮らし
[第24回]和のロウソク
石橋富士子
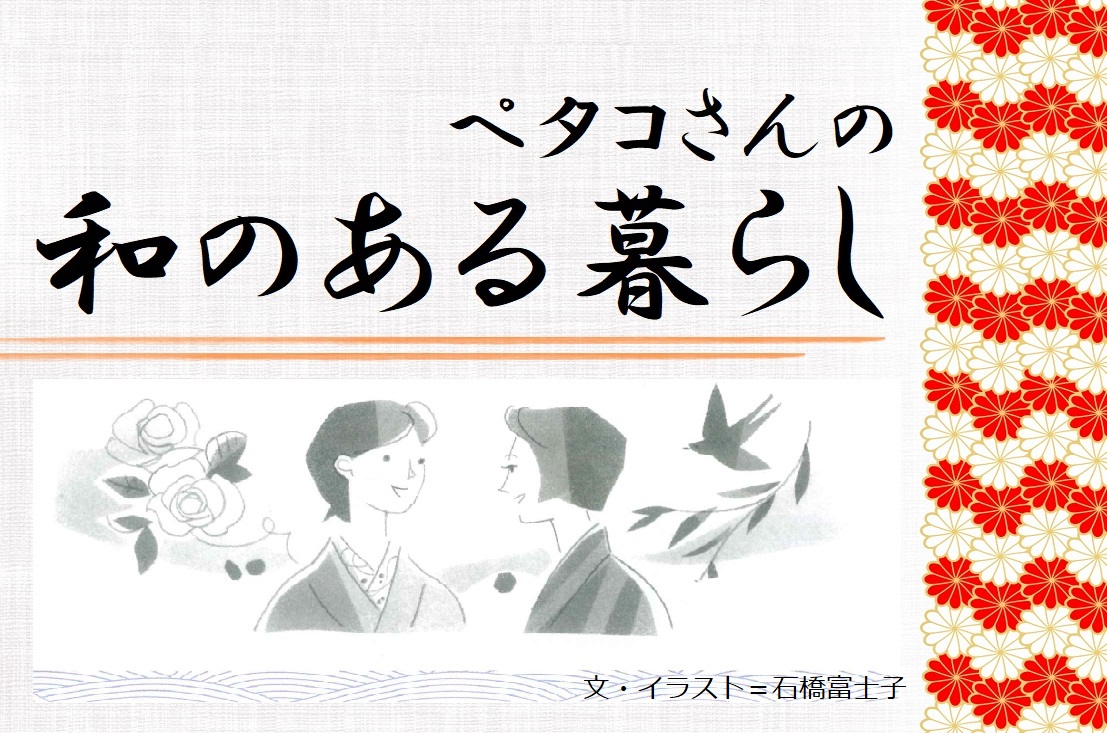
先日,仕事で会津若松を訪れました。取材も無事終わり,街を散策していると和ロウソクの看板を見つけて興味を引かれ,少しだけ寄ることにしました。
店の中にあったのは様々な和ロウソクときれいな模様が描かれた絵ロウソク。かねてから「絵ロウソクはきれいな装飾品」と感じてはいたのですが,伝統的な絵が描かれた和ロウソクを拝見しながらお店の方にお話をうかがうと,絵ロウソクが寒い東北で生まれた理由がありました。
日本のどこでもご先祖供養のための花を飾りますが,寒さの厳しい北国ではお花を手に入れるのもむつかしくなります。生花が飾れないのならせめてロウソクに花の絵を描いてお供えしたい,絵ロウソクはそんなご先祖様を大切にする心から生まれたそうです。
絵ロウソクで思い出すのは小さな頃に読んだ小川未明の「赤い蝋燭と人魚」。着物を着た人魚の姿と,真っ赤なロウソクが織りなす不思議ななまめかしさは子供心に不思議と惹かれるものがありました。
そういえば小さな頃によくあった停電。まっ暗闇の中,ロウソクが灯されるとホッとしたものの,その炎が揺らめくたびに揺らぐ屏風の影に心も揺らぎ,いつにも増して闇を濃くしたふすまの後ろに「何か」が潜んでいるような気がして首筋が寒くなったことを思い出します。
近年は停電もなく,LEDのおかげで闇の裾はずいぶん退き,物陰に潜んでいた「何か」の姿もだいぶ薄らぎました。
とはいえLEDがロウソクにとって代わっても,どうしても和ロウソクでなくてはならない場所があります。それは時代劇や落語,そして歌舞伎の世界での小道具としての存在。和を感じ,日本を感じるための江戸時代の雰囲気作りには和ロウソクはけっして欠かせません。
和ロウソクと西洋のキャンドル,同じように見えても構造も炎の燃え方も全く異なります。人手不足からロウソクの原材料である「ハゼの実」の入手も困難になっていると聞きますが,日本文化の一端を担う和ロウソクの灯が次の世代に伝わることを心から願っています。
(2015年9月1日発行 家庭科通信57号掲載)
著者プロフィール
石橋 富士子(いしばし ふじこ)
毎日を着物で暮らすイラストレーター。教科書,絵本などの他,和小物製作デザインやオリジナル落雁の型を使った落雁作りワークショップなどを開催。「家庭科通信」の表紙も創刊時から手がけている。著書に「知識ゼロからの着物と暮らす・入門」「知識ゼロからの着物と遊ぶ」(幻冬舎)。着物をもっと楽しむための刺繍和小物をつくる富士商会を2015年設立。https://fujipeta.com/
一覧に戻る