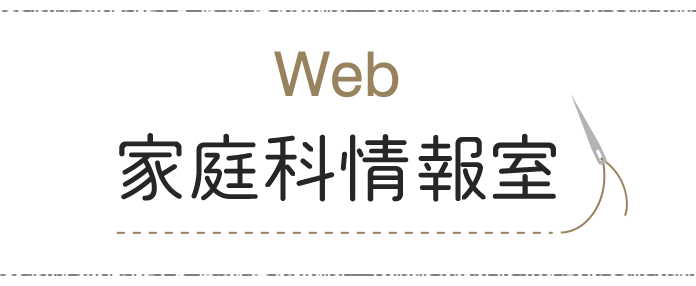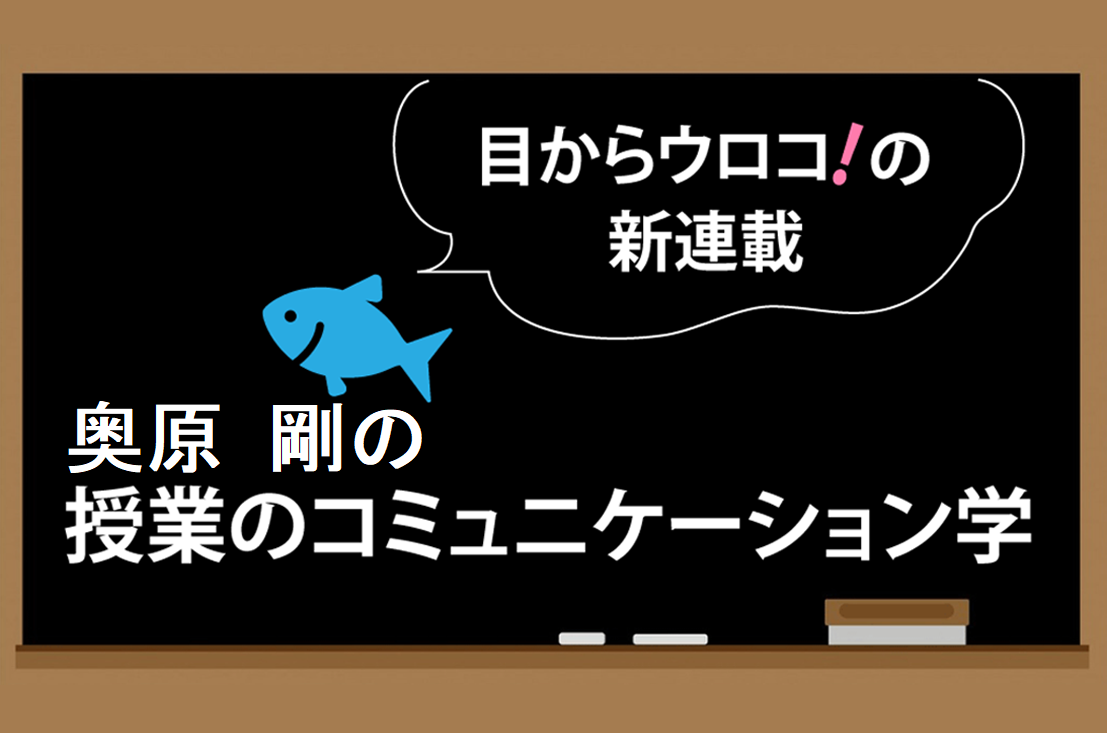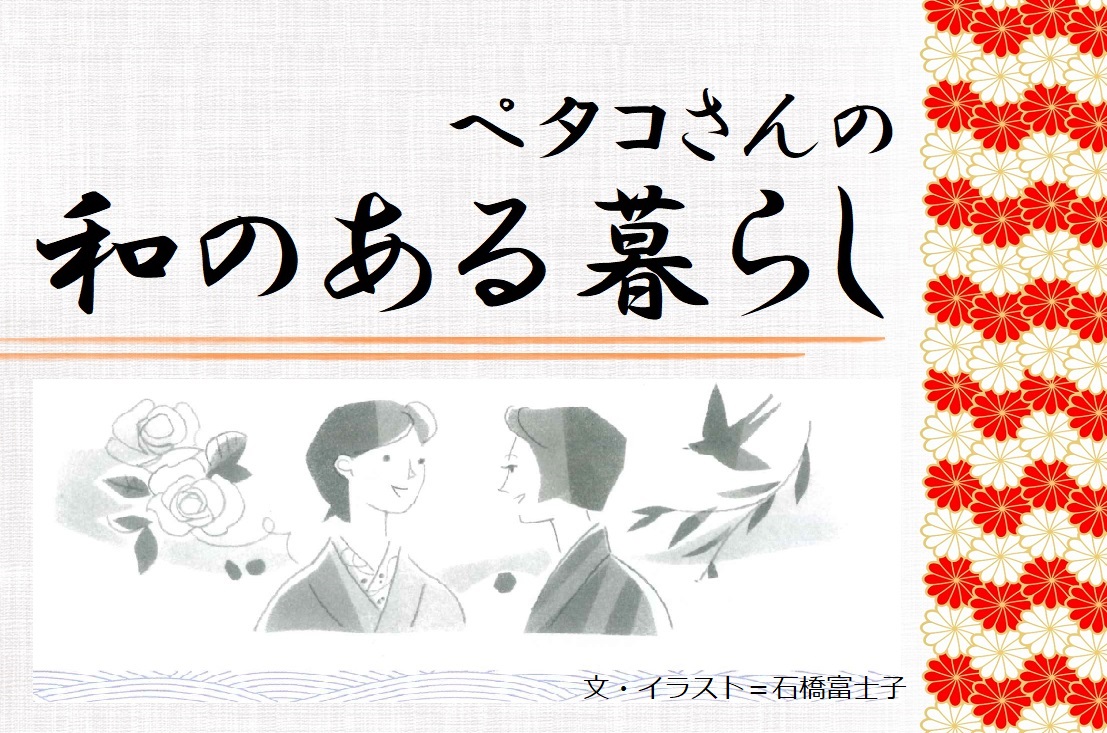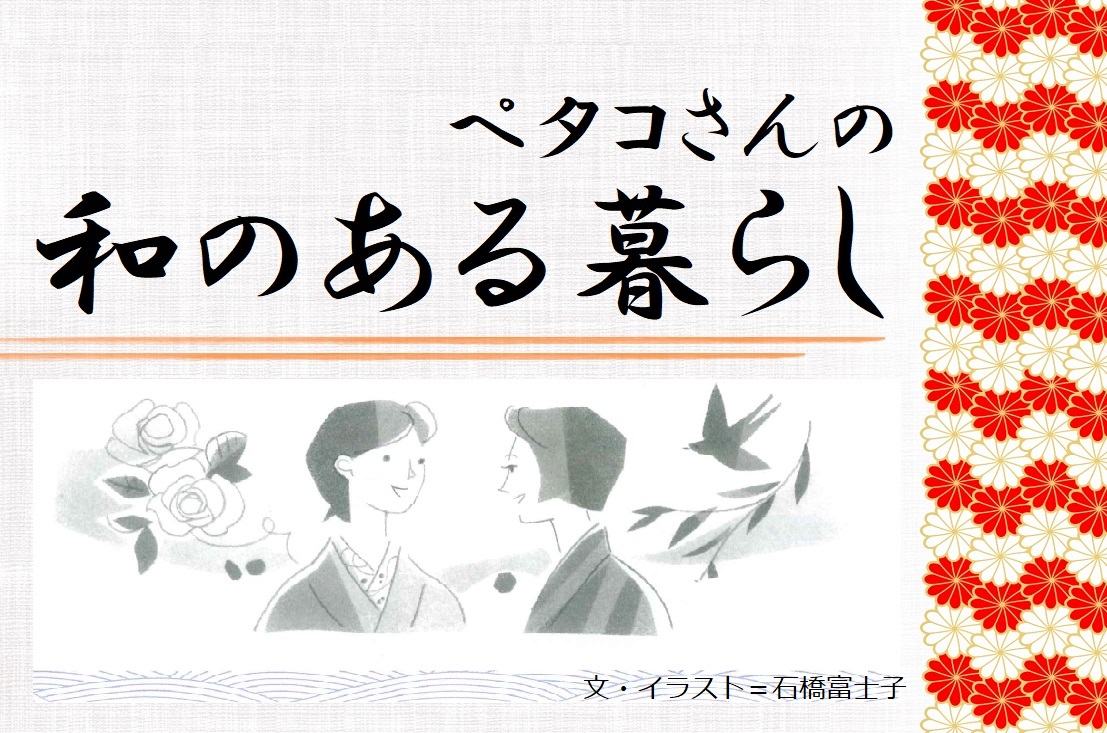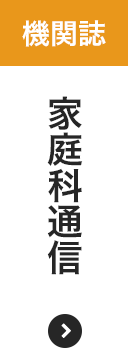ペタコさんの 和のある暮らし
[第25回]ご苦労さま,いろいろな道具を供養する
石橋富士子
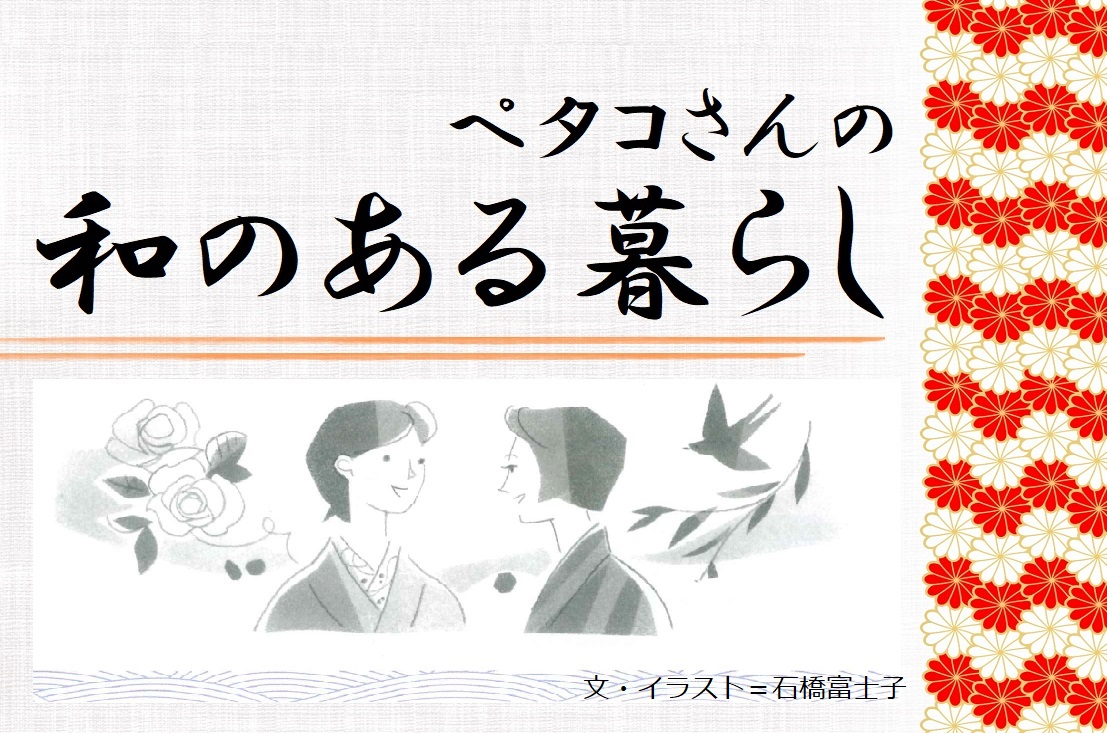
おつきあいのある下駄屋さんから「はきもの供養をします」と記された興味深いご案内が届きました。下駄や草履は,底がすり減ったら修理,ゆるんだ鼻緒はすげ替え,取り替えて長く履くもの。それでも修復不能なほどに傷んでしまった「はきもの」をごみとして捨てるのではなく,神社でお祓いしてから手放しましょうというのです。その案内をひと目見て「なんて素敵なアイデア!」と思いました。
たしかに足に慣れ親しんでよそ行きにならなくなったはきものは,ふだん履きや庭履きにおろして使っているものの,それもいつかはボロボロになってしまいます。
さんざん悩んで選んだお気に入り,愛着もひとしおで,たしかにごみとして捨てるには忍びないと常々思っていたのです。でも「はきもの供養」なら心穏やかに,愛しいはきものとさよならできそうだと思ったのでした。
「針供養」は古くからある行事で,曲がったり折れて使えなくなってしまった針のそれまでの働きに感謝し,やわらかい豆腐やこんにゃくに刺してねぎらい供養する行事です。供養のおこなわれる浅草・浅草寺淡島堂には毎年針仕事を生業とする裁縫関係や和裁士さん,趣味で縫いものをするたくさんの人が訪れます。
かくいう私も毎日を着物で暮らしていると,半衿つけやほつれなどのちょっとした縫い仕事が多く,手元から針と糸が欠かせません。毎日を着物だけで暮らしていた昔は,さぞや針と糸が身近で大切な道具だったことでしょう。
供養といえば,ともに日々を暮らした人形を供養する「人形供養」,茶道の世界ならお茶を点てるのに使った茶筅を供養する「茶筅供養」など,いろいろな供養があります。
暮らしのなかでお世話になったさまざまな道具たちの最後をきちんと送る「供養」は,毎日の生活や時間,ものを大切にする心につながるようで,慎ましいけれど豊かな暮らしかたを目指す上で必要な行事のように思えます。この「はきもの供養」のご案内をいただいて,自らの「もの」に対するけじめのような形として,あらためて「供養」というスタイルを暮らしのなかに取り入れてもいい,と感じました。
生活を便利に,そして豊かにして潤いを与えてくれるさまざまな道具たち。感謝の心をもって大切に扱う気持ちのありかたはとても日本的です。
八百万の神の存在を感じる日本ならではのとらえかたで,なかでも特にもの(道具)には長い年月
を経ると神が宿るとされ,「九十九神」と呼ばれます。きっと感謝しながら大切に使っていれば,役目を終えたあともきっとよいことをもたらしてくれるに違いないと思います。
冒頭の下駄屋さんからは「新しいはきものは新しい年におろすと,それが履く人を吉方,縁起のよい場所へと運んでくれるのよ」というお話も伺いました。新しい年度にはそんな「縁起」を担いでみるのもよいですね。
(2017年4月1日発行 家庭科通信60号掲載)
著者プロフィール
石橋 富士子(いしばし ふじこ)
毎日を着物で暮らすイラストレーター。教科書,絵本などの他,和小物製作デザインやオリジナル落雁の型を使った落雁作りワークショップなどを開催。「家庭科通信」の表紙も創刊時から手がけている。著書に「知識ゼロからの着物と暮らす・入門」「知識ゼロからの着物と遊ぶ」(幻冬舎)。着物をもっと楽しむための刺繍和小物をつくる富士商会を2015年設立。https://fujipeta.com/
一覧に戻る