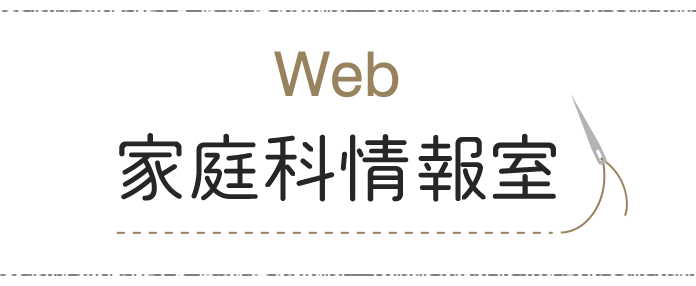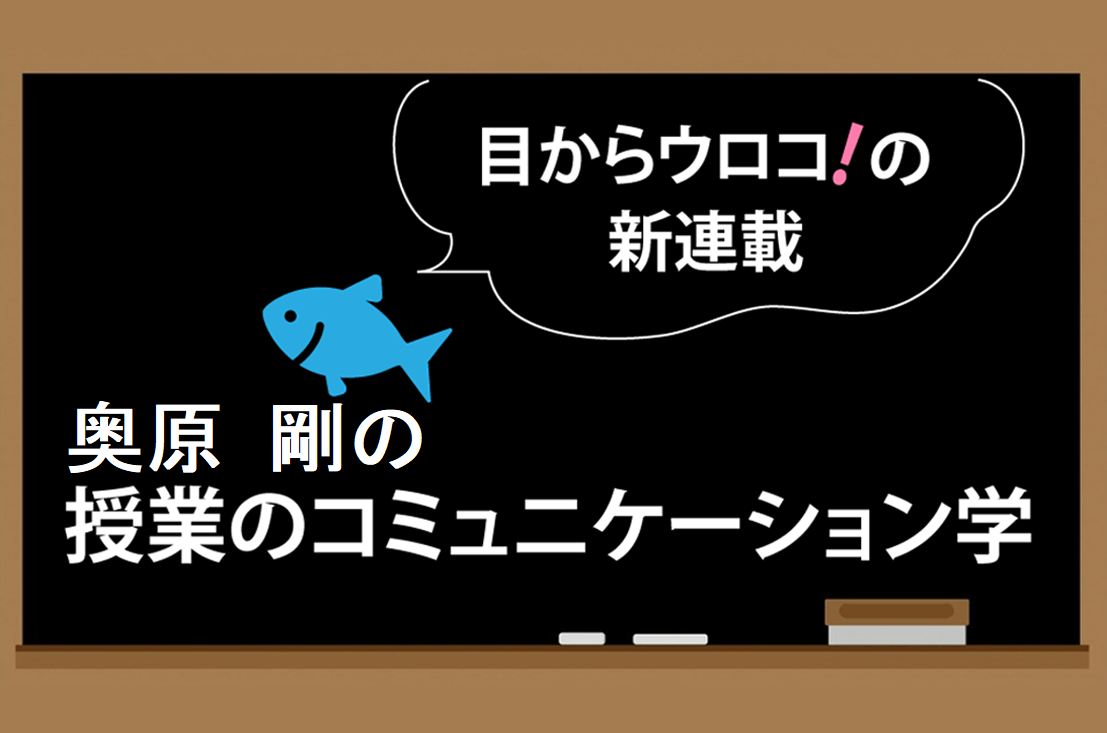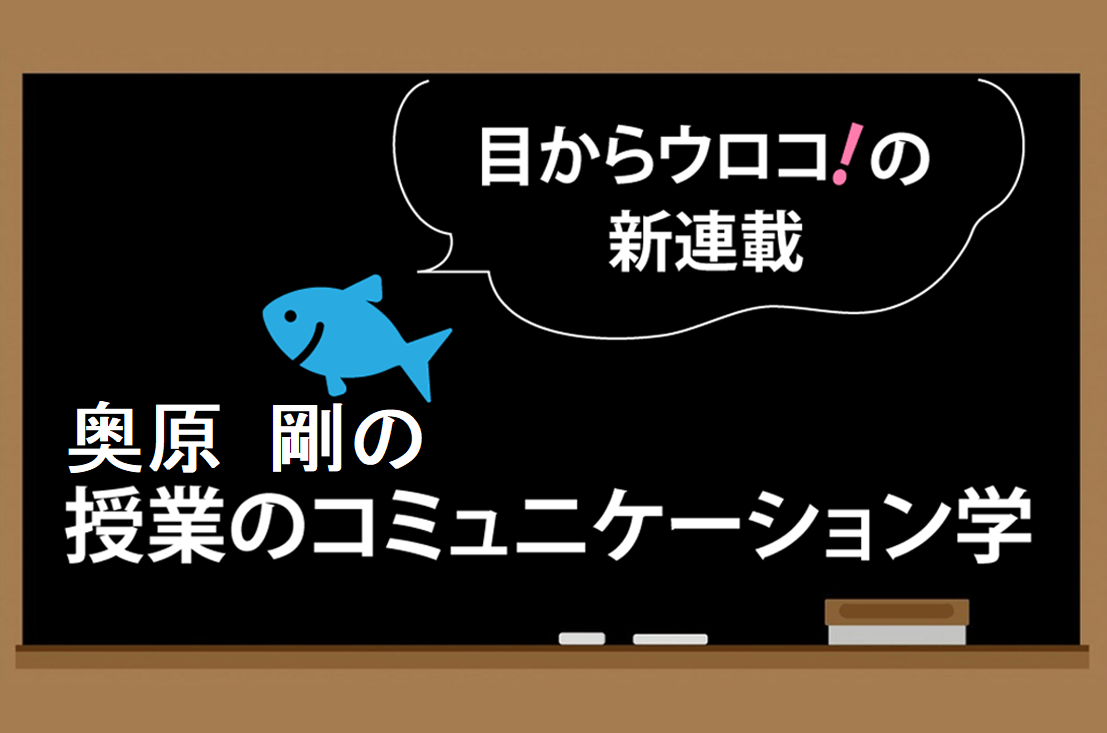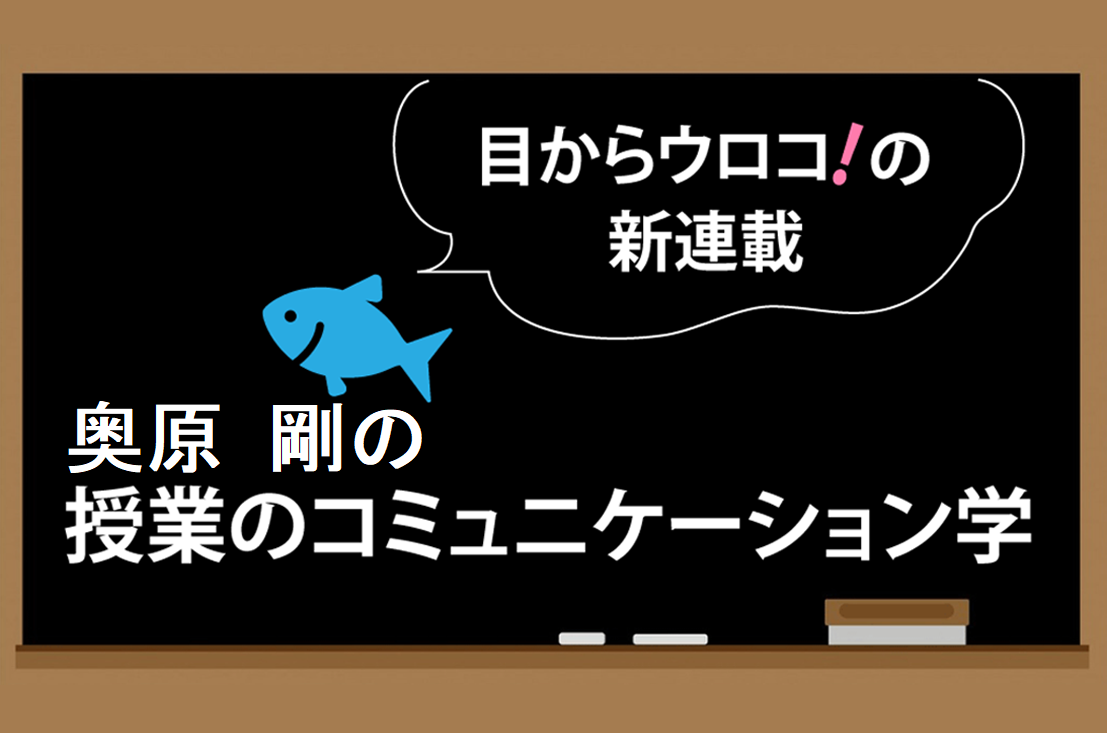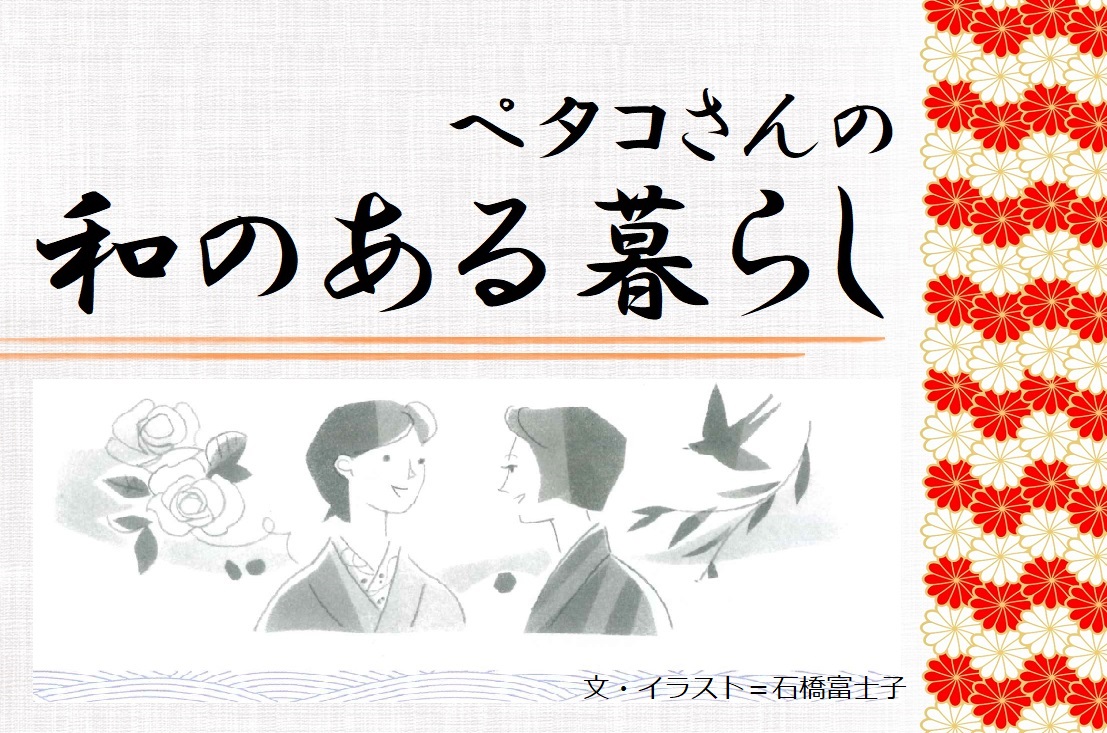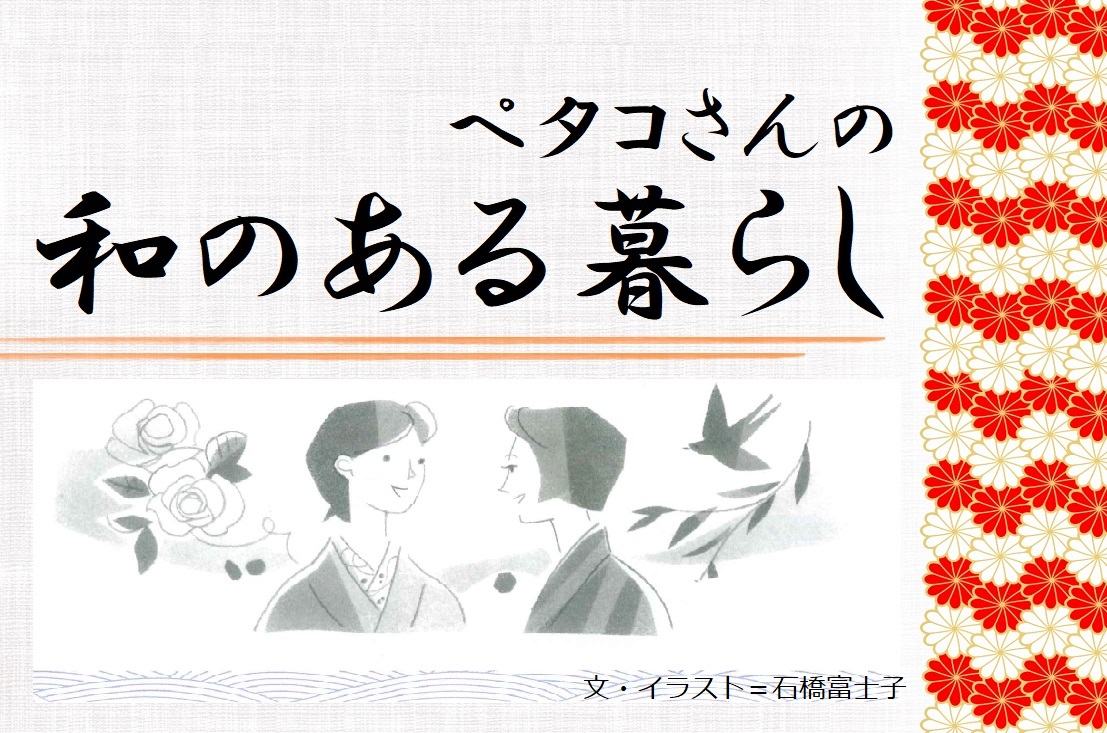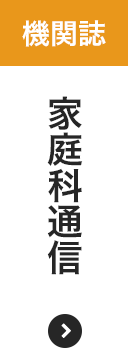授業のコミュニケーション学
[第3回]ストーリーで記憶に残す
奥原剛
- 2023.05.30
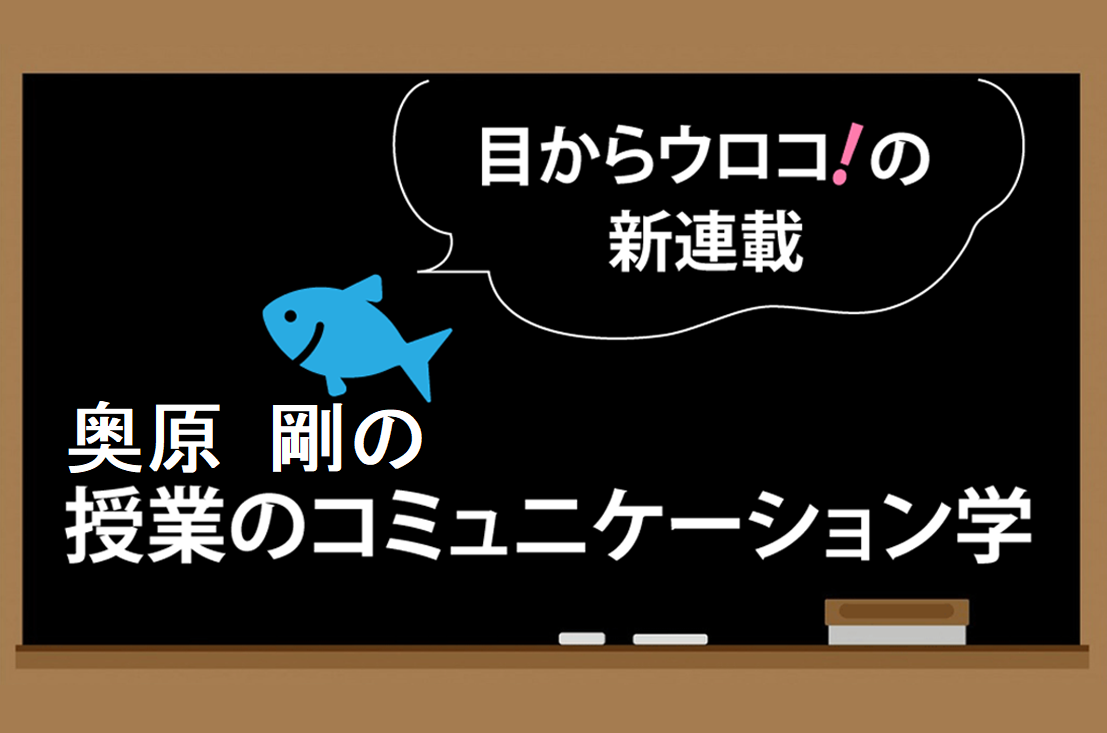
ニュージーランドの学校で生徒の記憶を検証したこんな研究があります*1。9~12歳の児童に対し,1年前の授業で教えた知識について質問しました。たとえば,「温度計の中に入っているのは何か」などです。児童の多くは,授業中の様子をあれこれと思い出して話しながら回答しました。たとえば,こんなふうに―「先生が水銀って何か知っているかって聞いたんだ。あっ,違うな。先生が温度計に入っているのは何か知っているかって聞いたんだ。そしたらトニーが手をあげて,水銀ですって答えたんだ」。1年前の授業で学んだ知識を正確に記憶していた児童は,そうでない児童より,上記のような具体的なストーリーを多く思い出していたそうです。なぜでしょうか?
図1をご覧ください。一見意味のない,このような図形は記憶に残りにくいのですが,「窓の向こうでシルクハットの男が葉巻をくわえている」と意味づけると,記憶に残りやすくなるでしょう。
また,112358132134という数字を記憶しろといわれても難しいと思います。実は,この数字はフィボナッチ数列と呼ばれ,1+1=2,1+2=3,2+3=5,3+5=8…という構造を持っています。ひとたびこの構造が見えれば,記憶するのは簡単でしょう。
人の記憶のなかの知識は,意味や構造によって関連づけられたネットワーク状で蓄えられています。記憶はマジックテープのようなもので,くっつく点が多いほど定着しやすいのです。ストーリーは,「だれが」「何をして」「何が起きて」といった点の集まりのマジックテープのようなものです。ですから,冒頭の研究で,児童は授業中の様子をストーリー風に思い出しながら正解を回答したのです。
人間のコミュニケーションのほとんどが,実はストーリーです。家族や友だち,生徒との会話は,「今日,だれが,何々をして,こうなって,私はこう思った」といったストーリーです。経済ニュースのような無味乾燥に見える情報も,「トランプ大統領の何々という発言で市場に懸念が広がり,株価が下落した」というように起承転結のあるストーリーです。
ストーリーは,人間の思考と記憶に最適のコミュニケーション形態といわれています。私の専門の医療のコミュニケーションでは,ストーリーを使った健康教育が注目されています。たとえば,「10~15人に1人は生涯のうちに〇〇病を経験すると考えられており,きわめて発病頻度の高い病気ですので,予防が大切です」というただ叙述するだけの知識の伝達は,図1のように記憶に残りにくいですが,「Aさんは44歳のときに〇〇病になり,3人の子どもと家のローンを抱えたまま会社を辞めなくてはなりませんでした。」といったストーリーが加わると記憶に残りやすくなります。先生方の授業におかれましても,ストーリーの力を活用してはいかがでしょうか。
* 1 Nuthall, G., & Alton-Lee, A. (1995). AssessingClassroom Learning: How Students Use Their Knowledgeand Experience to Answer Classroom AchievementTest Questions in Science and Social Studies.American Educational Research Journal, 32(1),185–223

著者プロフィール
奥原 剛(おくはら つよし)
東京大学大学院 医学系研究科 医療コミュニケーション学分野 助教。
健康・医療にかかわる情報を,市民・患者にわかりやすく伝え,よりよい意思決定を促すための研究をしている。医療機関,健康保険組合,自治体等の医療従事者に対し,わかりやすく効果的な健康医療情報を作成するための研修をおこなっている。
一覧に戻る