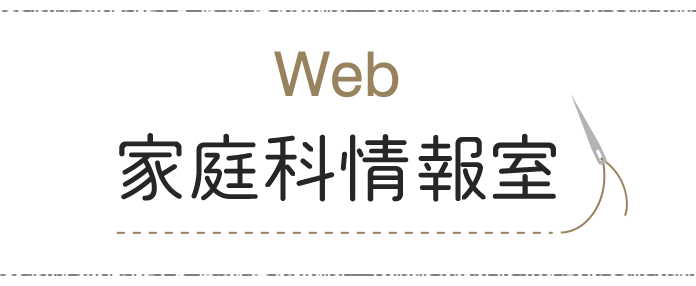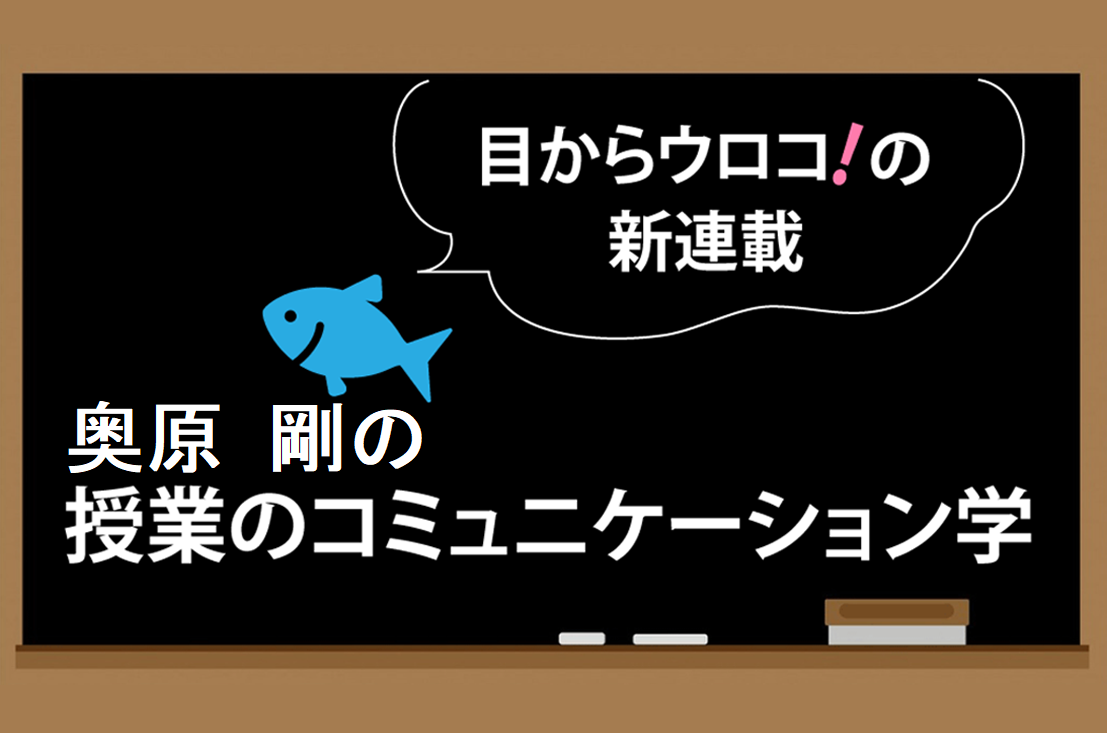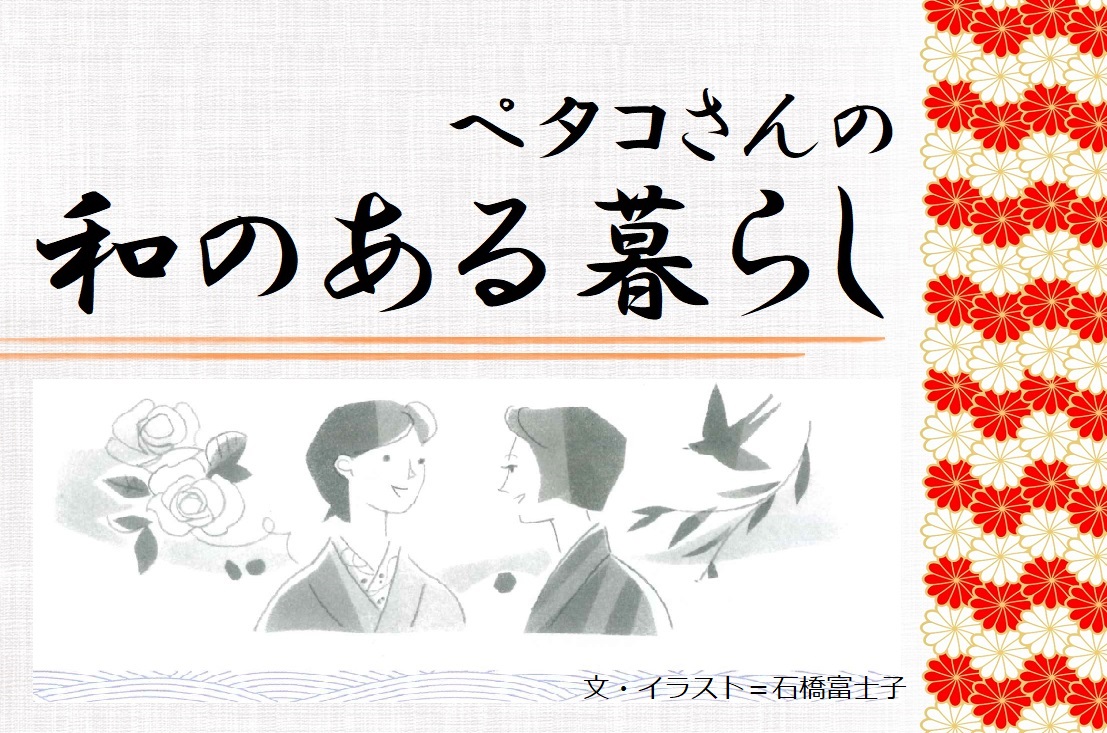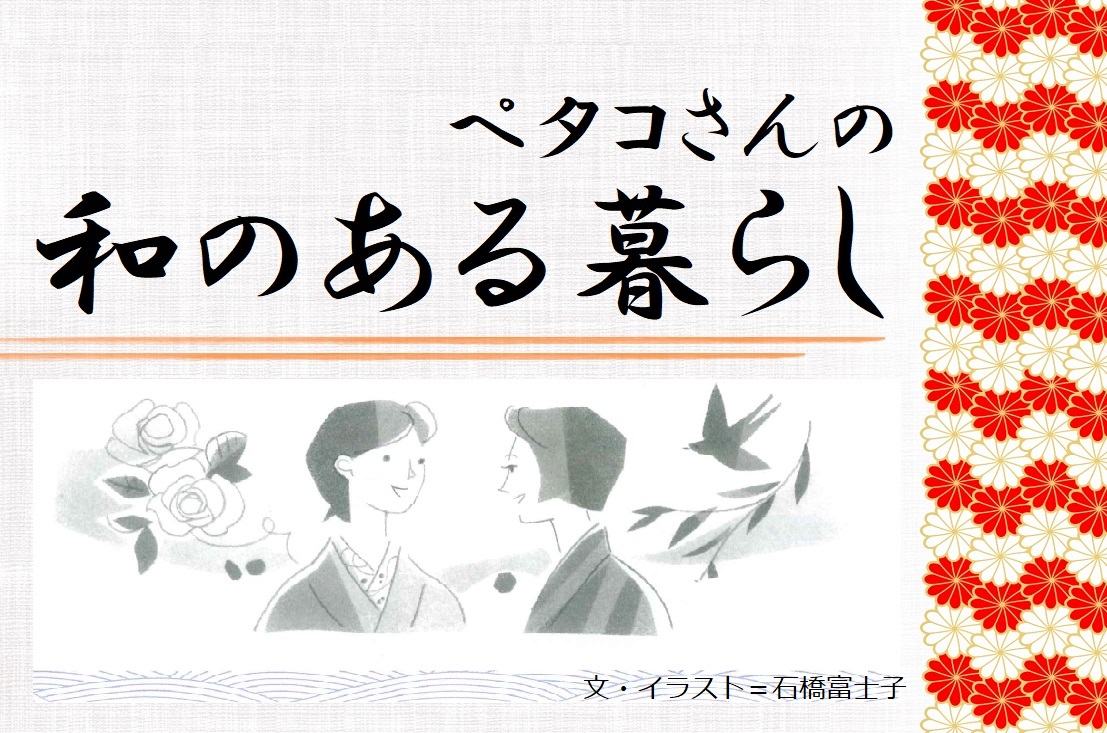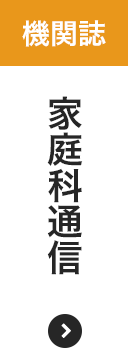授業のコミュニケーション学
[第4回]雑談の力
奥原剛
- 2023.11.28
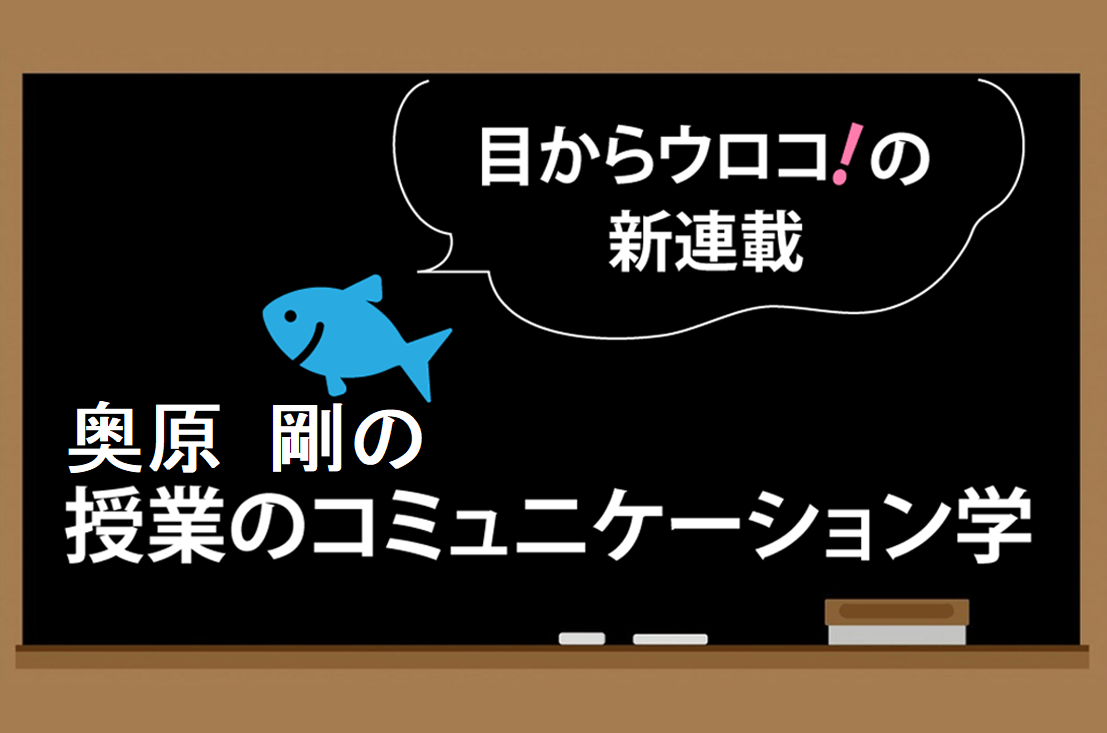
私が高校生だったのは約30年前ですが,今も高校の授業で聞いて記憶に残っている話がいくつかあります。実はその話のどれもが,授業の内容そのものではなく,先生が授業から脱線して話した先生自身の家族の話や,旅行の話といった雑談なのです。私は今も学会で偉い先生の講演を聴いたりした後で,肝心の講演内容はすっかり忘れてしまっているのに,講演者が脱線して話した雑談のエピソードだけが,くっきりと記憶に残っていたりします。雑談は,妙に記憶に残るのですよね。
私自身は,雑談をするのが苦手です。お天気がどうとか,あの人はどうでこうでとか,業務と直接関係のない雑談が,どうもうまくできません。しかし,周囲の人たちは雑談が好きなようで,身近な出来事や噂話などを私にしてくれます。それをぼんやり聞きながら,「人はなぜ雑談をするのだろう?」「雑談になんの意味があるのだろう?」と,かつての私は不思議に思っていたのです。
地球上の動物の中で,人間だけが言葉を使ってコミュニケーションをします。言葉によるコミュニケーションの起源にはいくつかの説があります。身振りから発生したという説や,歌から発生したという説。または,異性の注意を引いて逃さないためという説。そして,言葉によるコミュニケーションは,集団の絆を強めるための雑談から発生したという説があるのです。
動物園に行くと,猿たちが熱心に毛づくろいしていますね。あれは社会的グルーミングといって,お互いの信頼や絆を築くための行為です。お互いに毛づくろいして,「うちらは仲間,仲良しだよね」と確認し合っているのです。
猿から進化した人類の脳は,数百万年にわたる進化の中で,約500cc から1,500cc へと大きくなっていきました。それと並行して,人類の集団のサイズも,50人程度から150人程度へと大きくなっていきました。毛づくろいは,1対1でおこないますから,集団の人数が増えると,毛づくろいに必要な時間も増えます。鈴木さんや田中さんに加えて,村田さんや張本さんとも毛づくろいしなくてはいけなくなるといった具合です。しかし,1日の時間は限られていて,食べ物を得る時間も必要です。言葉なら一度に3~4人とコミュニケーションできます。
そこで毛づくろいの代わりに,言葉によるコミュニケーションが生まれたという説を,ロビン・ダンバーという学者が唱えています。言葉は人間関係を補強するために情報をやり取りするように進化した,という説です。雑談は毛づくろい,かつ,言葉の起源であり,絆を確認し補強するための方法なのだと考えると,雑談が記憶に残るのも,人々が噂話などの雑談に多くの時間を費やすのも,私は腑に落ちたのでした。
それからは,自分の授業中の話の脱線に,受講者との関係性を築く上で肯定的な意味を見出すようになりました。また,だれかの雑談を聞いているときも,「ああ,僕は今この人と毛づくろいをしているのだ」と理解すると,多少は苦手意識がなくなったのでした。めでたし,めでたし。

著者プロフィール
奥原 剛(おくはら つよし)
東京大学大学院 医学系研究科 医療コミュニケーション学分野 助教。
健康・医療にかかわる情報を,市民・患者にわかりやすく伝え,よりよい意思決定を促すための研究をしている。医療機関,健康保険組合,自治体等の医療従事者に対し,わかりやすく効果的な健康医療情報を作成するための研修をおこなっている。
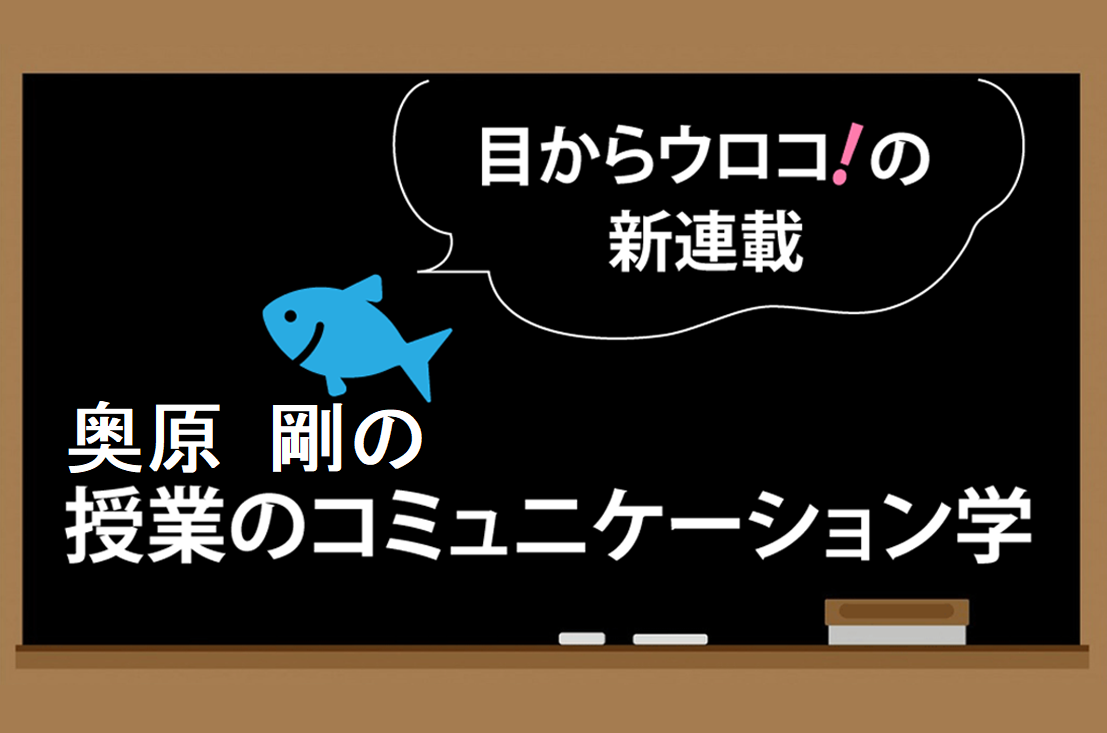
詳しくはこちら
一覧に戻る