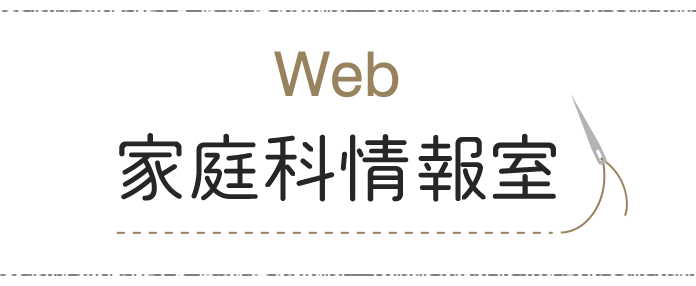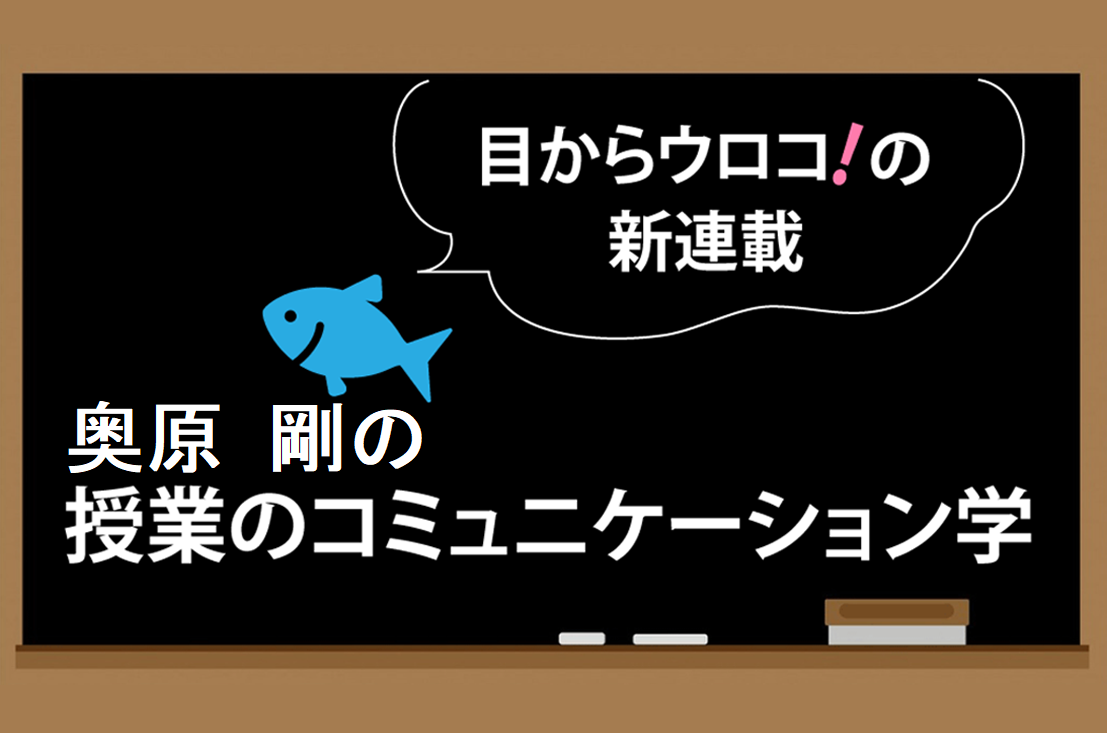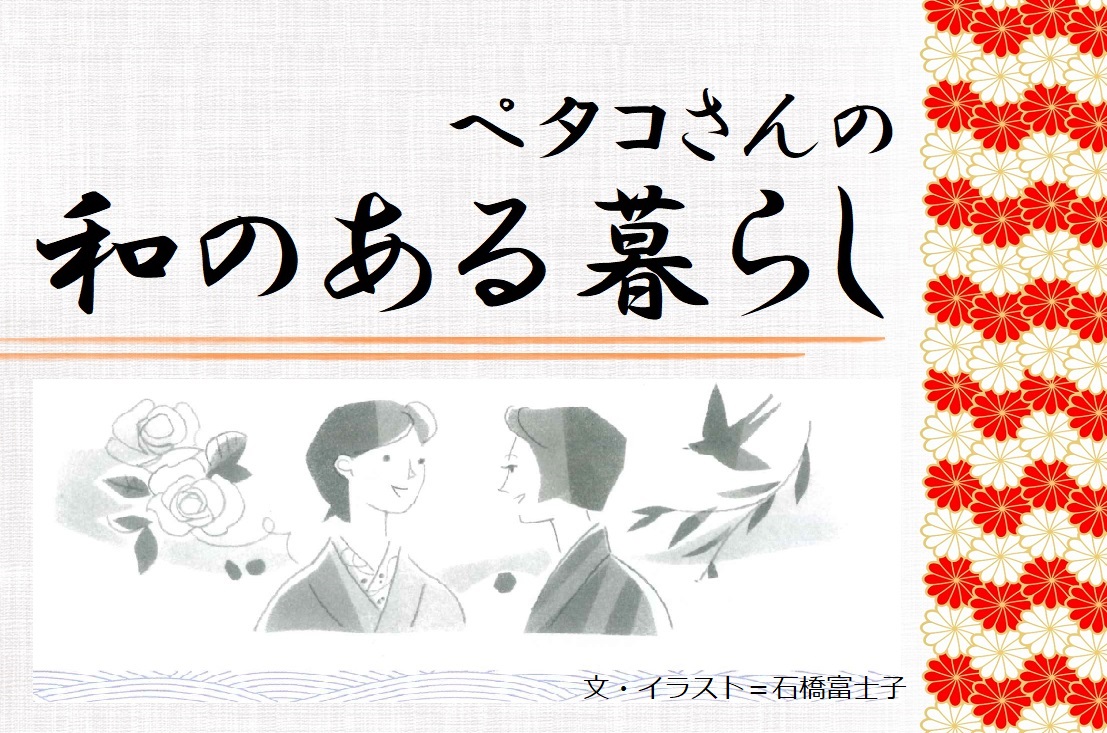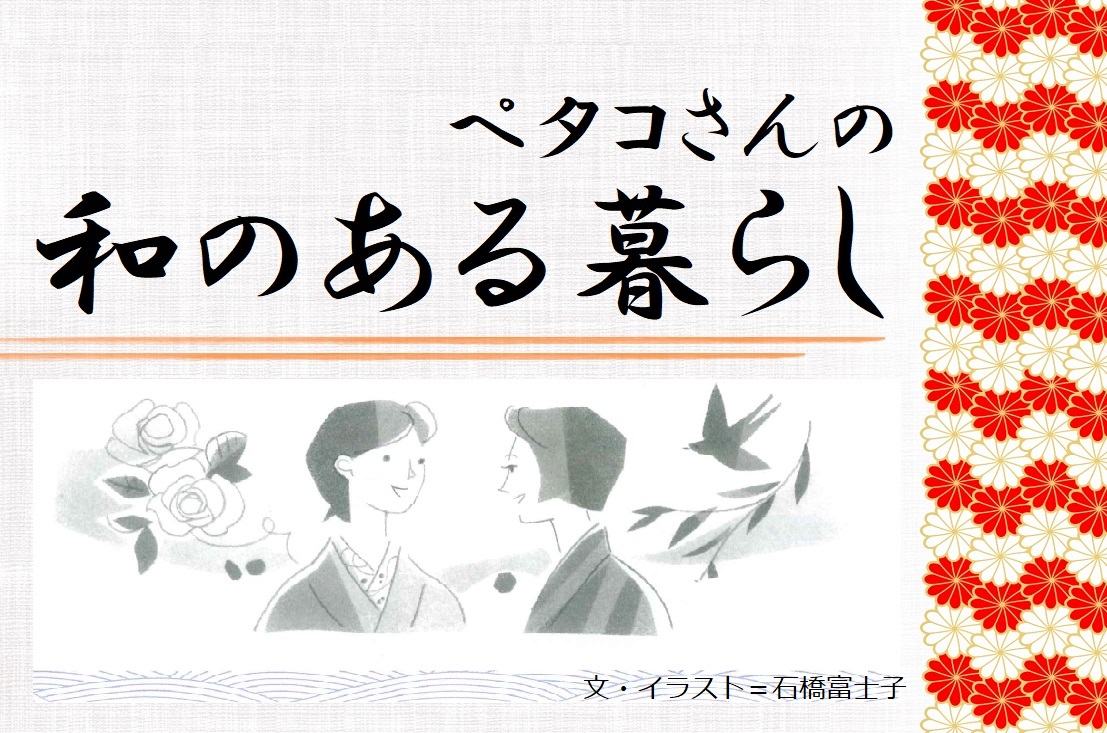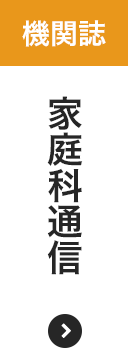授業のコミュニケーション学
[第6回]人を動かす10原則
奥原剛
- 2024.11.26
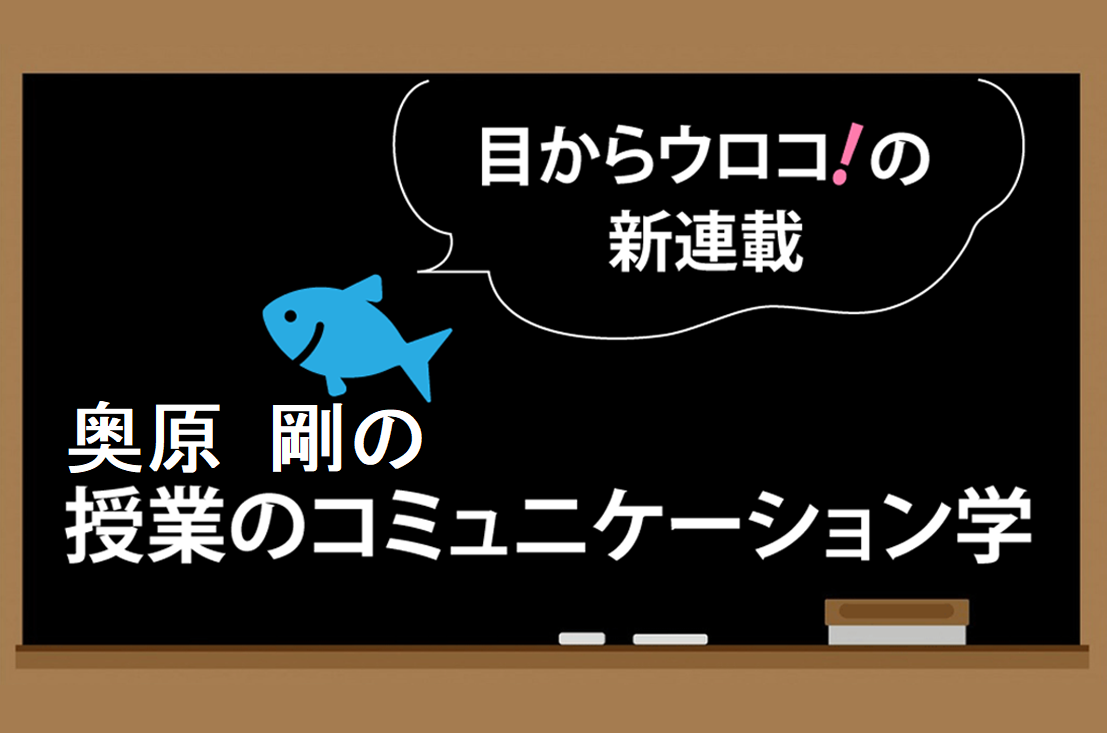
人生は,選択の連続です。就職か,進学か。育児か,キャリアか。愛か,お金か。うどんか,そばか。私自身も,最近,ある選択をしました。この1~2年で急速に私のおでこの生え際の髪の砂漠化が進んでいるため,いよいよ発毛剤を使い始めたのです。私と身長が同じであるトム・クルーズは,映画『ミッション:インポッシブル』の中で,CIA 本部の情報管理室に侵入するという困難なミッションに挑む際,「さあ,エベレストに旗を立てるぜ」と言いました。私もおでこの生え際に旗を立てるつもりで発毛剤を塗っております。これが正しい選択であったことを願うばかりです。
皆様も,生徒がマナーを守る,勉強するといった正しい選択をしてくれることを願っておられると思います。そんな皆様にも,お役立ていただけるよう,このたび,本連載をもとにした拙著『実践 行動変容のためのヘルスコミュニケーション―人を動かす10原則』を上梓いたしました。人の興味を引き,わかりやすく伝え,相手の考え方に変化を起こし,記憶に刻みつけて,行動してもらうために「何を」「どう」伝えたらよいかについて,社会心理学や教育心理学の研究と実践から,多くのことがわかっています。それらの知見を整理したものが,拙著でお伝えしている「人を動かす10原則」です。以下にご紹介します。頭文字で「お薬,シメジのシチュウ」と覚えてください。
オ:驚きを与える
心理学者たちは,「人は予想外の驚きに興味を引かれる」ことを明らかにしています。
ク:クイズを使う
クイズ形式で,自分で考えてもらうと,興味を引いて記憶に残しやすくなります。
ス:数字を使う
「5人のうち4人が〇〇している」など,ほかの人たちの行動を数字で示すと,行動してもらいやすくなります(社会的証明の効果)。
リ:ストーリーを使う
体験談などのストーリーを用いた説得はNarrative persuasion と呼ばれています。
シ:視覚的・具体的に伝える
視覚的に具体的に伝えると,興味,理解,記憶が促されます(二重符号化理論)。
メ:メリットとデメリットで感情に訴える
メリットやデメリットを強調して感情に訴えると,態度や行動の変容を促すことができます。
ジ:情報量を絞る
人の頭は家電のエコモードみたいなものです。情報過多は避けましょう。
シ:シミュレーションしてもらう
「いつ,どこで,どのように行動するか」の具体的なイメージが行動を促します(実行意図の効果)。
チュ:中学生にもわかるように伝える
情報が見やすく,読みやすく,イメージしやすいと,読者は書かれている内容を好みやすく,信用しやすく,行動しやすくなります(処理流暢性の効果)。
ウ:相手の欲求を考える
人を動かすには相手の根源的な欲求を理解する必要があります。

著者プロフィール
奥原 剛(おくはら つよし)
東京大学大学院 医学系研究科 医療コミュニケーション学分野 助教。
健康・医療にかかわる情報を,市民・患者にわかりやすく伝え,よりよい意思決定を促すための研究をしている。医療機関,健康保険組合,自治体等の医療従事者に対し,わかりやすく効果的な健康医療情報を作成するための研修をおこなっている。
一覧に戻る