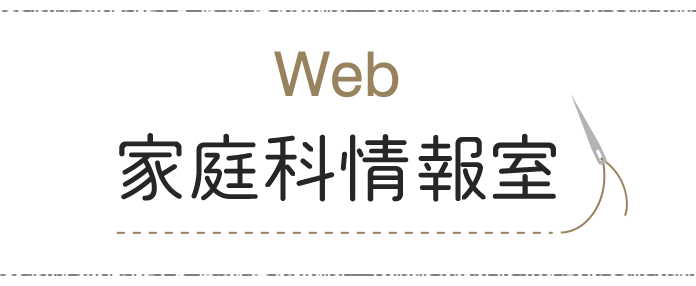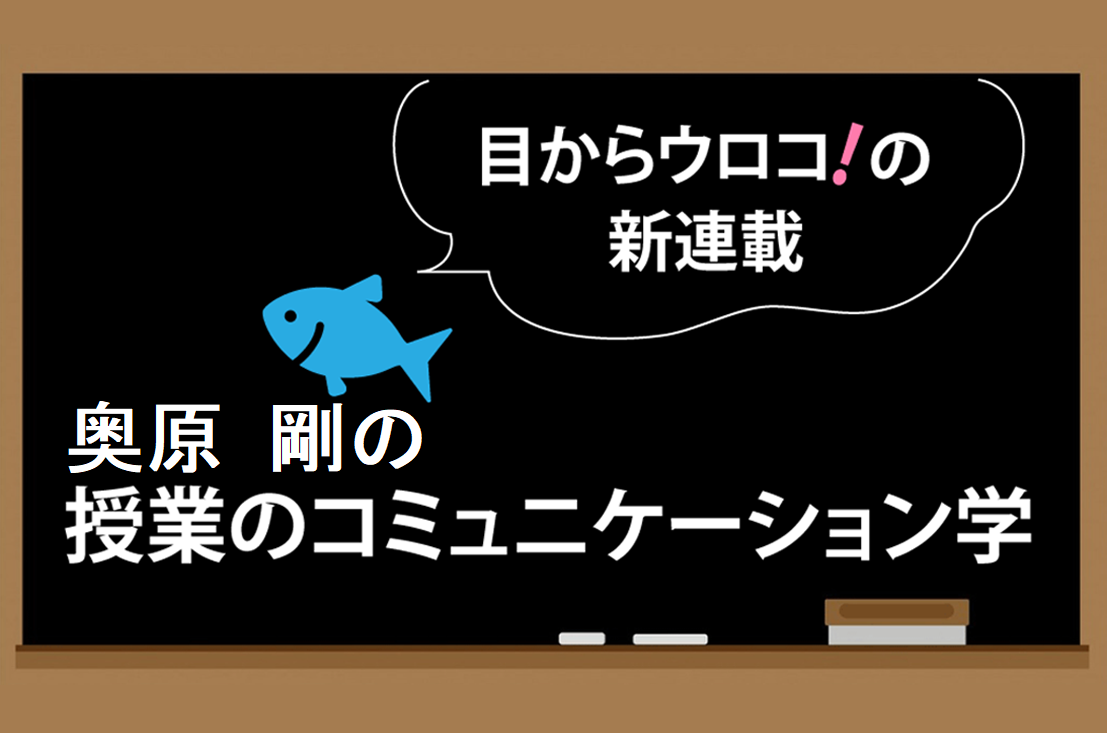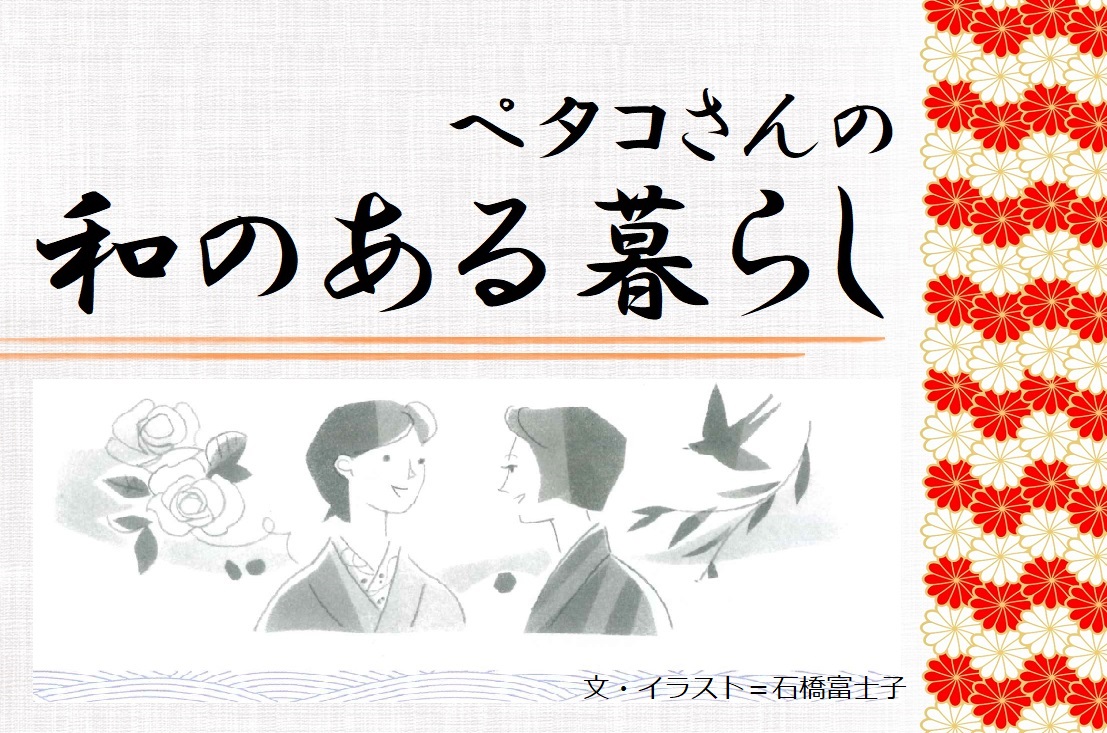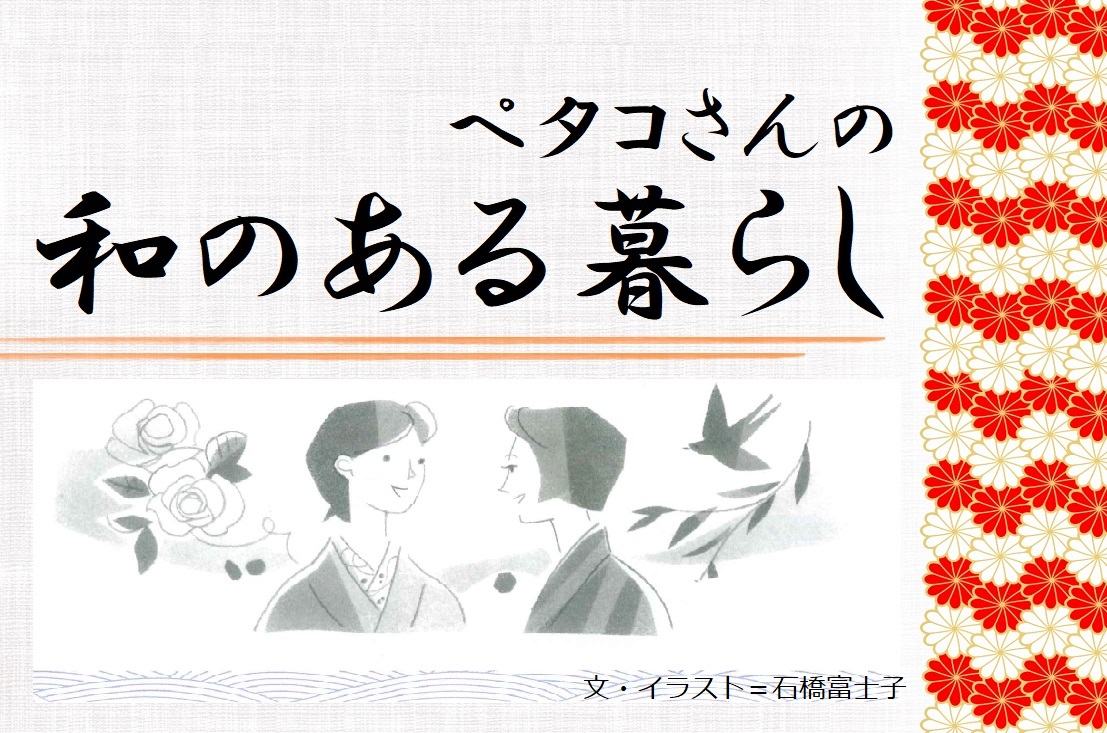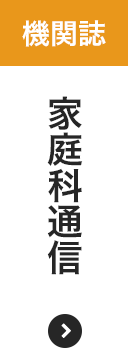授業のコミュニケーション学
[第1回] 教師の「知の呪縛」を解く
奥原 剛
- 2019.04.03
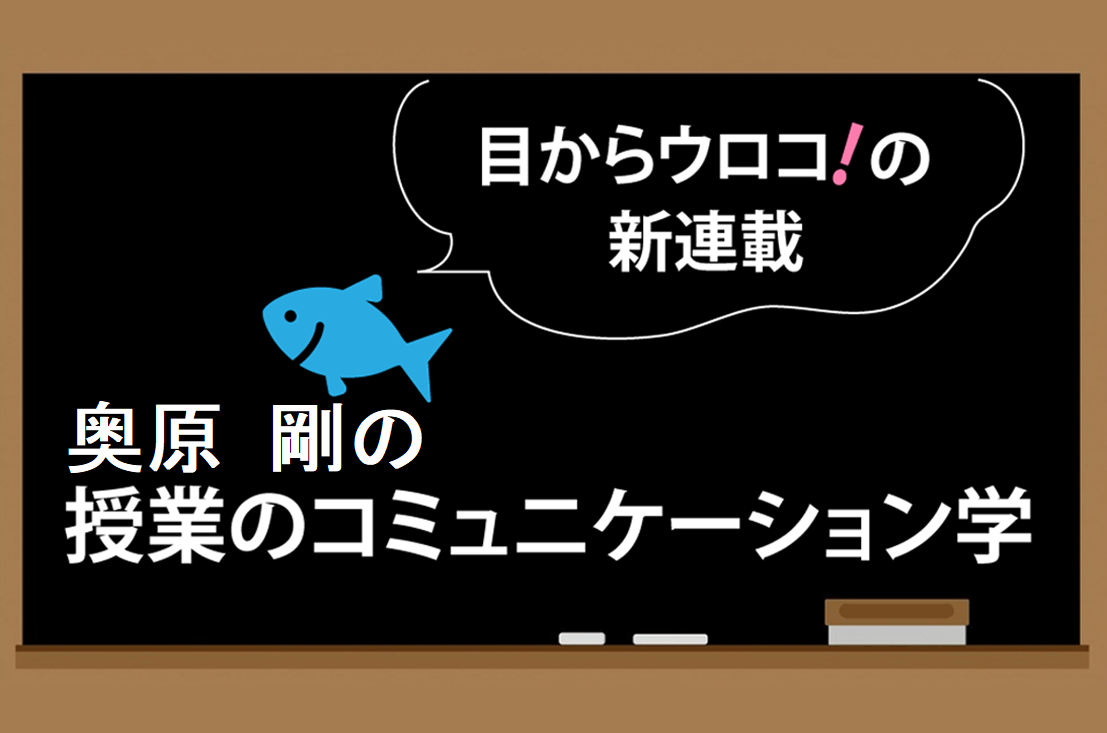
人間万事塞翁が馬と申します。何が禍福に転じるかわからないものです。最近の私は白髪が増え,額の髪の生え際も後退を始めました。しかし,老いは悪いことばかりではありません。良いこともあります。「ほら私,苦労してるのよ」と白髪を見せ大いに同情を買おうとして,「知らないわよ」と予想外のひんしゅくを買うことができます。電球が切れたら,スマートフォンのライトを広いおでこに向けて反射させ,暗い手元を照らすことだってできます。すごいでしょう。
最近,私の脳の劣化が伝染したのか,私のスマートフォンがたびたびフリーズするようになりました。私は「業務に支障をきたしてはいけないぞ」と自慢の気高く高邁な精神を発揮し,かつ「フリーズするのは君かスマホか,どっちかにしてくれ」との上司同僚からの熱いラブコールにもこたえ,先日,ついに携帯電話ショップを訪ねました。
ところが,営業の若い店員さんは,料金体系,スマホとセットの光回線のお得さ,オプションサービスなどをまくしたてます。私の劣化した脳には話が複雑すぎます。「もうどうでもいいや」と思考停止に陥り,買い替えずに帰宅しました。
しかし,店員さんを一方的に責めることはできないなあ,と思うのです――①店員さんはスマホを熟知している。②だから客の知識の少なさを想像できない。③かつ,店員さんは説明に慣れている。④だから客を置き去りにしてまくしたてる―― このような症状を,「知の呪縛」*1といいます。自分の知識の豊かさゆえに,相手の頭の中や心の中が見えなくなってしまうのです。知の呪縛は「先生」と呼ばれる人たちに多く見られます。知の呪縛ゆえに医師の話は患者にとってわかりにくく,研究者の話は市民にとって退屈です。
ここに,知の呪縛を体験するワークがあります*2。ペアまたはグループをつくります。1人がある図を見て,他のメンバーに口頭で図形を説明します。他のメンバーは口頭説明だけを頼りに,白紙に図形を描きます。そうすると,たいていは間違った図が完成します。授業と生徒の理解の間に,このようなギャップはないでしょうか。人に何かを説明するときは,「自分の頭の中に見えている絵が,相手にはまったく見えていない」という前提で説明することが大切です。このワークでは,説明者が,聞き手の理解を確認しながら,全体像の中の今どこを話しているかを説明する「メタ説明」(例:「上半分は以上です。次は下半分です」)をしながら進めると,聞き手の描く図形が正確になります。豊かな知識は宝ですが,知の呪縛にかかってしまうと,福が禍に転じてしまいます。気をつけたいものですね。
*1 Birch, S.A., &Bloom. P. (2007). The curse of knowledge in reasoning about false beliefs. Psychological Science, 18(5),382-386.
*2 佐藤浩一,中里拓也. (2012). 口頭説明の伝わりやすさの検討:説明者の経験と説明者-被説明者間のやりとりに着目して. 認知心理学研究, 10(1). 1-11.

▲左は出題の図形,右は口頭説明を受けて描いた図
著者プロフィール
奥原 剛(おくはら つよし)
東京大学大学院 医学系研究科 医療コミュニケーション学分野 助教。
健康・医療にかかわる情報を,市民・患者にわかりやすく伝え,よりよい意思決定を促すための研究をしている。医療機関,健康保険組合,自治体等の医療従事者に対し,わかりやすく効果的な健康医療情報を作成するための研修をおこなっている。
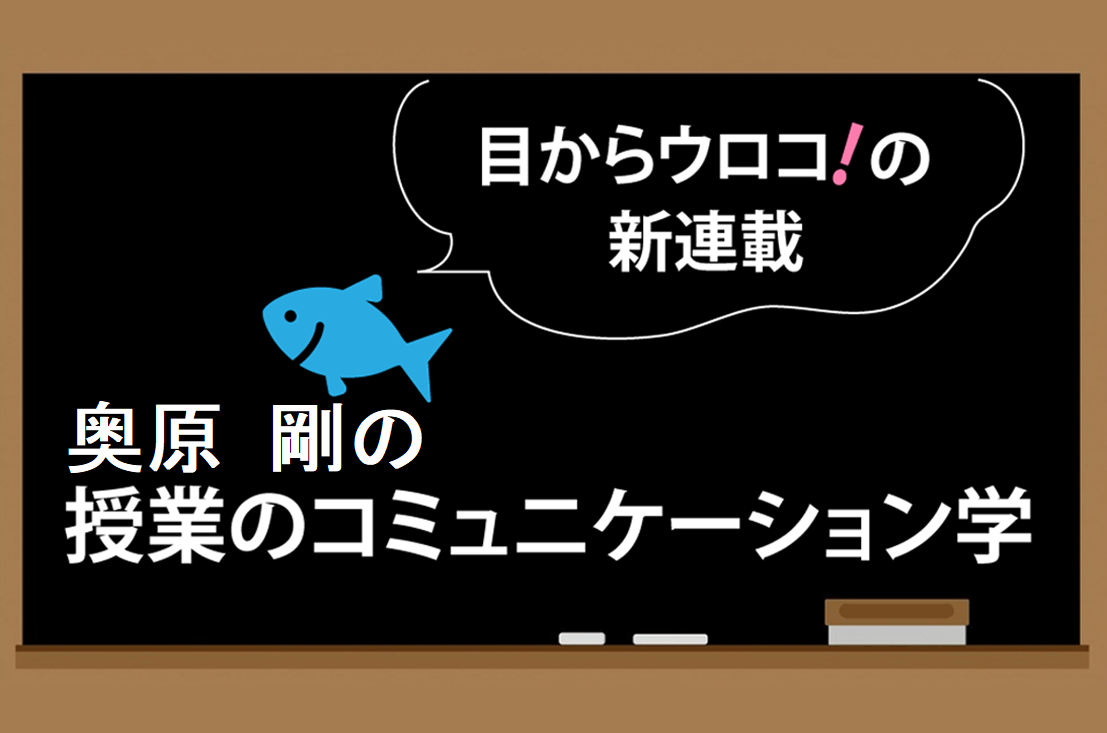
詳しくはこちら
一覧に戻る