人はなぜ走るのか?―賢く走るための理論と実践―
鍋倉賢治

東京マラソンの開催(2007年)を契機に「マラソンブーム」は各地に広がり、平日夜の皇居(東京)や大阪城周辺には、仕事を終えた多くのランナーが集まってきます。少々過熱気味ではあるのですが、以前は見向きもされなかったマラソンに多くの人が魅了されるのはなぜでしょうか。
僕が勤める筑波大学では、1992年からフルマラソンを走ることを目標とした体育「つくばマラソン」を開講しており、これまでに2,500名を超える学生達のマラソン挑戦を見届けてきました。彼らの大半は特別な運動経験のない普通の大学生です。
そのような学生にとっては、走ったときの身体の反応――マラソンを走るペースが思いのほか楽であること、しかし30分も走ると脚が痛くなることなど――、について体感することから始まり、やがて走る楽しさ・心地よさを知るようになります。しかし、授業の最終目標は「歩かず完走する」ことであり、そのためには42.195km、時間にして4~6時間も走り続ける必要があります。これが「途方もない壁」であることを、現実感をもって認識できるのも、10㎞程度なら気持ちよく走れるようになってからです。このようにして、学生は現状の自分とマラソンを走る課題とのギャップを少しずつ埋めながら、マラソンランナーへと成長してゆきます。
レース当日はお祭りのようなもので、同じ目的をもった老若男女、社会的属性も異なる多数のランナーに囲まれて気持ちよく走り出します。しかし、楽しいだけで終われないのもマラソンです。終盤になるにつれ身体の各部位から悲鳴が聞こえ始め、ここから本当のマラソンを味わうことになります。
準備に半年以上かけ、そして実際に苦しいレース(マラソン)と対峙して、一体何を得るのでしょうか。彼らのレポートを読み解くと、「マラソンへの挑戦」を通して学業や将来設計、人間関係などそれぞれが抱える問題と向き合い、解決や乗り越える勇気を得ていたことを窺い知ることができます。彼らの内面的成長を、自己効力感(自尊感情)という指標で評価したところ、面白い所見がみられました。
① 自己効力感はレースの前にすでに高まっていて、その向上は半年間のトレーニングに対する自己評価と関連する。
② そのため、レースで失敗し、歩いてしまった学生でも自己効力感は低下しない。
このような観点から、レースまでの過程こそが彼らにとってのマラソンであったことが理解できます。「マラソン完走」という大きな高い壁を乗り越えるために、「目標→計画→実践→評価・反省」というサイクルを半年間にわたり繰り返しながら自分自身をステップ・アップさせていく。この極めてシンプルでリアルな体験こそが、彼らを成長させるのです。
長期にわたりライフスタイルや行動規範を変えること、このことが一過性のイベントでは得られない「習慣化・生活化」を育み、そこに体育でマラソンを活用する意味があると考えています。利便性や効率化が求められる今の時代において、一見、非効率的で生産性のないマラソンは、喜怒哀楽を伴いながら自分と向き合い、五感を刺激する人間回帰に適したスポーツと言えるのではないでしょうか。
以下の書籍は、26年間継続してきたマラソン授業の経験や僕の研究室の学生達の研究成果をまとめたハウツー本です。マラソンを走ってみたい方はもちろん、マラソンや持久走の授業に苦心されている現場の先生方の参考になれば幸いです。
『保健体育教室』307号p.7より転載
■著者プロフィール
鍋倉賢治(なべくら よしはる)
筑波大学体育系教授
■著書
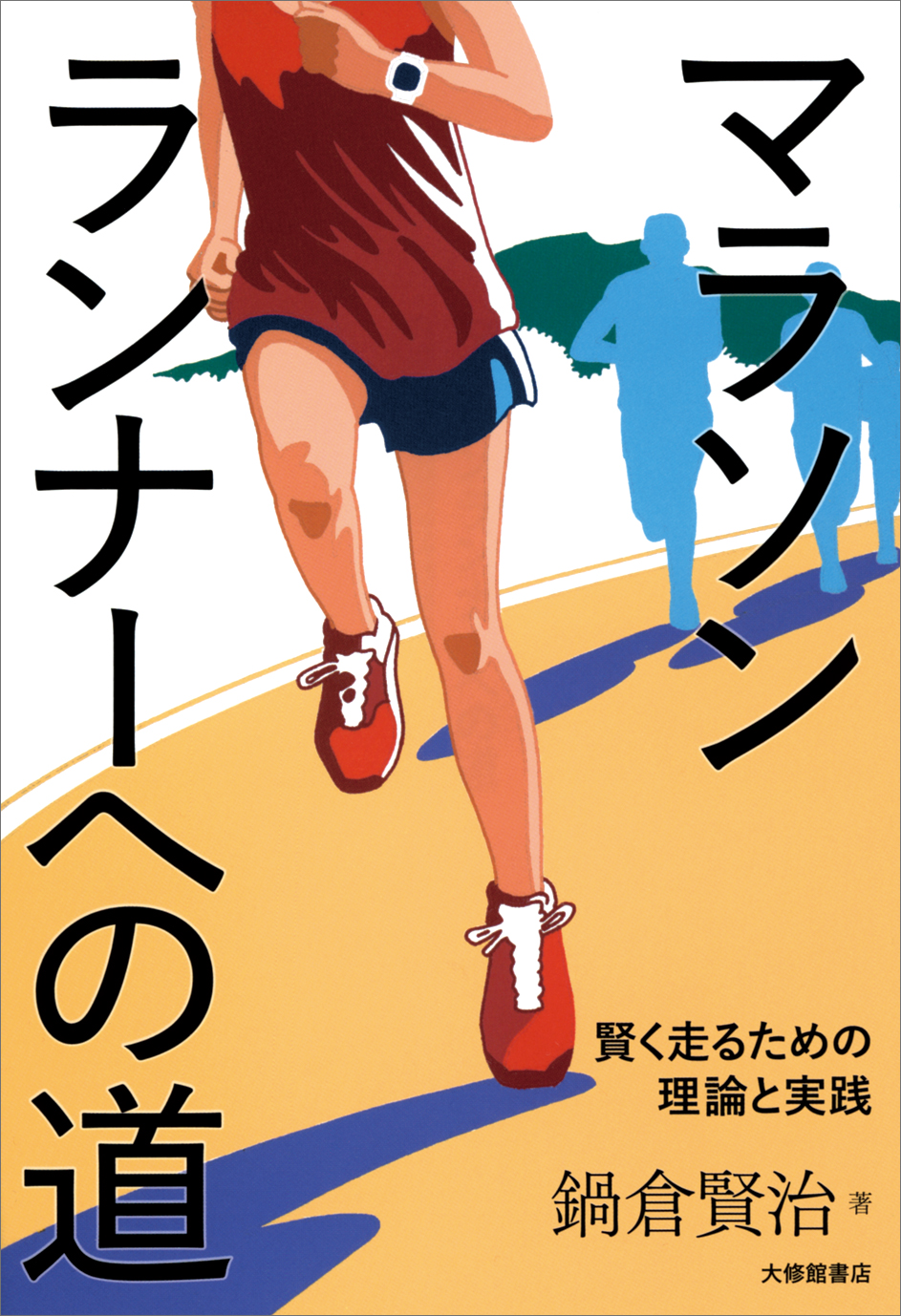
マラソンランナーへの道―賢く走るための理論と実践
鍋倉賢治 著
本体1,600円
https://www.taishukan.co.jp/book/b351984.html
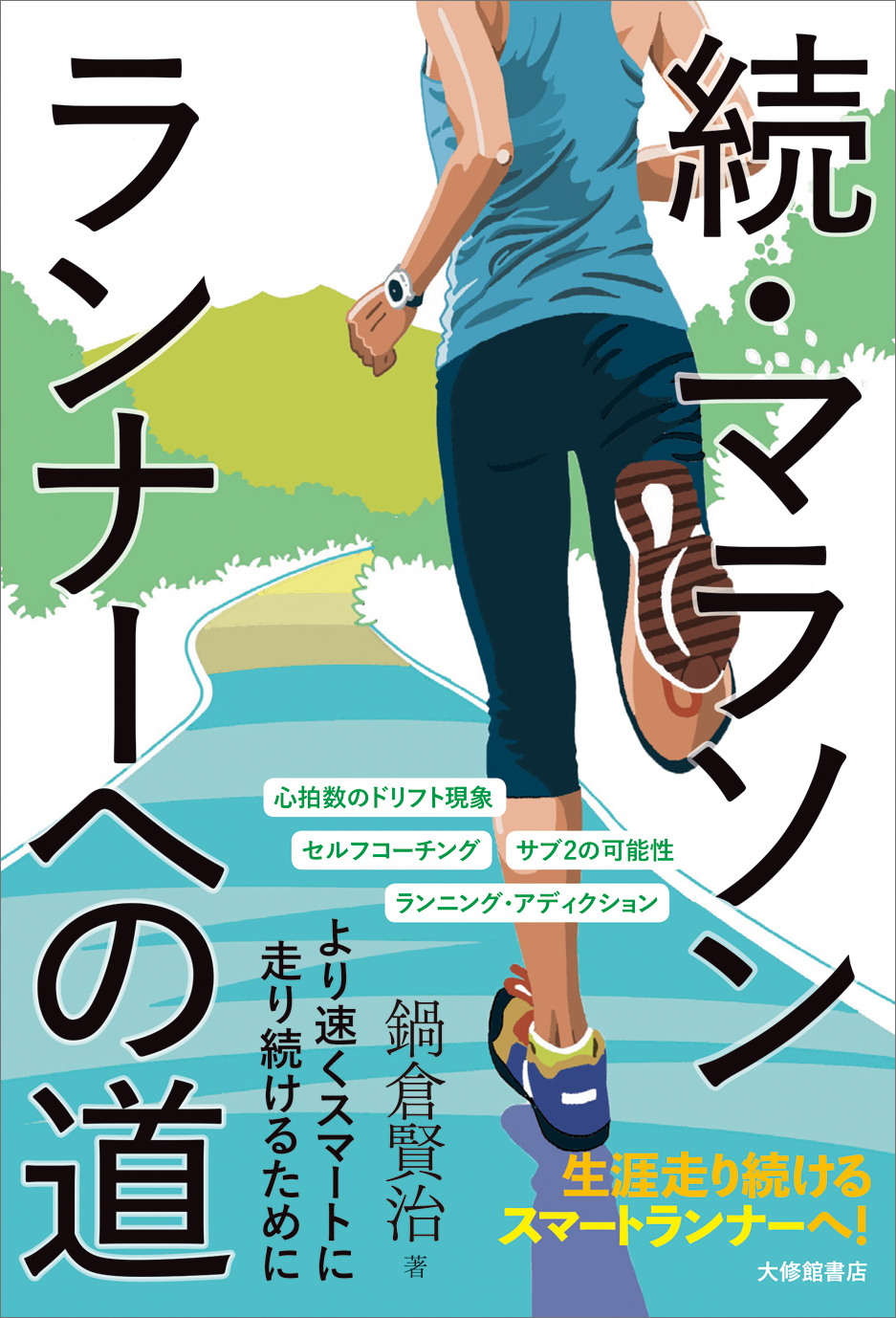
続・マラソンランナーへの道―より速くスマートに走り続けるために
鍋倉賢治[著]
1,600円
https://www.taishukan.co.jp/book/b379666.html
★大修館書店ランニング関連図書のご紹介★
試し読みや他のランニング本のチェックができる特設サイトをご用意しております。
以下のリンクより、ぜひご覧ください。
https://www.taishukan.co.jp/item/running/
一覧に戻る






