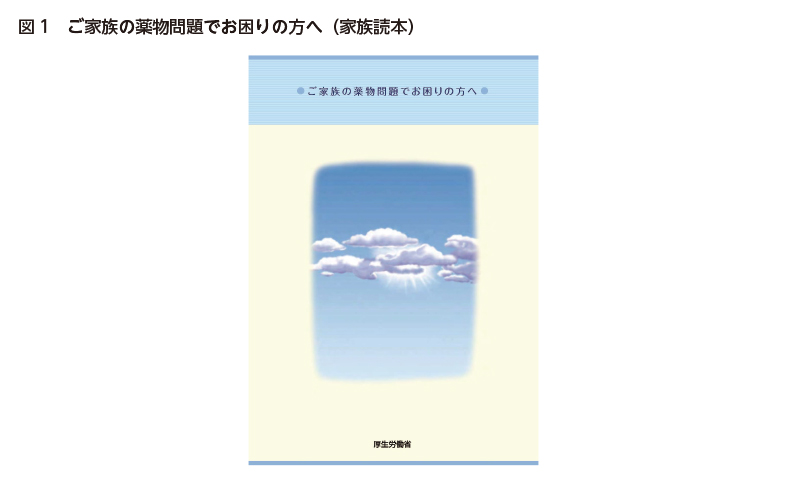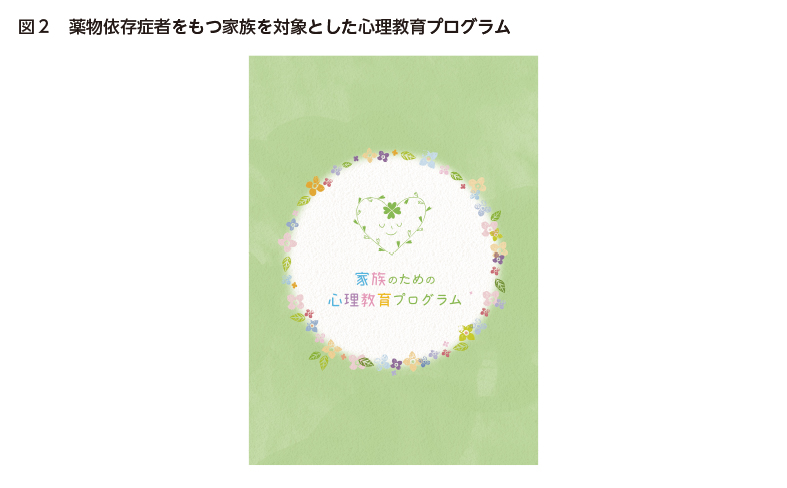「助けて」が言えない子どもたち―子どもたちに広がる市販薬の過量服薬(オーバードーズ)の理解と支援
⑥「助けて」が言えない子どもたちを支援する上でのポイント
嶋根卓也(国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部)
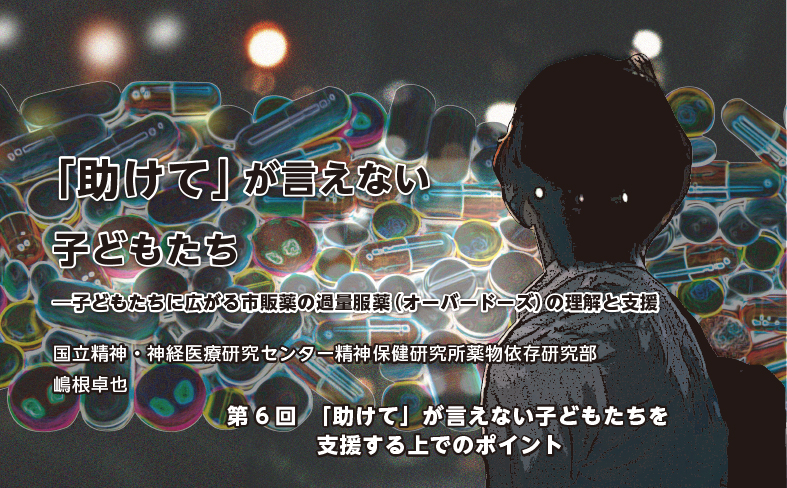
子どもたちの近くにいる教員が、子どもたちのオーバードーズの問題に気がつき、支援をする上で、どのようなことに注意すればよいでしょうか。最終回となる今回は、「助けて」が言えない子どもたちと関わる上での留意点について、特に養護教諭の場合を例にとってお話します。
オーバードーズしたことを言える安全な場所を作る
「助けて」が言えない子どもたちがSOSを出しやすくするために、私たち大人にはどのようなことが求められるでしょうか。
何よりもまず、オーバードーズしたことを咎められたりすることなく安心して安全に話せる場所を作っていくことがカギとなります。人目を気にせず話ができる保健室は、正直に話ができる安全な場所になり得ると思います。
オーバードーズの問題を抱える本人からしてみれば、オーバードーズしたことは本来隠しておきたい事実であり、教員に話すこと自体、勇気の必要な行動と言えます。つまり「オーバードーズしてしまった」という発言には、同時に「本当はやめたい」「助けて欲しい」というメッセージも含まれることを忘れないでください。
こうした発言を引き出すためには、子どもたちと養護教諭との信頼関係が重要となるのは言うまでもありません。オーバードーズしたことを頭ごなしに否定するのではなく、まずは正直に話してくれたことに「ありがとう」と感謝の気持ちを伝えつつ、そのオーバードーズの背後にあるつらい気持ちを理解していくことが求められます。薬物問題を抱えた子どもたちにとっては、「ダメ」と言わず、話を最後まで聞いてくれる味方が必要なのです。
サインを感じた時の声かけ
子どもたちとの関わりのなかで、子どもたちの「生きづらさ」に気づき、オーバードーズのサイン(第2回記事の「孤立する子どもたち」を参照してください)を感じたら、養護教諭は子どもたちにどのような声かけをしたらよいでしょうか。
これは自殺予防の分野で使われている方法ですが、一般的な事柄を伝えてから、核心的な質問をしていくという流れがよさそうです。「最近、市販薬などのオーバードーズに関するニュースが報道されているけど、◯◯さんの場合はどう?」「今、何か困っていることはない? よかったら話を聞かせてくれないかな」といった具合に声をかけ、困りごとを確認していくと、本音を引き出しやすくなるかもしれません。
もとより、薬物問題を抱えた人は、24時間ずっと「薬を使いたい」と思っているわけではありません。彼らの頭の中は、使いたい気持ちとやめたい気持ちが、常に綱引きしているような状態になっています。このつらい状況をやり過ごすには「飲むしかない」と追い詰められている場面もあれば、ふと「このままではいけないな」「できるならやめたいな」と考えることもあるのです。これは「両価性(アンビバレンス)」と呼ばれます。この両価性を意識しつつ、サインを感じたら積極的に声をかけていきましょう。
性急な変化を求めない
性急な変化を求めないという姿勢も重要なポイントです。「薬物をきっぱりやめさせること」が支援者の役割と考える人もいるかもしれませんが、断薬(薬を使わないこと)を強調しすぎることは、薬物問題を抱えた本人にとっては、時としてプレッシャーになることを忘れてはいけません。
オーバードーズの渦中にいる本人からしてみれば、オーバードーズは、つらい状況を乗り越え生きていくために必要な手段となっています。対人関係上のトラウマを抱えていることや、気分障害や発達障害といった他の精神障害を併存しているケースも少なくありません。このような場合、オーバードーズ自体が「自己治療」的な意味合いをもつため、オーバードーズを無理やりやめさせたり、力ずくで奪ったりすることで、メンタルヘルスの状態が前より悪化する可能性があります。
依存症の自助グループでは「今日1日」という考え方があります。これから先、薬物をやめられるかどうかはわかりませんが、「今日だけは仲間と共に使わないでいよう」という考え方です。この1日、1日の積み重ねが1週間、1か月、1年と薬物を使わない時間を延ばしていきます。養護教諭による支援に、この考え方を応用できないでしょうか。例えば、次に保健室で会うまでの間に、オーバードーズをしないでいるにはどのようなことができそうか、オーバードーズに代わる代替行動や対処方法を一緒に探していくといった関わりが有効かもしれません。
家族も当事者という視点
薬物問題を抱えた家族に対する支援も重要です。子どもの薬物問題を相談できず、「自分の育て方がいけなかったのではないか」と自らを責め、抱え込んでしまっている家族も少なくありません。家族には家族に対する支援が必要です。例えば、各自治体が設置している精神保健福祉センターでは、依存症家族を対象とする家族相談(個別)や、依存症のことを学ぶ家族教室、家族向けの心理教育プログラムを実施している施設もあります。一方、依存症家族同士が支え合い、回復を目指す自助グループとしての家族会という活動も全国に広がっています。
家族がこうした支援につながることで、依存症に対する理解が深まり、本人との関わり方を学び、家族自身が元気を取り戻すとともに、薬物問題を抱えた本人が治療や支援の場に登場しやすくなるというメリットがあります。
私たちのホームページでは、家族向けのパンフレットや、家族向けの心理教育プログラムなどを公開しています(図1・図2)。こうした資料を保健室に備えておくと、いざという時に役立つかもしれません。
おわりに
「助けて」が言えない子どもたち――子どもたちに広がる市販薬の過量服薬(オーバードーズ)の理解と支援――の連載は、今回で最終回となります。私は、教育講演で学校を訪問した際に養護教諭の先生とお会いする機会が結構あるのですが、子どもたちとの距離の取り方や、声かけが上手いなぁと感じる場面がこれまでに何度もありました。このような個人的な経験からも、子ども支援の最前線にいらっしゃる養護教諭の活躍に期待していますし、今回の連載が少しでも皆様のお役に立てたならば幸いです。
世間では、オーバードーズという問題行動そのものが注目されがちですが、「困った使い方をしている子どもは、同時に困っている子どもかもしれない」という視点でオーバードーズを捉えると、見える景色や子どもとの関わり方も変わってくるかもしれません。
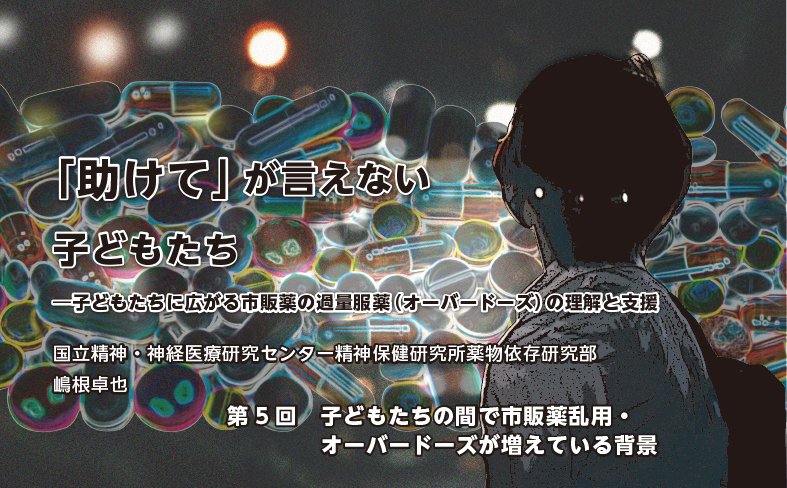
詳しくはこちら
一覧に戻る