座りすぎのリスク、知っていますか?
岡浩一朗
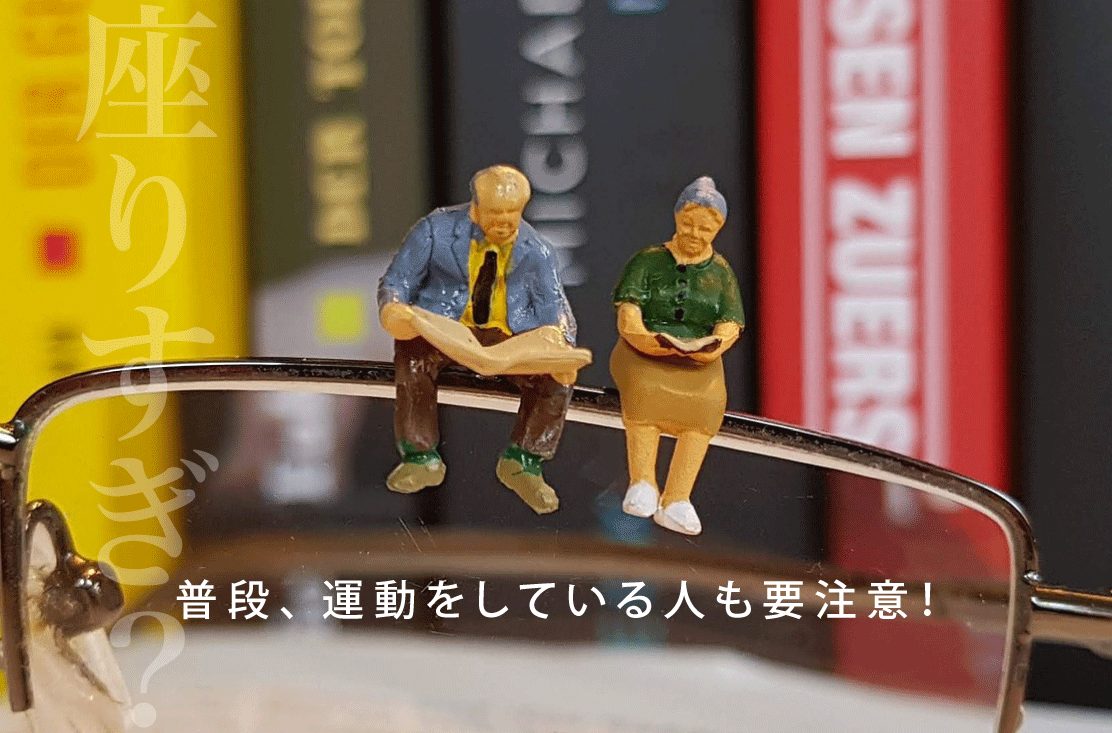
余暇におけるテレビ視聴やゲームなどの娯楽、仕事中の会議やパソコン使用によるデスクワーク、通勤時の自転車運転等の移動に伴う長時間の座位行動(座りすぎ)が、世界中の人々の日常生活全般に蔓延しています。近年、この「座りすぎ」がもたらす健康リスクが注目され、盛んに研究がおこなわれるようになってきました。座位行動とは、「座位、半臥位または臥位の状態でおこなわれるエネルギー消費量が1.5メッツ以下のすべての覚醒行動」と定義されています。
成人の一日覚醒時間における活動の内訳をみてみると、これまで健康づくりで注目されてきた中高強度の身体活動はわずか5%程度であり、大半の時間が低強度身体活動(35~40%)あるいは座位行動(55~60%)であることが知られています。低強度身体活動の多寡が多くの健康リスクと関連していることからもわかるように、いかにして座位行動に費やす時間を減らし、低強度身体活動時間を増加させることができるかが、公衆衛生上の重要な視点となっています。

座りすぎの健康影響について検討した先行研究のまとめによると、座りすぎが総死亡、心血管疾患死亡・罹患、がん死亡・罹患、糖尿病罹患に大きな影響を及ぼすことが明らかになっています。また、子どもを対象にした研究でも、座りすぎが肥満や体力だけでなく、認知機能や学業成績等へも悪影響を及ぼす可能性があることが指摘されつつあります。重要なポイントは、これら座りすぎの悪影響は、推奨される水準で身体活動を実施していたとしても認められる点です。最近は、余暇時間に運動はしているけれど、それ以外の時間に座りすぎている人のことを「アクティブ・カウチポテト」と呼ぶようにもなってきました。子どもの健全な発育発達や、働き盛りの人の生活習慣病予防、さらには高齢者の健康寿命延伸のためには、身体活動を増やすことに注力するだけでなく、いかにして座りすぎを減らしていくかも重要な鍵を握っていると言えます。
近年、座位と立位での作業姿勢を容易に切り替えることが可能なスタンディングデスクなどによる学校の教室やオフィスの環境整備により、子どもの授業中やデスクワーカーの仕事中の座位時間を減らす取り組みの成果も報告されるようになってきました。イギリスやオーストラリアでは、身体活動指針の中に座りすぎ対策に関する事項が取り上げられています。今後、日本でも同様の流れになっていくと思います。
日本でも、座りすぎの健康リスクについて検討した研究の成果が報告されるようになってきました。このテーマへの関心は徐々に高まってきており、最近ではテレビや新聞をはじめとするさまざまなメディアで特集が組まれるようになってきました。しかし、「座りすぎが問題だなんて、テレビをみて初めて知ったよ~」とおっしゃる方もまだまだ多く、十分に普及できていなことを痛感しています。
以下の書籍では、そのような方々に向けて、できる限りわかりやすく座りすぎの問題について解説したつもりです。今後も、多くの方々にこの問題について伝えていく努力を続けていきたいと思います。以下の書籍を手に取られた一人でも多くの方が、座りすぎの健康リスクに少しでも気づいていただき、まず自分のできることからで構わないので、座りすぎを解消するための対策を始めていただくキッカケにしていただけたらと思っています。
『保健体育教室』306号p.18より転載
著者プロフィール
岡 浩一朗 (おか こういちろう)
早稲田大学スポーツ科学学術院教授
著書

「座りすぎ」が寿命を縮める
岡浩一朗 著
本体1,400円
一覧に戻る






