スポーツ科学への誘い
友添秀則
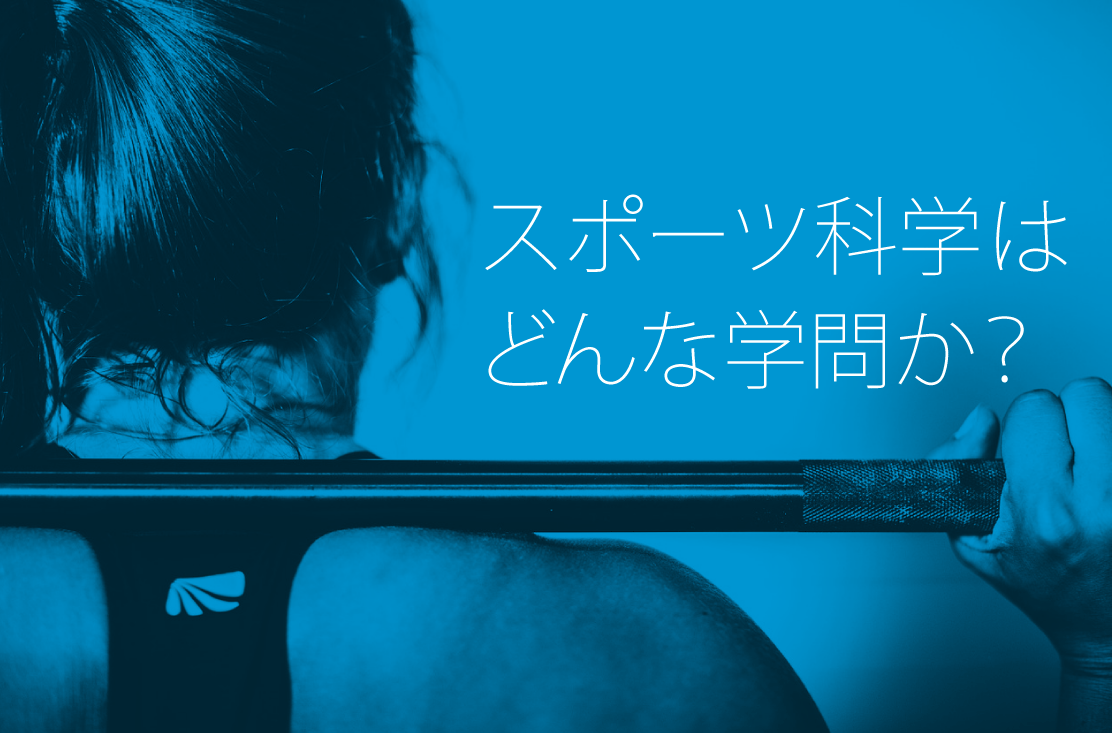
最近、「スポーツを科学する」ということがよく言われるようになりました。また近年、全国の大学にもスポーツ科学部やスポーツ科学科などのスポーツ科学を専攻できる学部や学科が多く生まれています。ここでは、スポーツを科学の対象とする「スポーツ科学」についてみてみたいと思います。
現代では社会の重要な一領域となったスポーツも、かつてはそれを「まじめな研究対象として扱うことは、スポーツ好きな英米研究者たちの間でさえ“Academic Taboo”であった」と言われてきました。スポーツを研究対象とすることに対する大きな抵抗は、スポーツの歴史と大いに関連があります。

今、私たちがスポーツと言っている近代スポーツは、元々、イギリスの民衆の間から生まれ、私立学校であるパブリックスクールで合理化・洗練化されてきたものです。当時民衆の間で行われたスポーツは賭けや賭博と結びついていました。また、街の通りやパブリックスクールで行われたスポーツも当初は、暴力に代表される粗暴性に満ち、肉体重視の反知識的性格が強いものであったとも言われています。このような理由から、スポーツは長い間、非学問的であるという印象をもたれてきました。
また他方で、20世紀に入って始まった国際的なスポーツ競技会の影響もあって、今度は、スポーツ科学は競技力向上を目的としたものに限定して考えられました。つまり、スポーツ医学に代表される、スポーツの自然科学分野に直結した領域だけとみなされるようになったのです。
本格的なスポーツ科学(sportwissenschaft、 sport science)の成立は、第二次大戦後、とくに1960年代半ば以降の欧米で始まります。この時期、欧米先進諸国では、国民のスポーツ需要の増大とともに、誰もがスポーツを日常的に楽しめるように、スポーツ・フォー・オール運動というものが起こります。この運動の展開とともに、生涯スポーツが国家的な重要施策として位置づけられ、スポーツが社会的認知を得るようになります。この時期を境に、文化的・社会的現象としてのスポーツが従来の体育や教育という枠組みを超え独自の研究対象として考えられるようになり、スポーツ科学が成立するようになります。
当初は、前述したように、スポーツ医学やスポーツ生理学に代表されるスポーツの自然科学的研究を中心に成立したスポーツ科学も、スポーツが社会にとって重要な一領域を占めるにしたがって、スポーツの人文科学的研究や社会科学的研究を包括した総合科学として発展してきました。なお、わが国では、このスポーツ科学に相当する学問領域を伝統的に、「体育学」や「体育科学」と呼んできました。
著者プロフィール
友添秀則 (ともぞえ ひでのり)
早稲田大学スポーツ科学学術院教授
一覧に戻る






