これからを生きる中高生に必要な性教育、考えてみませんか?
第1回 産婦人科医として現場で感じる日々のモヤモヤ①
重見大介(産婦人科専門医 日本医科大学非常勤講師)

みなさん、初めまして。産婦人科医の重見大介と申します。
このたび、このサイトで中高生に必要な性教育に関する連載を担当させていただくこととなりました。
貴重な機会をいただき、心より嬉しく思っております。
これまで、診療現場やオンライン相談を通じて、
「もっと早く受診してくれればここまで病気が悪化せず済んだはずなのに」
「性に関する知識をきちんと持っていないことで生じるトラブルをなくしたい」
「ポジティブな意味での性教育も若者には必要なはずなのに」
と思うことがたくさんありました。
私自身、学校にお声がけいただいて生徒向けや保護者向けの性教育講演をさせていただく機会があり、
学校現場での性教育にはたくさんの難しさや課題があることを理解しています。
ただ、やはり生徒さんと日々接する教職員のみなさんには
「これからを生きる中高生に必要な性教育」が何かをぜひ知っておいていただく、
産婦人科医としての視点を交えながら、連載記事としてお伝えして参ります。
産婦人科医として経験してきた事例の紹介、今の時代に中学・高校で必要な性教育、
学校でお話しした際の経験談、学校で適切に性教育を広げていくためには何が必要か、
などを書いていく予定です。
初回は「産婦人科医として診療現場で感じる日々のモヤモヤ」です。
診療現場で「モヤモヤ」してしまう事例
まずは、産婦人科の診療現場でモヤモヤを感じた事例をいくつか紹介します。
「こういうことが現実にあるんだな」ということを、少しでも想像してみていただければ幸いです。
(実際の経験をベースとしながら、少しデフォルメしています)
ケース1:緊急避妊薬をめぐる親子の動揺
深夜、制服姿の中学生と同伴の母親が来院しました。
「娘がネットで調べて72時間以内なら間に合うと知った」と切迫した表情でした。
話を聞いていくと、避妊のためにコンドームは使っていたものの、
コンドームが途中で外れてしまった場合の対処法や、
緊急避妊薬の仕組み、服薬後の副作用などについてはまったく知らず、
母親も「なんでそんなことも知らずに性行為なんてしたのよ」と戸惑いながら娘さんを叱責していました。
ケース2:月経痛をひたすら我慢していた高校生
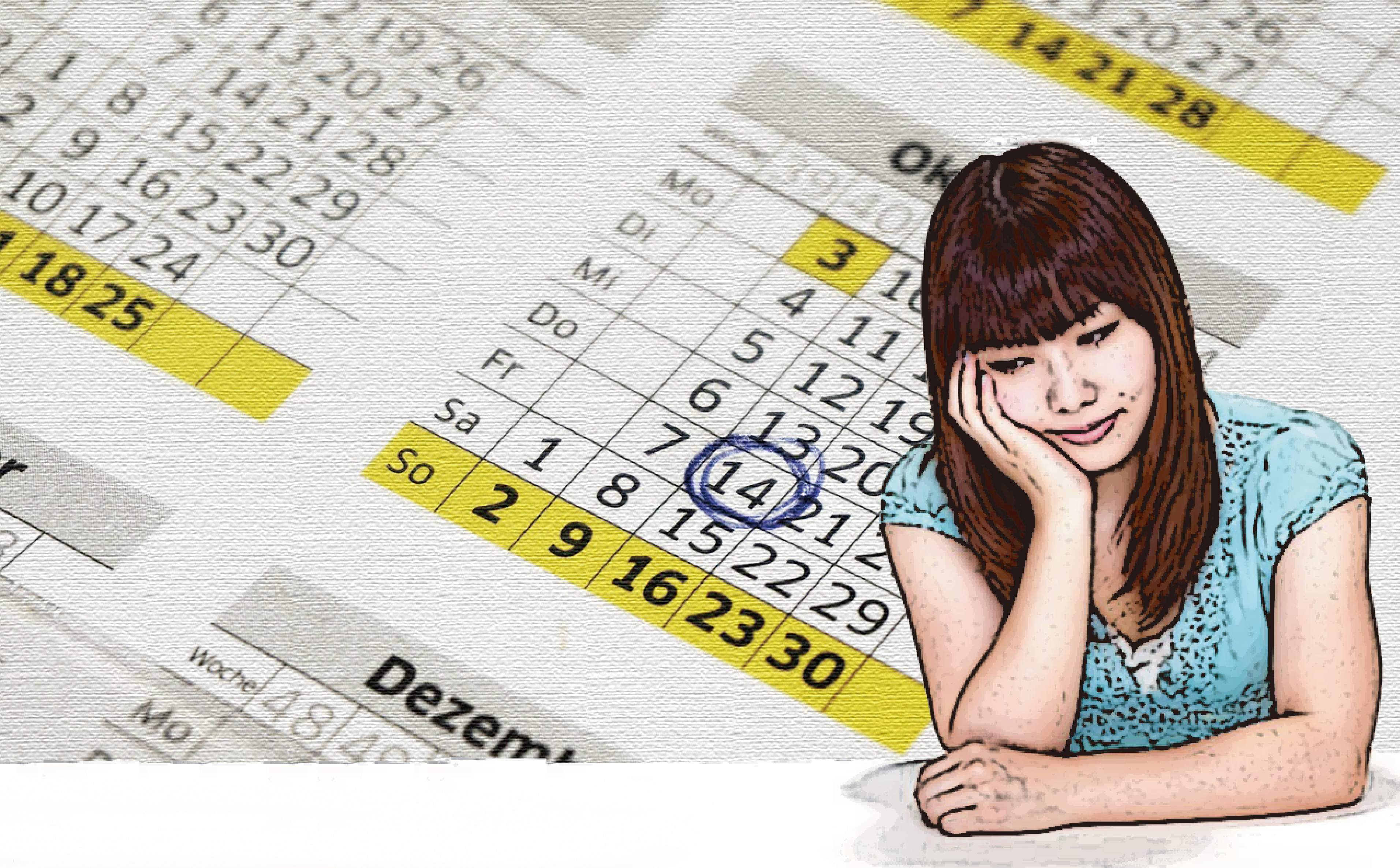
月経痛がひどく、市販の鎮痛薬を服用するも頻繁に保健室を訪れ、授業を休みがちな高校生。
保健室の養護教諭が受診を強く勧め、初めて母親と婦人科を受診しました。
問診と診察(お腹からの触診とエコー検査)をすると、子宮内膜症の疑いもあり、
鎮痛薬だけで凌ぐのは好ましくない状況だと考えられました。
彼女の日記には
「友達は生理痛がそんなに気にならないって言ってたし、担任の先生にも授業をサボるなと言われたので、
なるべく我慢しよう」
と書かれていました。
ケース3:過剰なダイエットで無月経に
高校2年生の女性。SNSにあふれる「細い=綺麗」という投稿に影響され、
1日600kcal程度に食事を制限し、激しいランニングを毎日続けていました。
2か月で8kg減量した頃から月経が止まり、そのまま8か月間も無月経となっていました。
体重減少と倦怠感を訴えて来院した際、骨密度の低下と高度の貧血が判明しました。
こうした生徒さんの不安や恐怖、大変さ、将来への影響を想像すると、胸が痛くなります。
実際、学校や家庭で出会った性に関する情報は限られ、だいぶ偏った知識を持ってしまっていたことが多い印象です。
こうした“性について知らないことによる不安や恐怖、大変さ”は、診療現場でも日常的に存在しています。
浮かび上がる3つのギャップ
では、なぜこのような事例が生じてしまうのでしょうか。
考える参考として、「3つのギャップ」を挙げてみます。
1)情報源ギャップ
生徒さんの主な情報源は友人・SNS・動画サイトであり、
検索上位には商業広告や体験談が並び、「適切な情報」を得るのが難しい状況にあります。
男子の場合、アダルト動画で誤った知識を得てしまうことも多いでしょう。
2)相談先ギャップ
性はセンシティブな話題であり、信頼できる人にしかなかなか相談できないものです。
家庭でそういった話を聞けない・相談ができない環境だと、
保健室頼みになるか、トラブルになって初めて発覚することになってしまいます。
3)価値観ギャップ
「生理痛は我慢するもの」
「中高生で産婦人科受診なんて恥ずかしい」
「好きなら性行為をして当然」など、
ジェンダーバイアスや勝手な思い込みは今も根強く存在しています。
終わりに
いかがだったでしょうか。
ショッキングな事例もあったかと思いますが、このようなことを少しでも減らすためには、
性教育が大きな役目を担うはずだと私は考えています。
次回は「産婦人科医としてオンライン相談・SNSで感じる日々のモヤモヤ」をテーマに、
より水面下の声やSNSに広がる誤解を紹介します。

詳しくはこちら
一覧に戻る






