歯車がうまく回らなくなったアスリートのメンタルケア
今井恭子(早稲田大学スポーツ科学学術院 非常勤講師)
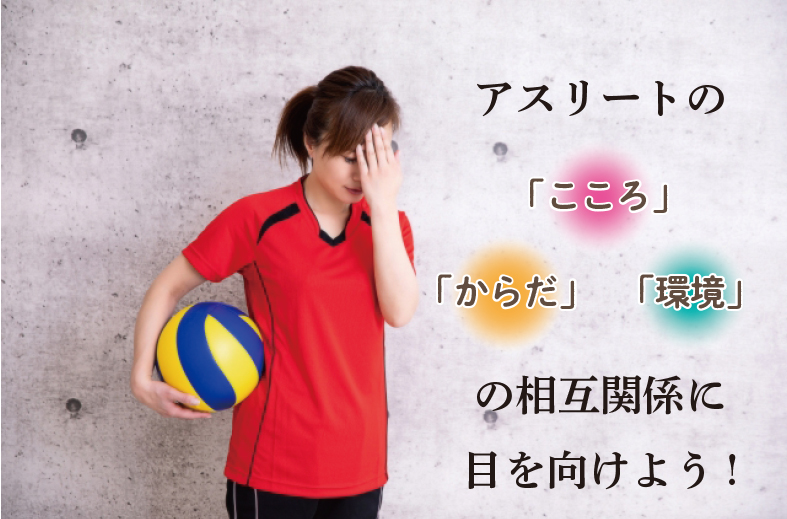
(写真:写真ACよりFineGraphicsさんによる)
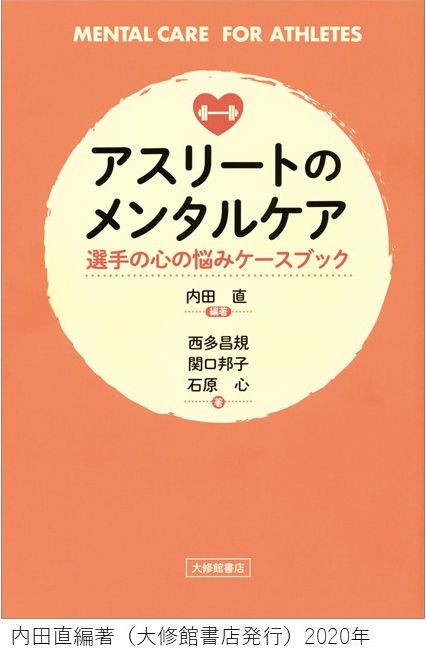 心のトラブルは,身体的な怪我や病気とくらべて気づきにくく,対応に迷う方も多いのではないでしょうか。本書(『アスリートのメンタルケア-選手の心の悩みケースブック』)では,中高生から大学生世代のアスリートに散見されるメンタル不調について,12の症例を用いてわかりやすく解説されています。
心のトラブルは,身体的な怪我や病気とくらべて気づきにくく,対応に迷う方も多いのではないでしょうか。本書(『アスリートのメンタルケア-選手の心の悩みケースブック』)では,中高生から大学生世代のアスリートに散見されるメンタル不調について,12の症例を用いてわかりやすく解説されています。
第1~3章では,思春期の悩み,競技環境の変化を伴う新人選手としての悩み,引退など,競技者の多くが通過する局面の中で見過ごされがちな問題に関して,対処の方向性が示されています。第4~5章では,過負荷な競技活動によってもたらされる心身の衰弱症状に関する問題について,予防と回復に向けた判断材料を確認できます。つづく第6~9章では,ADHD,摂食障害,性別違和,イップスといった対処に迷うことが多い事例について,経験や主観だけに頼ることなく,客観的に状況を理解する一助となるでしょう。第10~11章では,ストレスに関連する症候群を取り上げ,医学的な所見を得る重要性とともに,メンタルヘルスとの関わりについて触れられています。最終章では,選手のみならず,スタッフを含めてメンタルヘルスの維持・向上に努めることが,健全な競技環境の醸成につながるという提言がなされています。
いずれの症例からも,「こころ」「からだ」「環境」の3つが相互に関連していることが読み取れることと思います。周囲の大人が,心身の発達,食事や睡眠,環境など様々な背景要因に“アンテナを張っておく”ことは,選手たちが道筋を手繰り寄せる助けとなります。
大学で学生アスリートの心理相談を行っていると,中学や高校での競技経験が如実に影響を及ぼし,監督,コーチ,先生方の言動が,善悪に関わらず,深く心に刻まれているケースに多く出会います。身近な大人や先生に,心の不調を自ら発信する学生もいれば,弱さの象徴とみられる,メンバーから外されるなどの不安から隠しておきたい学生もいます。自分でも何が起きているのかわからない時もあるでしょう。結果的に,悩みが開示されずに「え,あの子がそんなに困っていたのか」と後から気づかされる,あるいは全く知らないまま次の道へと送り出していることは珍しくありません。
折しも新型コロナウィルスが猛威をふるい,あって当然と思っていた部活動がなくなる,大会が中止されるという前代未聞の渦中に学生たちは身を置いています。編著者である内田直医師が「メンタルの不調を呈しているアスリートの問題の核心をつかみ,再び高い競技力を発揮できる方向に導いていただける参考になれば」と述べているように,目標を失ったことに派生する心の不調に備え,教科教育とは異なるスポーツ現場ならではのご指導に際し,参照枠として手元に置いて頂きたい一冊です。
(『英語教育』2020年9月号「大修館の一冊」より一部修正して転載)
一覧に戻る






