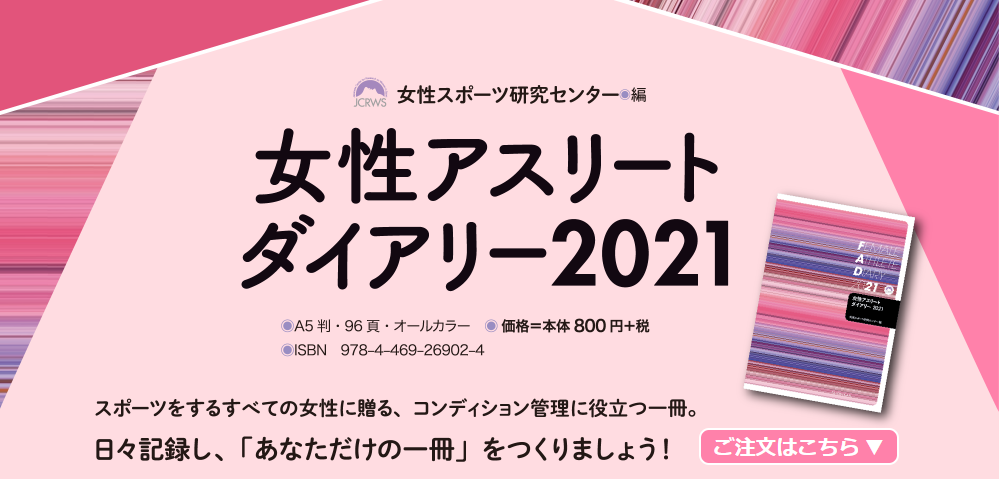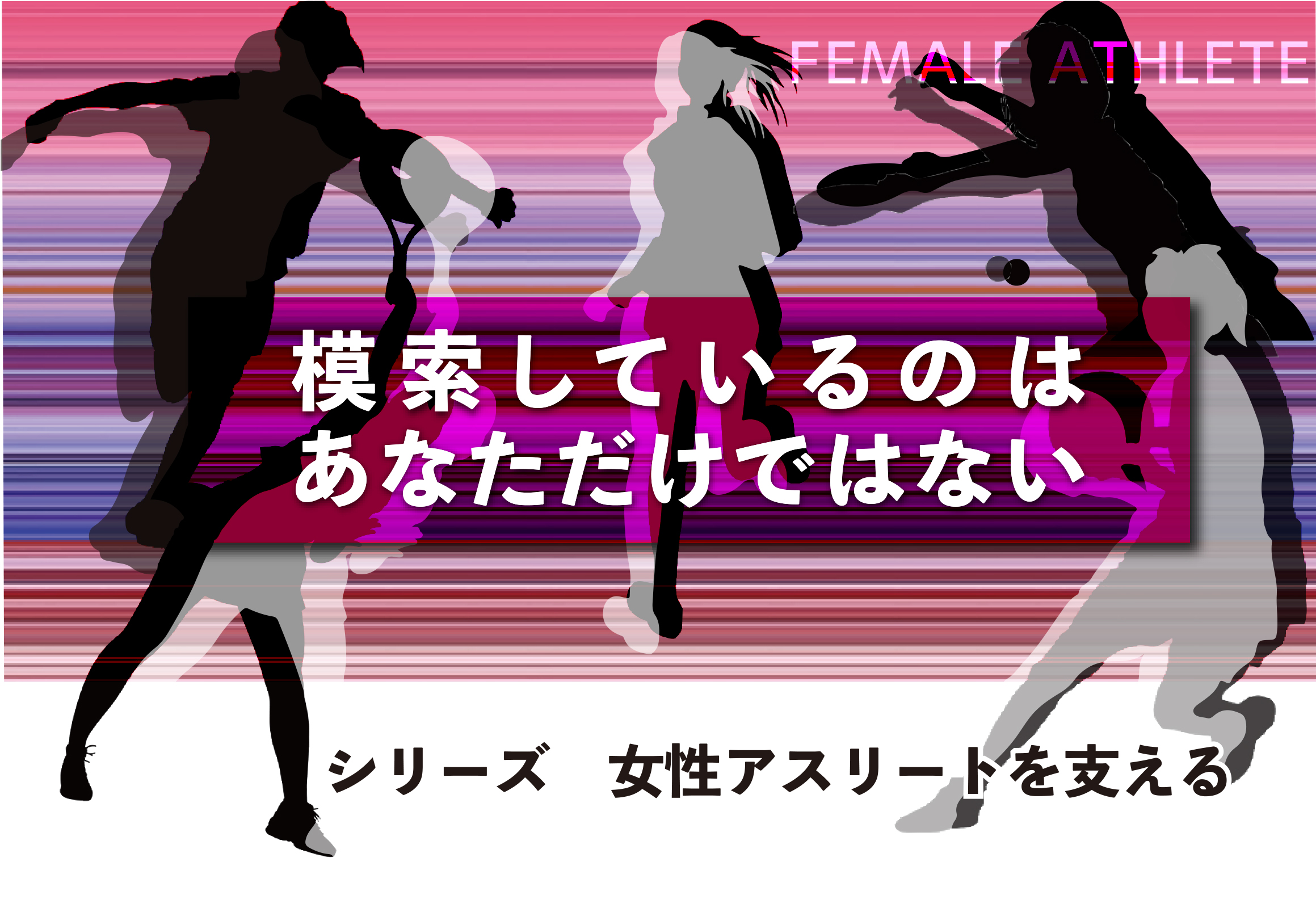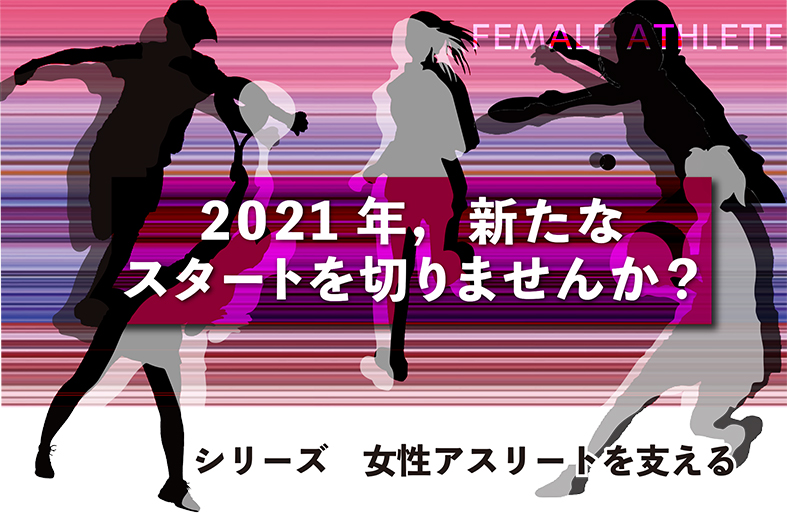女性アスリートを支える
第2回 女性アスリートの健康を考えるためのヒント
- 2020.12.14
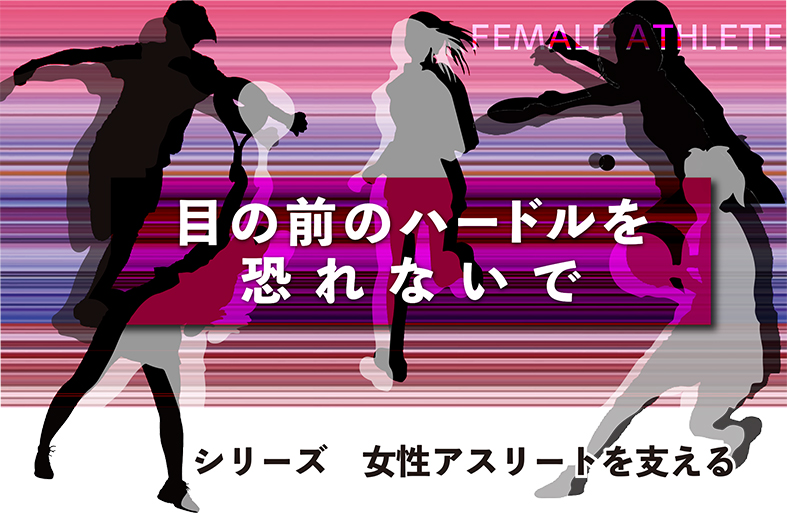
このシリーズでは「利用可能エネルギー不足」「無月経」「骨粗しょう症」など,女性がスポーツをする中で起こりうる健康課題についての『向き合い方・乗り越え方』を提言していきます。(全3回)
第2回「女性アスリートの健康のためのヒント」

「女性アスリートの健康課題」の現在地
「ハードルがある」の次のフェーズへ
「女性アスリートが無月経や疲労骨折になりやすい」という現状は, 20~30年前から大きくは変わりませんが,「そういうハードルがある」ということが科学的にわかってきたのはこの間の前進だと思います。ただ,そのハードルの「乗り越え方」が発展したか,浸透しているかといえばしていない。そこが足踏みしている部分であり,いま大事なことは,ハードルの「乗り越え方」を広めることだと思っています。
ハードルをどう乗り越える?
「ファーストステップ」(=対処の一歩目)が見えにくいことが一番の問題ですが,その解決に欠かせないのが,「情報」と「保護者,指導者など周囲の人」です。
インターネット等ですぐに調べられる時代なので,ファーストステップとなり得る情報があることが大事。なので,私自身も積極的に情報発信するようにしています。
また,情報を得た本人が,そこから次のステップ(たとえば受診など)に踏み出せるかと言えばなかなか難しい面もあるので,周囲の人が後押しとして機能することも必要です。そのためには,まずはより多くの大人に,女性アスリートの健康課題に関する知識が浸透することが大事だと思っています。

「健康課題」への向き合い方 -無月経を例に-
実際,どう困るの?
たとえば,「無月経で困る」ということに実感がわかないという声を聞くことがあります。アスリートへの調査などでも「ナプキンを買わなくていい」「煩わしくなくていい」という回答があるくらいなんです。
たしかに,無月経になってすぐに困る人はいません。しかし,無月経になるのにはいくつかの理由があって,どの理由なのかがその後の人生に重要な意味を持つんです。
「悪性の腫瘍」「染色体の異常」「エネルギー不足」など無月経の理由を放っておくと,前者2つの場合は,子どもがほしいと思ったときにまずはその治療が必要だったりします。
「エネルギー不足」の場合も,たとえば「試合でいい結果を出したい」アスリートであれば,骨が折れたりやる気を失ったり貧血になったりすることで「本当にしたいスポーツ」からどんどん離れていってしまうことになります。自分の努力,時間,お金など注いでいるすべてが,「エネルギー不足」によって無駄になってしまう。
こう聞くと,無月経になって放っておくことのリスクを実感してもらえたのではないでしょうか。

身体からのシグナルをポジティブに捉える
無月経は「シグナル」なので,それに正しく対応することが大事です。中には「無月経になった自分が悪い」と感じて,周囲の人にも言えないという人もいますが,あなたが悪いわけではありません。身体が「危険だよ」と教えてくれているだけなので,「教えてくれてありがとう」「よくぞ知らせてくれました」という感覚でいいんです。シグナルがあって,そのシグナルに対応するからこそ,健康に次に進めると思います。
「健康課題」とつきあうヒント
「今日の練習」と「今日食べる物」はセット
練習が終わって帰り際の学生に「今日は何を食べるの?」と聞くことがよくあります。「まだ考えていません」という答えがくると,「こんなにいい練習をしたのに,45分以内にご飯を食べないと,その疲労がとれずにどんどんマイナスになるだけだよ」と返しています。「今日はいい練習をするから,早く家に帰ってこれを食べよう!」と練習前に考えておくことが理想ですね。
「どんな練習をするのか」と「何を食べるか」は同じくらい大事。練習をして,ご飯もお風呂も終わって睡眠も含めて,はじめて身体にとってプラスになるので。

本能にしたがい,自分に合うことを選択する
身体の状態や練習の振り返りについても私はよく学生に聞くので,学生はその質問に答えるために「今日の調子はどうだったのか」「私はいま何が食べたいのか」と一度考えなければなりません。実は,その作業がとても大事。自分がどういう状態で今どうしたいのかを自問自答し続けていると,だんだんと自分に合ったものを選択できるようになってくるんです。
たとえば夏場の練習でも「他の人はやっているけど自分はもう無理,熱中症で倒れそう」と感じれば途中でやめていいと考えています。人によって限界は異なるので,身を守るためには大事なこと。その判断ができるように,ふだんからセルフマネジメントを意識させています。
笑顔で食べ物の話をする
体重などを気にしすぎると,本来は楽しいはずの食べ物の話も,どこか憂鬱なものになってしまいますよね。それを避けたくて,学生たちとは自然にわいわいと話す中で食事のことに触れるようにしています。
たとえば,差し入れでいただいたアサリを,学生たちが分けて持って帰るとなったときには「アサリってどう調理するの?」という話になって,「砂抜きするんだよ」「味噌汁に入れてもいいよね」「バターで炒めるだけで開くし」などという会話が生まれます。
ほかにも「今日はいい練習をしたからお肉だね」とか「帰ったら牛乳を飲むんだよ」などと話すと,帰りがけの学生たちからも「今日はなに食べよう」「一緒に食べに行く?」などという会話が聞こえてくるんです。
食べ物がそこにあると具体的な話になるし,実学のほうが頭に入りますよね。「これは食べてはダメ」というような話はしない,これがポイントです。

「健康課題」を記録する
書き残すことで見えてくる
「知らないうちに慢性疲労になっていました」とよく言われますが,スポーツ活動や体調の変化を記録していて見返してみたとしたら,休んでいない自分に気づくと思います。周囲の人も,時には自分でさえ気づかないことも,書き残していることで気づくことができます。
「毎日練習する=毎日自分の身体のことを知ることができる」ことだと思います。運動の記録は,当然ですが,運動をしていない人はつけることができません。日々の活動の思い出,歩んできたプロセス,やってきたことの証を残すことはとても大事です。
そのときの感覚を1行でもひと言でも書き残しておけば,何年か経っても役立つと思います。振り返って文字にするというのは心を整えるのにも大事です。らくがきみたいに,ノートの隅にちょこっと書いてあることはなぜか見返しますよね。そういうのを大切にしてもらいたいです。
(11月18日取材,企画・編集=大修館書店編集部,写真=ご本人よりご提供)
第3回「スポーツを楽しむ・頑張る女性に届けたいこの一冊」はこちら▼
鯉川先生にもご監修いただいた『女性アスリートダイアリー2021』の詳細はこちらをクリック↓
一覧に戻る