健康・医療に関わる賢い選択のために知っておきたいコツ
大野智(島根大学医学部附属病院臨床研究センター)

この連載のテーマであるヘルスリテラシーには,健康・医療に関する情報を「入手」「理解」「評価」「活用」するための知識や能力が求められます。今回は,まとめとして,それぞれの場面でのポイントやコツを整理してみます。
入手
さまざまな情報源から正確な情報を探し出す能力です。
健康・医療に関する情報は,普段の日常生活においてはテレビから,病気やけがをしたときはインターネットから収集しているケースが多いようです。しかし,それらの情報には医学的に不正確なものも含まれており,玉石混交であるのが実情です。そのため「正確な情報」をふるい分ける力が求められます。正確な情報とは,「人を対象とした臨床研究(コホート研究やランダム化比較試験等)の結果に基づく情報」です。それ以外の,具体的な研究に基づかない経験談や権威者の意見,細胞・動物実験の結果などは,無視するか話半分ぐらいに受け止めておけば十分です。
このように聞くと簡単そうに思えるかもしれませんが,人は誰しも,病気で不安なときなどは,必死になって必要以上に情報を集めようとしがちです。情報は多ければ多いほどよいわけではありません。情報の荒波に飲み込まれないようにするためには,情報の断捨離や断食が必要となるときがあることを頭の片隅に入れておいてください。
理解
情報を医学的な視点で正確に理解する能力です。
正確な情報とは,人を対象とした臨床研究の結果であることは先に述べたとおりです。もう少し具体的に言うと,「どのような症状・病気の人が」,「どのような治療をおこなって」,「どれくらいの効果が得られたのか」を整理して読み解いていくことになります。
しかし,世の中には,数字のトリックなどを使って見栄えをよくしているケースなど,“落とし穴”が潜んでいることがあります。さらに,マーケティングの名の下,「心理効果」を巧みに使って,患者や消費者にアピールしているケースもあります。健康食品・器具や化粧品などの広告やCMでよく使われている心理効果や数字のトリックについて,過去の記事で具体的に解説をしていますので参考にしてみてください。
◎情報の理解を妨害する心理効果を知っていますか?[2020.6.2]
https://www.taishukan.co.jp/hotai/media/blog/?act=detail&id=236
評価
情報が信頼できるものかどうか批判的に吟味する能力です。
具体的には,入手した情報が,「薬の効果ばかり強調されていて,副作用のことやコストのことが言及されていない」など,情報として偏りがないか,いわば一歩引いた第三者の目で見極めていく作業です。また,臨床研究の結果に基づく情報であっても,そもそも自分の病気のことに当てはまるのかどうかについても注意深く確認しておく必要があります。例えば,胃がんを対象とした臨床研究の結果は,肺がんや大腸がんにそのまま当てはまるわけではありません。
もうひとつ健康・医療に関する情報で覚えておいてほしい大切なことがあります。人を対象とした臨床研究で有効性が証明された治療であっても,全員に効果が得られるわけではありません。これを「医療の不確実性」と言います。今後,いくら医学が進歩したとしても,医療の不確実性はつきまとってきます。つまり,「正確な情報」であっても,そこには不確実な要素が伴っており,情報を評価(批判的吟味)する能力が問われてくる場面でもあります。
活用
情報をもとに決断・行動の意思決定をおこなう能力です。
意思決定プロセスのモデルとして,医療現場で普及している「科学的根拠に基づいた医療」があります。「科学的根拠」,言い換えると「正確な情報」は意思決定における判断材料になることに間違いはありません。しかしそれ以外にも,「利用できる費用・時間・労力(資源)」,「自分がしたいことや望むこと(好み・価値観)」などによって選択が変わってくることがあります。身近な例として,「降水確率30%」という数字(正確な情報)に対して,“傘を持っていく”あるいは“傘を持っていかない”という意思決定は人によって異なるかと思います。また,同じ人であっても,時と場合によって判断を変えることもあるでしょう。
ここで悩ましいのは,「資源」や「好み・価値観」は人によって異なる点です。そのため,同じ情報を入手し理解・評価しても,決断・行動の意思決定が人によって異なるということが起こります。情報の入手・理解・評価については医学的視点から「正解」がある一方で,情報の活用には唯一無二と言った絶対的な「正解」はありません。つまり,情報を活用する場面において「正解」がないということは,患者や消費者の立場からすれば,決断・行動の意思決定に二の足を踏んでしまうことにもなりかねません。
さらに,前述の情報を理解する場面に“落とし穴”があると紹介しましたが,情報を活用する場面にも“落とし穴”があります。その具体的な事例については,過去の記事を参考にしてみてください。
◎意思決定の場面で気をつけるべき落とし穴[2020.11.5]
https://www.taishukan.co.jp/hotai/media/blog/?act=detail&id=263
さいごに,ここまで9回にわたってヘルスリテラシーについて解説をしてきました。さらに詳しい内容を学んでみたい方,具体的な事例をもっと知りたい方などがおられましたら,拙著『健康・医療情報の見極め方・向き合い方』を手にとっていただけたら幸いです。
【関連書籍】
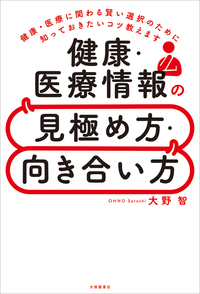

詳しくはこちら
一覧に戻る






