学校部活動と暴力
宮嶋泰子(スポーツ文化ジャーナリスト)
- 2021.02.24
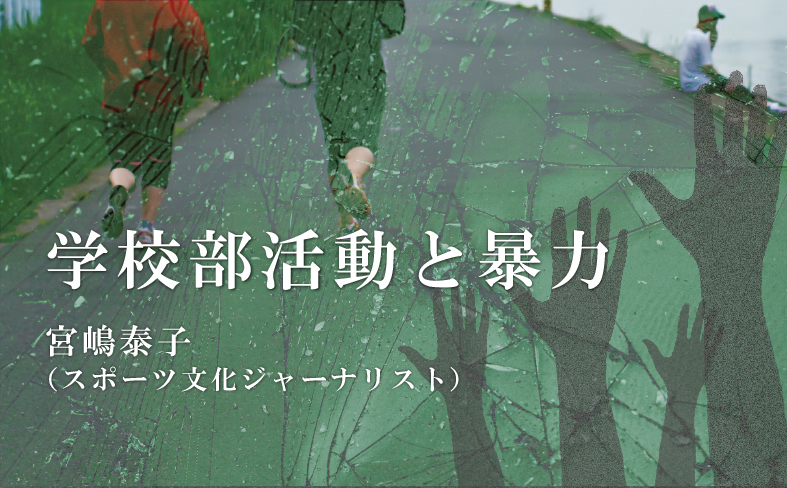
1.8年前の暴力根絶宣言
今から8年前,女子柔道日本代表選手に対する指導者の暴力が行われたことに端を発し,日本のスポーツ界全体で暴力根絶をしていこうという取り組みが本格的に始まった。2013年4月25日には「スポーツ界における暴力行為根絶宣言」が公益財団法人日本体育協会(現在の公益財団日本スポーツ協会)をはじめとして,公益財団法人日本オリンピック委員会,公益財団法人日本障害者スポーツ協会,公益財団法人全国高等学校体育連盟,公益財団法人日本中学校体育連盟の連名で採択された。
7年前の宣言の後,日本のスポーツの現場は変わってきているだろうか。日本に体育がもたらされたのは明治5年の学制発布の時だ。日本の学校体育は帝国主義の中で軍事訓練と形を変えながら終戦まで続けられた。また,明治時代に西洋から入ってきたスポーツも大学や旧制中学を中心に発展してきた。学校の中では常に上級生,下級生という上下関係が存在し,さらには,指導する教員が上にいて,指導される生徒が下にいるという上下関係ですべてが進んできた。体育会と呼ばれる組織だ。その上下関係は時に軍隊的要素を含み,上意下達,同調圧力,個より全体,女性蔑視などが見受けられ,命令に従わないものに対しては暴力が行使されることも少なくなかった。7年前に暴力根絶宣言がなされたにも関わらず,今でもいたるところで続いている。
2.体育会系について考える
『体育会系――日本を蝕む病』という本を執筆したサンドラ・ヘフェリンさんとお話をする機会を持った。ヘフェリンさんはドイツのミュンヘン出身で,日本歴22年。日独のハーフである。彼女によれば,ドイツでは今はスポーツにおける暴力指導はほとんどなくなっているという。かつては第二次世界大戦で日本とともに戦った軍事国家であったはずのドイツでなぜなくすことができ,日本はいまだに暴力問題が後を絶たないのか,そこにはとても興味深い話があった。
第二次世界大戦後,ドイツでは,なぜ国民がヒットラーを選んでしまったのかという徹底的な検証が行われた。当時ドイツでは父親が鞭をもって子供を躾ける方法が当たり前のように行われ,各家庭の中で暴力的行為が日常的に行われていたという。そうした家の中にある暴力が人々の正常な感覚を麻痺させ,ユダヤ人虐殺が行われていても何も感じなくさせてしまったという一つの結論が出されたという。今では家庭の中での暴力も法律で禁止されており厳しく罰せられるようになったという。こうした結果,スポーツ指導においての暴力も激減したというのだ。
また,ヒットラー政権時の反省から,現在はドイツの学校の授業中に手を挙げる時は,腕から挙げるのは「ハイルヒットラー」のようであることから,挙手はそっと人差し指を立てて静かに顔の横に上げることとされているそうだ。こうしたヒットラー軍事独裁政権への徹底的な反省がもととなって今のドイツがあるのだと聞き,日本の暴力がなくならないのは,やはりきちんと戦争に対する反省を行っていないからなのかと思ってしまった。と同時に,体育会系といわれるものの存在についても今一度考える機会を持った。
体育会系というのは,その中に入って上級生になれば居心地が良いことこの上なしの組織のようだ。下級生の面倒をこんなに見てやれるのも体育会系ならではと自慢する輩もおられることだろう。しかし,一年生は奴隷,二年生は平民,三年生は貴族,四年生は神様といわれる構造はスポーツや体育の健全な発展を妨げることも確かだろう。才能のある下級生はつぶされて当たり前,実力のある上級生にはどんなことでも従わざるを得ない,監督の命令には絶対服従という形もいびつだ。非常に民主的でない組織で,そこにはこれからの社会に必要といわれる多様性もその包含も見受けられない。
たまたまサンドラさんの知り合いのドイツ駐在員だった方のお子さんが日本に戻ってきて,サッカーを続けようとしたところ,学校の部活動では選手は全員坊主頭にしなくてはいけないというルールがあり,それにどうしても従うことができなかったため,泣く泣くサッカーを辞めてしまったという話も聞いた。スポーツは生涯にわたってその人の生活とともにあることが望まれるかけがえのないもののはずなのに,こうした一律のルールで個人を縛ってしまう組織の存在がどれだけ若者の可能性をつぶしてしまっているのかと思うと残念でならない。
3.ヒューマン・ライツ・ウォッチの報告書
2020東京オリンピック・パラリンピックを前に,非営利の国際人権組織であるヒューマン・ライツ・ウォッチが日本のスポーツの現状をヒアリングとデータ調査を行った。その結果,『「数えきれないほど叩かれて」日本のスポーツにおける子供の虐待』(全57頁)にまとめられた報告書では,日本のスポーツにおける体罰の歴史をたどるとともに,スポーツにおける子どもの虐待が,日本の学校スポーツ,競技団体傘下のスポーツ,トップレベルのスポーツで広く起きている実態が明らかにされた。ヒューマン・ライツ・ウォッチが行ったインタビューと全国的なオンラインアンケートによる調査では,50競技以上にわたるスポーツ経験者から,顔面を殴られたり,蹴られたり,バットや竹刀で殴られたり,水分補給を禁じられたり,首を絞められたり,ホイッスルやラケットでぶたれたり,性虐待や性的嫌がらせを受けたなどの訴えがあったという。驚くほどの子供への暴力による虐待が明らかになり,さらにはそれを通報する制度が整っていないという不備も明白になった。オリンピック・パラリンピックを開催しようという国の子供たちのスポーツ環境がこれではあまりに悲しすぎる。
日本のスポーツにおいての指導する側と指導される側の関係は,学校の教師と生徒という関係から出発しているために,どうしても上限関係になってしまう。それを横並びの関係になってほしいと思うのは甘いだろうか。選手とコーチがなんでも相談し,一緒に考えていける相手になれば,より大きな力がそこで生まれるように感じるのだ。選手は指導者の所有物ではない。時々勘違いをする人がいるのか,どんな競技でも学校内の暴力事件の報告が後を絶たない。選手が指導者の思い通りにならない時,感情が先走って暴力が生まれる。預かっている選手たちの良いところを引き出してあげるのが指導者の役割,生徒や選手は預かりものという発想があれば,暴力は生まれないと思うのだ。
一方,このところハラスメントという言葉が独り歩きしている面もあるように思う。選手や生徒が「ハラスメントを受けた」と主張すると指導者が罰せられるケースが多くなり,どうしてよいか戸惑う指導者が出てきているという。
ソフトボール監督の宇津木妙子さんは,シドニーやアテネでメダルを獲った教え子たちをコーチとして様々なチームに送り出しているが,最近そうした悩みを相談されるという。そんな時に教え子たちに伝えるのは「大切なことは日常的に一人一人と正面から向き合って,じっくり話をしてお互いの気持ちを確認しあっておくこと」だと言う。一方的に指導者の気持ちを押し付けるのではなく,相手の考えていることや気持ちを常にキャッチしておくことが気持ちのすれ違いを防ぐ鍵なのだろう。
4.対話型の指導へ
指導者たちは一方通行の上意下達型の指導から対話型の指導へと徐々に移行し始めている。とはいえ,まだまだそこには体育会系の残滓があり,スムーズにいくとは限らない。同質であることをよしとしてきた文化の中でいかに個性的であることが素晴らしいかを教えるために,東京女子体育大学で新体操の監督も務める秋山エリカ教授はこんなことを話してくれた。
多くの学生の中から一握りだけを選手として競技会に出場させる新体操団体の場合,選手として選ばれなかった学生のモチベーションをいかに保つかは重要な問題だ。重要なのは「みんながそれぞれの役割をもって,一つの作品を作り上げていくという意識を醸成させること」だという。数人のグループを作って,一人一人に「無人島に行くときにあなたは何を持っていきますか。なんでもいいですよ」と問う。そして,「みんなで持ち寄ったもので,後から来た客人をもてなすとしたらどんなもてなしができるか考えてみよう」と問いかける。一人一人が持ってきたものが違うからこそ,そこで生まれるもてなしはバリエーション豊かなものとなり,客人も喜ぶというものだ。一人一人が違うからこそチームは魅力的になるということを教える手法だと感心した。
こうした一連のコーチたちへインタビューを行い,そのコメントを集める作業を始めて,指導の奥深さをひしひしと感じているところだ。興味のある方はカルティベータのウェブを覗いてほしい。(https://thecultivator.jp/)
一覧に戻る






