文武両道は成り立つ①
体力向上は学力向上に寄与する!?
神戸大学大学院人間発達環境学研究科 助教 喜屋武享
- 2021.04.20
-
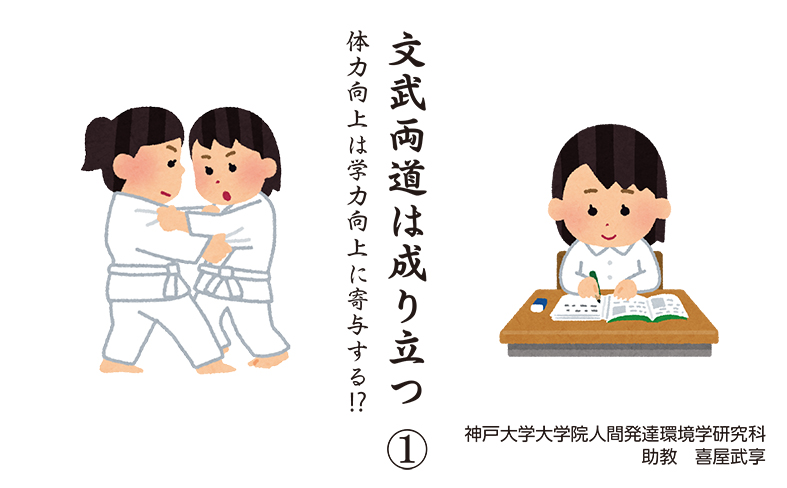
文武両道の意味を辞書でひくと「文事と武事その両道に努め秀でていることを指す語であり、現代では、勉学と運動(スポーツ)の両面に努める人物に対しても用いられる」とあります。文武両道は、鎌倉時代から明治維新に至るまで続いた武家政権の教えに由来する言葉です。江戸時代初期の陽明学者である中江藤樹は『翁問答』の中で「文と武は元来一徳であって、分かつことができない。したがって、武なき文、文なき武は共に真実の文ではなく、武でもない。」と文武両道の教えを説いています。また、『養生訓』で有名な儒学者、貝原益軒は「武芸の直接の目的は、戦場の使、日常の使にあるが、究極の目的は、武徳の涵養にある。すなわち武芸により、心身を統治することである。」と述べています。これらの教えを現代社会に当てはめてみた時、運動やスポーツは単なる競技力の向上を目指すに止まらず心身を鍛練することであり、勉学にも努め極めることで初めて文武両道ということができます。
2021年2月20日、ラグビー日本代表(当時)福岡堅樹選手が医学部医学科に合格したことが報じられました。文武両道を象徴する記憶に新しいニュースです。ラグビー日本代表の練習は選手たちから“地獄”と比喩されるほど過酷であることが知られています。特に宮崎県で臨む約1ヶ月間の長期合宿は、早朝から夜間まで、1日3部構成で激しいトレーニングと実戦練習が行われます。福岡さんはそうした練習の合間を縫って受験勉強に励み合格を勝ち取りました。このようにスポーツと勉学を両立させ、二足の草鞋で両道を極めるスポーツ選手は「天から二物を与えられた」特別な人たちなのでしょうか。
この15年間で、運動やスポーツと脳機能や学力との関係を探る研究が活発になっています。子どもを対象とするこれまでの研究成果をまとめた報告1によると、運動は短時間であっても集中力や作業遂行能力といった認知機能の改善をもたらすことが認められています。さらには、運動を継続し体力を高めることで、学力にも好影響を与える可能性が高いとされています。日本の小中学生を対象とした筆者らの研究においても、日頃から活動的であること2や運動部活動へ加入していること3が、認知機能の改善や学力の向上に有益であることを示す結果が得られています。グラフは、沖縄県南部の中学校5校に在籍する1年生を3年生まで追跡調査した研究の結果です。学業成績に影響を及ぼす要因は様々ありますが、この研究では、学習時間やモチベーション、親の学歴、家族構成、BMIなどあらゆる要因の影響を統計的に除外してもなお、体力の向上が学力の向上に寄与することが示されました4。さらに最新の研究成果からは、体力の向上が、とりわけ成績の低い教科の改善をもたらす可能性が明らかにされました5。これらのエビデンスは、「武」を極めることが「文」の習得にも貢献しうることを示した知見であると言い換えることができます。
.jpg)
日本における子どもの運動機会といえば、体育授業や運動部活動、地域のスポーツ活動等です。文部科学省は「子どもの体力向上」をスローガンに掲げ、これらの活性化に注力してきました。例えば、特設webページで体育授業の実践例を紹介したり、適切な部活動のあり方に関するガイドラインを作成したり、地域のスポーツ活動に助成金を交付する等の取り組みを展開してきました。これらが功を奏してか、2018年までの10年、子どもの体力運動能力は緩やかな上昇傾向にありました。
しかしながら、これらの体力向上施策には、運動習慣がある子どもとない子どもの二極化や性差(女子の活動量が低い)等いくつかの課題があることが指摘されてきました。この背景には、運動嫌いなど個々人の特性に関わる問題だけではなく、子どもを取り巻く時間・空間・仲間の減少や子どものスポーツ活動に費やす家計的余裕がないなど、環境や経済的な問題も影を落とします。最近では、部活動顧問の過度な負担が社会問題として取り上げられるようになるなど、従来の子どもの体力向上施策に見直しが求められている状況です。
体力向上の基本となる子どもの運動促進場面を考えた時、地域・家庭・学校などいくつかのコミュニティが思い浮かびます。その中でも学校は、子どもが1日の大半を過ごす場所であり、施設・設備が充実しているだけでなく子どもを指導できる人材が揃っていることから、運動促進を含むヘルスプロモーションを効率よく実践できる場として期待されています。学校における子どもの1日は、登校、教育日課前活動、各教科学習、休み時間、昼食、掃除、放課後、下校で構成されます。これまでにも休み時間や教育日課前後の運動促進プログラム等が試みられてきましたが、やはり先に述べたような問題は残されたままでした。
そこで近年、諸外国を中心に注目を集めるのが教科学習場面を活用した“アクティブ・レッスン・プログラム6,7”です。アクティブ・レッスン・プログラムは、「運動しながら勉強をしよう」というもので、教科学習中に学習内容と関連のある短時間の運動を行う身体活動プログラムです。単なる学習中の小休憩とは異なり、学習の要素を運動に組み込むことがポイントです。簡単な例をあげると、足し算、引き算などの四則計算の答えを運動で表現したり、いくつかのマス目の中に漢字がランダムに書かれたマットを用意し、出題者によって読み上げられた順番通りにジャンプして移動するなどの活動があります。これにより、所定の教育課程の進捗を阻害することなく活動量を上げることが可能になります。
小・中・高等学校での教科学習というと、多くの人は、椅子に腰掛け机に向い先生の話を聞いたり問題を解いたりする光景を思い浮かべるでしょう。最近、学校教育ではクラスメイトとディスカッションをしたり、学んだことを発表したりする場面も少なくありませんが、やはり座学中心の学習が一般的です。このような伝統的な学習スタイルを否定するわけではありませんが、短時間であっても運動をすることによってその後の集中が高まるとする科学的知見を頼りにすれば、運動しながら勉強するということは理にかなった学習方法といえます。このように、アクティブ・レッスン・プログラムは、子どもの体力向上施策に係る諸課題を一掃しつつ、学力向上にも貢献する可能性を秘めた学習法略であり、文武両道を叶える手段として期待できるものです。
次号では、既に実践されているアクティブ・レッスン・プログラムの具体例を紹介します。
一覧に戻る






