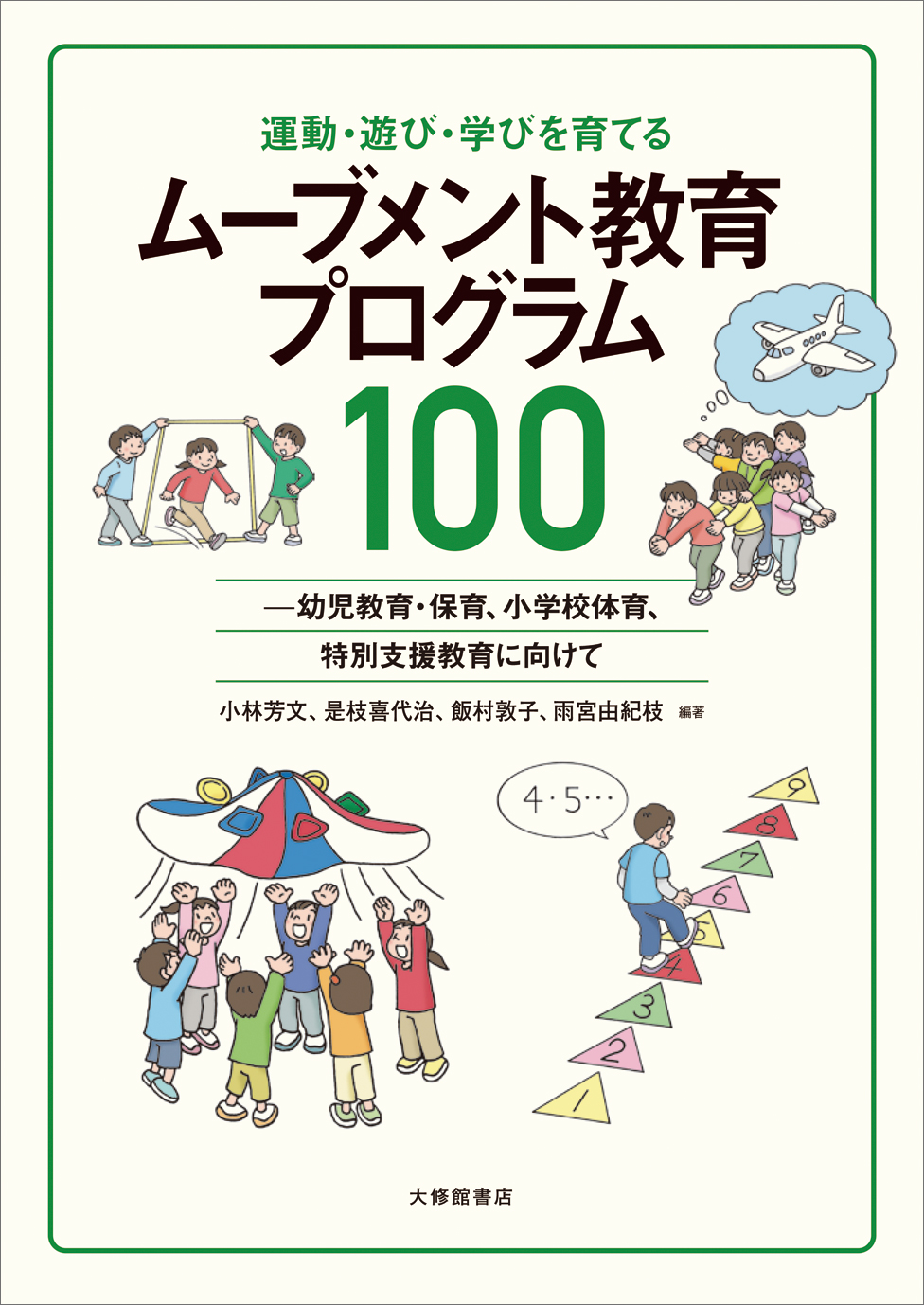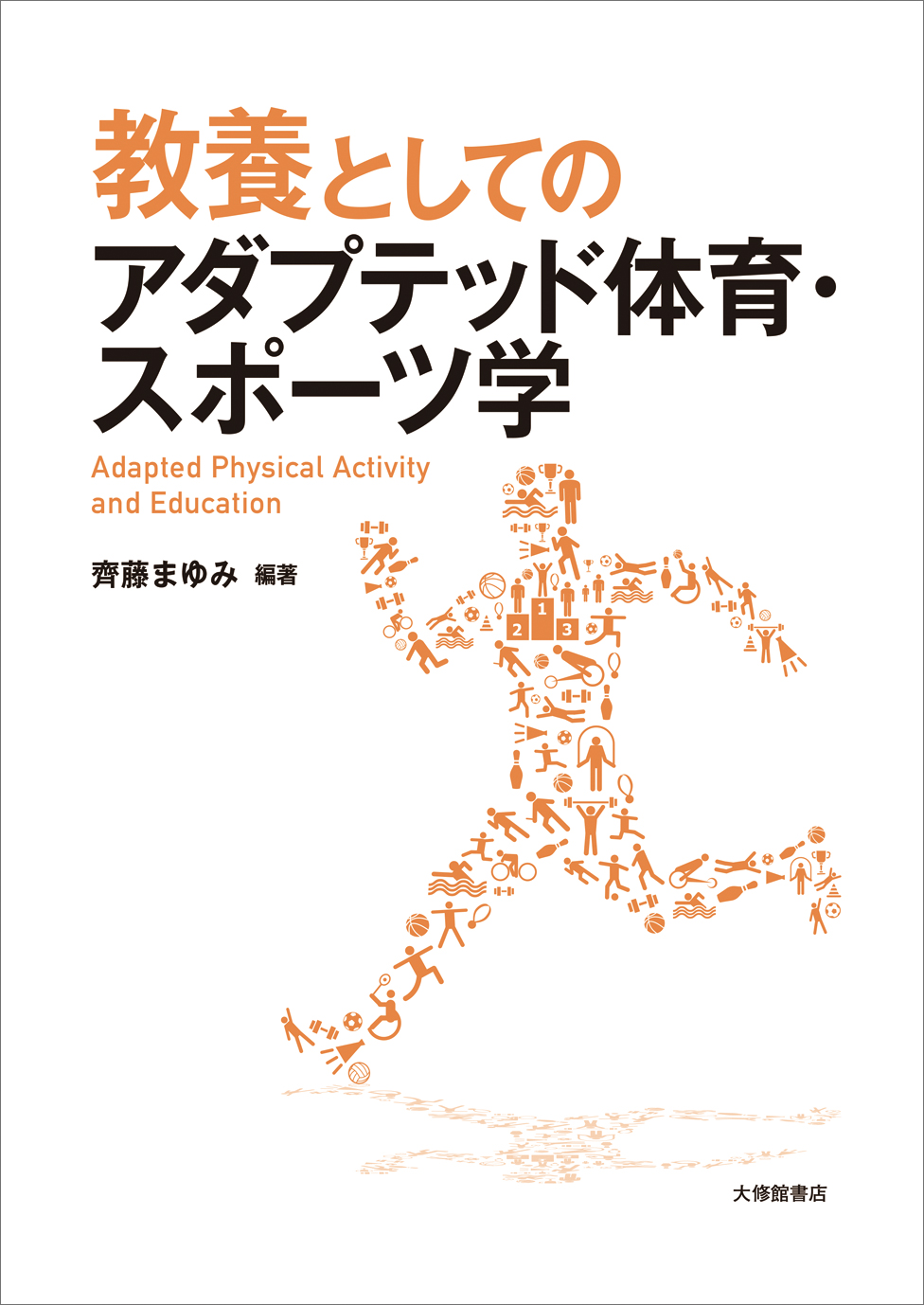肢体不自由児のムーブメント活動を掘り下げる①
是枝喜代治(東洋大学教授)
- 2023.01.23
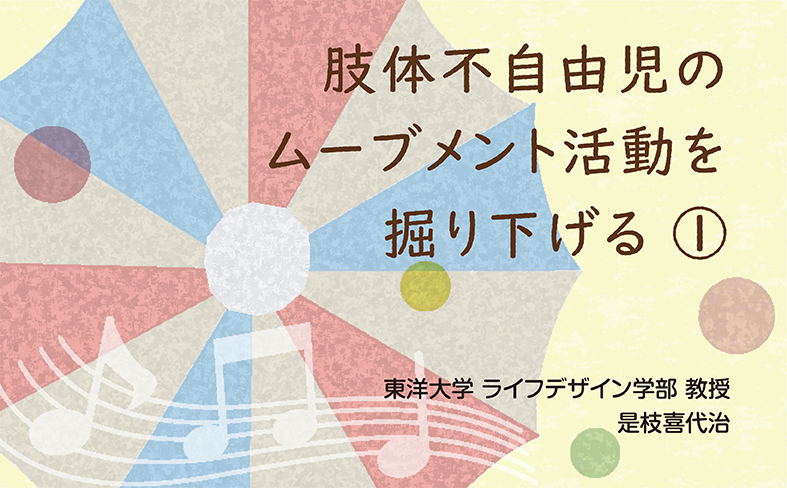
今回は、「ムーブメント教育・療法」を長年研究・実践されてきた是枝喜代治先生に、肢体不自由のある子どもの支援に焦点を当て解説いただきます(全2回)。(編集部)
ムーブメント教育・療法とは
ムーブメント教育・療法とは、米国のフロスティッグ博士によって体系化され、小林芳文氏によって日本に紹介された子どもの全面発達を支援する教育方法の一つです。ピアジェの発達理論を背景に、子どもが自ら動きたくなるような環境(遊具や人的環境など)を上手く設定し、子どもの自主性や自発性を尊重しながら、軽運動をとおして運動能力のみでなく、心理的諸機能(認知能力、問題解決力など)を育てていく「動きをとおした学びの支援法」と言えます。
関連する書籍も多数刊行されていて、特別支援学校を中心に児童発達支援事業所や放課後等デイサービス、小学校の通常の学級などの様々な場で、子どもの特性や発達の段階に合わせた取り組みが進められています。
肢体不自由の子どもに対するムーブメント活動の意義
脳性マヒなどの肢体不自由のある子どもたちは、その障害の特性から、成長と共に身体の変形や抗縮が進んでいきます。そのため、できるだけ座位や立位などの抗重力の姿勢を取らせながら、楽しい運動遊びを経験させていくことが重要です。
支援に際しては、安全面に十分配慮しながら、子どもと支援者・子ども達同士が一緒に楽しめる活動を積極的に取り入れていく必要があります。例えば、腕の拘縮を防ぐために支援者が子どもの手を無理に伸ばすよりも、目の前に好きなオモチャを置き、子ども自ら手を伸ばせるような環境を意図的に作り出すことで、自発的な動きや行動を引き出すことができます。
学校や療育機関、さらには家庭の中でこうした取り組みを日常的に行うことは、身体の変形や拘縮の予防に役立つと共に、外界や事物を認識する力を高めたり、人や物に対する関心を広げたりすることにつながります。肢体不自由の子どもの支援を考える際に、運動機能の発達だけに視点を当てるのではなく、人と関わるために必要な言語・コミュニケーションの力や社会性の育成など、子どもの総合的な育ちを支えることに留意して支援を展開していくことが大切です。
肢体不自由の子どものムーブメント活動の実際
パラシュートやボールプールなどの活動では、肢体不自由の子どもが日頃経験することの少ないダイナミックな揺れ刺激が体験できます(写真参照)。自発的に動くことが難しい子どもたちにとって、他動的であっても、外部からの揺れ刺激を体験することは、身体意識(body awareness)の育ちにもつながります。
また、支援者が長座位の姿勢で床に座り、子どもを膝の上に乗せて後ろから抱きかかえ、子どもと一緒に前後・左右にゆっくりと揺れる活動(転んだ・起きた・だるまさん)などは、狭い空間でも簡単に取り組める楽しい運動遊びの一つです。ただし、こうした活動を行う場合、個々の子どもの心地よい揺れ刺激の程度を把握しておくことが重要です。人が体感する「揺れの心地よさ」は、一人一人異なります。不規則で激しい揺れが好きな子どももいれば、均等でゆっくりとした揺れが好きな子どももいます。その時の子どもの表情や仕草などをよく観察しながら、無理なく楽しくできる運動遊びを展開していくことを心掛けるべきでしょう。


今、学校現場で求められていること
令和2年の特別支援教育資料によれば、肢体不自由特別支援学校は全国に352校あり、在籍する児童生徒数は30,905人です。ここ数年、学校数や在籍者数の大きな変動はありませんが、全体的に在籍する子どもの障害の重度重複化が進んでいて、特に医療的ケアの必要な子どもの割合が増えています。
現在、学校現場では「発達段階の幅広い子どもたちに対して、どのような教育内容を設定して取り組めば良いのか」「医療的ケアの必要な子どもに対して、具体的にどのような支援を展開していけば良いか」など、様々な課題が生じています。同様に、肢体不自由特別支援学校での勤務経験が長い教員が定年を迎えるケースが増えていて、具体的な支援方法や配慮の在り方などを若手教員にどのように伝達・継承していくかといった課題も見受けられます。教員たちが共に日々の授業づくりを進める中で、子どもの実態把握の方法や支援のノウハウなどを体験的に伝達していくことが求められています。
まとめ
本記事では、「ムーブメント教育・療法」の紹介を含め、主に肢体不自由のある子どもの支援について、その意義や内容、学校現場の課題等について紹介してきました。実際に肢体不自由の子どもの支援を担当されている先生方、就学前の療育機関等に携わっている先生方の参考になれば幸いです。
次号(こちらから)では、肢体不自由特別支援学校で取り組まれている授業実践について、実際の学習指導案を含めて紹介していきたいと思います。
参考文献
・小林芳文、他編(2021)運動・遊び・学びを育てるムーブメント教育プログラム100-幼児教育・保育、小学校体育、特別支援教育に向けて.大修館書店.
・文部科学省(2021)特別支援教育資料(令和2年度).
編集部からのおすすめ書籍(表紙をクリックできます)
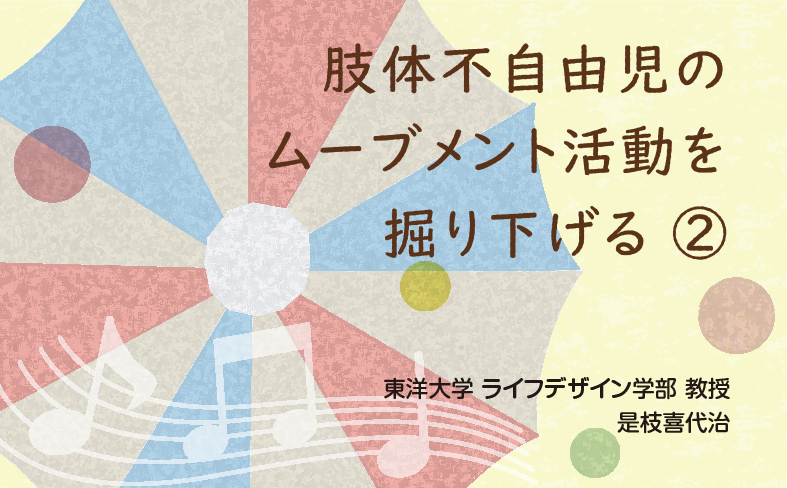
詳しくはこちら
一覧に戻る