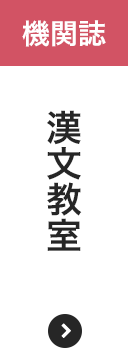悩める創作者のための 伝わる〈古文〉の書き方
第7回 助詞の使い方 ――準体法で古文らしさUP――
田中草大
- 2025.12.05
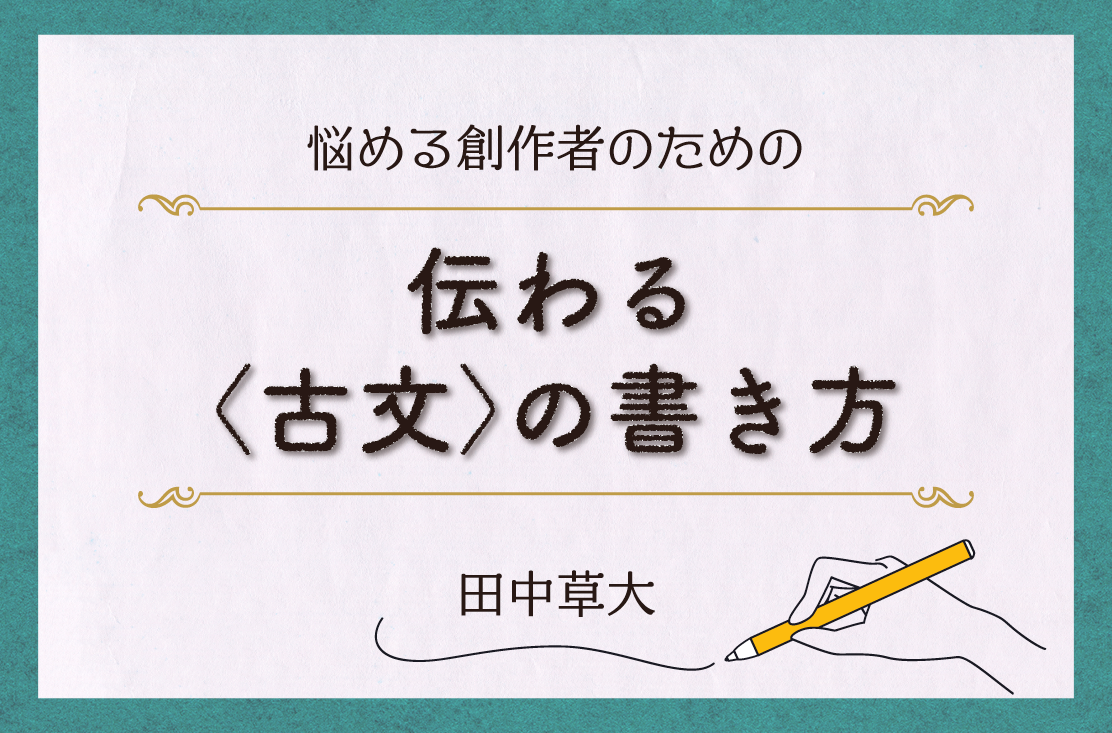
助詞については今後の回の中でも扱っていきますが、この回ではいわゆる格助詞 [1]について解説します。と言っても古文の格助詞は幸いにも現代語と共通するところが大きく、「を」「に」「と」「より」など、おおむね現代語の感覚で使って差し支えありません。
ただ、古文らしく書くための格助詞の使い方として押さえておくとよいポイントが二つあります。①主節の主語と、②準体法です。以下、それぞれ解説していきます。
①主節の主語
解説の前提として、まず「節(せつ)」という文法的な概念について知っていただく必要があります。節は簡単に言えば「述語を中核とする単語たちのまとまり」のことであり、例えば「猫が町を歩く。」であれば、「歩く」という述語が中核として一つあり、それに対して「猫が」や「町を」といった語句が内容の補足(誰が歩く? どこを歩く?)をして一つの節が構成されている、という捉え方です。
しかし「節=文」でありません。なぜなら、「日が沈むと、猫が町を歩く。」のように、一つの文に述語が複数ある(=節が複数ある)場合もあるからです。
この場合に、文のメインとなる節のことを主節と呼び、それ以外の節のことを従属節と呼びます。メインであるというのは、日本語の場合、普通「文末に来る」ということによって判定されます。次の例を参考にしてください(主節の述語に二重線を、従属節の述語に一重線を引いています)。
例:日が沈むと、猫が町を歩く。
僕は、遊びに熱中する猫が好きだ。
さて以上が前置きで、ここでやっと古文の話になります。古文では、主節/従属節における主語の示し方について次の2点のことが言えます。
①主節では、主語は原則として無助詞で示される。
例:昔、男φありけり。(昔、男がいた。)
山φ高し。(山が高い。)
※φ(ファイ)は、そこに言語要素が「無い」ことを示します。
②従属節では、主語は無助詞または「が」「の」で示される。
例:昔、髪φ美しき男ありけり。(昔、髪が美しい男がいた)
昔、髪の美しき男ありけり。(〃)
基本的には、古文では主語は「が」や「の」を介さず名詞を直接置くという考えでよいでしょう。特に、主節ではこのことを強く意識してください。例えば「男ありけり。」を「男がありけり。」としてしまうと、古文らしさが大きく損なわれます[2]。
他方、従属節の場合は、無助詞でもよいですが「が」「の」を入れても構いません。助詞を入れないと意味が通じにくそうだと感じる場合は入れるとよいでしょう。
《注意》ここで「無助詞」と言うのはあくまで格助詞「が」「の」についてのことであり、係助詞「は」「も」等は主節の主語に入れても差し支えありません。
例:男は帰りにけり。(『平中物語』25段)
涙もとどまらざりけり。(『大和物語』168段)[3]
主語にせよ連体修飾にせよ、「が」と「の」をどう使い分けるかということが問題になりますが、実はこれが非常に難しく、現在でも研究が続けられている問題です。
使い分けの中でよく知られているのがいわゆる「尊卑」に基づくもので、その対象への親愛や逆に軽侮を示す場合には「が」を使い、敬意や心的距離を示す場合には「の」を使うというものです。「少将の形見にはよるの衾、康頼入道が形見には一部の法花経をぞとどめける」(『平家物語』「足摺」[4])のような例が知られています。
ただ、「の」「が」を使うときにいちいち「これは親愛か、軽侮か、敬意か……?」と考えるのはあまり現実的ではありませんし、それから実を言うと「が」「の」の使われ方には歴史的な変化も起こっています[5]。一般的に言えば、古くは「の」の方が広く用いられていましたので、「の」を基本にしつつ、「ここは『が』の方がしっくり来る/通じやすそう」というところでは「が」を使うという考え方で問題ないと思います。
なお、「の」にはない「が」の特徴として、体言だけでなく用言(連体形)を承ける用法があります。古文らしい表現ですが、これを使う場合は「の」ではなく「が」ということは覚えておくとよいでしょう。
②準体法
現代語では、次のように意味の希薄化した「こと」「の」がよく用いられます。
例:火を着ける[こと/の]は私の仕事だ。
猫が狩りをする[の]を見た。
古文では、この内「こと」はそのまま使ってOKですが、「の」はダメです。
例:火を着くる[○こと/×の]は我が務めなり。
「火を着くるのは~」としてしまうと、古文らしさが損なわれます。
「の」が使えない代わりに、古文には別の選択肢があります。それは次のように、「何も付けない」という方法です。
例:火を着くるφは我が務めなり。
猫が狩りをするφを見けり。
このように古文では、活用語が「こと」などの名詞を介さずに連体形だけで名詞相当の振る舞いをすることができます。このような表現を「準体法」(準体句とも)と呼びます。
準体法は、現代語にも「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」「言うは易し、行うは難し」「事無きを得た」「逃げるに如(し)かず」などの表現に残っています。古文らしさを出せるテクニックなので活用していきましょう。
練習問題
ここまでの説明の復習として、練習問題に取り組んでみましょう。次の文を古文にしてください。
①女が西へ去るのを見た。 ※た:連用形+けり
②空が青いことに心が打たれた。
③鳥が鳴くのを真似て、あの男が笛を吹く。
④昔の本を読むのは、昔の人に会うようなものだ。
解答例
①女の西へ去るを見けり。
②空の青きに心打たれけり。
③鳥の鳴くを真似て、彼(か)の男、笛を吹く。
④昔の書(ふみ)を読むは、昔の人に会ふがごとし。
解説
①文の構造としては「[女が西へ去るの]を(誰かが)見た。」となり、「女が」は主節ではなく従属節の主語。よって古文では無助詞でもよく「の」「が」を入れてもよいです。古文としては、「女」に付くのは「が」より「の」が普通ですが、「女の西へ去るを~」とすると読者に「『女の西』って何?」と思われそうである、という場合は、「女が西へ去るを~」としても差し支えないでしょう(近代の古文には例があります)。
なお、「女が西へ去るを見けり。」だと、「女が」が「去る」ではなく「見けり」に係っていると誤読される恐れがあります。充分な文脈があって誤読の恐れが低い場合はこのままでよいですが、文意をより明確にしたい場合は、「見けり」の主語も入れて「我、女が西へ去るを見けり。」「我見けり、女が西へ去るを。」のようにするとよいでしょう。
「去るのを」は、直訳すると「去ることを」となりますが、準体法で「去るを」とすると古文らしさが出ます。
②文の構造としては「[空が青いこと]に(私は)心が打たれた。」となり、「空が」は主節ではなく従属節の主語です。よって無助詞でもよく「の」「が」を入れてもよいです。入れる場合、「の」と「が」で、古文としてより自然なのは「の」です(例:「今朝は、さしも見えざりつる空の、いと暗うかき曇りて、雪のかきくらし降るに……」『枕草子』275段[7])。
一方、「心が打たれた。」の「心が」は主節の主語なので、こちらは無助詞にします(→「心φ打たれけり」)。
「青いことに」は、直訳すると「青きことに」となりますが、準体法で「青きに」とするとより古文らしさが出ます(この場合は「空の青さに」と、単純に名詞の形にするのもよいでしょう)。
③文末に当たる「あの男が口笛を吹く。」が主節で、「鳥が鳴くのを真似て」は従属節ですので、「男」には「が」「の」を入れず、「鳥」には入れても入れなくてもよいです。入れる場合は、「鳥」と相性が良いのは「の」ですが(例:「白き鳥の、はしとあしと赤き……」『伊勢物語』9段[8])、近代には「鳥が~」の例もありますので自らの語感に任せてどちらを使っても構いません。
「鳴くのを」は「の」を残すと古文らしさが損なわれますので、準体法で「鳴くを」とします。
「あの男が笛を吹く」はそのまま訳すと「彼(か)の男笛を吹く」ですが、これだと「男笛」という名詞があるみたいにも見えますので、「彼の男、笛を~」とか 「彼の男 笛を~」のように読点やスペースを入れて区切れを明示するとよいでしょう。
④「読むのは」は、そのままだと古文らしさが損なわれますので準体法で「読むは」とします。係助詞「は」は主節の主語であっても用いて構いません。
「ごとし」(←「~ようなものだ」)は、「の」「が」が付きますが、ここでは体言ではなく用言(会う)を承けていますので「が」を使います。
なお、文末部分が「昔の人に会ふがごとし。」となっているので、主節の主語なのに無助詞ではなく「が」が付いているように見えますが、ここでは「ごとし」に対応する主語は「昔の人に会ふ(こと)」ではなくその前の「昔の書を読む(こと)」であると考えてください。「ごとし」は文末に来ても「の」「が」を伴える、と覚えておくとよいでしょう[9]。
[1] 「体言または体言に準ずるものに付いて、その体言が他の語にどんな関係で続くかを示す助詞」(『日本国語大辞典』第2版)。「が」「を」「に」「へ」「と」「より」などがこれに当たります。 [2] 平安時代のような古い古文でも、例外的に主節の主語が「の」「が」を伴うことがありますが、非常に細かい話になるため割愛します。関心のある方は小田勝『古代日本語文法』・同『実例詳解古典文法総覧』の「主格」の項目をご参照ください。 [3] それぞれ、小学館・新編日本古典文学全集『竹取物語 伊勢物語 大和物語 平中物語』501頁・408頁より引用。 [4] 『日本国語大辞典 第2版』の「が」の項目における挙例。入道に「が」が使われるのに対して少将に「の」が使われるのは、身分の差(少将の方が高い)を反映したものと解釈できます。 [5] 例えば、代名詞(「我」「汝」など)は全体の傾向とは異なり「が」を伴う特徴があるのですが、「なんぢ(汝・爾)」に「が」が続くか「の」が続くかを国立国語研究所『日本語歴史コーパス』(中納言2.7.2・データバージョン2025.03)で調査すると、17世紀までは例外なく「が」が続く(例:汝が為)のに対して、18世紀になると「の」が続く例も見られるようになり、19世紀にはむしろ「の」が続く形(例:汝の為)が多数派になります。 [6] 小学館・新編日本古典文学全集266頁。 [7] 小学館・新編日本古典文学全集430頁。 [8] 小学館・新編日本古典文学全集122頁。 [9] ややこしいですが、「ごとし」は用言を承ける場合は「が」を省いてもよいので、ここは「昔の人に会ふφごとし。」としてもOKです。体言を承ける場合は「の」は省略しません。
著者プロフィール
京都大学大学院文学研究科准教授。専門は日本語の歴史。主な著書に、『平安時代における変体漢文の研究 』(勉誠出版、2019年)、『#卒論修論一口指南』 (文学通信、2022年)など。
X(旧Twitter): https://x
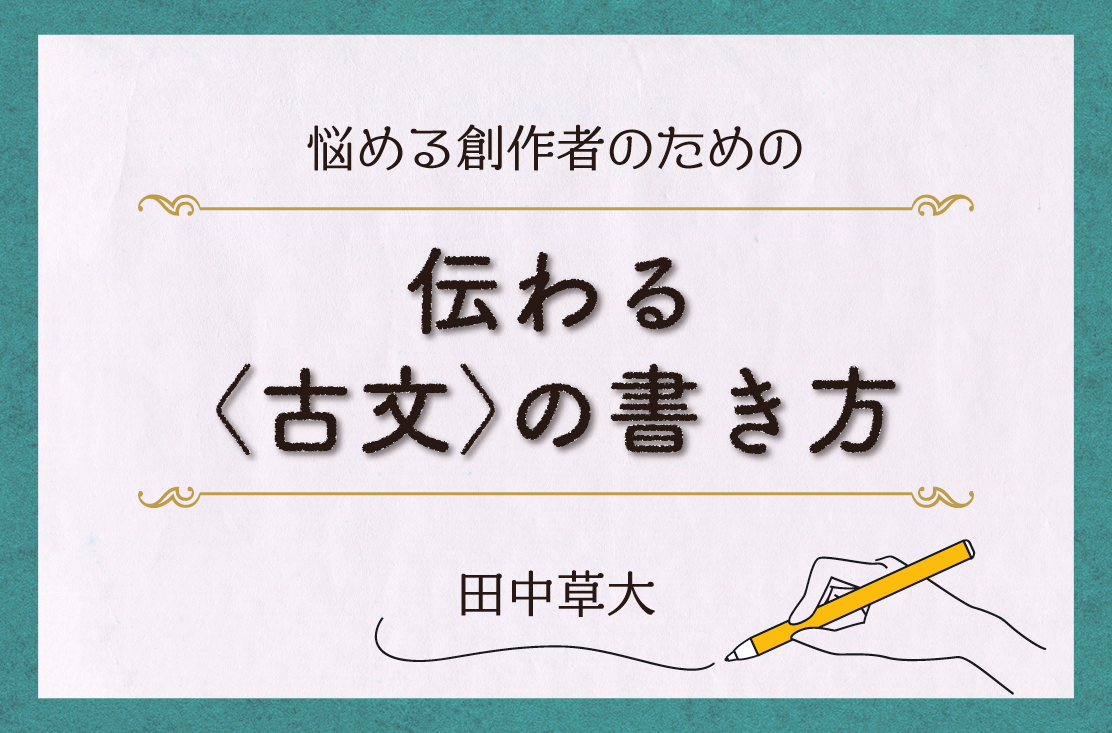
詳しくはこちら
一覧に戻る