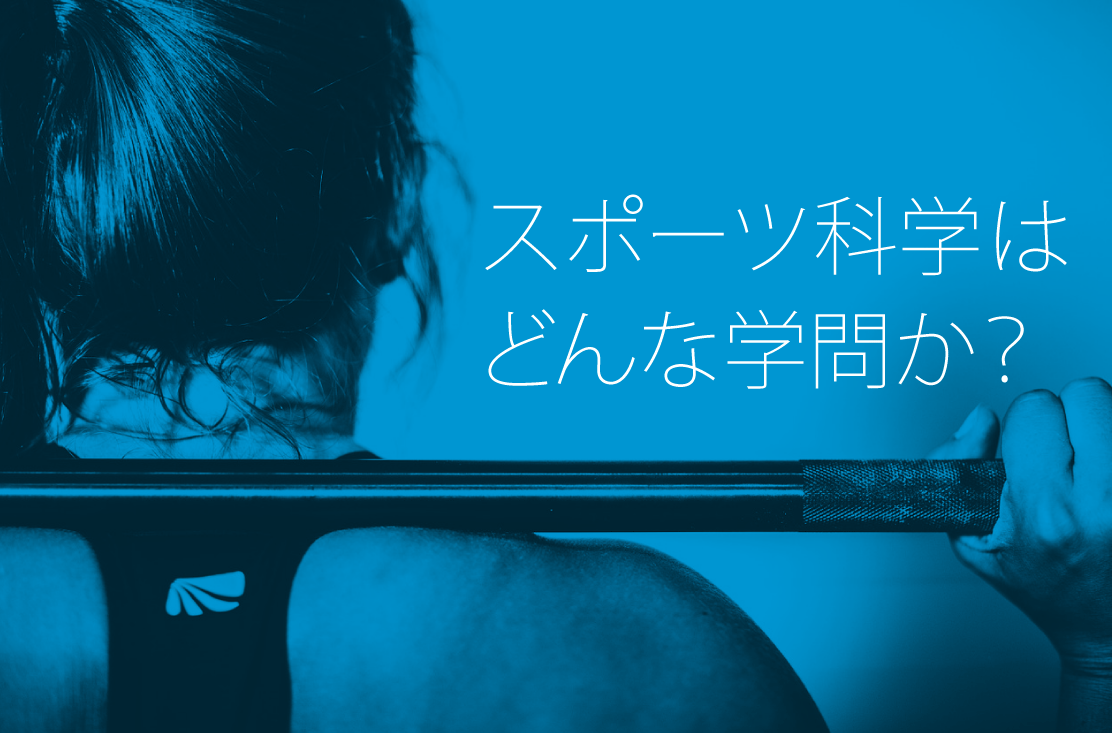【おすすめ本】そのトレーニング,古くないですか?
日本トレーニング指導者協会

昭和から平成を経て,令和という新時代を迎えた今日,改めてトレーニングについての体験的小史を振り返ってみると,それに対するイメージは“当時”と“今”とでは随分と様変わりしていることに気づく。もちろん,その変化に気づくのは昭和生まれで,しかも現在ではもう40代半ば以上の人たちにほぼ限られるのではないかと思う。
腕立て伏せや腹筋・背筋,さらには坂道や石段でのダッシュ,うさぎ跳び…。おそらく,該当する年代の多くは,汗と泥にまみれ苦悶の表情を浮かべながら,へとへとになるまで身体をいじめ抜くという過酷でネガティブな光景しか思い浮かんでこないのではないか。そういう意味で,“当時”のそれは,まさに“スポ根”を象徴する鍛錬活動の一つとして捉えられていたといっても過言ではない。
すなわち,競技のパフォーマンス向上やケガの予防などに役立てるというより,精神的鍛錬のほうに圧倒的に重きが置かれていたように思うのだ。それを物語るように,本人はもとより当時の部活動指導者もおそらく,トレーニングとは,実は罰則の一環という程度の認識だったという人も少なくないはずである。
ところが,平成という時代に急速に進化と深化を遂げたスポーツ医・科学によって,なにしろ憂鬱以外のなにものでもなかった“モノクローム”の風景は,トレーニング本来の役割が明確になるにつれ,次第に明るい色調を帯びるようになってきた。トレーニングは他者からやらされるものではなく,みずからが頭を使って取り組むものだ,と。
そんななか,2007年に出版されたのが,『スポーツトレーニングの常識を疑え!』(当協会 編著)だった。2001年には,日本の国際競技力向上への支援を目的として国立スポーツ科学センター(JISS)が開設されるなど,平成の半ばにはトレーニングも旧来の考え方から脱却し,本来の目的遂行のために科学的に活用されるようになってきた。それに伴って,トレーニングの常識も世の中に広く認知されるようになった。とはいえ,トレーニングにおける科学も日進月歩だ。旧態依然に甘んじ,指導の現場で直面するさまざまな事実や疑問を常識に合致しないと切り捨ててしまっては,人も科学も成長はない。そういった“慣れ”に対して,大きな一石を投じたのがこの本だった。
それからさらに10年が経過し,新たに発行されたのが本書である。まず,トレーニングの科学を知り,その一歩,あるいは二歩先にはまた何か新しい発見があるのではないかという仮説を立て,常に既存の科学を超えていこうとする努力を結実させたのが,本書の最大の魅力であるといっても過言ではない。例えば,より優れたトレーニング計画を立案する手法として,ピリオダイゼーションをさらに高いレベルで用いるための超回復理論に代わる『フィットネス-ファティーグ理論』の紹介など,随所に“常識を超える”新たな考察を読み取ることができる。
本書は,日本トレーニング指導者協会が誇る指導陣が,日々の研鑽から培ったさまざまな理論と実践について,競技・種目別の話題,バリスティックエクササイズ,スプリント,アジリティ,コア・体幹,ジュニア期のトレーニング,スポーツ傷害予防,ストレッチング,ファンクショナルトレーニング…など,あらゆる観点からトレーニングに鋭く斬り込んだ最新の情報が満載。部活動の指導者にとっても,指導力アップに欠かせないバイブルとなるはずだ。
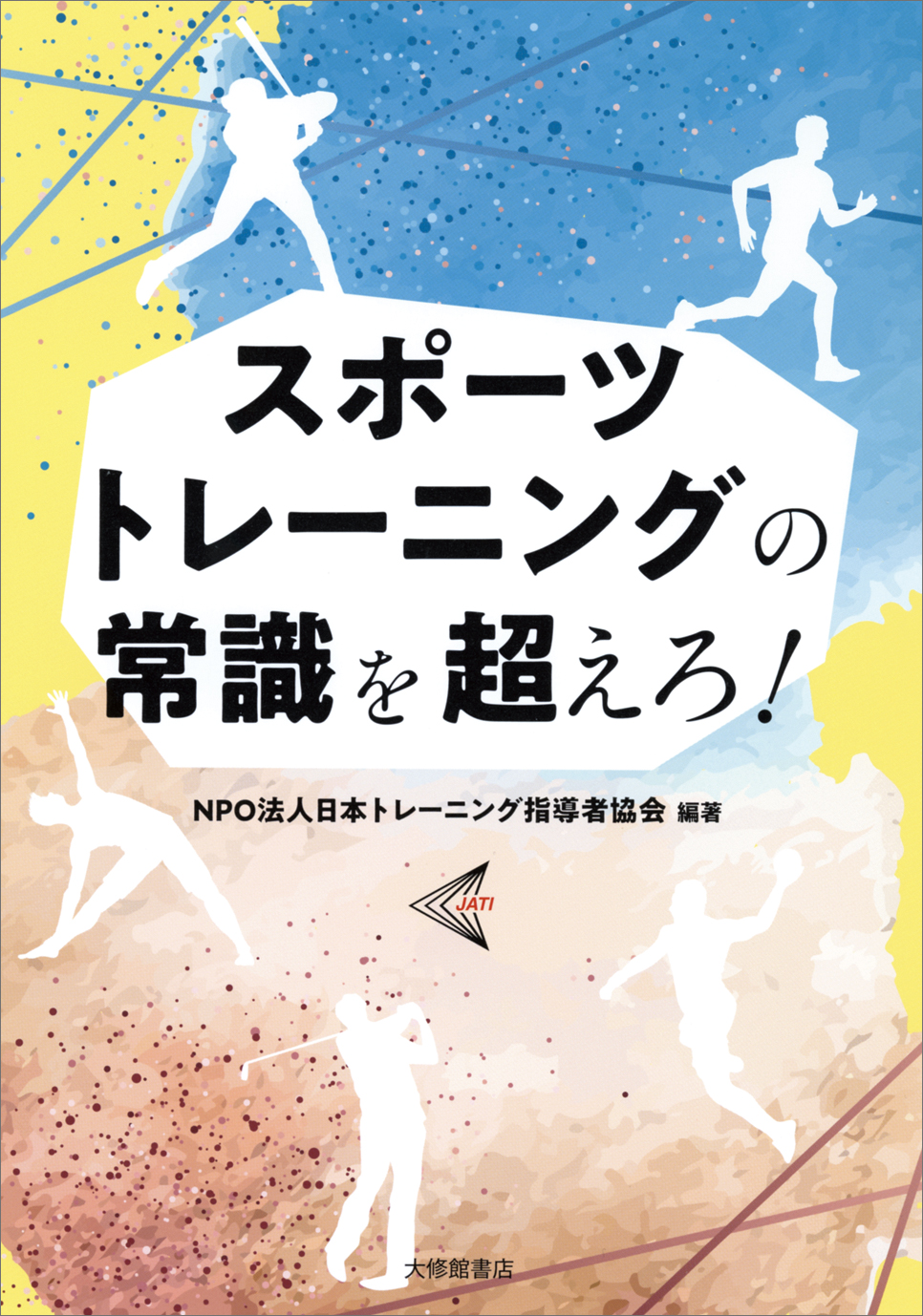
NPO法人日本トレーニング指導者協会[編著]
一覧に戻る