【先出し一部公開】<緊急座談会>長引く休校。体育の視点から見て何が問題?
鈴木聡×佐藤善人×福島健明×小島大樹
- 2020.04.24
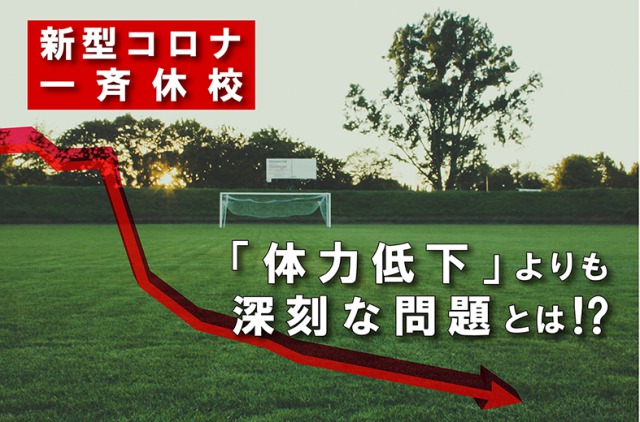
座談会の趣旨
新型コロナウイルス感染症対策による学校の休校が続いています。
現時点では、緊急事態宣言にあわせて大型連休後の5月7日を学校再開日とする地域が少なくないですが、先は見通せません。また、仮に学校が再開したとしても、「新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン」にも示された、三密(密閉、密集、密接)を徹底的に回避すること等は引き続き求められるでしょうから、普段行われているような体育授業を行うことは困難だと言わざるを得ません。
しかし一方で、子どもの運動不足が身体面・心理面に悪影響を及ぼすとのエビデンスも少なくなく、事態を静観しているだけでは別の問題が生じかねません。
こうした背景のもと本座談会では、(1)学校の休校は体育の視点から見て何がどう問題なのか、(2)学校に来られなくとも体育の学びを止めない方法はないのか、(3)学校が再開するとしてどういった体育授業であれば実施可能なのか、を考え、最後に(4)アフターコロナの体育の在り方を展望してみたいと思います。
*本座談会は、東京都の外出自粛要請に鑑み、オンライン(Zoom)上で行いました。また、その特性を生かし、Facebookグループ「体育授業のプラットフォーム」から約50名の先生にオブザーバーとして座談会にご参加いただきました。
座談会メンバー
鈴木 聡=司会・東京学芸大学教授
佐藤善人=東京学芸大学准教授
福島健明=三鷹市立第五小学校校長
小島大樹=調布市立第三小学校指導教諭

「体験」の喪失
鈴木 まずは長期間の休校の何が問題なのかを体育の視点から整理してみたいと思います。はじめに学級担任の立場から小島先生、お願いします。
小島 「学校」の役割を社会的有用性、平たくいえば「将来役に立つ力」を育むことだとすると、体育では「社会性」が身につくことや「体力」の向上等がそれに該当すると思います。休校によってそうした力を育む機会が失われている現在の状況は確かに厳しいです。しかし私は、学校の役割が社会的有用性を高めるだけだとは全く思っていません。特に体育は、「純粋に運動を楽しむ」場であると考えています。その意味で、友達と運動を楽しむという「体験」ができないことがとても心配です。一斉休校になって出てくる体育関連の話題は、「心身の発育発達」に関することがほとんど。それは私もよくわかるのですが、しかしそれ以上に、「体験」の喪失が何より問題ではないかと思います。
本校では、医療従事者等を親にもつ子ども80名程度(全校の約1割強)を対象に学校を開いています(4月11日時点)。そこで子どもに「いま何がしたい?」といった簡単なアンケートをとったところ、最も多かった回答は「校庭に出て友達と遊びたい」でした。少なくとも子どもたちからは「体力低下が心配」という声は聞かれませんでした。
鈴木 体育授業が子どもたちに何を保障してきたのかが問われているのかもしれませんね。つづいて管理職の立場から福島先生、お願いします。
福島 本校では、主幹教諭や主任教諭等が中心となって、チームとなってこの危機をどう乗り越えられるかを必死で考えています。しかし、「本当に5月から再開できるのか」「年間カリキュラムをどうすればいいのか」「各教科でどんな授業ができるのか」など悩みは尽きません。そのようななかでも、学校が再開したら単に知識・技能を習得させればいいとか、体育でいえば「とりあえず体力を元に戻せればいい(落とさなければいい)」といった考えにはならないようにしたいと考えています。
個人的に心配しているのは、新聞等でも話題になっていますが、子どもと親との関係がストレスフルな状態になっている家庭のことです。体を動かすことでなんとか子どもたちがストレスを発散させられないか。しかし、なにしろ“Stay Home”ですので、家の中でできるストレスの発散方法や子どもたちが満たされる時間の過ごし方について発信していく必要を強く感じています。
鈴木 小学校現場の貴重な情報をありがとうございます。一斉休校になって間もない3月初旬、小学生のママ友たちが「学校の体育って本当にありがたかったのね」といった話をしているのを耳にしました。今まで「当たり前」だったから気づかれていなかった体育の重要性が、はからずも広く知れ渡る機会になったのかもしれません。
さて、佐藤先生は、大震災や豪雨などの被災地の子どもにみられる身体的・心理的な変化に関する研究をされていますが、そういった視点も含めて今回の休校をどう捉えているのかお聞かせください。
佐藤 スポーツ庁や日本スポーツ協会が様々なエビデンスをもとに「1日 60 分程度の運動をしましょう」という指針を出しています。一斉休校前の通常の状態であれば、体育の授業(45~50分×週3回)や休み時間、運動部活動等で多くの児童生徒がその指針をクリアできていたわけですが、いまはそのどれも止まっている状態で、運動時間が減った子どもは多いと思います。ただ身体面に関しては、学校が再開されて運動時間が十分確保できるようになれば戻ってくる可能性が高いので、そこまで大きな問題ではないかもしれません――学校がいつ再開されるのかが読み切れないので断言はできませんが。それよりも、小島先生がおっしゃったように、「その瞬間自体が楽しい」という経験ができないことのほうが私も心配です。
また心理面でいえば、福島先生がおっしゃったように、外に出られなかったり家庭内がぎくしゃくしていたりしてストレスフルの状態になってしまっている子どもは少なくないと思います。そのストレスですが、休校期間中(1~2カ月)に溜まったストレスは、休校が終わったら、つまり学校が再開されたらすぐに解消されるわけではなく、ストレス状態は継続するという結果を示した研究があります。ですので、いま、いかにして子どもがストレスを抱えにくい状況をつくっていけるかを考える必要があると思います。
鈴木 そのソリューションの一つとして、動画コンテンツが挙げられます。最近は誰もが気軽にアクセスできる動画が増えてきていて、個人的にはとてもいい傾向だなと思っています。先生方のなかでこんな遊びや運動ができるよというアイデアがあれば教えてください。
佐藤 私が日ごろ子どもたちとやっている遊びは、スキンシップとか交流がある遊びが中心なので……
鈴木 典型的な密集、密接ですね。日常であればとても楽しい運動遊びですが。
佐藤 スポーツ庁や文部科学省、各自治体あるいは著名人がYouTube等でいろいろな提案をしています。まずはそういったものを先生方がご覧になって実際にやってみる、そのうえで子どもにフィードバックしてあげるといいのではないかと思います。
いま、子どもたちは
鈴木 私の自宅は住宅街にあるのですが、普段の春休みよりも子どもたちの遊ぶ声が聞こえてくるように感じます。子どもたちはいま何をして過ごしているのでしょうか?
小島 3月の休校期間中に学級の子ども一人ひとりに電話をして、「普段何して過ごしてる?」と聞いたところ、外に出てドリブルやリフティングの練習をしたり、他にも少人数で集まって遊んでいたりする実態はありました。ただ、知人の教師から聞いた話ですが、平日の昼間に子どもたちが公園で遊んでいてうるさいと、学校に苦情がきているそうです。在宅勤務の方や、そもそも外で遊ぶなんてけしからんと考える大人からの通報なのでしょう。こういうことがあると、子どもは外に遊びに出たくても本当に遊んでいいのだろうかと不安を抱えてしまいます。
鈴木 最近のある調査で150人近い保護者アンケートをとったところ、一番の課題は「子どもの運動不足」だったそうです。緊急事態宣言のさなかにあっても、感染対策を意識したうえで散歩やジョギングをすることは問題ないとも言われていますが、それでも地域の目があって、日常的に外に出たり、運動したりすることができない子どももいるのでしょうね。
福島 私が一番危惧しているのは「二極化」です。休校期間中に全家庭の子どもがランニングや散歩程度の運動のために外に出られる状況かというとそうではありません。保護者の仕事状況次第では毎日家の中にいなければならないという子どももいるわけです。これは先ほど話題に出た動画配信、オンライン授業でも同じことがいえます。例えば学校から保護者宛にメールを送ったり郵便物を届けたりしたとしても、同じ理解をいただけているとは限りません。ましてオンラインは、そもそも環境がないという家庭もあるでしょう。オンラインはとても便利ですが、学びの二極化を助長する可能性もあります。一方で、だからといって、全く取り入れないというのも違う気がしています。非常に悩ましいところです。
体育の学びを止めない方法
鈴木 オブザーバーの先生のなかで、子どもの運動を支援する取り組みを行っている方がいらっしゃれば、ぜひご発言いただきたいのですが。
オブザーバー① 私学の小学校で体育専科をしています。休校の延長が決まった4月初旬に、学校から「(他教科同様に)体育の宿題を出してほしい」と依頼されました。急な話だったので、結局「ラジオ体操をしよう」とか、「なわとびをやってみよう」といったものになりました。
オブザーバー② 同じく、小学校で体育専科をしています。本校でも宿題を出しました。「行った運動、回数、時間」を書けるプリントを配ったうえで、行う運動はお手玉やフラフープといった軽い運動でもいいから、工夫してやってみようねと伝えています。それから家でできる運動の動画を体育科で4本作成し、配信しています。教師と体じゃんけんをするものや、軽いステップを踏むダンスの動画です。
オブザーバー③ 高校の体育主任をしています。本校では、現時点でGWまでの休校が決まっています。休校期間中の体育はというと、1・2年生は1人1台タブレットをもっているので、彼らには、自分が運動をしている動画を送る、という課題を出しています。休校がさらに長引けば、個人ではなく学級でチャレンジできるような課題を出したいと思っています。身体接触はできないけれど、みんなで1つのものに向かって挑戦する楽しさはオンラインでも味わえるのではないかと考えています。他にも、自分に合ったサーキットをつくったり、「個人探究」と題して個人技、例えば陸上競技の三段跳びを究めたり、といった取り組みも検討しているところです。
オブザーバー④ 教育委員会に勤めています。個人の意見になりますが、オンラインの学習コンテンツが充実してきていることは望ましいことだと思います。心配なのは、それらを活用した授業が「教師から子ども」への一方向的になりがちであることです。教師と子どもの双方向型の授業を実現するためにはどのようにすればいいのかを模索していく必要があると思います。
(4月11日収録、企画・編集=「体育科教育」編集部)
*以降は、体育科教育2020年7月号で詳報。
https://www.taishukan.co.jp/book/b512547.html
一覧に戻る







