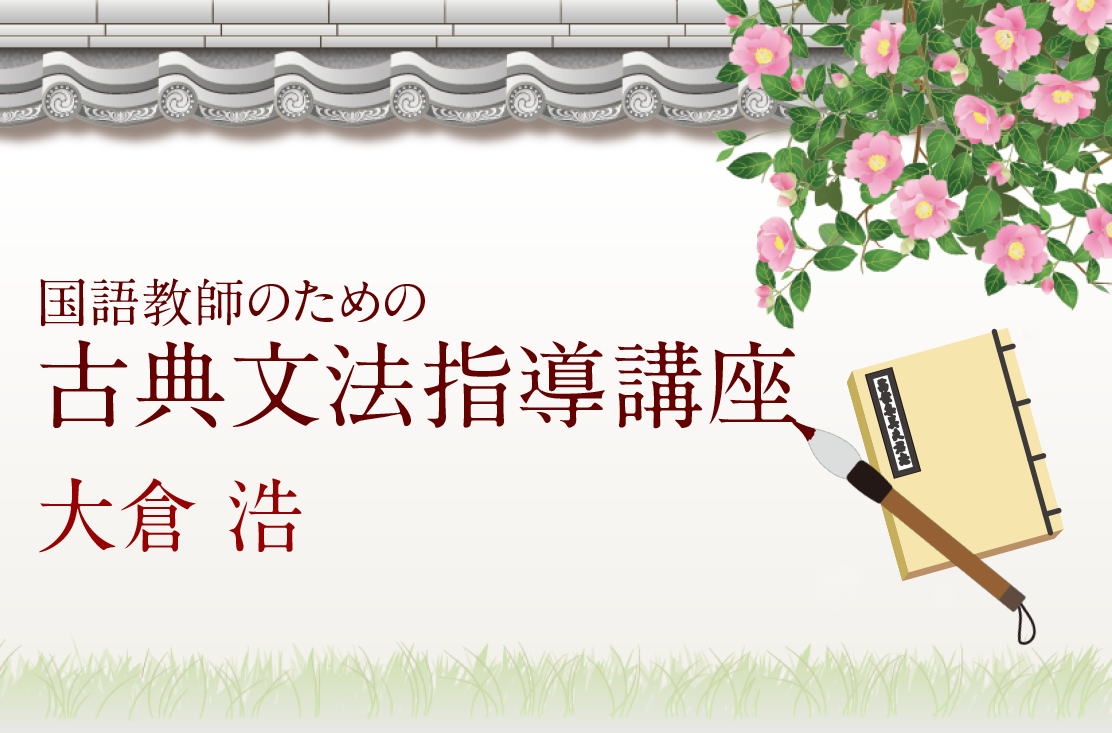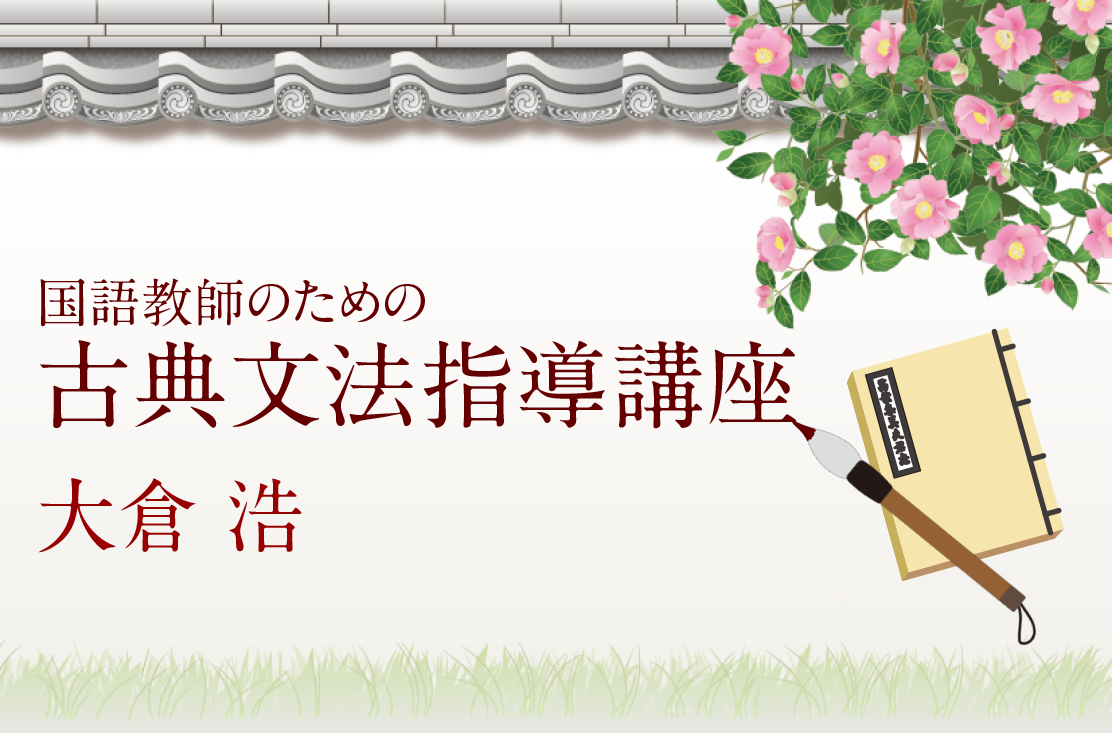【新連載】国語教師のための古典文法指導講座
第1回 なぜ「古典文法」を学ぶのか
大倉浩
- 2019.04.03
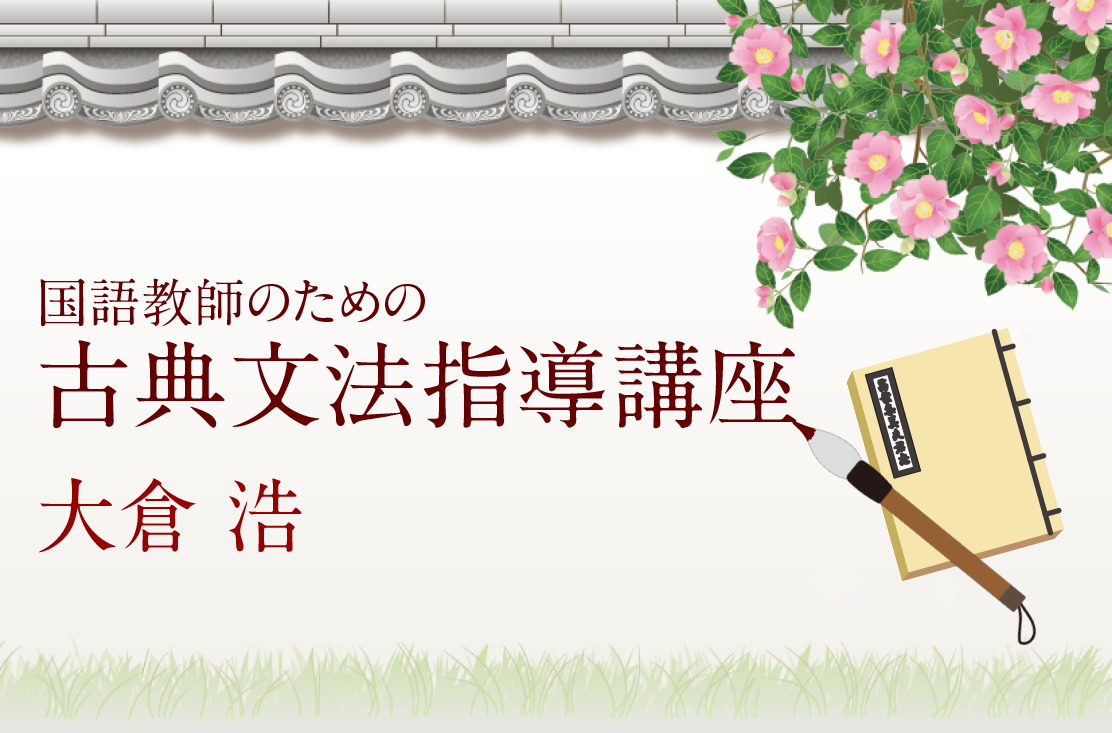
「物知り」先生でなく「訳(わけ)知り」先生になろう
私は大学で「日本語史」を担当しています。教職科目でもあるので、受講生には国語教師を目指す学生も多いのですが、「古典文法が好きだ、面白い」という学生は1~2割ほど。多くは古典作品の内容や登場人物、時代、作者に興味を持つ学生です。
これは健全?なことかもしれませんが、古典文法好きの私としては、古典の言葉そのものの面白さに、もっと気づいてほしいのです。そして、動詞・助動詞の意味や活用をたくさん覚えている「物知り」ではなく(記憶力では、若い生徒たち、AIには勝てませんから)、「古語の動詞には一段活用、二段活用、四段活用があるのに、なぜ三段活用はないのか?」「過去完了や推量の助動詞がたくさんあるのはどうして?」などの疑問にも答えられる、「訳(わけ)知り」の先生になって、生徒の日本語そのものへの関心を高めてほしいのです。このコーナーも、そのきっかけになればと思って書いていきます。
では今回は私のほうから皆さんに逆に質問です。
◆質問◆そもそも「古典文法」を学ぶのは何のため?
「大学入試に出るから。」と生徒たちは答えるでしょうね。先生方だって「ここは試験に出るから大事だぞ!」と教室で言っていますね。逆に言えば、受験以外では使わないのが「古典文法」の現状なのです。でもそれは、数学や物理だって同じですね。なぜ「古典文法」はその中でも影が薄いのでしょうか? おそらく、実生活で「古典文法」を使う場がほとんどないからでしょう。
質問に戻って考えると、「古典文法」とは、古典の文章を正しく読解するための手段・方法(ツール)です。「古典文法」を学んで、古文を正しく品詞分解して単語を切り出し、わからない単語は古語辞典を引いて意味を確かめ、現代語に訳して読解していくのが、古典の勉強の基本です。つまり、「古典文法」は品詞分解のための手段であって、勉強の目的はあくまでも古典作品の読解のほうです。
昭和の終わり頃までは、古典作品の現代語訳は充分に整備されていませんでしたから、生徒たちは教室で先生に指導してもらいながら、自力で古文を品詞分解し、辞書を引き、読解していくしかありませんでした。大学も、受験生がこうした読解の手段をちゃんと身につけているかどうか、入試問題で試していたわけです。
しかし、平成も終わろうとしている現在、主な古典作品の現代語訳は書籍でもネットでも容易に入手でき、さらに漫画化され映像化されたものも数多く存在します。古典の専門家が丁寧に訳した現代語訳を読めば、初心者が時間をかけて苦労して訳さなくても、すぐに作品の読解にとりかかれるのですから効率的です。美味しい焼きたてのパンが手軽に買えるのなら、自分でわざわざ小麦粉をこねてパン作りをする人は少なくなるのと同じです。
では、古典の教科書は全て現代語訳付きにして、「古典文法」の学習は、やめてしまってよいでしょうか。(そうなったら楽しそうだと思う方もいるでしょうが)残念ながら現代語訳のできない古典があるのです。和歌や俳諧、歌謡などの韻文です。これらは音の響きや韻律が、内容と同じくらい重要な要素ですから、専門家でも現代語に完璧に翻訳はできません。ちょうどビートルズの曲やアナ雪の歌が、原語で聞いたり歌ったりしないとしっくりしないのと同じです。古典の韻文は、「古典文法」を学んで、原文を自ら読まないと読解しきれないのです。御存じのように、『伊勢物語』や『源氏物語』にも多くの和歌があって、和歌をふまえた表現も多く見られます。「古典文法」が、読解にはまだまだ必要なのです。
「古典文法」について、ちょっと「訳知り」になったでしょうか。授業でも、全文訳にこだわらず、和歌や敬語表現など訳しにくい部分でも、「古典文法」によって理解に近づけることを、生徒さんたちに気づかせることから始めてみてはどうでしょうか。
『国語教室』第108号より転載
→古典文法に関するご質問を、こちらからお寄せください。
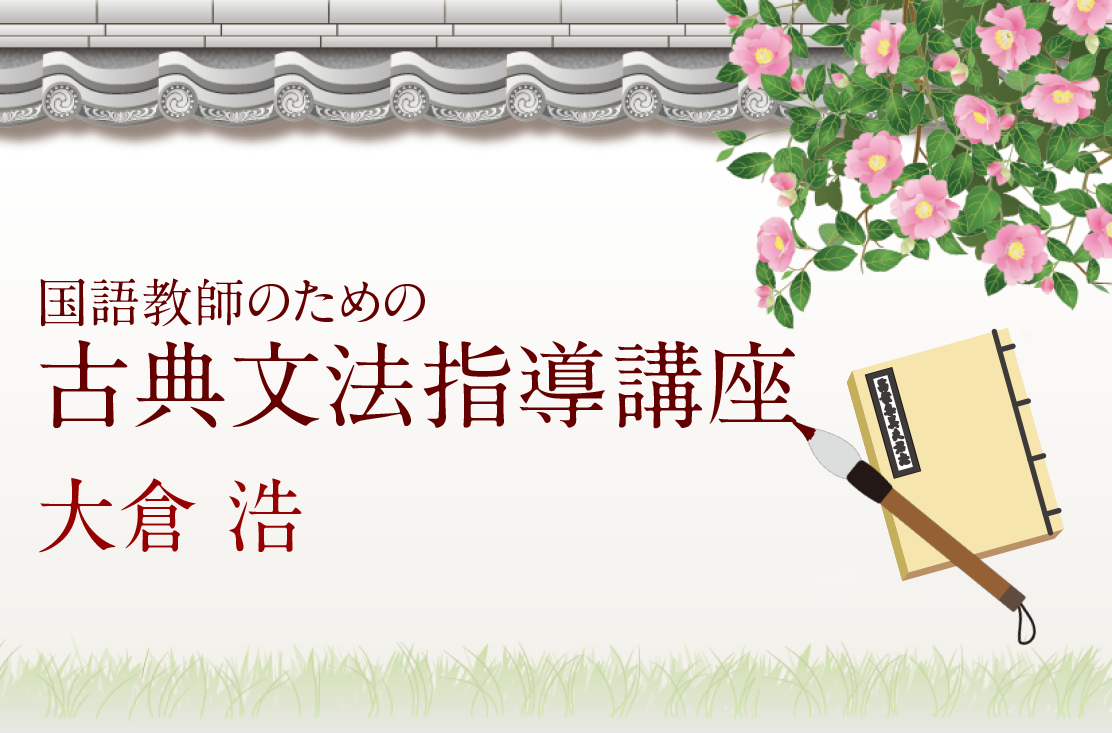
詳しくはこちら
一覧に戻る