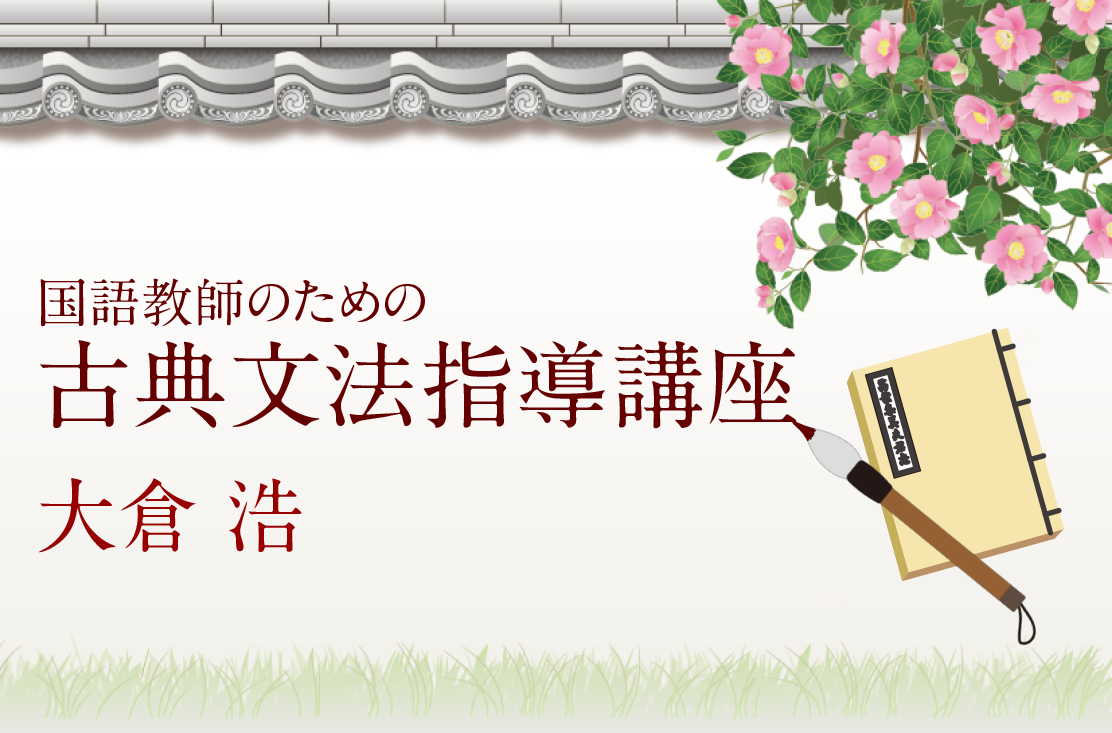国語教師のための古典文法指導講座
第15回 「き」+α=「けり」?――古文日記に挑戦①
大倉 浩
- 2025.08.27
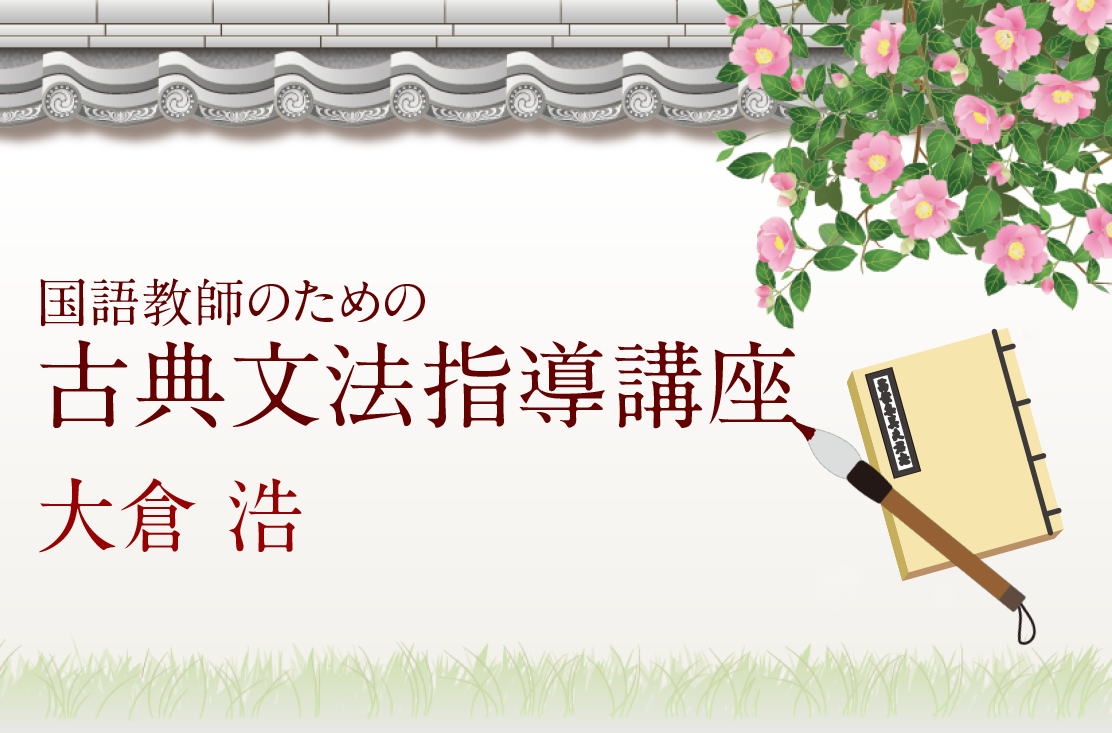
古文作文を続けながら、古文解釈の鍵の一つである助動詞のお話をしていきたいと思います。まず、高校二年生を想定して、元となる現代文の日記から。
四月四日 晴れ。今日から新学期が始まった。
クラス替えで2組になった。担任は国語の大倉先生だ。
この日記を、古語と古典文法の知識を使って、現古辞典などを手がかりに古文訳してみます。
卯月四日 天晴。けふより新しき学びの年始まりけり。
組替へにて二組に加はりき。組役は国語の師大倉殿なり。
前々回に助動詞一覧表をとりあげたので、最初は未然形接続の「る」「らる」から始めるべきかもしれませんが、今回は日記にもよく使われる、過去回想の助動詞「き」と「けり」について考えます。
現代日本語では、時制(テンス)の過去は主に助動詞「た」で表しますが、古文では「き」と「けり」があり、直接経験の過去は「き」、間接経験の過去・伝聞は「けり」、という違いがあって、『土佐日記』や『徒然草』などの随筆を読む際には、その使い分けに要注意! と教わります。次の例、
その人、ほどなくうせにけりと聞きはべりし。(徒然草)
その人が亡くなった(けり)という伝聞を、作者自身が直接聞きました(し)、ということがこの使い分けからわかったりします。先ほどの古文訳でも、新学期に気づいた気持ちで「けり」を、その日に自分が経験したことには「き」を使いました。
このような意味の違いから、「き」と「けり」を対立した別種の助動詞のように捉えがちですが、むしろ基本形と発展形というように、関連づけて考えたほうが、両語の違いが捉えやすいと思うのです。
というのも、助動詞「き」の語源は、定説は無いのですが、「き/し/しか」という不思議な活用パターンから推測すると、「き」と「し/しか」は元々は別系統の助動詞で、後に意味の共通性から一つの助動詞のようにまとまってきたものと思われるからです。さらに連用形接続ということから、「き」はカ変動詞「来」と、「し/しか」はサ変動詞「す」と、それぞれ動詞と語源的に関連があると考えると、「 来し方」「せしか」のようなカ変動詞・サ変動詞との変則的な接続も説明がつくように思うのです。いずれも、一千五百年以上の昔、文献以前の日本語についての仮定・憶測ですが、それほど助動詞「き」は古くから使われているのです。
いっぽう「けり」は、一千三百年前の『万葉集』にも用いられていて、語源として「来あり」が推定されています。「けり/ける/けれ」という活用からも、ラ変動詞「あり」が含まれていることがうかがえますが、注目は「来」のほう、カ変動詞連用形です。つまり、「けり」は、助動詞「き」と、語源ではカ変動詞「来」を介して間接的なつながりがありそうなのです。別種の助動詞ではないのです。
こうした語源的なつながりを踏まえて、単純な過去を意味する「き」に、「あり」がプラスされて、過去の事柄に対する話し手の様々な認識を加える「けり」が発達してきた、というように仮定すると、「けり」が間接経験・伝聞だけでなく、継続や詠嘆、気づきなど、文脈によって様々な意味を表すこともうなずけるのではないでしょうか。現代語でいうと、
~き。 :~シタ。
~けり。:~シタノダ。~シタコトダ。
のように、「けり」は「き」プラスαの意味を持つ発展形と考えると、両語の意味の違いも捉えやすくなると思います。
このように、助動詞を語源の視点で探っていくと、無関係に見えた助動詞の間の関係が見えてきたり、意味・接続や活用の共通点がわかったりするのです。
『国語教室』第123号より転載
著者プロフィール
大倉浩(おおくら ひろし)
筑波大学名誉教授
→ 古典文法に関する質問をする
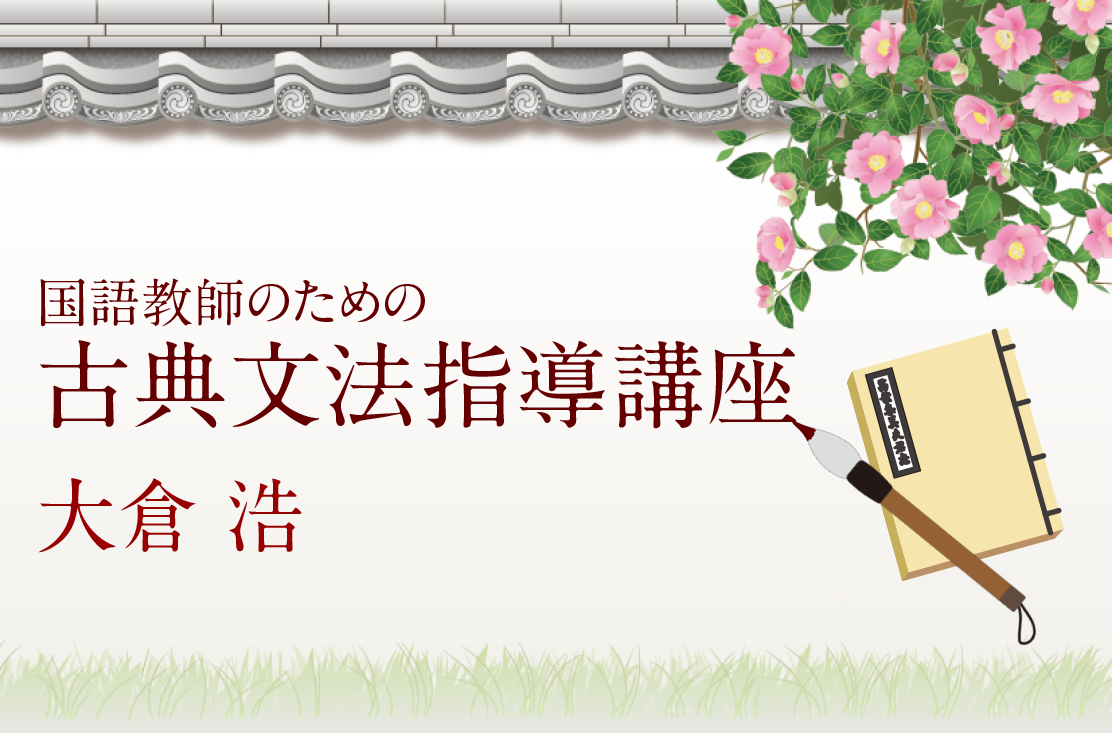
詳しくはこちら
一覧に戻る