国語教師のための古典文法指導講座
第14回 紫式部はどこに居る?――紫式部にファンレターを書こう⑪
大倉 浩
- 2025.08.25
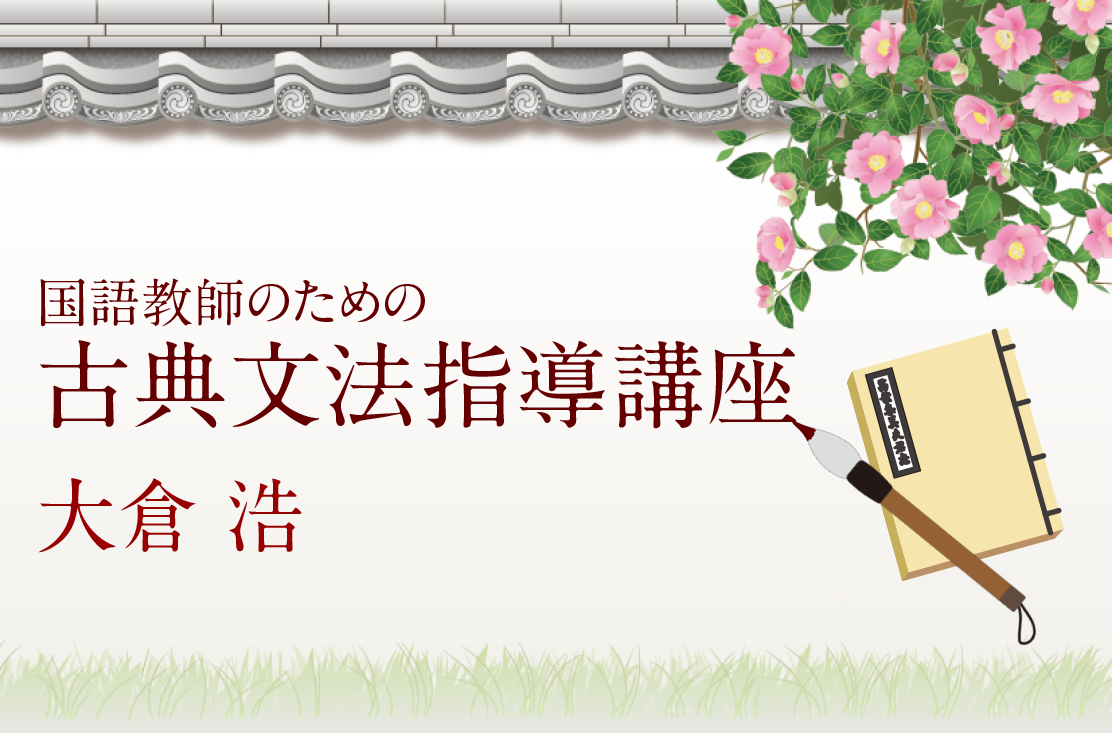
前回、助動詞一覧表の話を始めたところでしたが、本誌の今回の特集が紫式部の書いた『源氏物語』ということですので、これまで考えてきた、紫式部あてのファンレターの古文訳をひとまずまとめておきましょう。
おもとのものしつる物語「きりつぼ」を読みはべりき。死ぬる桐壺更衣ぞ、いとあはれにはべりける。
現古辞典などを使って、現代語を古語に置き換えればすむと思っていた古文訳でしたが、「死ぬ」は、活用が異なるだけでなく、古語ではナ変動詞だけで完了の意味合いを含んでいたので、「死にたる桐壺更衣」のように完了の助動詞を加える必要はありませんでした。また、「ぞ…ける。」の係り結びを使った強調の表現で、気持ちを伝える工夫をしたり、手紙なので丁寧語の「はべり」も入れました。
なにしろ千年もの時間が経過しているのですから、同じ日本語でも現代語と古文には様々な違いがあります。簡単に現代語訳できないからこそ、古典文法を学んでその違いを埋める必要があるわけですが、語順や修飾・被修飾の関係などには変化がありませんから、用言の活用の変化、助詞・助動詞の用法などが要注意となるわけです。
また、これらの変化は文法だけの問題ではなく、実際は発音やアクセントの変化とも関連しています。奈良時代の四段活用動詞の已然形と命令形には発音の区別があった(「書けば」のケと「書け!」のケは別の音)ことがわかっていますし、平安時代では、四段活用動詞の終止形と連体形の間で、アクセントが異なっていたと考えられています。
さて、ファンレターですが、あて名や住所はどうしたらよいでしょうか。ご存じと思いますが、「紫式部」という名は通称で、本名は不明です。特定するには、越前守などを務めた藤原為時の娘、あるいは、後冷泉天皇の乳母となった賢子の母、というように、本名が判明している人物に関連付けるしかありません。平安文学の他の女流作者たちの多くが、「道綱母」とか「孝標女」のように、本名が伝わらない境遇にあったことも、当時の作品と作者との関係を考える上で忘れてはならないことです。
また、彼女の住所も、京都の父為時の邸、あるいは為時任地の越前や越後、宮仕え先である中宮彰子の居る宮中の藤壺、彰子実家の道長邸(土御門殿)など、一つに決まりません。ただ、彼女の場合は、『源氏物語』執筆中から宮中では有名人になっていたようですから、『源氏物語』の作者、というだけで当時の京都ならファンレターが届いたかもしれません。といっても、ポストも郵便制度もない時代ですから、結局は自分で、あるいは使いの者が彼女の居所を訪ねて、書状を手渡しするしかないわけですが。
さらに紫式部さんに読んでもらうためには、どんな紙にどんなふうに書けばよいでしょう。ファンレターではなくラブレターですが、やってはいけない例が、「虫めづる姫君」(『堤中納言物語』)にありますね。
いとこはく、すくよかなる紙に書きたまふ。仮名はまだ書きたまはざりければ、片仮名に……
これではダメで、薄様の上等な紙に、流麗な仮名文字で書かなくてはいけないでしょう。ただ、彼女は、漢学者でもあった父為時の影響で漢字・漢文にも通じていたようですから、「更衣」などは漢字のままで大丈夫かもしれません。さらに『源氏物語』にちなんだ和歌を詠んで、一つ添えるぐらいのアピールが必要かもしれません。
古典文法再入門として古文作文をしようと、その手始めに紫式部へのファンレターを考えたのですが、いざ始めてみると、文法にとどまらず、文学や言語文化、日本の歴史など、古典探究にも発展できそうな色々な要素があることがわかりました。次は、古文日記に挑戦しようと考えています。
『国語教室』第122号より転載
著者プロフィール
大倉浩(おおくら ひろし)
筑波大学名誉教授
→ 古典文法に関する質問をする
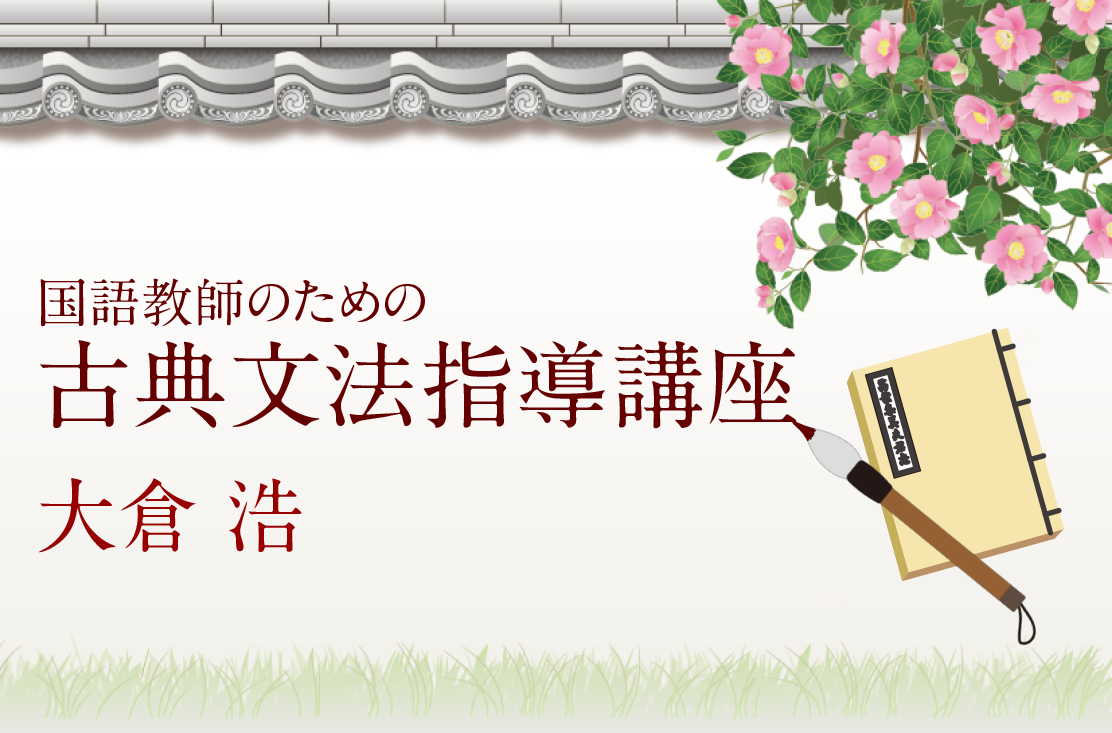
詳しくはこちら
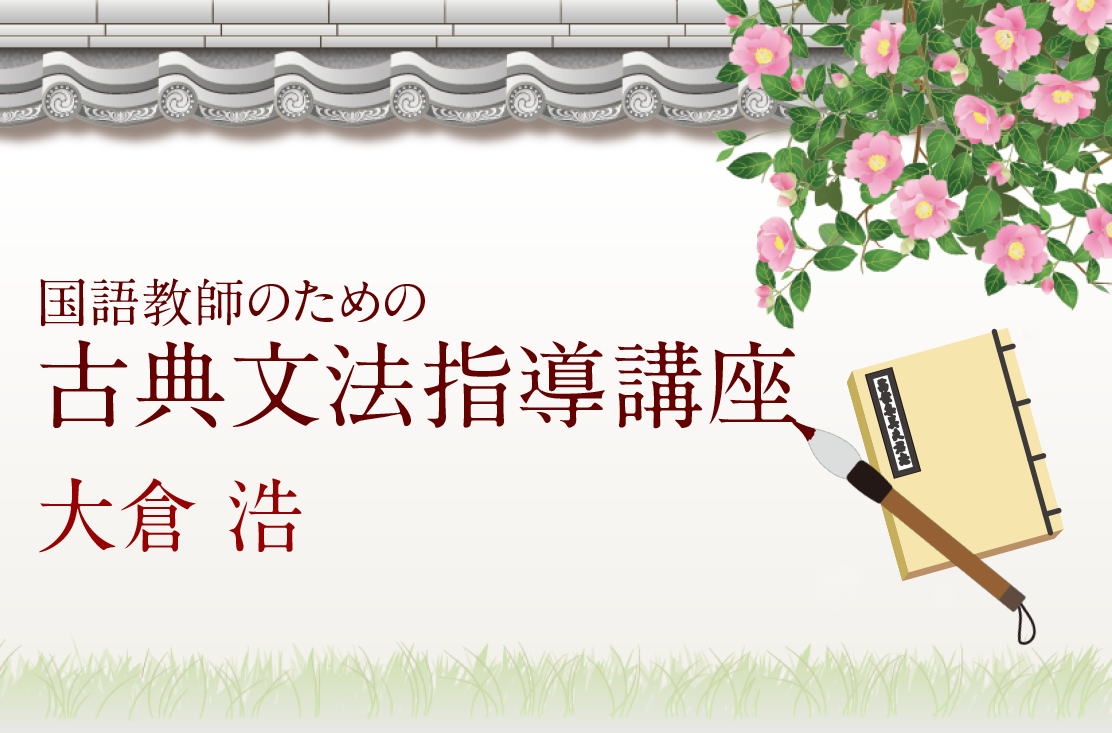
詳しくはこちら
一覧に戻る






