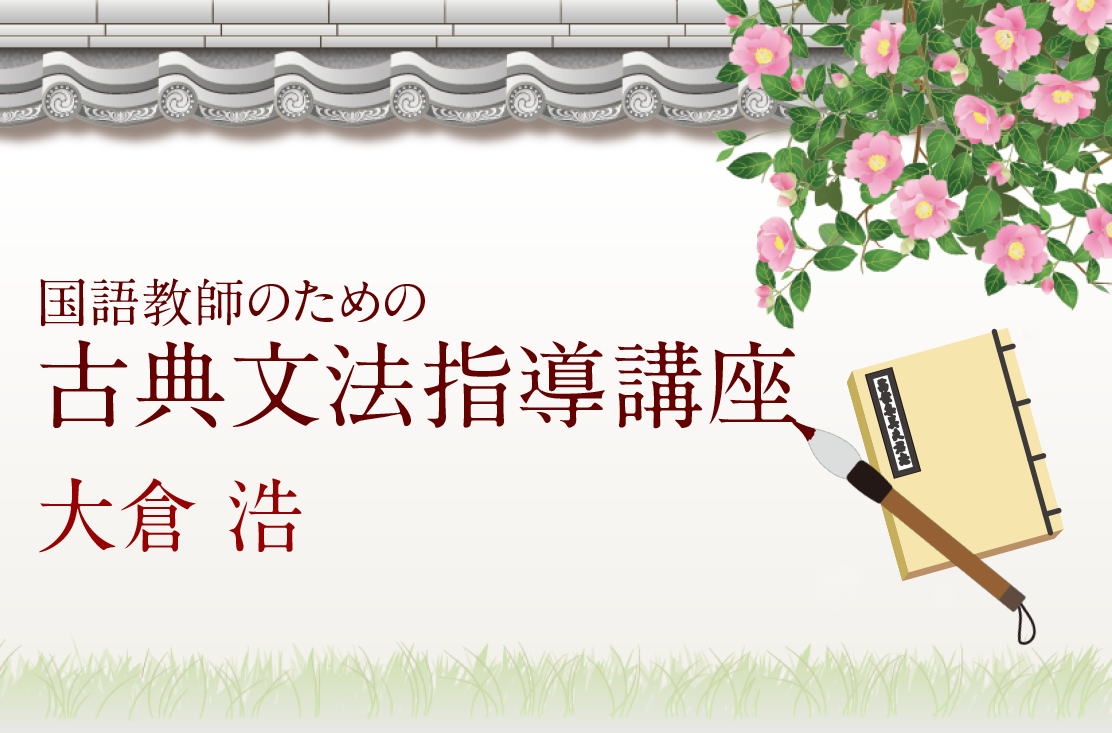国語教師のための古典文法指導講座
第13回 助動詞一覧表を眺める――紫式部にファンレターを書こう⑩
大倉 浩
- 2025.08.22
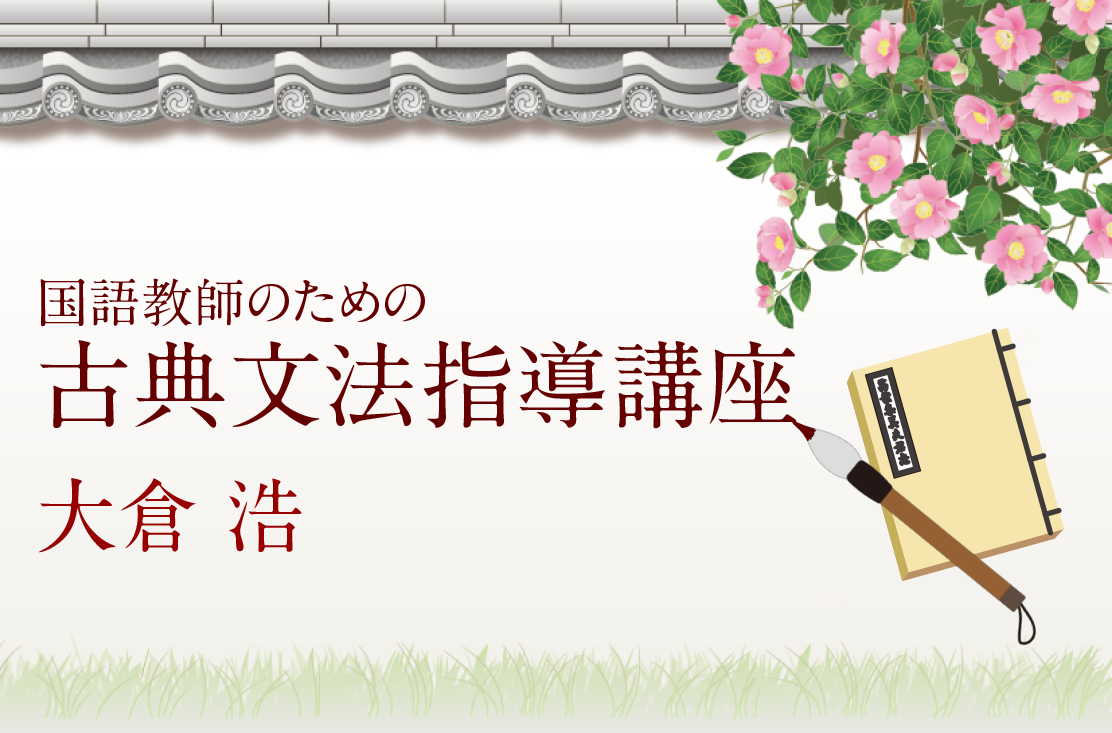
前回「ぞ・なむ・こそ」という「強調」の係助詞が、物語など平安時代の散文において、メリハリを作る働きを持ち、やがてこの働きが接続詞に取って代わられていくという話をしました。
今回は「結び」のほうの形式、活用形ではなく、文末によく現れる助動詞を見てみます。前回同様『竹取物語』の冒頭部分です。
今は昔、竹取の翁といふ者ありけり。野山にまじりて竹を取りつつ、よろづのことに使ひけり。名をば、さぬきのみやつことなむ言ひける。その竹の中に、元光る竹なむ一すぢありける。怪しがりて、寄りて見るに、筒の中光りたり。
文末は「けり・たり」など助動詞ばかりですね。現代の物語(小説)でも、語り手が過去の出来事として「た・であった」と物語るように、古文でも過去の助動詞「けり」が物語の地の文で多用され、動詞や形容詞だけで結ぶことはあまりありません。そして助動詞は、日本語の歴史の中で大きく変化してきました。古語の助動詞約三十語のうち、現代語に残っているのは十語ほど、残り三分の二が衰退しているので、衰退した助動詞の意味・接続・活用を憶えていかないと古文の読解は進みません。
ただ、助動詞三十語をしっかり憶えようとしても、「つ・ぬ・たり・り」がともに完了の意味であったり、「る・らる」が受身・自発・可能・尊敬と四種の意味を表したりと、助動詞と意味が一対一の関係にはないので、憶えづらいし解釈でも迷いがちです。接続も、未然形・連用形・終止形・連体形それぞれに接続する助動詞が複数あり、完了の「り」のように、已然形接続か命令形接続か、古語辞典や副読本でも見解の異なるものもあります。さらに、活用も様々で、六種の活用形のない不完全な助動詞も半分以上あります。打消推量の「じ」のように「○・○・じ・じ・じ・○」と変化しないものもあります。
かりに助動詞三十語すべての意味・接続・活用を憶えられたとしても、すぐに古文の読解が深まるでしょうか? 将棋の駒それぞれの動かし方を憶えたからといって、すぐに将棋が指せるわけではないですよね。各駒の特徴を組み合わせて攻撃や防御を整える、つまり、各駒の共通点や相違点といった関係性がわかってはじめて将棋が指せるようになるのだと思います。助動詞の学習も同様です。助動詞個々の意味・接続・活用を知ることは必要ですが、他の助動詞との関係を知っておくこともとても重要です。そして実は、助動詞一覧表は、そうした関係を教えてくれる便利なツールなのです。
古典文法の副読本や古語辞典、もちろん教科書にも、見開きで「助動詞一覧表」が必ず示されています。助動詞の順序は微妙に違っていますが、多くの場合、未然形接続の「る・らる」「す・さす」から始まって、連用形接続→終止形接続→連体形接続→体言・その他と、接続形の順序に並んでいます。これには理由があるのです。
まず、一覧表を右から左へ俯瞰してみてください。連用形接続には「完了・過去」という「時制」の意味の助動詞が集まっています。終止形には「推量」、連体形には「断定」と、似た意味の助動詞がまとまっています。もちろん例外もありますが、接続と意味が無関係ではないことがわかります。さらに活用を見てみると、未然形接続の助動詞は活用形が完備しているものが集まっていて、連用形接続はやや不備、終止形接続は多くが不備になっています。接続と活用も関係があるのです。それだけでなく、動詞に接続する助動詞の順番も、例えば、
思は・れ・たる・べき・なり。
というように、一覧表の順序に従っています。
ということは、一覧表のどのあたりに位置している助動詞か、周辺の助動詞には何があるか、一覧表を手がかりに、ざっくりと助動詞を束ねて憶えていくことができそうですし、そこには個々の助動詞の意味や接続・活用の理由も隠れています。詳しくは次回になりますが、皆さんも助動詞一覧表を俯瞰してみてください。
『国語教室』第121号より転載
著者プロフィール
大倉浩(おおくら ひろし)
筑波大学名誉教授
→ 古典文法に関する質問をする
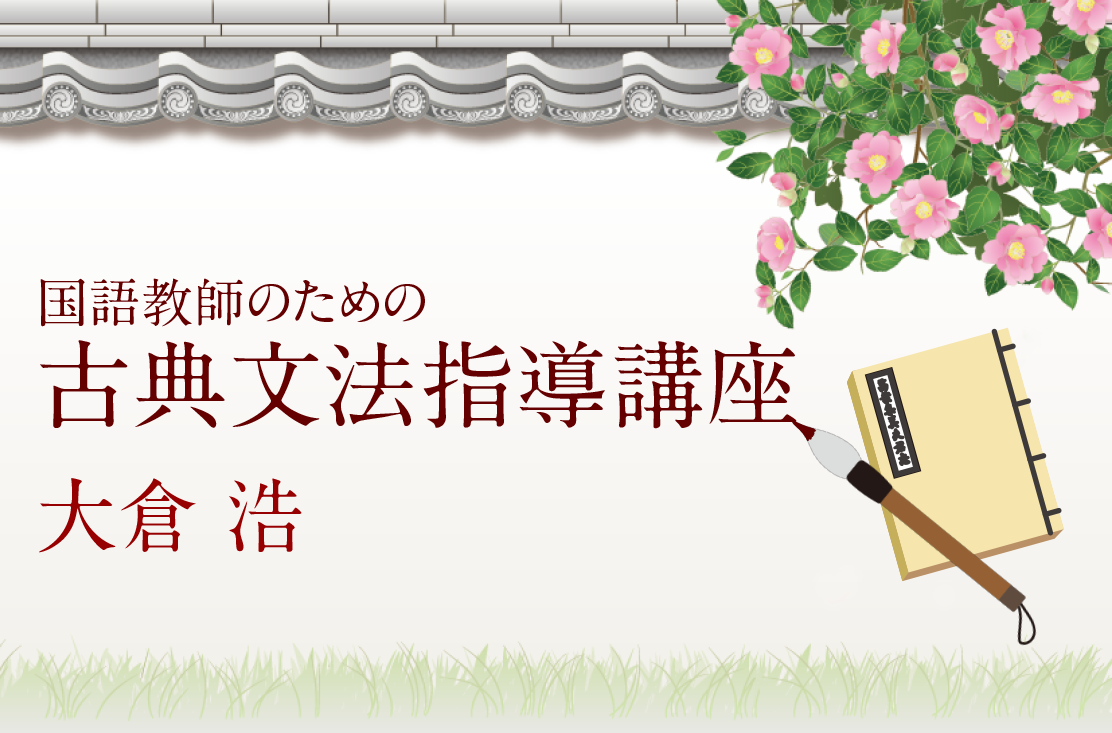
詳しくはこちら
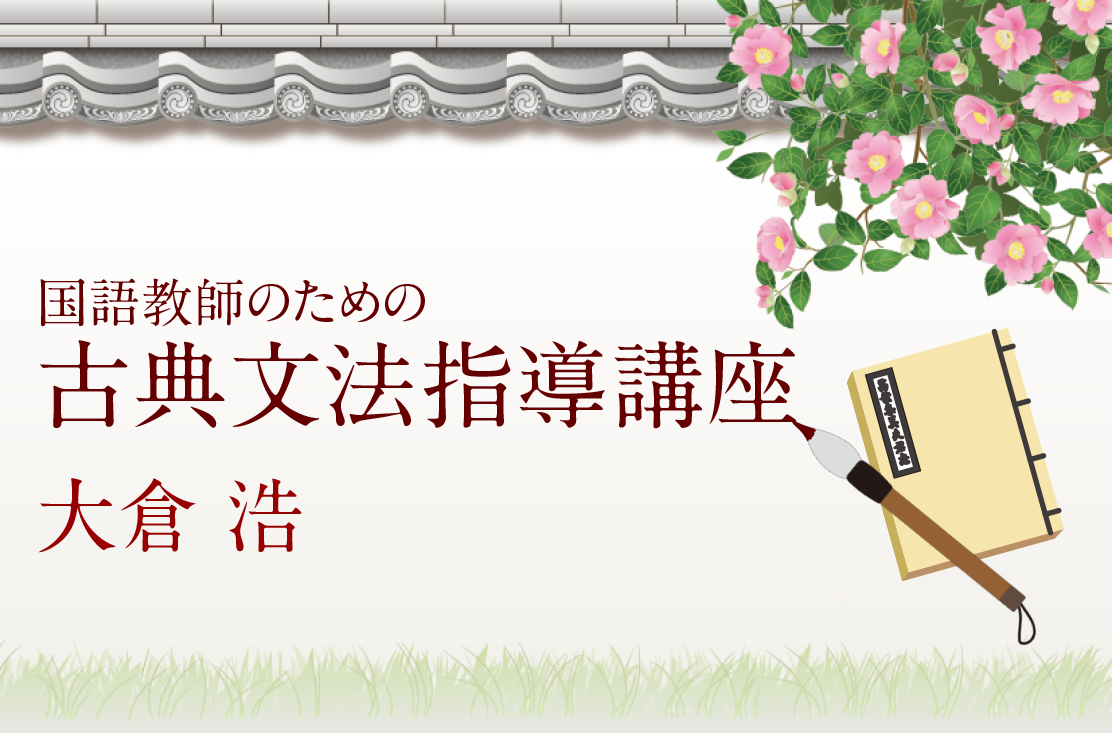
詳しくはこちら
一覧に戻る