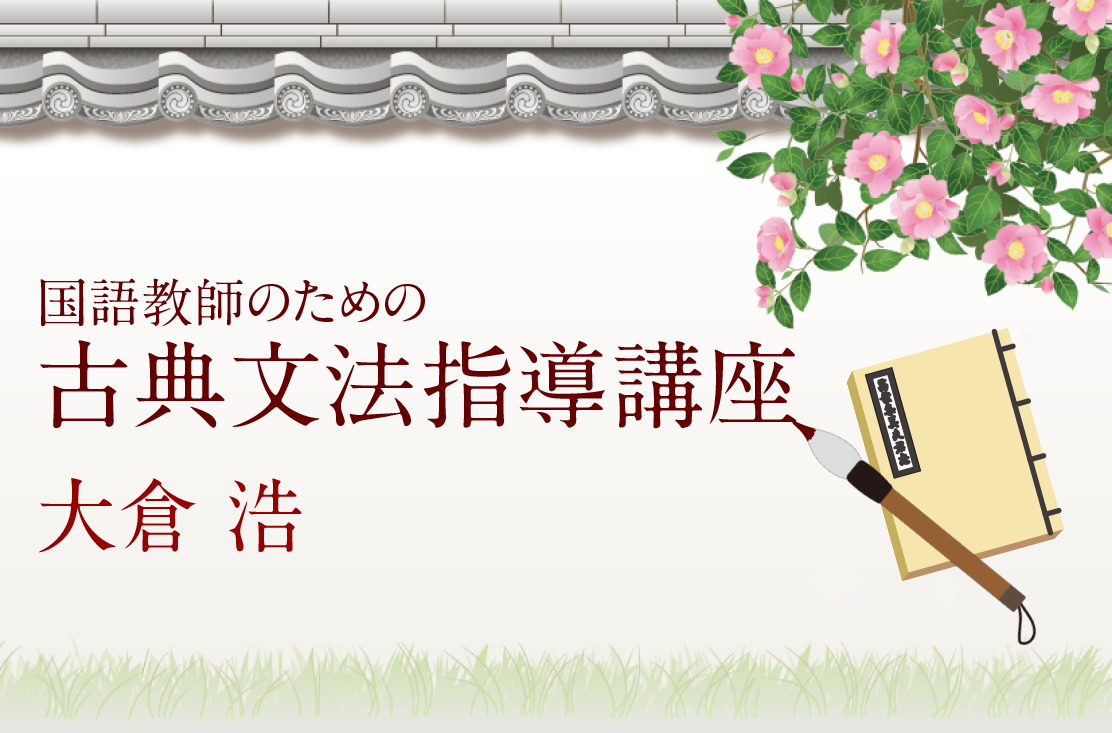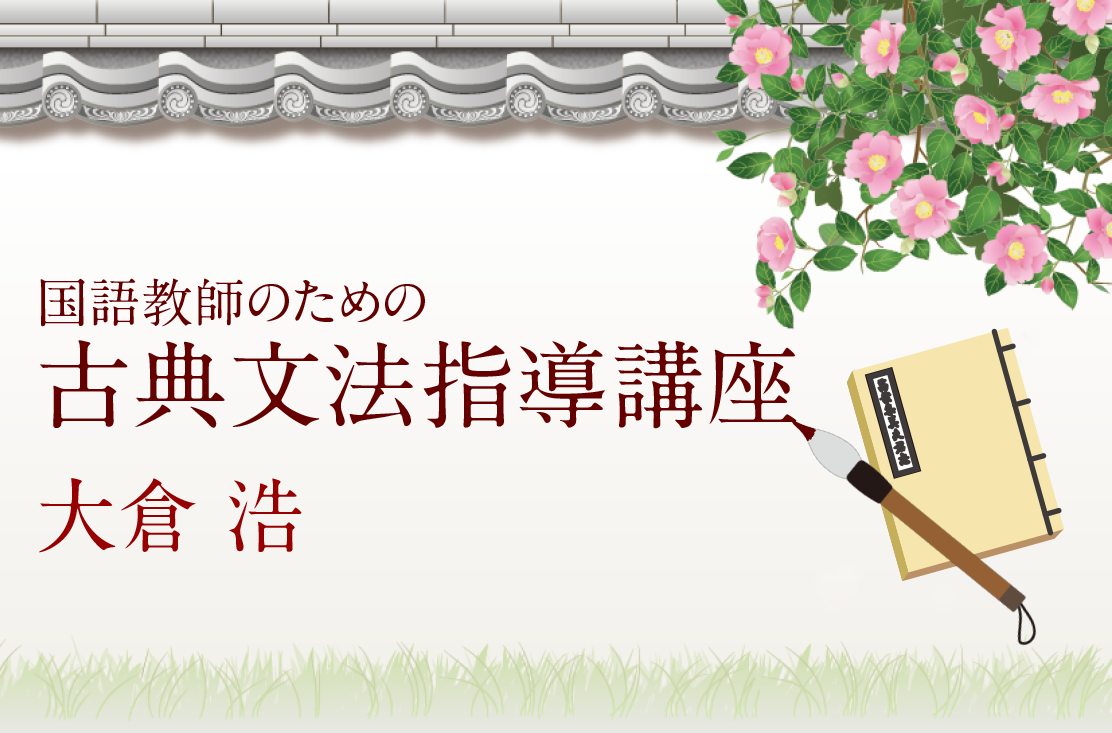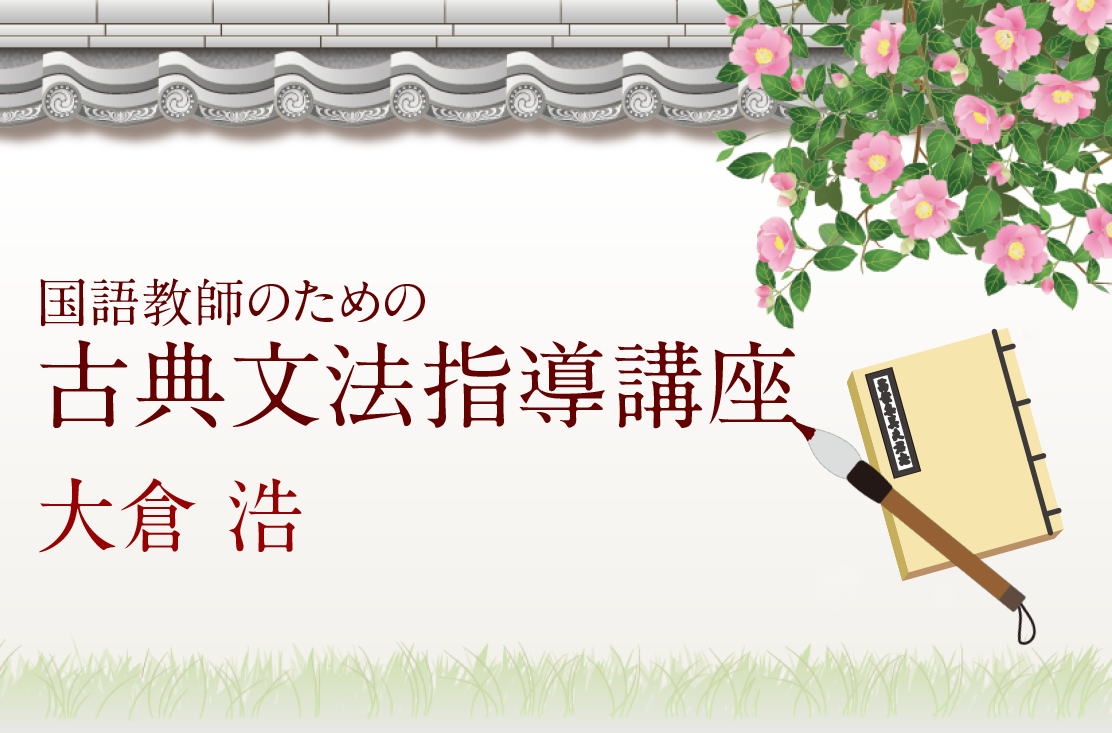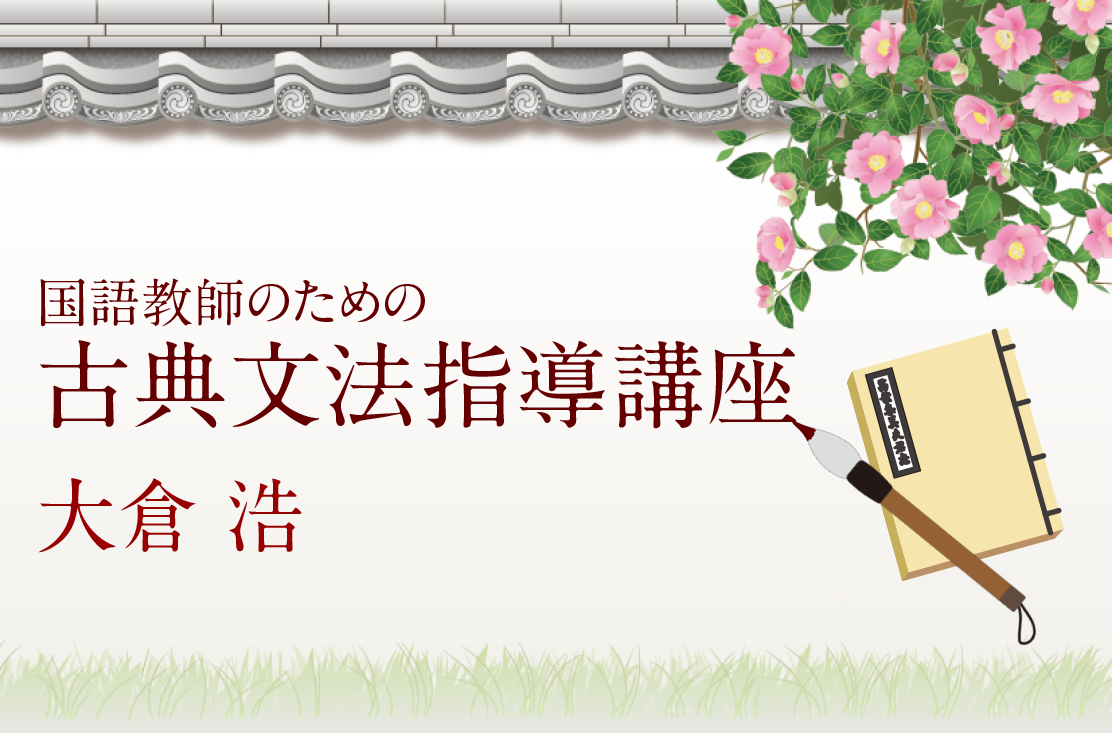国語教師のための古典文法指導講座
第2回 「古典文法」と「文語文法」はどう違う?
大倉浩
- 2019.06.18
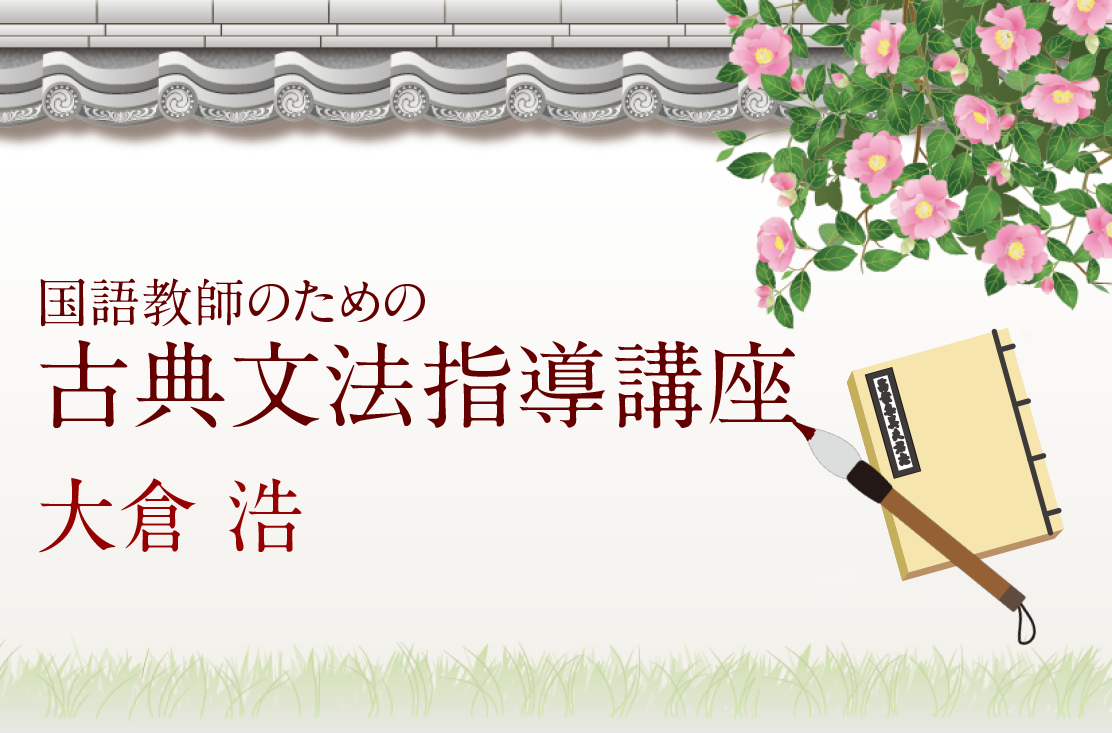
第1回では、和歌など口語訳しきれない古典の韻文を読解するには「古典文法」が必要だ(だから学ぶのだ)、と述べました。しかし、それだけ必要な文法なのに、生徒さんも古文の先生も、用語の難しさや活用の暗記に振り回されて、学んでいても正直あまり「ありがたみ」が感じられないのは何故なのでしょうか。今回はこの理由を、「古典文法」と「文語文法」との違いから考えたいと思います。そこで質問です。
◆質問◆「古典文法」と「文語文法」はどう違う?
名称が違うのですから何か違いはあるはずです。「文語文法」が昔の名称で、「古典文法」が現在の名称でしょうか? ハズレではありませんし、そうした認識を持っている教科書編集者や研究者も少なくありません。ただ、現行(次期も)の学習指導要領では、「文語文法」と呼ばれていて、「古典文法」という呼び方ではありません。しかし、高校の副読本や参考書では、ほとんどが「古典文法」で、タイトルに「文語文法」とある参考書は、ほんのわずかでした。(アマゾンで参考書検索をしたところ、489件対6件でした。)共通部分も多い両者ですが、新旧ではなく、内容にも違いがあるのです。
その一つは、文法が扱う日本語の範囲です。『古事記』『万葉集』などの古文から明治の文章までの日本語の書き言葉、つまり「文語」を対象とするきまりが「文語文法」です。(これに対し、現代の日本語の話し言葉「口語」のきまりが、「口語文法」です。)いっぽう、平安時代を中心とした「古典作品」にあらわれた日本語を対象とするきまりが「古典文法」、という対象の違いです。対象とする範囲が「文語文法」のほうが広く長いと言えそうです。例えば、「係り結び」という文法のきまりは、文語でも平安時代の古典作品でも守られていますから、両方の文法で扱います。しかし、形容詞の活用について見ると、「文語文法」では「良く・ば、悪しく・ば」のような仮定の言い方が、江戸~明治時代の文語にあるので、未然形に「く・しく」を認めます。いっぽう「古典文法」は、平安時代では「良く・は、悪しく・は」という「連用形+は(係助詞)」の用法であったので、形容詞未然形に「く・しく」は無く、「から・しから」しか示しません。副読本によっては、活用表の未然形の枠内に、(く)(しく)のようにカッコをつけて示し、注記するものもあります。
二つ目は、学ぶ目的です。「文語文法」は、文語を読んで書くために学ぶ規範文法です。「古典文法」は、前回述べたように古典作品を読解するため(品詞分解をして古語辞典を引けるようにするため)に学ぶ記述文法で、生徒が文語文を書いたり、文語で短歌や俳句を作ったりすることを目的にはしていません。解釈に使っても、表現には使わない、いわば片道キップの文法なのです。
特にこの第二の違いが、教室での「古典文法」を覚えにくく「ありがたみ」を感じにくいものにしているのではないかと、私は思っています。英語の文法grammarだって難しく、暗記することも多いのに、「古典文法」ほど生徒さんに嫌われていないのは、英文読解だけでなく、自分で書いたり話したり、英語で表現して使うためにも必要だからではないでしょうか。現在完了・過去分詞……たくさん覚えることがあっても、使うことがあれば達成感もあります。けれども「古典文法」はたくさん覚えても、古文を解釈して文法問題を解くばかりです。自分で書いたり話したり、表現に使う場面がまず無いのです。今風にいえば「コスパが悪すぎる」のではないでしょうか。
もちろん、表現に「古典文法」を有効に使う先生方の試みも様々あり、この『国語教室』でも度々紹介されています。さらに、新指導要領ではこうした表現活動も採り上げられていますから、「古典文法」のあり方も変わっていく可能性があります。このことについては次回以降に述べさせてください。
『国語教室』第110号より転載
→古典文法に関するご質問を、こちらからお寄せください。
一覧に戻る