隠れた名作を教室へ ~近現代文学再発見~
第2回 桃太郎(芥川龍之介) 文豪による昔話の再話を読む
桜蔭中学高等学校 平塚夏紀
- 2019.08.05

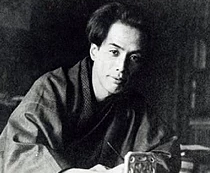
1 芥川と童話
芥川文学の多様性と教材としての魅力に迫るため、今回は、「桃太郎」という作品を取り上げてみたい。
芥川龍之介は、鈴木三重吉が主宰する「赤い鳥」という童話雑誌に参加している。「赤い鳥」の標榜語(モットー)にある、〈世俗的な下卑た子供の読みものを排除して、子供の純正を保全開発する〉という理念に芥川も賛同したと見えて、大岡昇平と芥川龍之介の子息芥川比呂志の対談「芥川龍之介を語る」『日本の文学 第29巻付録』(昭39・10、中央公論社)に次のようなやり取りがある。
芥川 病気のときに自作の童話を、枕元に坐って読んでくれたことがあります。「杜子春」を。自分で一度読んでたしかめる気もあったのですかね。
大岡 あれは、そうとうむずかしい童話ですね。
芥川 子供の読むものにはやかましかったようです。雑誌では「赤い鳥」(鈴木三重吉編集の童話雑誌)を読まされました。ところが普通の本は読ませてくれなかった。
大岡 なるほどお父さんは三重吉の新しい童話運動を積極的に支持してたんですね。
また、芥川は自殺の直前まで自身の童話集『三つの宝』の出版を計画していて、彼の没後に刊行されている。このように芥川が子供の読みものに関しても深い関心を持っている作家であったことを確認したうえで、小説「桃太郎」教材化の可能性を見ていきたい。今回は、芥川の「桃太郎」を読むことを主眼としながらも、関連する神話・昔話を紹介し、生徒たちに親しんでもらうこともねらいとしている。
2 小学校唱歌「桃太郎」の歌詞
ところで、桃太郎に対して生徒たちがあらかじめ抱いている印象はどんなものだろうか。犬・猿・雉を従えて鬼ヶ島の鬼を征伐した勇敢な少年というように、肯定的に捉えている人が多いのではないか。「桃太郎さん、桃太郎さん~~♪」で始まる唱歌で親しんでいる人も多いことだろう。その唱歌の三番までの歌詞をまずは引用しておきたい。
一、桃太郎さん 桃太郎さん お腰につけた 黍団子 一つわたしに 下さいな
二、やりましょう やりましょう これから鬼の 征伐に ついて行くなら やりましょう
三、行きましょう 行きましょう あなたについて 何処までも 家来になって 行きましょう
ここまでは、誰もが慣れ親しんでいる歌詞だが、この後の歌詞については知らない生徒が多く、授業で紹介すると驚かれるにちがいない。
四、そりゃ進め そりゃ進め 一度に攻めて 攻めやぶり つぶしてしまえ 鬼が島
五、おもしろい おもしろい のこらず鬼を 攻めふせて 分捕物を えんやらや
六、ばんばんざい ばんばんざい お伴の犬や 猿 雉は 勇んで車を えんやらや
明治時代の唱歌として小学校で歌われていたのが驚きの歌詞であるが、生徒とともにこの歌を歌った上で、歌詞の内容について考えたことを話してもらい、四番以降の歌詞がなぜ歌われなくなったかについても意見を出してもらうといいだろう。
3 神話と桃
桃太郎では、おばあさんが川に洗濯に行ったときに桃が流されてくるわけだが、芥川はこの桃がもともとどこにあったかということから書き起こしている。
むかし、むかし、大むかし、ある深い山の奥に大きい桃の木が一本あった。大きいとだけではいい足りないかも知れない。この桃の枝は雲の上にひろがり、この桃の根は大地の底の黄泉の国にさえ及んでいた。何でも天地開闢の頃おい、伊弉諾の尊は黄最津平阪に八つの雷を却けるため、桃の実を礫に打ったという、――その神代の桃の実はこの木の枝になっていたのである。
この桃の木に生った桃が赤ん坊を孕む桃で、このうちの一つが八咫烏につつかれて人間の国の谷川へと流れてきたのだというのである。生徒の中には、記紀神話になじみが薄くこの設定を聞いてもピンとこない人も多いと思う。記紀神話を教えるというと何か国粋主義的な雰囲気がして避けられているのかもしれないが、前回取り上げた「おしの」における宗教と同様、イデオロギー的な立場にかかわらず日本の古代神話の内容をある程度教養として知っておくことは生徒が将来生きていくうえで重要なことだ。鈴木三重吉が『古事記物語』にわかりやすく物語をまとめてくれているので、関連箇所をプリントにして読み合わせたうえで、この小説「桃太郎」の書き出しに戻ると設定の面白さが味わえる。
4 既存のイメージを覆す設定
桃太郎の鬼ヶ島征伐の目的は童話ではあまり明確に語られず、「鬼なんだから悪いやつに決まっていて、それを倒そうとする桃太郎は善人に決まっている」などと特に疑問を感じずに聞いたり読んだりしているだろうが、芥川の小説「桃太郎」にはそんな人々のイメージを壊す様々な設定が仕掛けられている。桃太郎が鬼ヶ島へ征伐に行く目的は本作では「お爺さんやお婆さんのように、山だの川だの畑だのへ仕事に出るのがいやだったせいである。」と語られていて、「老人夫婦は内心この腕白ものに愛想をつかしていた」と説明されている。勇敢な正義の英雄のイメージからは程遠い。
犬・猿・雉に黍団子をあげて仲間にする場面にも様々な設定がちりばめられている。犬を仲間にする場面を引用する。
桃太郎は意気揚々と鬼が島征伐の途に上った。すると大きい野良犬が一匹、饑えた眼を光らせながら、こう桃太郎へ声をかけた。
「桃太郎さん。桃太郎さん。お腰に下げたのは何でございます?」
「これは日本一の黍団子だ。」
桃太郎は得意そうに返事をした。勿論実際は日本一かどうか、そんなことは彼にも怪しかったのである。けれども犬は黍団子と聞くと、たちまち彼の側へ歩み寄った。
「一つ下さい。お伴しましょう。」
桃太郎は咄嗟に算盤を取った。
「一つはやられぬ。半分やろう。」
犬はしばらく強情に、「一つ下さい」を繰り返した。しかし桃太郎は何といっても「半分やろう」を撤回しない。こうなればあらゆる商売のように、所詮持たぬものは持ったものの意志に服従するばかりである。犬もとうとう嘆息しながら、黍団子を半分貰う代りに、桃太郎の伴をすることになった。
ここで生徒に考えてもらいたいのは、桃太郎が黍団子という餌で犬を家来にしたことの意味についてである。「あらゆる商売のように」という部分から明らかなように、桃太郎と犬の関係は雇用主と被用者の関係となっている。雇用主である桃太郎は、いかに安い報酬で犬を使用するかを考え、自分でも日本一かどうか怪しい黍団子を日本一と持ち上げて「一つはやられぬ。半分やろう。」と言う。それでも「一つ下さい」を繰り返す犬も結局半分の黍団子で労働力を提供することになってしまう。「所詮持たぬものは持ったものの意志に服従するばかり」という言葉からも分かる通り、労働力を不当に安く買いたたく社会への風刺になっていると言えるだろう。
他の童話からの設定の引用は、この小説の読みどころの一つだ。犬か猿を噛み殺そうとし、「もし雉がとめなかったとすれば、猿は蟹の仇打ちを待たず、この時もう死んでいたかも知れない。」と書かれているのは、猿蟹合戦からの引用であるし、鬼ヶ島に「打出の小槌という宝物さえある」というのは一寸法師を連想させる。このほかにも鬼についての説明の中で瘤取り爺さんの話、大江山の酒呑童子の話、羅生門の茨木童子の話が持ち出されている。時間がかけられるのならば、この一つ一つの作品をプリントにして生徒と読み合わせたいところである。
『宇治拾遺物語』や『御伽草子』の原文または現代語訳を示すことで古典に親しむ単元につなげることもできる。紙芝居を準備して生徒に実演してもらうのもいいだろう。これまであまり昔話に触れてこなかった生徒にそのきっかけを作ることができたらいいと思う。おそらく教室にいるほとんどの生徒が酒呑童子や茨木童子の話を知らないので他の童話を読む時間はなくとも、酒呑童子や茨木童子のエピソードの紹介は最低限必要であろう。
5 現代につながるメッセージ性
小説「桃太郎」では、鬼たちは熱帯的風景の広がる孤島で平和を愛し、踊りを踊ったり詩を歌ったりして生活している。そして、人間は恐ろしいものだと孫に話して聞かせている。そんな中、桃太郎が侵略してきて乱暴狼藉の限りを尽くして「あらゆる罪悪の行われた後、とうとう鬼の酋長は、命をとりとめた数人の鬼と、桃太郎の前に降参」する。
「では格別の憐愍により、貴様たちの命は赦してやる。その代りに鬼が島の宝物は一つも残らず献上するのだぞ。」
「はい、献上致します。」
「なおそのほかに貴様の子供を人質のためにさし出すのだぞ。」
「それも承知致しました。」
鬼の酋長はもう一度額を土へすりつけた後、恐る恐る桃太郎へ質問した。
「わたくしどもはあなた様に何か無礼でも致したため、御征伐を受けたことと存じて居ります。しかし実はわたくしを始め、鬼が島の鬼はあなた様にどういう無礼を致したのやら、とんと合点が参りませぬ。ついてはその無礼の次第をお明かし下さる訣には参りますまいか?」
無論、鬼ヶ島征伐の大義など最初からないのである。桃太郎は明瞭な回答を与えることができない。生き残った鬼たちは桃太郎への復讐を考えるようになり、
寂しい鬼が島の磯には、美しい熱帯の月明りを浴びた鬼の若者が五六人、鬼が島の独立を計画するため、椰子の実に爆弾を仕こんでいた。優しい鬼の娘たちに恋をすることさえ忘れたのか、黙々と、しかし嬉しそうに茶碗ほどの目の玉を赫かせながら。
鬼ヶ島をこのように変えたものは何だったのか。生徒たちにじっくり考えてもらいたいところだ。大正時代に書かれた小説であるが、今なお重要な示唆を与えてくれる作品である。
【取り上げた作品】桃太郎
[初出]『サンデー毎日 夏期特別号』1924(大正13)年7月
【参考リンク】鈴木三重吉「古事記物語」

詳しくはこちら
一覧に戻る






