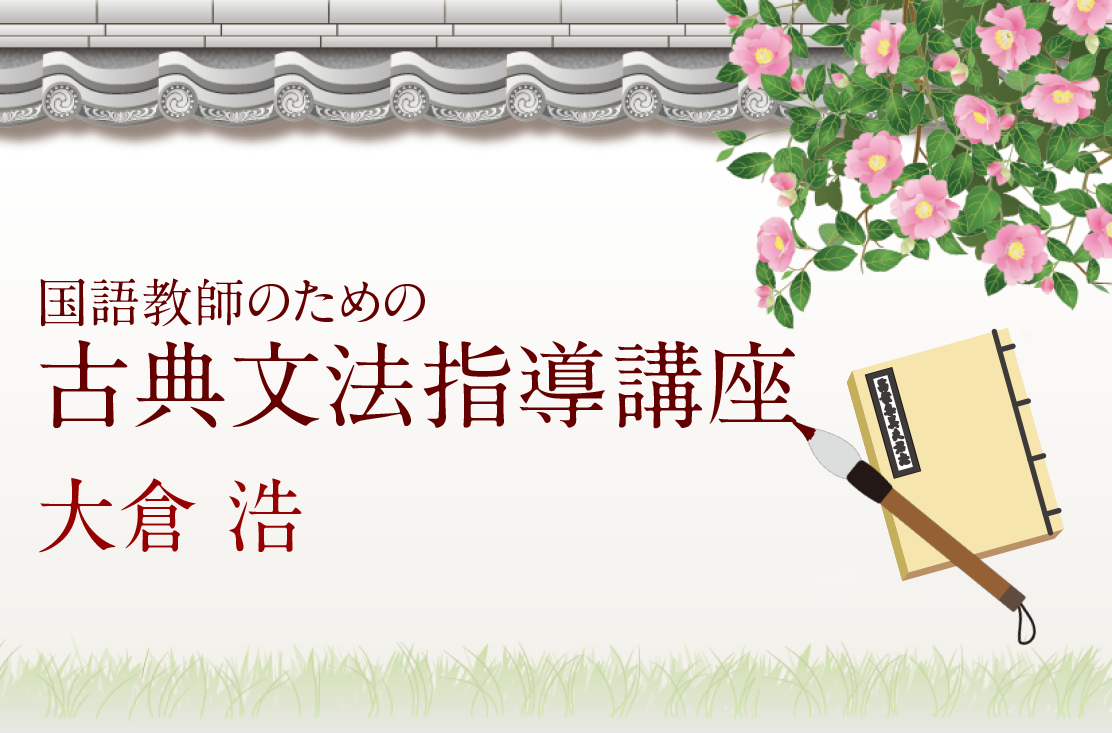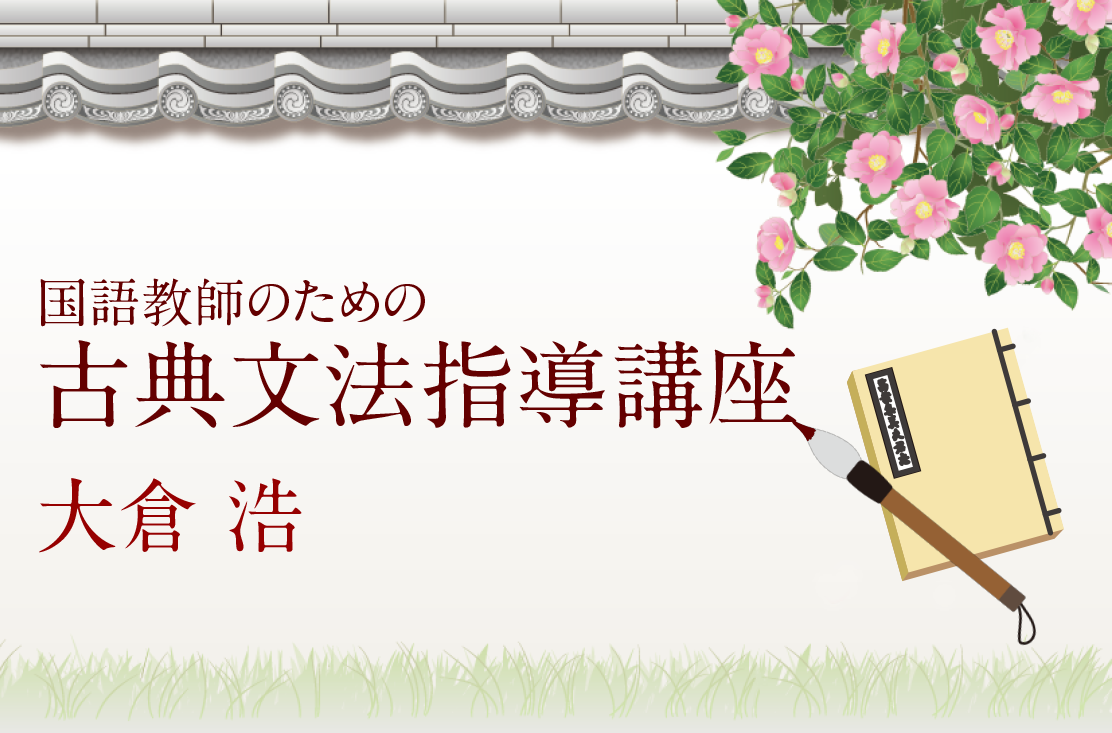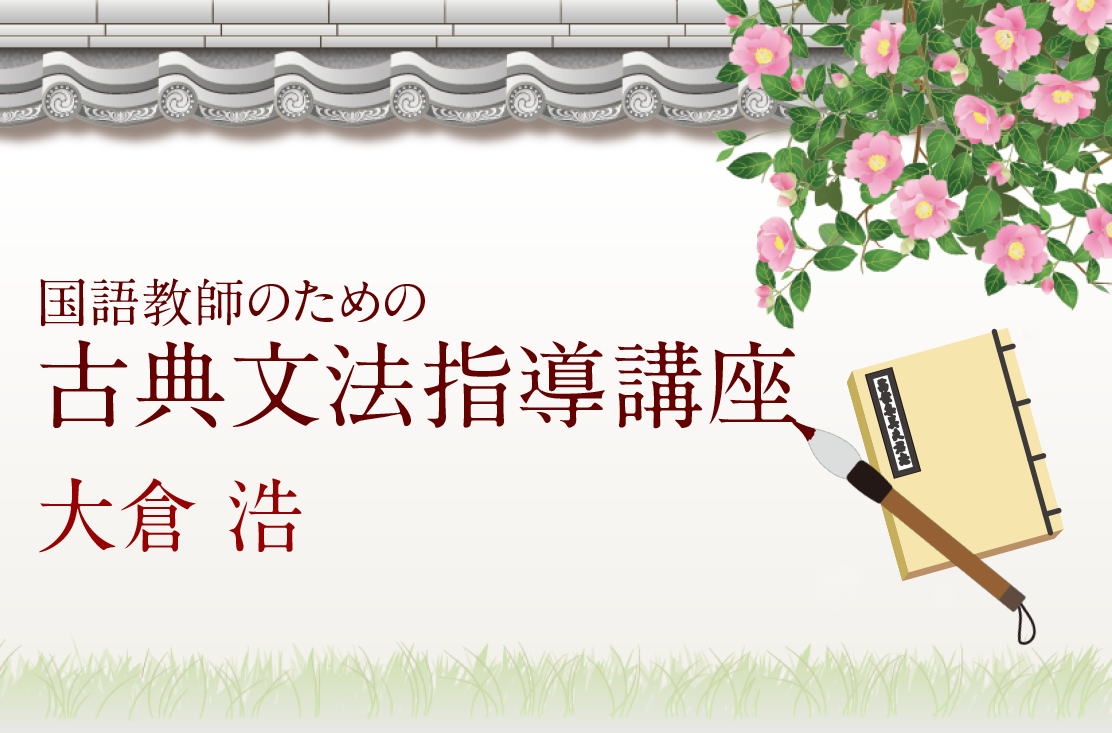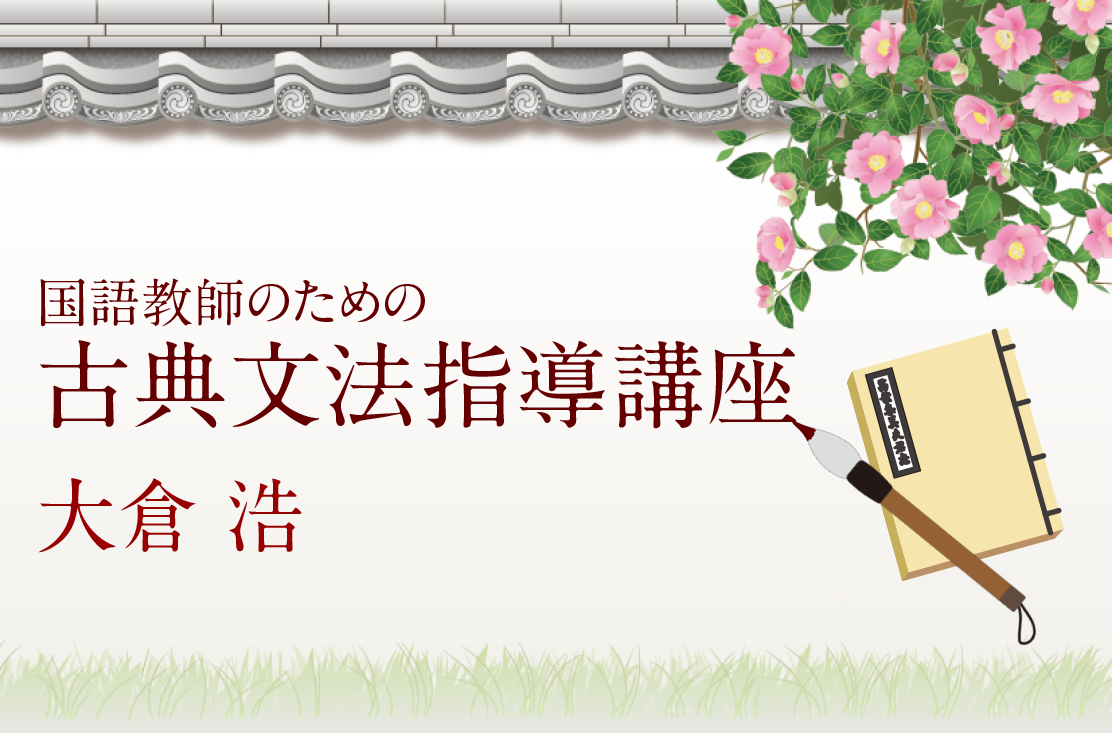国語教師のための古典文法指導講座
第3回 自分の「名前」を「なまへ」に変換!
大倉浩
- 2019.11.27
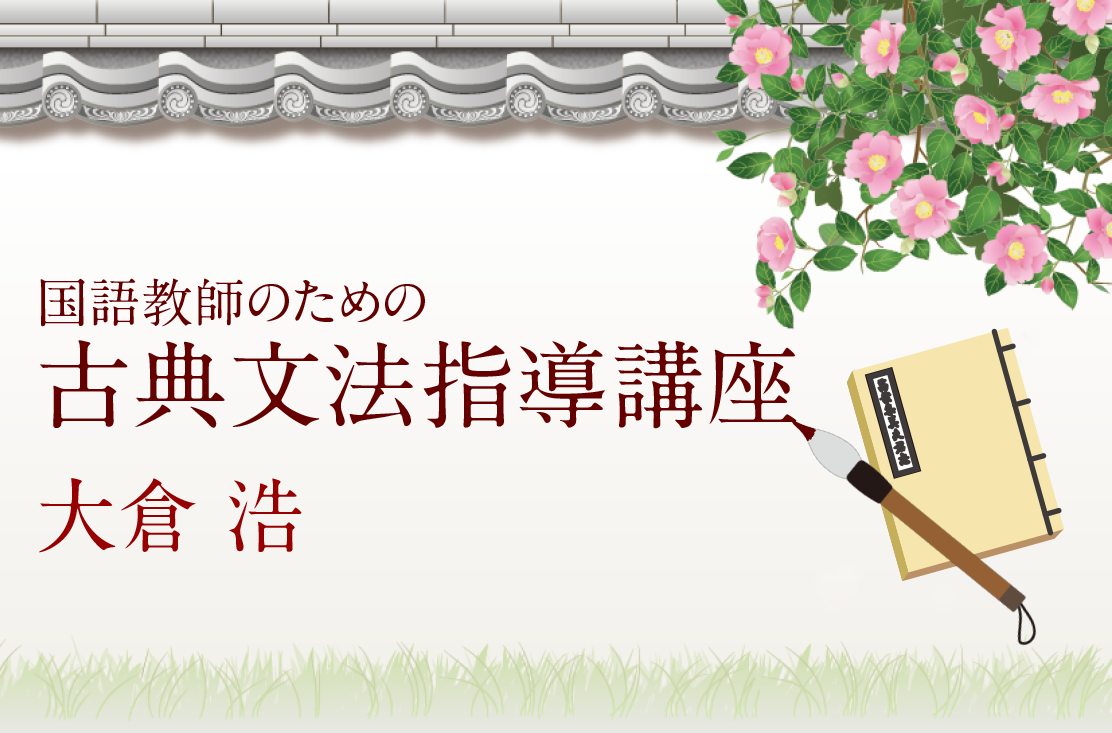
第2回では、読解・解釈専用になっている現在の「古典文法」のあり方を、「文語文法」と比較して述べました。生徒さんが書いたり話したりという表現活動に、現状ではほとんどつながらない「古典文法」ですが、新指導要領での創作活動のこともあり、今回はそのきっかけにもなるようなことを考えてみました。
◆課題◆ 自分の姓名を歴史的仮名遣いで書き直そう。
いろは歌を書いたり、古文を写したりするのも古典文法を使うきっかけになるのですが、やらされている感じが残ります。いちばん身近な言葉、自分の名前の変換から古文作文に繋げてみます。
例えば、私の名前「大倉浩」は、
おほくら(の)ひろし
のようになります。歴史的仮名遣いは、『広辞苑』など多くの国語辞典で、現代仮名遣いの見出しの後に、漢字表記とともに「大倉 オホクラ」のように示していますから、まずはこれでわかります。すると、麻生太郎氏は「あさふ(の)たらう」に、櫻井翔くんは「さくらゐ(の)しゃう」になります。国語辞典でうまく見つからない場合は、漢和辞典で、使われている漢字の音(字音)や訓を調べて、その歴史的仮名遣いから考えます。綾瀬はるかさんのように「あやせ(の)はるか」で、変わらない人もいますが、学校名や地名などを加えれば違いは出てくるはずです。例えば「大修館高校一年生 鈴木祐介」君は、「たいしうくゎんかうかういちねんせい すゞきのいうすけ」君になります。
すでに生徒さんたちも古文の読み方で、
ゐ→い ゑ→え かう→こう しゃう→しょう
となることは知っていても、自分の名前の「利恵」が「りゑ」と変換されるとけっこう衝撃的ですよね。「ゑ」の仮名じたいが漢字「恵」のくずしなのです。また、読み方は同じ「マイ」さんでも、「真衣」は「まい」で変わりませんが、「舞」さんは「まひ」になります。そうです、「舞ふ」というハ行四段活用動詞の連用形「舞ひ」に由来するからです。「ヒロシ」は「広し」、「タカシ」は「高し」で、古語の形容詞終止形なのです。このように文法の知識も必要なのです。書き方がわかったら、古典の教科書やノートの氏名欄は歴史的仮名遣いで書くのも楽しいかもしれません。
もちろん、全てのイやエの音が、昔はヰwiやヱweの音だったわけではありません。約千年前の平安時代には、犬(いぬ)のイiと猪(ゐのしし)のヰwiが別の日本語の音として区別されていたので、それぞれ「いぬ」「ゐのしし」と仮名表記していたのです。千年前には漢字の言葉もまだ中国語からの外来語の意識でしたから、中国語の発音を取り入れて「観音さま」を「クヮンオンさま」と呼んでいたわけです。平安時代の発音に従って当時の人が書き記した文章も、現代人には、複雑な仮名遣いの古文の文章に見えますが、千年間の日本語の発音の変化がじゃまをしているだけで、当時の人たち(識字層ですが)には無理なく読めて理解できた文章なのです。自分たちの名前を書くだけでも、読むだけだった古文が身近になってきませんか。
さて、古文作文のレベルをもう少し上げていきます。次の課題です。
◆課題◆ 紫式部にファンレターを書いてみよう。
イケメン光源氏くんがタイムスリップして現代日本のOLさんの前に現れる騒動を描いた面白いマンガを、高校の先生から紹介いただきましたが、その裏返しです。現代の我々から平安時代に連絡してみましょう。スマホではつながらないでしょうから、手紙です。そうすると、紫式部の住所は? 宛名は? 当時の京都のことや彼女たちの生活に関心が向いてきます。さらに、彼女に読んでもらうためには、当時の日本語で表現しなくてはなりません。どう書いたらいいか? 次回考えていきましょう。
『国語教室』第111号より転載
→古典文法に関するご質問を、こちらからお寄せください。
一覧に戻る