座談会
新課程の国語 いよいよスタート!
石原徳子・大井和彦・杉本紀子・永田里美・藤森裕治・山下直
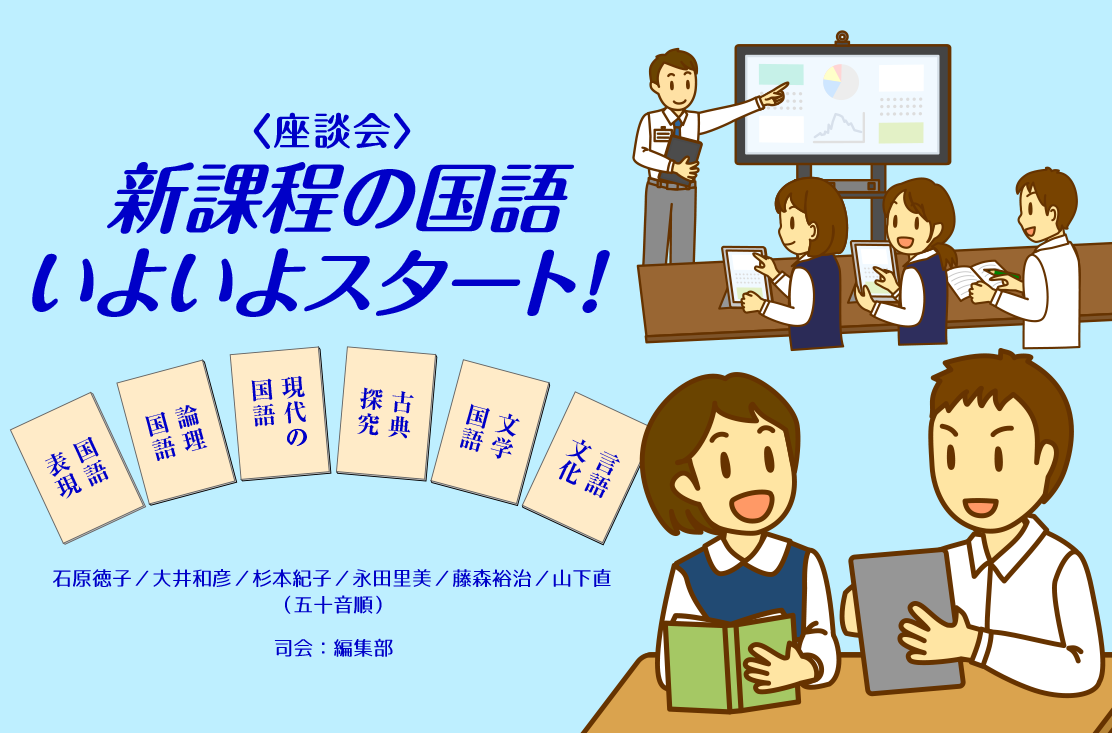
今春から、いよいよ高校国語での新課程の授業が始まります。「戦後最大の改革」と呼ばれた学習指導要領の改訂。新しい国語科の授業は、どのようなスタートとなるでしょうか。大修館書店では、必修科目4点、選択科目7点、計11点の新教科書を刊行します。各教科書に込められた思いや、それを使ってどのような授業が考えられるかについて、編集委員の先生方に語り合っていただきました。

新課程、ついにスタート!
──いよいよ新課程が始まります。学校現場ではどんな雰囲気でしょうか?
永田 新しい教科書の採択も決まって、いよいよ始まるんだな、というイメージができてきたという印象です。表現する時間が増えることで、観点別の評価をどうしようと不安に思っている先生が多いと感じています。
石原 勤務校では2、3年、実験授業をしていたので浸透はしている印象です。やはり評価はネックですね。
山下 義務教育ですでにやっていることを、高校でどうやるか、ということなので、本来であれば、あまり構えすぎる必要はないのかなと思います。
藤森 生徒自身の成長は数値的・機械的には評価しきれないものです。話し合いが表面的にうまくできても、パフォーマンスだけで実はあまり中身のない生徒も多い。逆に話すのは上手でなくても、なぜできなかったか、どういう点ができず悔しかったか、ということが正確に説明できれば力はあるとも言えます。評価は指導の実態によるでしょう。
石原 確かに、どうしても5段階評価などの数値的な評価に収斂してしまう面があって、限界を感じています。
藤森 限界があるのは事実なので、ある程度割り切ってもよいと思います。観察による評価を、しっかり行った上で。
大井 論理と文学を分けられるのか、という不安を示す先生も多いですね。でも、そういう限定的な見方よりも、もっとコンピテンシーに着目するといいのかなと思います。教えることの実質はそれほど変わっていなくて、それらのコンピテンシーが科目ごとに明示されたというふうに受け止めるべきなのでは、と。
山下 そうそう。ちなみに「現代国語」ができた当時は、何を教えればいいかわからないと言われていたんですよね(国語=古典の時代)。でも、研究会等の実践発表ではいまや現代文の方が主流になった。今回の改革も、いきなり「活動」を全部やらなきゃ、と考えるのではなく、できそうなところから徐々に慣れていけばいいと思います。あとで詳しく話しますが、そういうニーズに合致した教科書になりました。
杉本 新課程に抵抗感がある先生は、取り組む活動のイメージがあまり湧かないのではないかなと思います。大修館の教科書には、「やってみよう!」と思える活動のヒントが満載なので、活動が思いつかない、イメージしづらいという先生こそ使ってほしいな、と思います。
取り組みやすい「現代の国語」
──では、具体的な新教科書の話をうかがいます。「現代の国語」2冊はどんな教科書になりましたか。
山下 さっきも話に出ましたが、すんなり入れる、ということを意識しました。国語はすごく変わった、と世間では言われていますが、抵抗を感じない、使いやすいと思ってもらえる教科書にしたいと思いました。「話す・聞く」「書く」単元の冒頭に、活動の参考になる「導入」という文章を入れるなど、工夫を凝らしました。
石原 「こういう風にやれば話せるようになる」、という自分自身の経験もふまえて作りました。スライドを用いたプレゼンやスピーチなど、実際の社会で役立つ内容を豊富にそろえられたのがよかったです。取り上げた活動も、楽しそうに仕上げられました。
大井 「話す・聞く」などの「現代の国語」的な学びについて、国語科のアイデンティティ、他教科では担わない部分をはっきり示したという意味で、大きな意味をもつ変革だなと思います。特に『現代の国語』(現国706)のほうは、最初からコンピテンシーを明示している感じがしますね。
藤森 文章があって、それを受けて書く活動が設定されていることが多いですが、慣れている先生は逆にして、まず書かせてから、その後に文章のお手本として読む教材に進む。そうすると、生徒の食いつきが変わってくるでしょう。『現代の国語』の吉見俊哉「インターネット時代の音楽産業」(109ページ)も、統計資料を用いた文章のお手本として学ぶところがとても多い。どうすれば生徒に教材への興味をもたせるか、という観点では、このような教材・単元設定は、文章を読むことへの意欲が高まるので非常にいいですね。
石原 「社会への視点②」(186ページ)の、いわき野菜の魅力を伝えるCM作成の活動も。相手を意識して伝える、ということの学習にすごくいいですね。動画を使う授業も楽しそう。いまの生徒は動画の編集なども大変上手なので、動画を作りながら学ぶ授業もやってみたいと思いました。

神奈川県立多摩高等学校教諭
大井 『新編 現代の国語』(現国707)は、スキルを段階的に勉強していく流れがしっかり感じられます。従来の「国語総合」と異なる点として、活動やスキルに紐づける形で評論など「読むこと」の教材が並んでいるのがいい。「ザ・現代の国語」ですね。
山下 話したり書いたりすることが苦手な生徒も、この教科書に沿ってやれば本当に力がつきますよ、というものになった。それから、国語科では、「何ができるようになったのか」が見えなくなりがちですが、今回は単元のねらいが明示されているし、素材も具体的なので、生徒も何ができるようになったかが見えやすい。見た目では、『新編 言語文化』(言文706)と同じで、紙面の作り方がとてもビジュアルで、見ていて楽しいですね。
大井 経験がないと活動のアイディアが見えにくいですが、大修館の教科書では活動の中身や目標が一目で見えるので、やりやすそうです。
永田 教員が使いやすいのはもちろん、生徒にとっても目標がわかりやすいものになっていますよね。「活動」というと無理やりやらされているように感じる生徒もいるかもしれませんが、今回の教科書では、単元の目標にもとづいて具体的な活動が載っているし、その目的に見合った文章が載っているので、やるべきことが見えやすく、モチベーションも上がりそう。
藤森 具体的な教材では、『新編 現代の国語』(現国707)は座標軸の思考ツール(127ページ)が載っているのがいいなと思いました。
石原 いかにも「現代の国語」らしい「構成」「論理」などの要素に加えて、「パン屋の手紙」「企画書 となりのトトロ」のような心に訴える「依頼文」や「企画書」の例も、両方の教科書に入っているのがうれしい。心に訴えながら文章の目的に応じて必要な要素が押さえてあり、「いいお手本」になりそうです。
言語文化の「窓」を閉ざさないために
──「言語文化」はいかがでしょう。
永田 『言語文化』(言文705)の編集会議では、指導要領もふまえて、「つなげること」「広げること」「深めること」を意識しました。教科書の構成や、1冊をとおしたコラムなど、随所にその思いを盛り込みました。生徒には教科書を出発点にしていろいろな「言語文化」を学び、自身の表現にもつなげてほしいと思います。
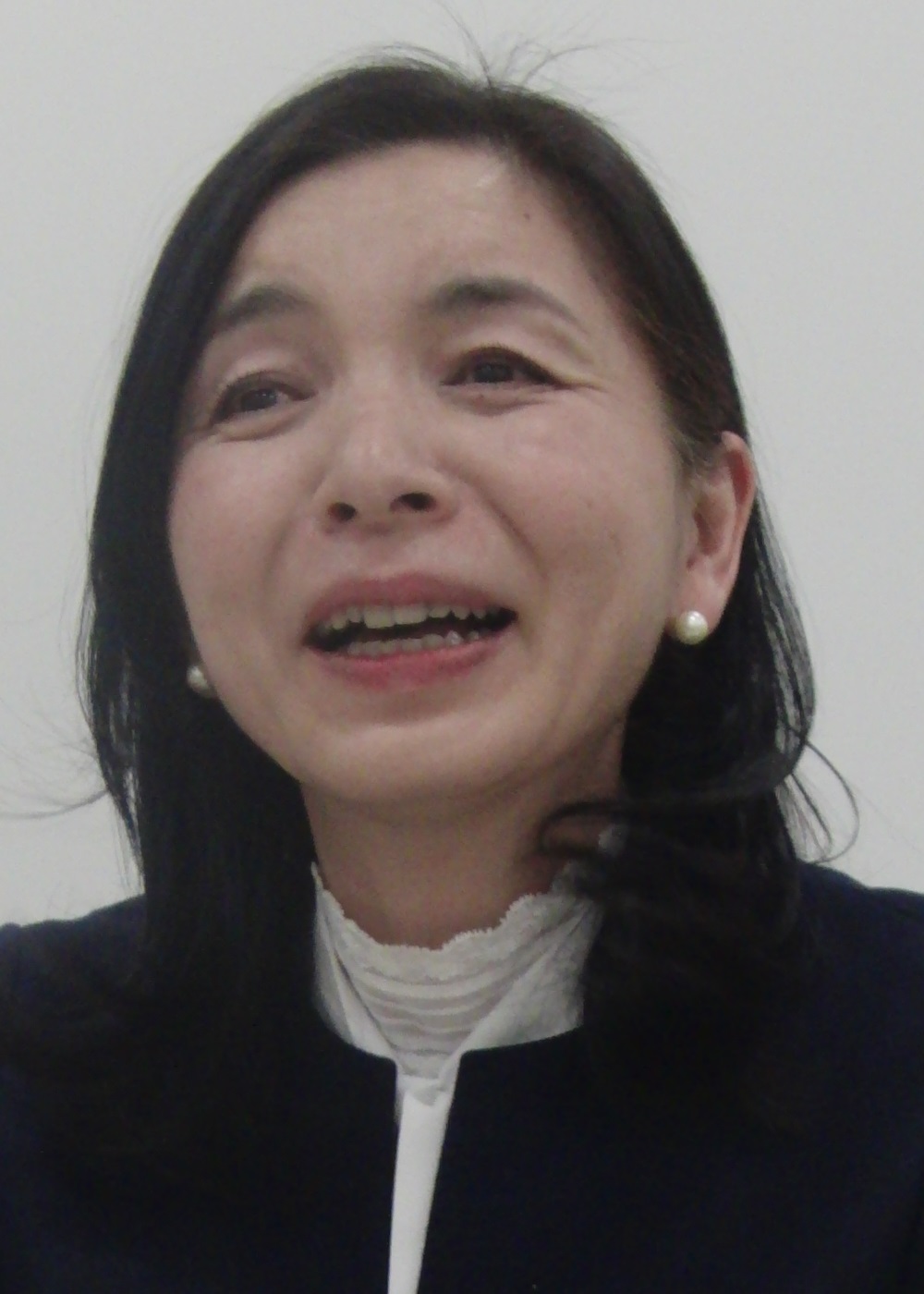
明星大学准教授
藤森 『言語文化』の学びでは、言葉をとおして世界を見つめることを意識してほしいと思います。各国で、いろんな形や向きをした、言葉の「窓」がある。それらを知ることで、生徒が自分の「窓」に新鮮な風を感じられるような教科書になってほしいと考えました。それを体現するのが巻頭の吉岡乾「世界を見わたす窓」(10ページ)。著者はパキスタンの少数言語の研究者で、なくなりそうな言語が増えていることを指摘し、言語がなくなると、その言語の「窓」もなくなってしまうことを意味する、と言います。私たちも、自分たちの「窓」を閉ざしてはいけない、ということを伝えたいですね。
永田 『言語文化』の見返し「世界の言葉」が気に入っています。「言語文化」そのものへの「窓」にもなるページですね。文化だけでなく、それらを表す言葉があることを知ることも重要です。私は特に、「もう帰れない場所に帰りたいと思う気持ち」という意味の、「ヒライス」という言葉(ウェールズ語)が好きです。そういう言葉があるということは、そういう価値観をもつ文化があることを示していますね。これは、「伊勢物語」の切ない恋、「はるばる来ぬる旅をしぞ思ふ」にも通じる世界観があるようにも感じます。また古語における反実仮想の考えにも通じるかもしれません。このページから、文化の中の言葉、言葉の中の文化が目に見えるので、生徒もそれぞれの言語文化の旅に出るきっかけになると思います。
杉本 指導書を書きながら、今までと同じ教材でも切り口が違うことを実感しました。例えば中原中也「サーカス」(108ページ)と、その英訳「Circus」(110ページ)。同じ教材でも、訳と比べることで新しいことが見えてくる。「探究 災害の記録」(137ページ)も、実際に単元を設定し、勤務校でやってみました。「災害」というテーマですが、コロナ禍を経験した生徒だからこそ刺さるものがあったようです。そういう意味でも、古典から近現代へのつながりを生徒が実感できるものになったと思います。
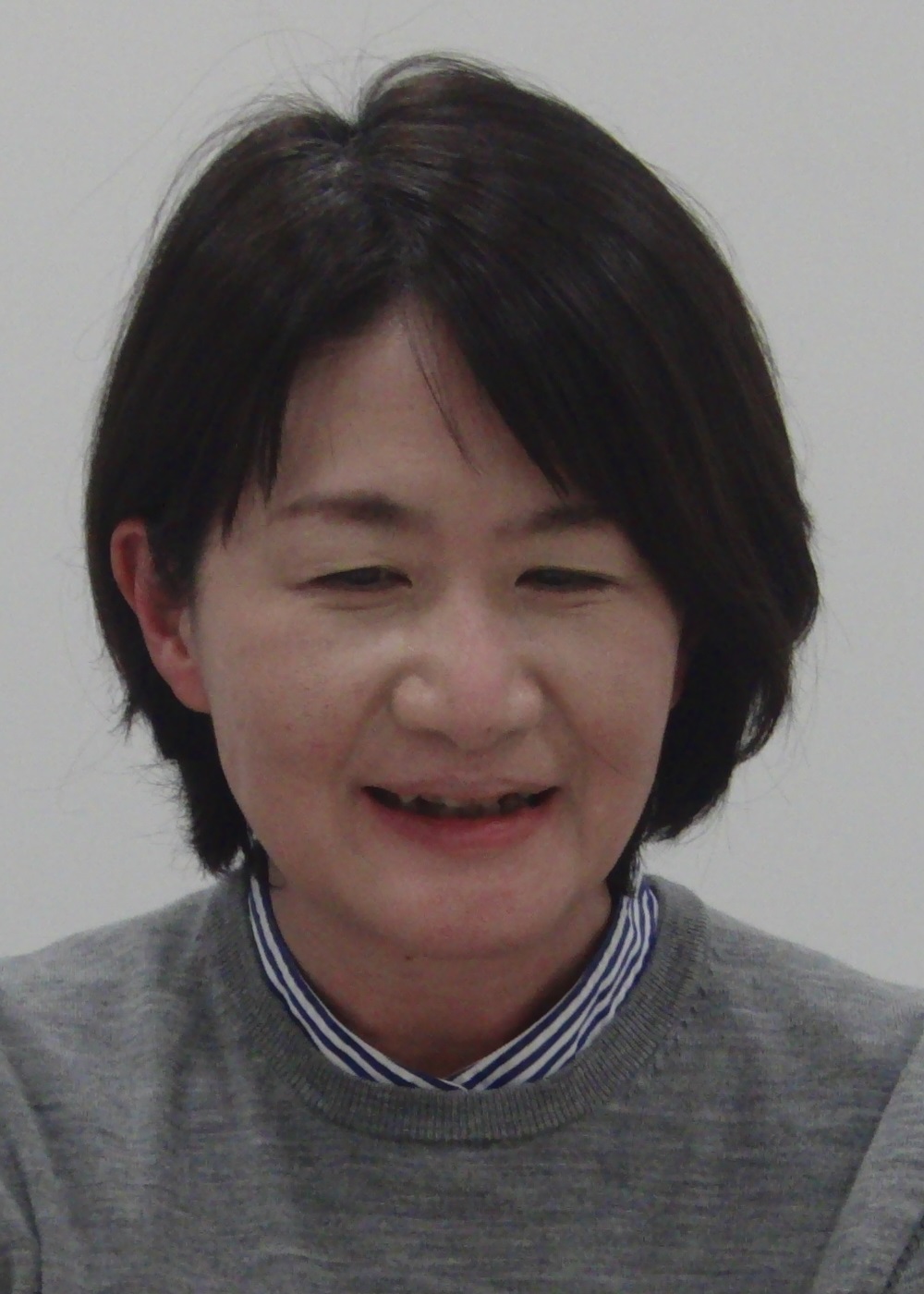
東京学芸大学附属国際中等教育学校教諭
石原 『言語文化』は、「伊勢物語」の「かきつばたの折句」(195ページ)の英訳「IRIS」に感動です。今生きている世界での言語文化的な広がりが実感できます。
永田 そのほかにも、現代文編では、ヘミングウェイ「橋のたもとの老人」(101ページ)を載せていて、英語の原文をふまえた教材化をしています。そのような随所でのつながり、「言葉のタネ」が1冊を通じてたくさんまかれているので、生徒たちにどんどん耕していってほしいですね。
大井 『新編 言語文化』(言文706)は、国語総合の新編系を使っている高校生が食いついてくる教科書。小説・古典は定番化を目指した部分もありましたが、評論・随想などで、文化や言葉への認識を深められる教材を多く収録しました。
山下 これは『言語文化』もですが、ぱっと見は「国語総合」と似ている感じがするので、なじみやすくて、使いやすそうな印象です。なじみのある文章も豊富でいいですが、カラフルさと紙面のビジュアルさも際立っていて、まさに「便覧一体型教科書」ですね。
藤森 『言語文化』を「窓」だとすると、『新編 言語文化』は「風」だと思います。作中で風が吹いている教材を探すと、村上春樹「鏡」(56ページ)にも、「羅生門」(82ページ)にも、佐藤多佳子「一瞬の風になれ」(49ページ)も川上弘美「水かまきり」(30ページ)も、全部重要な箇所に風が出てくる。でも、これは意図的な編集ではなく、偶然の結果。裏を返せば、こんなふうに教材間でいろいろなつながりを見出せる。いろいろな使い方があるおもちゃ箱のような教科書です。見返しの「キーワードで読み解く言語文化」は、現・古・漢でのつながりを視覚化していて、まさにそういう精神を体現しています。
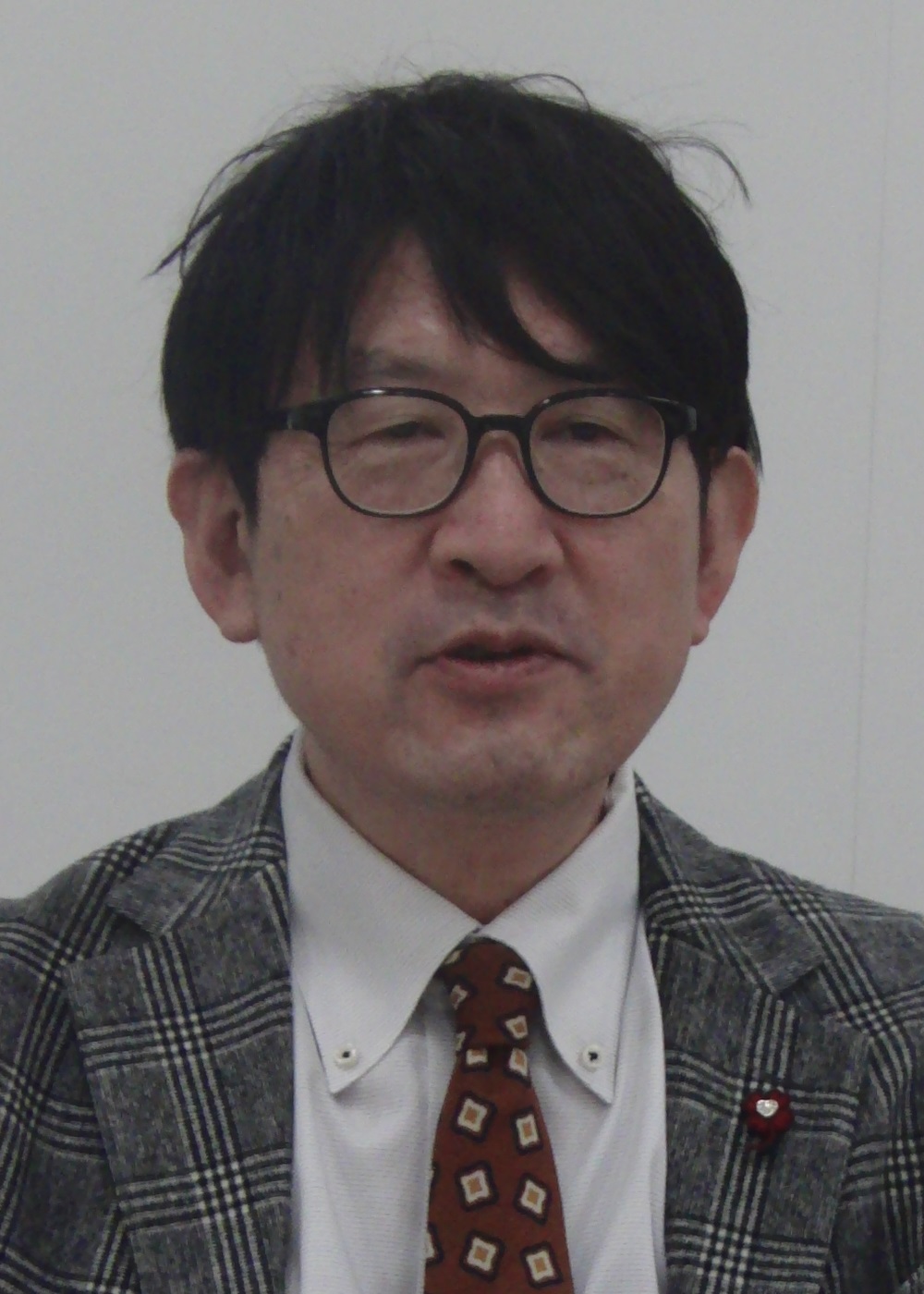
文教大学教授
杉本 『新編 言語文化』の読書案内がすごくいいなと思います。図書館司書がいない学校では、生徒に読書の魅力を伝えるまとまった時間がほとんどとれません。教科書内でたくさん紹介してくれるのはすごくありがたいし、生徒もわくわくするのではと思います。
「考える人」をつくる選択科目
──では最後に、選択科目の教科書については、いかがでしょうか。
山下 どの科目でも、深く考えることが大切です。「文学国語」も、読んで感じたことを伝えるためには論理的にならざるを得ないし、「論理国語」で論理的に説明する上で何かに着目するときには、文化的な素養も必要でしょう。各科目で学ぶ内容はおのずから通じていくと思います。

専修大学教授
藤森 いろんな仕掛けができそうな教科書ですね。教科書を使って、自由に組み合わせてほしい。
杉本 そうそう。教える材料がたくさんあって、選べる楽しさがある。教科書を全部終わらせないといけない、という考え方ではなくて、やりたいところを選んだり組み合わせたりして楽しんでほしいですね。
大井 『新編 論理国語』(論国706)では、野矢茂樹「論理的な人とはどういう人か」(18ページ)が最初に載っていて、全員が論理に向き合える構成でいいと思いました。そもそも論理とは何? っていうことを、身近なところから学べる。

東京大学教育学部附属中等教育学校教諭
杉本 『新編 論理国語』の「ウォームアップ」がすごくいいですよね。
山下 「ウォームアップ」「例題」というコーナーを入れて、この単元ではこういうことをやるんですよ、というのを、単元の冒頭ではっきり示したのが工夫したところです。その後に本教材をやって、最後に設問に取り組む「フォーカス」で締める、という流れを意識して作りました。
石原 『新編 論理国語』のほうは、「対比をとらえる」「主張をつかむ」など、学習の方向を示す単元名になっていて、その具体的なスキルが「ウォームアップ」で示される、という流れがいいですね。
大井 『論理国語』(論国705)に関しては、バリエーションの豊富さを意識しました。哲学・言語系を充実させつつ、「贈与論」などの新しいテーマの教材も入れたので、そのあたりのつながりも見てほしいです。
杉本 『論理国語』は単元名の横に問いかけが付いているのも魅力的ですね。たとえば、第Ⅰ部の第3単元「共同体のいま」には、「――社会において価値あるものとは何か?」という問いかけが付いています。発問が思いつかないときに助かるし、単元のねらいも見えやすい。
石原 単元名の横の問いかけ、私も好きです。「考える」ことにつながっていくイメージがもてます。コラム「テーマと読書」も、アカデミックで素敵。
永田 『文学国語』(文国704)は考えを深めて、それを豊かに表現することもナビゲートしてくれる教科書というコンセプト。あまり難しく考えすぎず、国語という科目の日常生活に密着した側面を考えてほしいです。例えば、生活の中で映画や小説に接したときの感じ方をどう表現することができるのかといったことにつなげたり、さらには人生の日々に潜む「文学の香り」を感じることにつなげたり。そしてそれを感じ取るための教材がこの教科書には豊富にそろっています。
藤森 『新編 文学国語』(文国705)は、「古典の世界」が入っているのがいいですね。「山月記」(90ページ)の隣に「竹取物語」(114ページ)が入っているのも、「月」のイメージで共通する世界観を感じられます。
石原 『新編 文学国語』は創作の活動が入れられたのがよかったなと思います。「誰もが小説家になるわけではないのに、なんで学校で文学の創作をやるのか?」という疑問が浮かぶときもあったんですが、文学作品を読むときの着眼点がよくなることがあるんだな、と気づきました。自分で書くことで、書き手の工夫やすぐれた描写に気づき、学習者の中の文学の世界が豊かになる。
杉本 3冊の「古典探究」(『精選 古典探究』(古探708)、『古典探究 古文編』(古探706)、『古典探究 漢文編』(古探707))について、まず、教材のラインナップに安心感があります。それから、芥川龍之介「英雄の器」など、古典への興味が湧いてくる近代以降の文章も盛りだくさん。読み比べの学習もぜひ使ってほしいです。
藤森 『国語表現』(国表701)は、実用的な部分に加えて、「たほいやゲーム」(210ページ)など、楽しい要素も入れました。このほかにも折句、回文など、遊び心が満載の教科書になっています。
──必修も選択も盛りだくさんですが、それぞれに特色のある内容となりました。
杉本 新しい教科書には、活動のヒントがたくさんあります。私もここにあるいろんな活動にチャレンジしたいし、生徒にもぜひ、これをヒントにしながら学習してもらえるといいかなと思いました。
山下 何かを表現するときって、すごく考えると思うんです。それぞれの科目の特性をふまえて、「考える」人を作る、ということが軸になっていると思います。
永田 必修も選択も、社会人になっても手元に置いてほしいし、置いてもらえる教科書にできたのではないでしょうか。
──ありがとうございました。
(聞き手・編集部)
『国語教室』第117号より転載
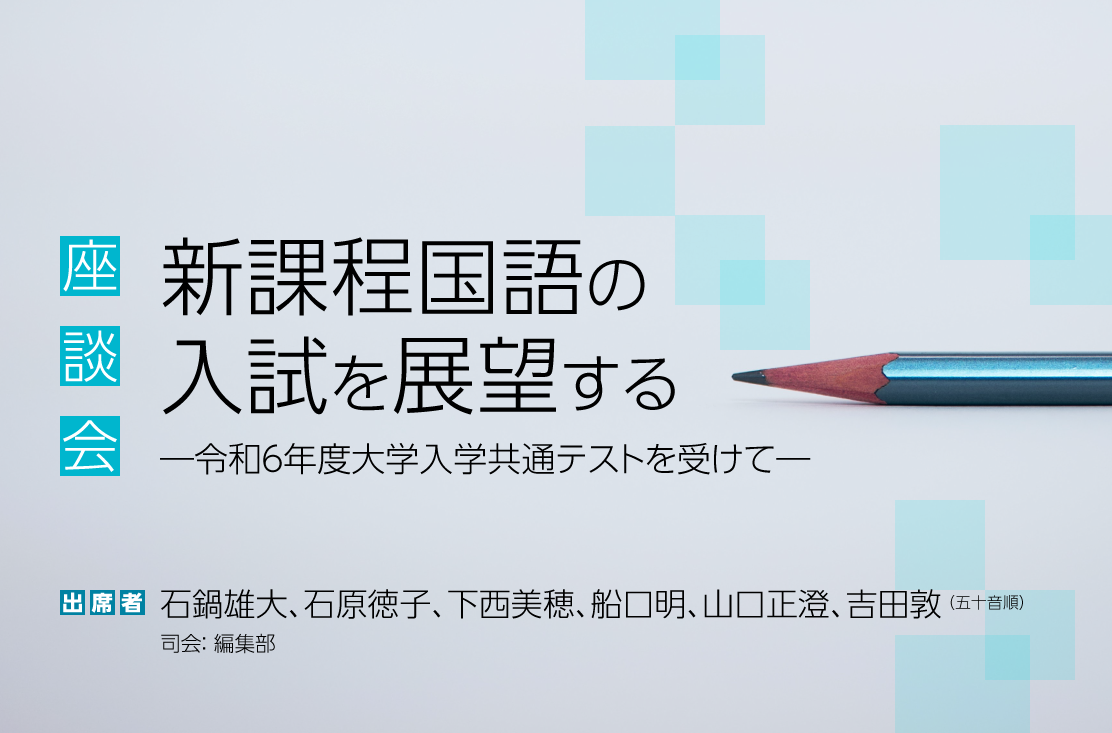
詳しくはこちら
一覧に戻る






