〈座談会〉司会・聞き手:編集部
新課程国語の入試を展望する――令和6年度大学入学共通テストを受けて
石鍋雄大 石原徳子 下西美穂 船口明 山口正澄 吉田敦
- 2024.05.29
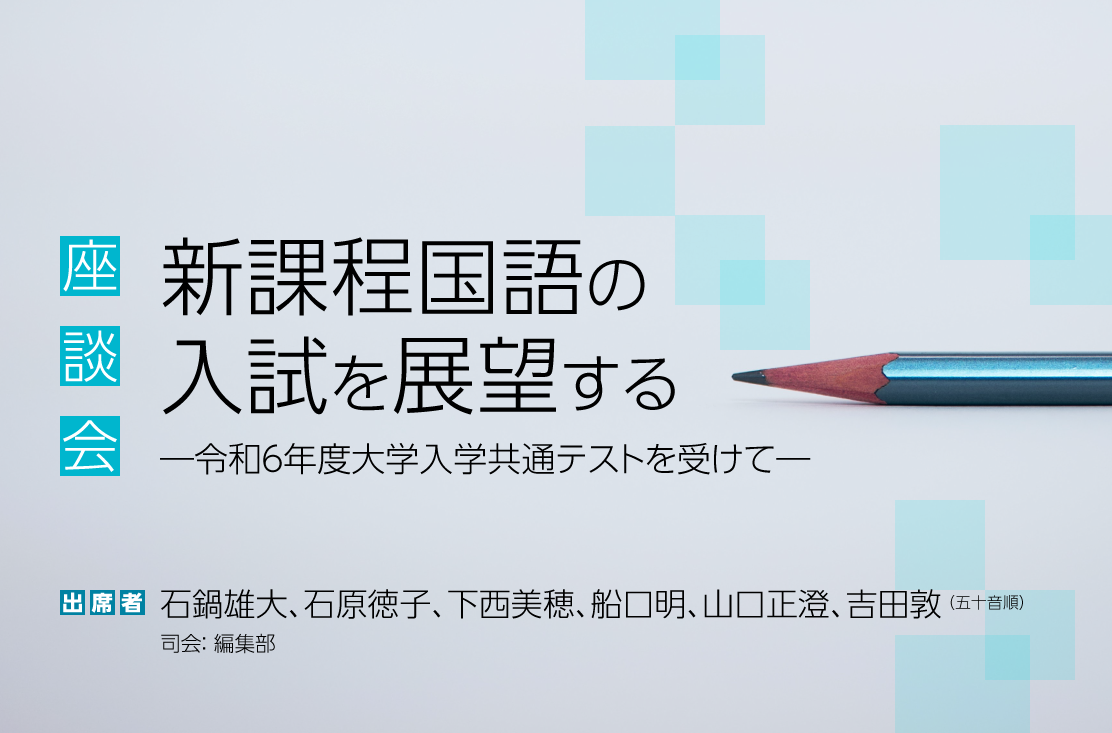
令和7年度入試から、新課程に則した大学入学共通テストが行われます。
国語の大学入試はどのように変わるのか、これからどのような授業を行っていけばよいのか。
今年1月に行われた令和6年度大学入学共通テストの状況もふまえて、高校現場と予備校の先生方6名に語り合っていただきました。
令和6年度大学入学共通テストを受けて
――まずは、今年の大学入学共通テストについて、どんな印象をもたれましたか。
下西 現任校では多くの生徒が「簡単だった」という手応えで、あまり差がつかなかったようです。

船口明(ふなぐち あきら)
代々木ゼミナール国語講師。教育総合研究所主幹研究員。
船口 一見拍子抜けするくらいにセンター試験に戻ったな、と感じると思います。来年から始まる新課程の共通テストでは、実用的な文章を問う第3問が増えて、時間も90分になります。それもふまえてどのような問題になるのかと注目していましたが、扱う内容が増えることを見越して、今年は全体的に負担を軽減しようとしたのかな、という印象です。
石原 古典では、1年生で習うような知識問題が多く出題されていました。「古典分野は基礎をしっかり勉強していれば大丈夫だ」という手応えが得られたのではないかと思います。細かい知識を問う問題も少なく、「読めているかどうか」よりも、「読んだ上で、自分はどう考えるか」が問われているように感じました。また新しい傾向の設問としては、特に第1問の評論で、生徒が書いた文章を推敲する設問が出題されたのは新鮮でした。新課程の「書くこと」に配慮した設問ともとらえられますが、課題文とは異なる意見を生徒が書いた、という設定になっているところがおもしろいですね。
石鍋 推敲の設問は確かに新鮮でしたね。授業でもこうした「思考力・判断力・表現力」を伸ばす授業をしていかなければならないな、という思いを新たにしました。また評論文(渡辺裕『サウンドとメディアの文化資源学』)は二項対立で論じるタイプのものでしたが、どちらかに意見が偏るような単純なものではなく、二項を超えるような見方が示されているのも興味深いところでした。全体的には、「新指導要領の内容をきちんと学んでいれば大丈夫ですよ」というメッセージだと受け止めました。
船口 第1問の評論で出題された渡辺裕は、センター試験で過去にも出題されていますし、今回と同趣旨の私大の問題もあります。そういう意味では、やはりこれまでの過去問をしっかりと解いて対策しておくことも重要だといえそうです。
山口 全体的には易化という評価なのでしょうが、一方で、受験生の視点で見ると、80分で解ききるには、やはり分量的に厳しいとも感じました。作問者の視点では、問題作成方針で多くの制約がある中で、その条件に従って工夫して作られており、出題上の苦労を感じました。

吉田敦(よしだ あつし)
代々木ゼミナール教育総合研究所所長。
吉田 評論で出題された生徒の文章例や、古文で出題された本文についての解説文は、おそらく作問者が独自に作ったものです。やはり関連する内容の読み比べの対象となる文章を、既存の文章から持ってくるのは、相当難しいのでしょう。
船口 予備校としては「全体的に易化」といった評価をしてはいるのですが、答えは合っていても本当に読めている生徒がどれだけいるかは微妙、ということも感じます(本年の第1問 問4など)。例えば、本文に出てきた言葉をそのまま選択肢で探すといった機械的な読みをしてしまう生徒もいますが、文章を読み取って自分の中で解答を作成できている生徒のほうが、迷いなく正解を選べたのではと思います。傍線部の根拠を問う設問、特に本文中の言葉を別の表現で言い換えて問う設問が近年増えてきていますが、機械的にではなく、自分の頭でしっかり本文が読めているかを見る傾向になっているのではないでしょうか。
石原 本当にそう思います。本文で出てきた言葉を機械的に探す、ただ「言葉を結ぶ」ような読みをしてしまう生徒が多いです。述べられていることのキーワードを抜き出すことはできるんですけど、じゃあそれって具体的にどういうこと? と聞いていくと、意外と理解できていないことが多いです。
船口 同じ単語同士を結ぶような作業は、AIが得意ですよね。そういう、傍線部付近と選択肢を結ぶAI的な読み方ではなく、しっかりと内容を理解して読みましょう、という作問者の意図を感じます。大学に入ってから読む文章には、そもそも傍線なんか引いてありませんからね(笑)。
石原 私も授業をしていてその点が不安で、本当に生徒にとっての深い学びになっているのかな? ということをよく考えます。今回の共通テストのような問題をとおして、生徒が自分で考える習慣をつけられるようになるといいな、と。
山口 先ほど話題になった評論の問題では、生徒が推敲する際に、自分の書いた表現をより具体的にするにはどうすればよいか、という設問も出題されています。そうした具体と抽象を行き来することも、生徒は苦手なのかもしれません。その根底には、基本的な語彙力不足もあるのではないでしょうか。語彙力があれば、言葉を紡いでいった先の結びつきも理解できるのではないか、と。センター試験から共通テストになっても、言葉の意味を知ることの重要性は変わらないですね。
船口 その意味では、第2問の小説(牧田真有子「桟橋」)で語句の意味を問う設問が復活したのはよかったです。語句の問題は過去問で問われたものが重複して出題されることも多いので、しっかりと過去問を解いておくことが大事です。
小説を読むのが苦手な生徒たち?
山口 新課程の共通テストについては、出題範囲の問題もあります。前提としては必修科目である「現代の国語」「言語文化」からの出題ということにはなるのでしょうが、特に古典や文学的文章については、「言語文化」だけではカバーしきれない部分も大きいのではと思います。現代文の論理的な文章についても同様ですね。実質は「論理国語」「文学国語」「古典探究」で学ぶべき内容も出さざるを得ないのでは、というのが実感です。
石鍋 特に理系の生徒は「文学国語」などを採らない場合も多いので、厳しい面があるのではと思います。必修科目の学びについては、なかなか「国語総合」時代のようにはいかず、変えていかなければならない部分もありますね。
船口 小説でいうと、最近の生徒は塊としてのストーリーを受容する経験が本当に少なくなってきているなと感じますね。1時間のテレビドラマは言うまでもなく、彼らの大好きなYouTubeやTikTokでも、10分を超えればもう長く感じてしまう。小説を読むことで、本来は他人の人生を追体験することができるわけですが、自分の関心の幅から外れるものは「興味ない」で済ませてしまう生徒も多いようです。

石原徳子(いしはら のりこ)
横浜創英中学・高等学校教諭。大修館書店国語教科書編集委員。
石原 本当にそうだと感じます。ちょうど今1年生の授業で「羅生門」をやっているんですけど、最近は下人の「盗人になる」という決断を理解できなくて、「残念な結末」「もっと正義を貫いたほうがよい」と受け取る生徒も多いです。今回の第2問の小説に出てくる風来坊のおばさんも、「寅さん」のような人物というか、現代だと生きづらいかもしれないようなキャラクターですよね。こういう自分とは異質な人物の考えや行動について、納得はできなくてもいいんですけど、「こういうことか」と理解することが大事なはず。そこが苦手な生徒が多くなったなという印象です。
船口 他者やさまざまな人物像に出会うためのモデルが少ないのかもしれません。ネットの世界では自分の関心のあることを深堀りすることはできるのですが、ますます自分の狭い興味の中だけで済ませてしまう生徒もいるのではないでしょうか。自分の中で重ね合わせる人物像が少ないというか。それで読解だけでなく、人間関係も苦手になっている生徒もいるように思いますね。
AIの進展と記述式問題
――共通テストからは離れますが、記述式の設問についてはいかがでしょうか。
吉田 AIによる記述問題の自動採点だと、評論はとても精度が高くなってきましたが、小説はまだうまくできないという実態があります。本文に書かれていない部分も補って読む必要があるからだろうと思いますが、そうした書かれていないことを読み取る力を生徒につけさせるにはどうするか、考える必要があります。
船口 正直なところ、論理的な文章に関しては、AIの採点技術は驚くべきレベルで進歩していますね。
山口 生成AIによる文章もなかなかのレベルになってきていますよね。志望理由書の下書きをAIにさせる生徒も出てくるんだろうな、と(笑)。そういう面も含めて、生徒を取り巻く状況が変わってきていますね。
石原 記述式の採点は大きな論点ですね。記述答案の採点は基準を揃えることが難しく、受験生の多い入試では、共通テストのような選択式がふさわしいとも言われます。でも、特に定期テストでは、生徒が一生懸命に書いてきたものを読んで評価してあげたいな、という思いが強いです。
船口 言語自体が抽象的なものなので、記述式の採点基準がある程度ぶれるのは当然だと思います。特に定期テストなどの小規模なものではどんどん書かせて、採点結果に疑問をもつ生徒が出たなら、先生と話し合いながらその都度解決していけばいいのではないでしょうか。
石原 予備校の先生にそう言っていただけて嬉しいです(笑)。
下西 実際に書かせることで初めて気がつくこともありますよね。こんなところでつまずいてたのか、ということも、選択式だけだと全然わからないです。現任校では国公立を目指す生徒が多いので、記述問題の対策ではマンツーマンでの指導が欠かせません。1年生から授業の中で記述の対策をしていますけど、最後の最後はやはり個別に対応せざるを得ないという状況です。特に小論文では国語だけに留まらない幅広いトピックが問われることもあって、私は「書くこと」の指導についてはまだまだ模索中という状況です。
多様化する入試に対応するには
――2次試験や総合型選抜などへの対応についてはいかがでしょうか。
下西 小論文しか出題しない学校もあれば、従来どおりの細かい文法の知識を問う学校もあって、すべてに対応できるように授業で網羅するのは難しいですね。

石鍋雄大(いしなべ ゆうだい)
東京都立大泉高等学校附属中学校教諭。大修館書店国語教科書編集委員。
石鍋 読み比べなどでも、生徒の興味・関心に合わせて、いろいろなテーマを組み込んでいると、単元が膨大になって、時間がかかりすぎる面があります。
山口 総合型選抜の小論文、面接やプレゼンなどについては、国語科だけではなく、他教科との連携を横断的に行っていくことも重要だと思います。また、来年度の共通テストに追加される第3問のグラフや図表の読み取りなどについても、理系科目はもちろん、今年の「現代社会」でも出題されていますね。当然、「現代の国語」や「論理国語」で学ぶべき部分もありますが、すべてを国語科で扱おうとするのではなく、各科目の専門性も考慮して、持続可能な指導をしていくことが重要ではないでしょうか。
吉田 グラフの読み取りについては、代々木ゼミナールで、「棒グラフや折れ線グラフを読んで、その内容を70字程度で表現してみる」という活動を提案した人がいました。初めは「右上がり」や「左上がり」といったことしか書けないのですが、慣れてくるとさまざまなことが表現できるようになっていくようです。一つの方策として、そのような活動も考えられます。
石原 生徒によってさまざまな着眼点がありそうなので、解答を比べさせるなどすると、とてもおもしろそうですね。
下西 さまざまな視点ということでは、関連する情報を自分で見つけてきて意見文を書く、といった学習にも発展できそうですね。現在は、一つの文章を読んで、その内容をわかりました、で通用する状況ではなくなってきているなと思います。やはり関連する文章・資料を読み比べさせて、そこからどのようなことがわかるか、ということまで考えさせないといけないですね。生徒たちは意外とそういう活動は楽しんでやるんですが、関連する文章を探してくる教員側の負担はすごく大きいです(笑)。
山口 それも、国語科の中で連携できるといいかもしれません。一人でできることには限界があるので、授業の中で使う資料やスライドなどは共有にして、うまく協力し合えるとよいのではないでしょうか。
これからの国語に向けて
――最後に、これからの国語に向けて、先生方の思いや展望をお聞かせください。
石原 私たち教員自身が、「探究者」でありたいなと思います。今回の共通テストでは、古文の「桂」という言葉に注目して書いた解説文の問題がとてもおもしろいと感じたのですが、こういう読み比べというか、探究的な問いを大事にしたいです。ある文章について、A先生は別の関連する文章を持ってきて、私はまた別の文章を用意してというように、お互いに刺激を与え合いながら発展的・探究的な学びを楽しめるとよいな、と。正直なところ、国語の文章について、受験生は「入試があるから読む」というのがほとんどだと思うのですが、本来あるべき姿は「読みたいから読む」「考えたいから考える」だと思います。実際には時間の制約などもあるので難しいんですけど、授業者が探究者であることで、そうした学びを深め合っていけると理想だな、と考えています。

下西美穂(しもにし みほ)
東京都立戸山高等学校教諭。大修館書店国語教科書編集委員。
下西 先ほどのグラフや読み比べのお話でも感じたんですが、教員側も、新しいことにチャレンジできるチャンスだ、と思っています。関連するグラフや文章を見つけてきたりするのはすごく大変です。でも、やはり楽しいんですよね。「これ使えないかな?」と、雑談するような状態で、教員も生徒と一緒に悩みながら楽しむ、くらいのつもりでいいんじゃないかと思います。
船口 その楽しんでいる雰囲気が生徒に伝われば、「国語の先生になりたい」と思う生徒も増えますよ、きっと。
石鍋 「生徒と一緒に作る」という感覚はすごくわかります。さまざまなルールや制約から、ときどきははみ出てもいいんじゃないでしょうか。今日の授業でもすごくはみ出ちゃったんですけど(笑)。ある評論文で、初出の語にルビが振ってあって、2回目以降からはルビがないのに、最後のほうでまた同じ語にルビが振られていたんです。それに生徒が気づいて、「なぜだ?」って私も生徒と一緒に、1時間ほど考えました。そのときの生徒の様子がすごく自発的で楽しそうだったのが印象的で。やはり小論文のための小論文学習や話し合いのための話し合い学習というか、表面的で受け身な学習はできるだけさせたくないなという思いがあります。通過点としての小論文などがあって、卒業時にこういう力がついてほしいな、という授業が作れたら、本当に楽しいものになるのではないでしょうか。
山口 「関連する文章や学習材を新たに発掘していく」のは大変さとともに、楽しさも生まれてくると思います。また、先ほども申し上げたように、国語科だけにこだわらないということも考えられるのではないでしょうか。例えば、「現代の国語」でも「推論」を扱いますが、以前には平成29年度試行調査の「現代社会」で推論について出題されています。国語科だけでなく他教科でも同じ力が求められているんだ、ということを知ると、教科間で有機的につながり合えるのではと思います。教員同士も楽しみながら、うまく協同して、チームで動いていけるといいのではないかと考えています。
――ありがとうございました。
2024年1月20日
『国語教室』第121号より転載
プロフィール
山口正澄(やまぐち まさずみ)
東京都立小台橋高等学校教諭。大修館書店国語教科書編集委員。
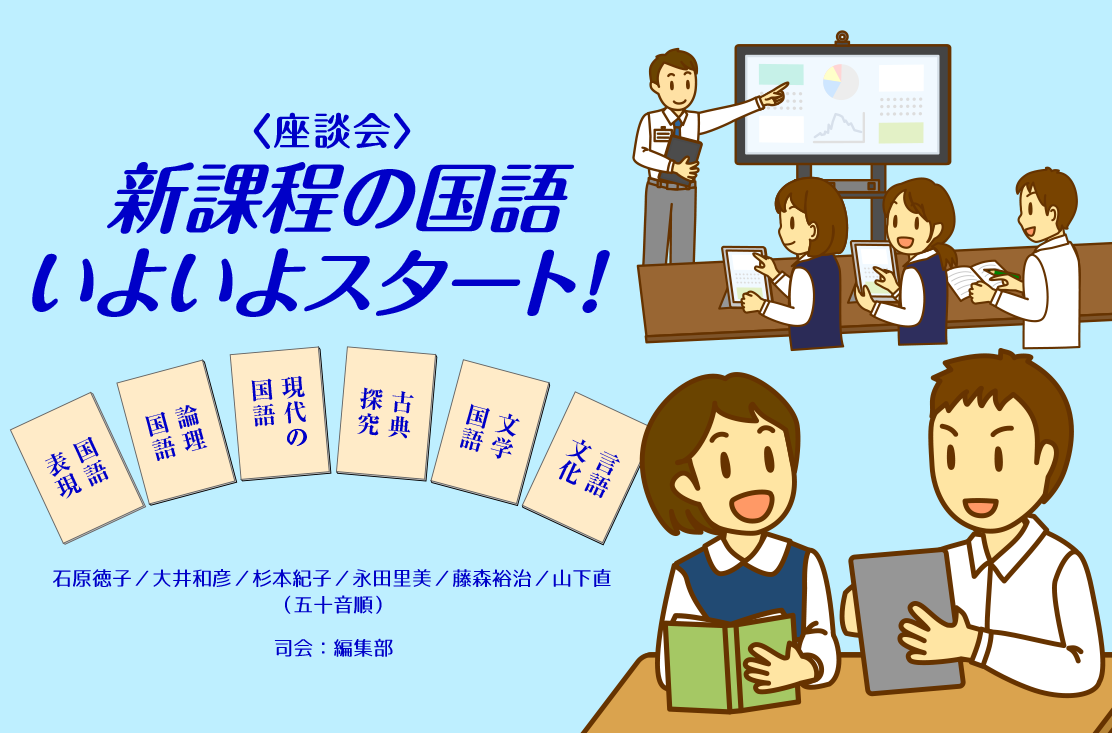
詳しくはこちら
一覧に戻る






