〈対談〉 新井紀子✕野矢茂樹
生きるための論理
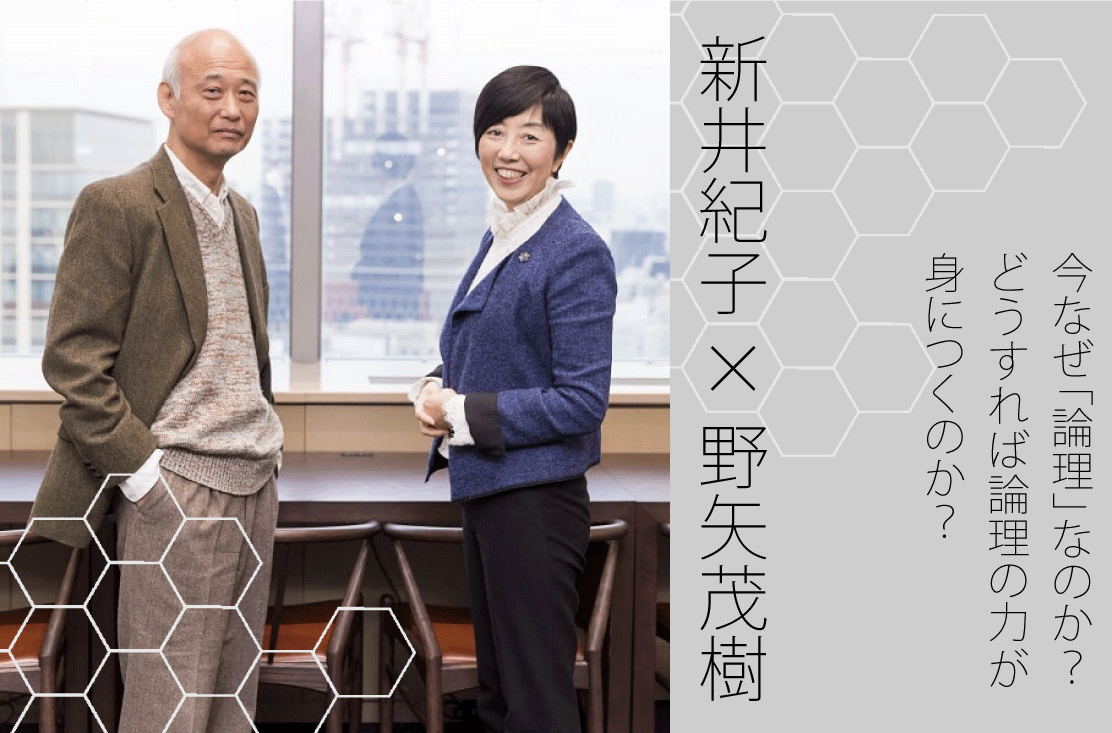
 2022年から実施される新しい高校学習指導要領では、論理的思考力の育成が強く打ち出されています。
2022年から実施される新しい高校学習指導要領では、論理的思考力の育成が強く打ち出されています。
論理とは何か。 どうすれば論理の力が身につくのか。 今なぜ論理が求められているのか。
AI研究をふまえて子供の読解力低下に警鐘を鳴らす数学者、新井紀子先生と、長年論理トレーニングの必要性を主張してきた哲学者、野矢茂樹先生に、じっくり語り合っていただきました。
(2018年12月3日、国立情報学研究所にて)
「教科書が読めない」子供たちの衝撃

野矢:まず、新井さんのご著書『AIvs.教科書が読めない子供たち』の話から始めましょうか。この本の中で、リーディングスキルテストという方法で子供たちの読解力調査をされています。本当のことを言うと、私は読んだとき、とても信じられなかったんです。なんでこんな問題ができないんだろう、と。
新井:子供たちの読解力に関して、科学的に検証する方法論が今までなかったと思うんですよ。システマティックな調査をしてデータを出してみたら、子供たちが予想以上に文章を読めていなかったということがわかったんです。
野矢:やっぱり、実際目に見える形でデータを集めるっていうのは、すごく貴重なことですね。私は机上の空論と言われかねないことを、書いたりしゃべったりしているもので(笑)。
新井:いえいえ、そんなことありませんよ(笑)。このリーディングスキルテストの結果を見ると、「ここは得意だけど、こっちが苦手なばかりに成績が上がらないんだな」とかっていうことがすごくよくわかるんです。そういう診断書があるわけだから、もっと一人一人に合った教え方をしてあげればいいんじゃないかと思うんです。
野矢:新井さんは、そうやって子どもたちの国語力の人間ドックをやってくれているんですね。そして私が今まで出してきた論理トレーニングの本や『増補版 大人のための国語ゼミ』はその処方箋に当たるのかもしれません。
論理をつかめない子供たち

新井:このあいだ小学四年生に国語の授業をしたんですが、板書を写せない子がクラスで20%くらいいました。文字を一文字ずつ写す子がいるんですね。一文字写したら、顔を上げてまた探すんですよ。だから、どこまで写したのかわからなくなっちゃう。これでは意味が頭に入っていないですよね
野矢:ノートがとれない子どもは昔からいたんでしょうけど、それとはまた意味が違いそうですね。
新井:今は電子黒板で教科書の紙面がスクリーンに映し出されるんですね。本文に空欄があって、生徒はそこに入る言葉を穴埋めすることが多いみたいなんです。それで、ノートがとれない子が増えたんじゃないかと。それから、小学六年生から中学一年生になると、「AであることをBといいます」というような定義文が、教科書で出てくる頻度が格段に増えるんですね。でも、リーディングスキルテストをやってみると、そういう定義文が読めていない。
野矢:定義が読めないっていうのはどういうことですか。非常にシンプルな定義でもだめなんですか。
新井:たとえば、「2で割り切れる整数を偶数といいます。」というような文の意味がきちんと理解できていないんです。でも、それができないのは子供たちの能力がないからではないはずです。定義の読み方をもっとシステマティックに教えてあげればいいと思います。この文から、①整数である、②2で割り切れる、という二つの要素を抜き出して、きちんとチェックさせる。そういう確認のしかたを、自転車に乗るときの方法論みたいに、意識して教えるべきだと思います。

野矢:なるほど。単に定義を一個頭に入れることができない、という話じゃないんだな。定義っていうのはいくつもの定義からなる体系があるから、その体系が理解できないっていうことですね。それはやはり、論理が把握できていないんでしょう。また今の子供たちは、分析することも同じく苦手になっているということかもしれません。定義文を分解してチェック項目にするという作業は、まさに分析するっていうことですよね。
新井:はい。定義文が読めていないと、推論もできない。物事の論理や関係がわからないから、伸びしろが小さいんですよ。実は、こういう能力ってAIもあまり得意じゃないんです。だから、AIにできないことこそ、子供たちもできなかったということになるんです。
野矢:たしかに、推論によって物事の関係がつかめれば、できることの数が飛躍的に増えますからね。
新井:学力が指数級数的に上がるんですよ。例えば、何通りかの物事のパターンがあったときに、そのすべてを覚えるんじゃなくて、推論によって一つの場合から他のすべての場合にたどり着けるようになる。でもそれができない子供は、定期試験のたびに大量に覚え、すぐに忘れて、というのを繰り返します。そして、学ぶということがわからないまま大学生になってしまう…。
野矢:やはり子供たちの力で明らかに落ちているものがあって、その一つが関係をつかまえる力ではないかと。ちょっと曖昧な言い方なんだけれど、言葉がどんどん断片化しているという感じがするんです。切り取った言葉がそのまま流通していくような時代になり、言葉がどんどん切れ切れになっている。
新井:本当にその通りです。
野矢:特にSNSがそれを加速していると思うんです。この部分とこの部分はどうつながるのか、この部分は全体の中でどういう意味をもっているのか、そういった関係をつかむのが苦手になってきているんじゃないでしょうか。だからこそ、言葉と言葉の関係がどうなっているか、つまり、論理をつかむ力が、ますます重要になっていると思います。
「論理の力」を育むには
野矢:私は、国語力をつけるには要約が最も有効だと信じているんですよ。文章を木に例えると、いちばん重要な幹=言いたい中心的な主張があって、それから枝葉=主張を説明したり、支えたりする部分があるはずです。要約の訓練を重ねることによって、その幹の部分だけをうまく切り出して文章の構造を取り出せるようになるわけです。その力がないと、幹も枝葉もなくて藪みたいになって、文章を読んでも頭に入らなくなる。先ほどの板書を一文字ずつ写そうとする子供は、藪どころか、文字ごとにばらばらに見えている可能性がありますね。

新井:本当にそうですね。さらに言えば、私は「見たとおりに書ける」ということも、とても大事だと思います。例えば、オセロのゲームの様子を実況中継するという活動を小学生にやらせたりしています。それから、料理レシピ。私、お料理が大好きなんですけれども、『暮しの手帖』のレシピは、すごく再現性が高いんです。
野矢:どういうことですか?
新井:『暮しの手帖』に書いてあるとおりにやれば、そのとおりにできるんですよ。誰が作っても同じ味に仕上がるようなレシピになっているということです。
野矢:ああ、それは「見たとおりに書く」というだけではなくて、相手が求めていることをその相手にわかるように書くということですね。正確に書くことに加えて、「これじゃあ相手はまだよくわからないな」とチェックできる力。そして相手にあわせて書ける表現力。
新井:そうそう。だから、オセロの実況中継も、見ていない人にもわかるように、正確に言葉で伝える学習をさせています。
まず、「語学としての国語」を
野矢:高校生や大学生がまず身につけるべきなのは、凝った文章、職人芸的な読解を要求する文章ではなく、一度読めばわかる文章、それを書いたり、読んだりできる力ではないかと思うんです。私は「語学としての国語」と呼んでいるんです。高校の国語にはこれまでそういう観点が乏しかったのではないでしょうか。
新井:私もそう思いますね。これから日本は移民を受け入れる方向になっていくと思うんですが、バックグラウンドが多様な人々がもっとたくさん学校に入ってくるでしょう。そのときに、前提なしで日本語をきちんと読めるような、システマティックな方法論が必要だと思うんです。そういうものが、これまで確立されてこなかったのではないでしょうか。
野矢:でも、だいぶ小学校、中学校は変わってきていると思いますね。高校はまだ遅れているけれど。

新井:国語っていうのは、文学ではなく、国語なんですね。だから、日本語で書かれている文章がきちんと読めるようになること、例えば数学の問題文が正しく読めるというのは、数学ではなく、国語の役目だと思います。
野矢:国語って、全教科のベースになるものですからね。もちろん、文学は文学で、また別にきちんとやるべきだとは思います。でも、優先順位の問題ですよね。
新井:そうですね。
野矢:教師がやるべきことは、誰もができることを、誰もができるようにするということだと思うんです。例えば、先生方は何年も同じ文学作品を読んでいるから、読むときの目の付け所もわかっているわけですよね。どんなにすばらしい作品なのかを生徒に言いたくて、うずうずしている。それを初めて読む生徒に教えてあげると、ワッと目を輝かせてくれる。
こういうのも楽しい授業だとは思うんですが、どちらかと言うと、文芸評論家のような人がやる、一種の職人芸なんじゃないかと思います。まずは、誰が読んでもわかるような「普段着の文章」を教えなくちゃいけない。そう言うと、「そういう授業はつまらないんじゃないですか」って言われることもあるんです。でも本来の教師の喜びって、職人芸を見せつける喜びじゃなくて、できなかった子供ができるようになるのを見る喜びですからね。
変わる入試とこれからの国語
野矢:高校がいちばん変わらない理由は、大学入試が変わらなかったからでしょう。大学入試の国語は、一度読めばわかるような文章を使って問題をつくるノウハウをこれまでもっていなかったと思うんですよね。だいたい、二、三回読まないとわからない文章を示して、二、三度読ませる時間を与えずに解かせる問題なんてナンセンスなんですよ。
新井:そうですね。私の文章は意味があまりにも明らかで、一度読めばわかってしまうので、センター入試には絶対に使われないと言われます。選択肢の問題にならないんですよ。

野矢:ところが、私の文章はよく入試に出ちゃうんですよ。 不本意なことに(笑)。「大学入学共通テスト」というのが始まろうとしていますね。その試行調査(プレテスト 2018年11月実施)を見ました。私自身は、一度読んだらわかる文章をちゃんと一度読んでわかる力という観点から、この新しい入試の方向性は全く正しいと思っているんです。
新井:私も、国語のプレテストを拝見しました。今回は全体的にいい問題だったなと感じました。古典の問題を見て感じたんですが、「教養として古典に親しむ」という目標が達成されるのなら、古典の問題に現代語で注釈や人間関係があらかじめ書いてあってもいいと思いました。それで古典学習の負担が減りますよね。そして、野矢先生がおっしゃるような、「普段着の文章」が、普通に正確に読めて書けるようにすることを目指すのが、正しい教育の姿なんじゃないかなという気がします。
今なぜ論理なのか
野矢:「昔と比べると国語力は落ちてるんですか」ってよく聞かれるんですよ。私は「昔のほうがよかった」とは言いたくないので、「基本的な国語力は変わらないんだけれども、今のほうがより論理的な国語力や、コミュニケーション力が求められるような状況・時代になっているということじゃないですか」と答えているんです。
新井:おっしゃるとおりだと思います。先ほど、誰でも同じ味が再現できるレシピという話をしましたけれど、それって実はすごいことなんですよ。特別な人だけでなく、すべての人に、プロの味にアクセスする権利があるということですから。それはつまり、民主主義ということなんです。民主主義を真の意味で実現するための国語教育ということです。再現性の高い料理レシピのような文章を読んだり書いたりできるということが、多様性に対する寛容さにつながっていく。わかる人にしかわからない職人芸というのは、不寛容ではないでしょうか。

野矢:いや、職人芸も大事だと思いますけどね。でも、おっしゃっていることはよくわかります。「国語は数学と違って、正解がない」とよく言われますね。それも、ある真実を突いているとは思うんですよ。だけど、まず正解があるところでしっかりとトレーニングしておくことが、必要だと思うんです。それはなにも、「国語にはすべて正解がある」ということが言いたいのではなくて、その後、正解のない問いかけへと踏みこんでいくことも必要になってくる。でも、論理的に考える力を重視していこうというときに、正解のある教育と正解のない教育が混在すると、混乱してしまうと思うんです。まずは、正解がある、「語学としての国語」をしっかり身につけるべきではないでしょうか。
新井:まずは「普段着の文章」を読んだり書いたりできる、ということですね。
野矢:そうです。そして、そのうえで、正解のない世界に入っていくということも大事です。そういうときには、我田引水ですみませんが、ぜひ、哲学やろうよって思います(笑)。問題を抱えてモヤモヤした状態で生きていく力をつけるには、哲学ほどいいものはないと思いますからね。
新井:本当に、野矢先生の文章は「論理国語」の教材にぜひ加えてほしいですね。私の立場からは、「数学は言葉である」ということも、素材としてほしいです。
──ありがとうございました。
『国語教室』第109号(2019年2月)より転載
プロフィール
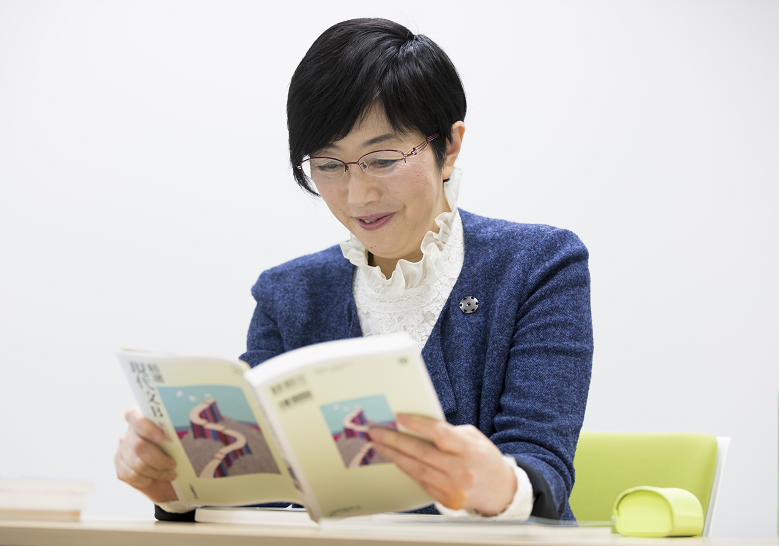
新井紀子(あらい のりこ)
数学者。国立情報学研究所教授。人工知能プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」(東ロボ)に携わり、中高生の読解力を診断する「リーディングスキルテスト」を開発。近著に『AIvs.教科書が読めない子供たち』など。

野矢茂樹(のや しげき)
哲学者。立正大学文学部哲学科教授。平明な文章による論理学入門書を多く執筆。練習問題を解きながら論理力を磨く「論理トレーニング」シリーズは、大きな反響を呼んだ。近著に『増補版 大人のための国語ゼミ』など。
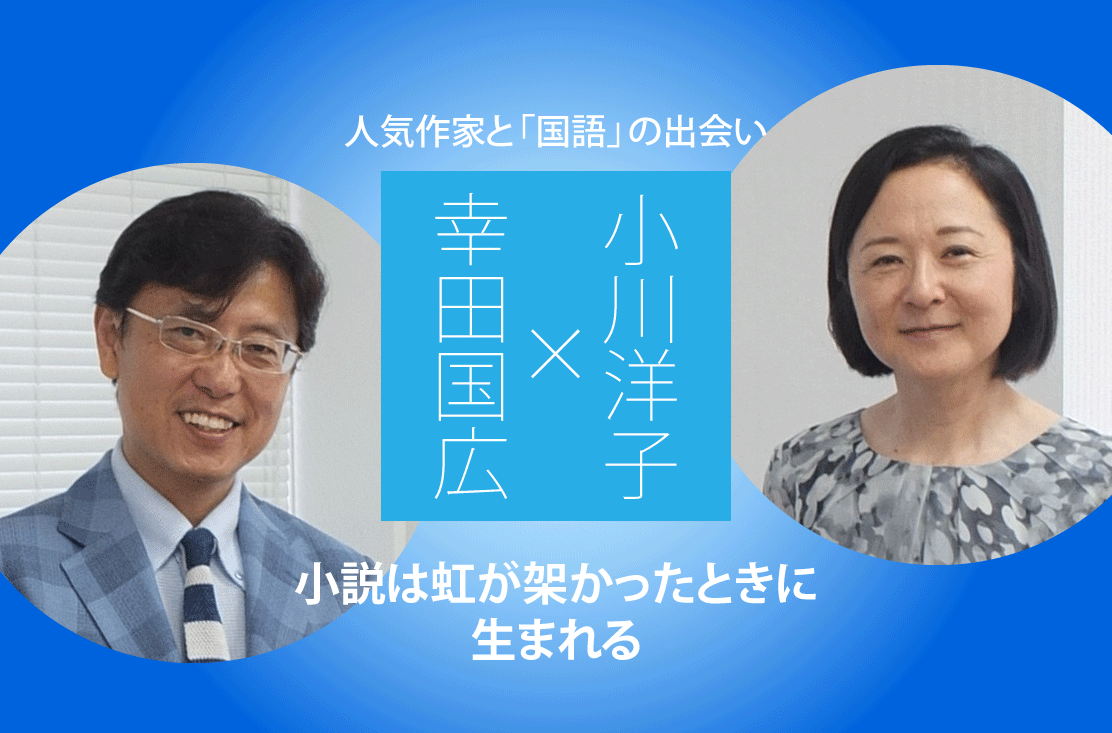
詳しくはこちら
一覧に戻る






