〈対談〉 小川洋子×幸田国広
未来につながる国語の力
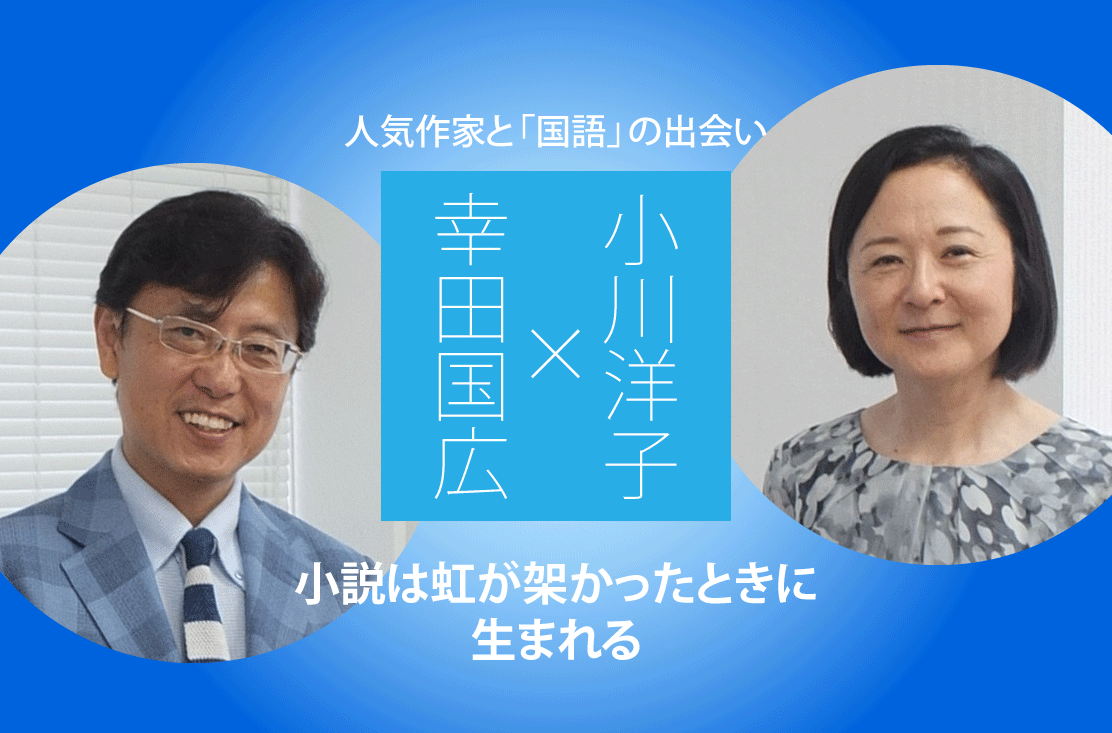
 戦後最大規模ともいわれる高校国語の学習指導要領改訂。
戦後最大規模ともいわれる高校国語の学習指導要領改訂。
文学はどうなるの? 実用的な文章を扱う意味って?
教科書にも多くの作品が掲載されている小川洋子先生と、新指導要領にもお詳しい幸田国広先生に、これからの国語について語り合っていただきました。(2018年8月24日、大修館書店にて)
小説は虹が架かったときに生まれる

小川:学年の初めに国語の教科書をいただくと、どんな作品が載っているのかなと思って見るのが楽しみでした。よく覚えているのは「こころ」「舞姫」、あとは「山月記」が非常に忘れがたいです。でも、私が高校生の頃に定番だったものが、今変わってきているんでしょうね。
幸田:小川先生が高校生のときに人気教材だった「こころ」「山月記」、あるいは「羅生門」などは、今日までずっと定着しているような状況ですね。ですから、高校の国語教育というと、小川先生の頃と今の授業の光景というのはそれほど変わらないと思います。
小川:高校生の私にとっては、自分の作品が教科書に載るなど、信じられないことです。ですから、ものすごく時代が変わってしまったようなイメージなんですけれど。
幸田:たしかにそうですね。小川先生の作品は各社、ぜひ載せたいと考えていて、現在15冊くらいの教科書に採録されています。教科書に現代作家の適当な長さの作品を入れようとすると、どうしても予定調和的になったり、教訓的な話になったりしがちですが、小川先生の作品は違います。
小川:私の小説は、たしかに結論があいまいで、読者をここへ運びたいという目的地が最初から決まっているわけではありません。
幸田:でも、小川先生の作品は、コントラストというか、正反対なものが同居しているイメージがあるんですね。美とグロテスクであったり、瞬間と長い時間であったり、静と動であったり。言葉の奥行きや、その作品の奥深さみたいなものを感じとれる、稀有な現代作家なんじゃないかと思うんです。
小川:ありがとうございます。AとBという、遠いところにあると思っていたものが、実は間に虹が架かっているんだなとわかったときに、小説って書けるんです。自分の中にある、すでにもっているもので小説を書くのではなくて、自分がもっていないものと出会ったとき――。数学はわかりやすい例なんですけれど、数学者なんて自分とは縁がないと思っていたのに、実は美しさを求めている人々なんだと気づかされたとき、パッと虹が架かって、ああ、これは小説になるなと直感するんです。結局、正解は何かはっきりはわからないけれど、読んだ生徒さんたちが意見を交わし、話し合う過程の中で、いろいろ見えてくるような作品が書ければいいなと思っています。
幸田:まさにこれから新しく変わる高校の国語の授業も、決められた正解に向かって落とし込んでいくのではなく、答えのない問いにいろいろ知恵を出し合いながら、何か答えらしきものを見つけていこうとする、そういう学習活動を重視しましょうという方向になっているんです。先生の文学的な特性、作品の特徴として、読み終わった後、「なんとなくこういうことですよね」では終わらないところがあるので、まさにこれからの国語の授業にうってつけなんじゃないかなと思っています。
古典と現代をつなぎ直す

幸田:小川先生の「千年の時が与えてくれる安堵」という随筆で、『枕草子』のことを書いておられましたね(『カラーひよことコーヒー豆』所収)。あれがまさに「言語文化」という新しい必修科目の精神なんです。現代の我々が、生涯にわたって言語文化としての古典に親しめるようにするには、どんなふうに古典と向き合って、どんなふうに古典を学べばいいのか。「言語文化」は、分断された古典と現代をつなぎ直すという、大きなシフトチェンジをしようとしてつくられた科目なんです。
小川:私も高校時代にちゃんと古典を勉強しておけばよかったのに、と思います。 幸いこういう仕事をしていますので、教科書を読み返したりして、実は古典がおもしろいんだということに大人になって気づくんです。それに現代の作家の新訳などで、文法の規則を覚える苦行から解放されて読むと、文学として大変おもしろいし「ああ、人間って何百年たっても変わらないんだな」という、あたりまえのことを気づかせてくれます。すばらしい原文自体は歴然としてありますので、その感動を素通りしてしまうのはもったいないですね。
幸田:「言語文化」とは別に、選択科目では「文学国語」という科目が新たに誕生します。この中では、ただ単に小説や詩歌を読むだけではなくて、創作活動も取り入れています。高校の国語の中で、創作をここまで正面から掲げたのは、恐らく初めてだと思うんですけれども、高校生が小説をつくったり、詩をつくったりということを、先生はどんなふうにお感じでしょうか。
小川:たぶん大人が想像する範囲をこえるものを彼らはつくるんですよ。機会さえ与えれば、大人たちも驚くし、本人も自分の中にこんなものが隠れていたのかと発見することになると思います。何かをつくることは、できた作品が鏡になって、そこに映っている自分を見るという体験になるはずです。思春期の子は誰でも、モヤモヤして正体がわからないものをどうにか外へいったん出して、自分でもその正体と向き合いたいと望んでいますよね。スポーツで発散したり、絵を描いたり、音楽で表現したりというかたちで、その心のモヤモヤと付き合える人もいるんでしょうけれど、言葉で表現することでも十分できます。それを私は「アンネの日記」を読むことによって発見しました。やはり読書体験からスタートしているんです。言葉で自分を自由にできるんだということを読書によって学んで、恥ずかしいのですが、(一度も採用されませんでしたけれど)朝日新聞の短歌のコーナーに投稿したりして……。私はここに生きているんだということを発信したかったんでしょうね。誰かに読んでもらえることが喜びだったんです。
幸田:やっぱり読者を得ないと書いたもの、表現は完結しないと思います。ですから今回の学習指導要領では書いたら終わりではなくて、それを他者の目で評価してもらったり、感想をもらったりというようなことを、必ず入れるようになっているんです。クラスで何かを書かせたら、それを文集などにしてみんなで読み合うといいですね。先生が一人で一生懸命添削してコメントを一言書くよりも、多くの読者の目に触れて、いろいろな人からいろいろなことを言ってもらえる機会が得られると思います。創作の授業は特に、どうやって交流するかという手立てを考える必要があるのではないかと思うんです。

小川:批評することがまた勉強になりますね。創作のための日本語と、批評のための日本語は微妙に違います。他者の作品を読んで、それについて何かを言うためには、また違う日本語の能力を引っ張ってこないとできないので。
幸田:そのとおりです。今回改訂された学習指導要領では、一方で、古典から近現代までの文学をトータルに扱う「言語文化」という必修科目を置いて、その上に「文学国語」「古典探究」という、文学系の選択科目が積み上がっていきます。もう一方で、実社会や実用や論理を扱うのが「現代の国語」という必修科目で、その上に「論理国語」「国語表現」という選択科目が積み上がっていきます。新しい学習指導要領は、このように大きく二つの系統に構造化されているのです。
自分で困難を切り開く
幸田:いろいろな困難が待ち受けている社会が目に見えている中で、これまで以上に正解を覚えていく教育ではなくて、自分で考えて、自分の言葉で表現して、自分で困難を切り開いていくという教育が求められます。思考力・判断力・表現力を鍛えていく方向に変わっていこうとしているんですね。国語でも、話し方や話し合いの仕方、方法論や考えるためのトレーニングの仕方などを教える、ベースになるような科目が必要ということで設置されたのが「現代の国語」です。

小川:私たちが子どもだった頃に比べると、パソコンとかスマホが生まれたときからある今の子どもたちは、案外文章をつくる作業を日常的にやらなくちゃいけないんですよね。そこで誤解が生じたりして問題になるわけですけれど。ですから、日本語の特徴や使い方をちゃんと勉強して、正しく道具として使いこなせないと、現代社会で生きていけないということなんでしょう。哲学やノンフィクションなど一見、文学と離れた論理的な表現が求められる分野でも、結局は文学的な表現にもつながってくると思います。そういう能力を勉強した上でまた「こころ」を読めば、基礎的なものとして絶対に読解にも役立つと思います。
幸田:そうですね。「現代の国語」で学んだことが方法論として「言語文化」に生かせるし、「言語文化」で学んだ言葉の奥行きをもって「現代の国語」を相対化することができるし、と相互に影響し合う関係にあると思うんですね。だから小川先生がおっしゃったように、相互に学んだことが生かせれば、今までよりも豊かな国語科の学びをつくっていくことにつながるのではないかなと思っています。
小川:日本語は本当に奥深いと思います。もう使い古しているはずなんですけれど、秘密がまだまだ隠れていますよ。作家は、それをいつも探しているんです。同じ言葉でも日常生活で使うのと、小説のある場面で使うのとでは、意味合いが全然違ってくる。でも、そもそも言葉は自然界にあるものではなくて、人間がコミュニケーションのためにお互い了解し合ってこしらえたものですので、本来論理的にできているんですよね。小説も、なんとなく感覚とか感受性とか、ぼんやりしたものでつくられていると思われがちですが、実はものすごく緻密な計算をしています。たとえば百枚の小説で途中の二枚ぐらいの場面を書き換えると、結局全部変えないといけなくなったりします。編み物と一緒で、間違えた目だけを直せばいいというわけにはいかないんです。非常に筋道立てて構築されていると思います。
幸田:特に先生の作品は、本当に緻密に考えられていると思います。
小川:ただ、作品に考えた痕跡を残しちゃいけないんですけれどね。あくまでも自然に物語のほうから生まれ出てきたかのように見せかけるためには、じっくり考えて書かないといけない。スラスラ読める文章にするためには、スラスラ書いちゃ駄目なんです。ですから実社会で要求される論理的な能力を国語で養うことは、言葉の勉強にとって重要だと思います。若いときは自分がもっている以上のものを見せたいという気持ちで書いてしまいがちです。でも、30年ぐらい書き続けていくと、見せかけのものから腐っていくなとわかってきます。余計な飾りを付けない、シンプルな言葉で実は心理が伝えられるんだと、書けば書くほどわかってきます。たとえば、今年8月に行方不明になった山口県の2歳の男の子が、発見されたときに「ぼく、ここ」って言ったそうですね。たった4文字のなんの飾りもない、日本語が生まれたときのまんまの言葉。でもそれが大変深い意味をもつ。これが文学だと思うんですよ。
幸田:その言葉は発見者の方がおっしゃっていましたね。なぜあの「ぼく、ここ」という言葉に感動するのか、今、小川先生のお話でわかりました。奥深いですね。

小川:それを聞いて「あ、それが大事な声だ」ということを受け止める人がいたわけです。発する人がいて、受け取る人がいる。そこに文学が成り立っています。文学と実生活、やっぱりどちらも欠けてはいけないということですね。
幸田:そうですね。トータルな国語科ということを考えたときに、文学と実生活とが相互に影響をし合っているんだということを自覚しながら組み立てること。たとえば、高校であれば三年間の中でどんなふうに個々の学習全体をデザインしていくのか。そういう発想が大事になるんだろうと思っています。
国語とは気長にお付き合いを
──最後に、高校生へのメッセージをお願いします。

小川:私の作品を教科書で読んでくれている高校生がいるんだなと思うと、本当に幸せです。作家としてこんなにうれしいことはありません。「高校生のときに出会ったけれどわけがわからなかった」という体験でも、いつか「ああ、あのときそういえば」と感動を新たにすることが必ずあると思います。つまり、文学とは長い付き合いになるんです。教科書で出会った文学でも、そのとき、そのときの瞬間的な出会いではなくて、実は一生をとおして関わり続ける可能性があるので、あまり短気を起こさないでほしいと思います。
幸田:高校生には、「食わず嫌いをするな」と伝えたいですね。国語で学ぶことは小説、評論、漢文、古文などたくさんあります。もし苦手な授業があれば、教科書のほかのページを読んでみるとおもしろい発見があるかもしれないと思います。
──ありがとうございました。
『国語教室』第108号(2018年10月)より転載
プロフィール

小川洋子(おがわ ようこ)
小説家。多くの作品が教科書に掲載されている。近著に『口笛の上手な白雪姫』『不時着する流星たち』など。

幸田国広(こうだ くにひろ)
早稲田大学教育学部教授。高校国語教育の歴史や新学習指導要領に詳しい。著書に『高等学校国語科の教科構造』など。
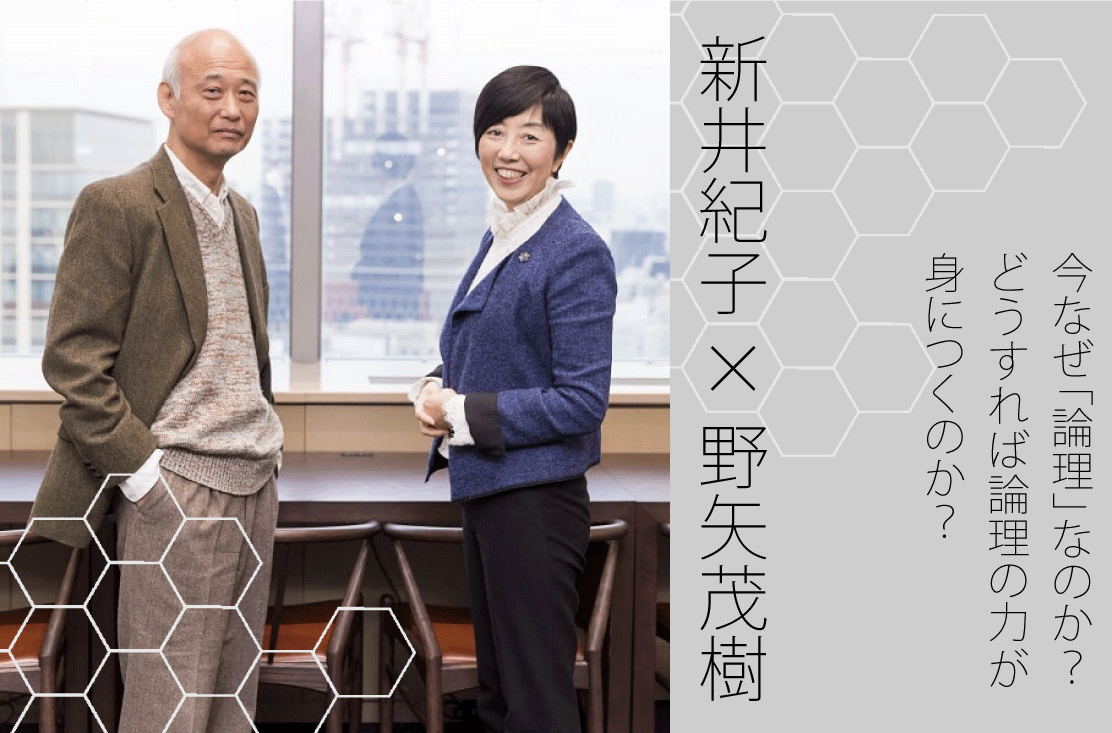
詳しくはこちら
一覧に戻る






