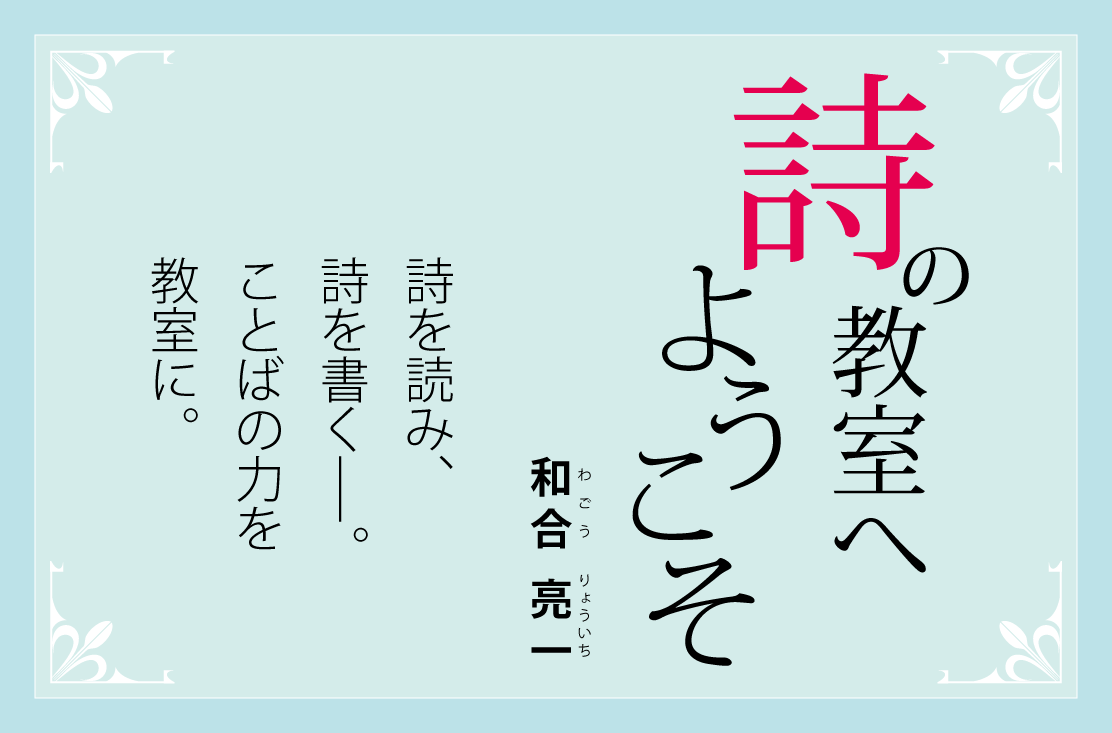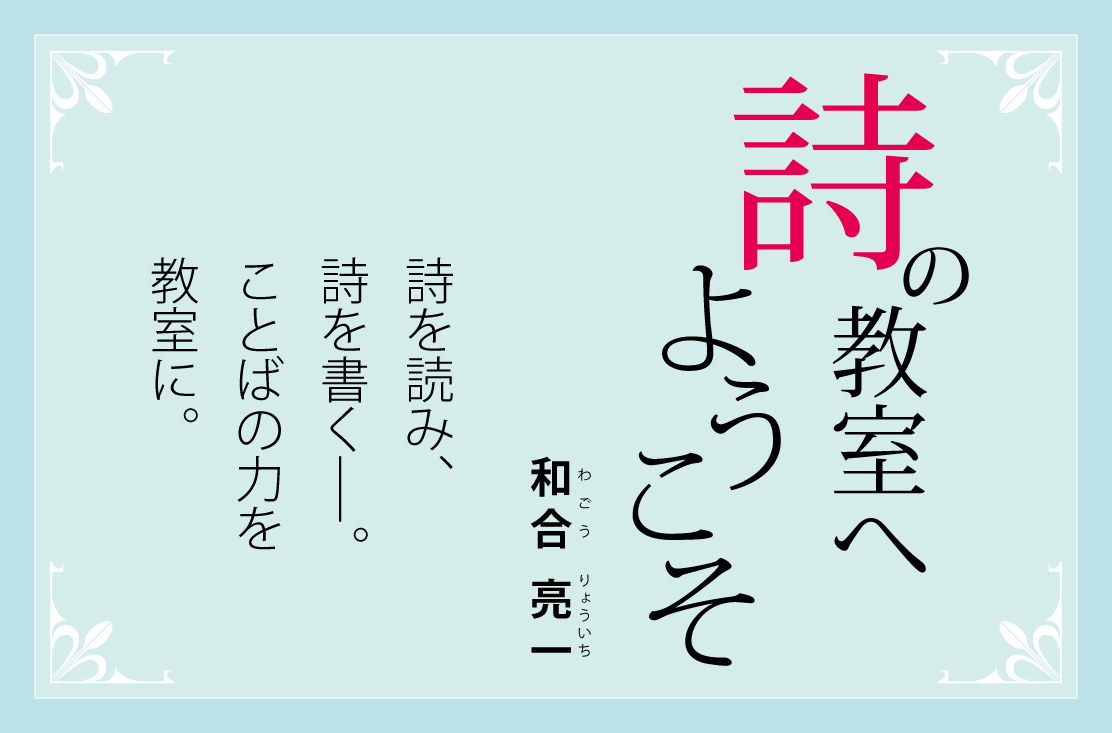詩の教室へようこそ
第8回 自分だけの声と言葉を届けるために
和合亮一
- 2024.06.11
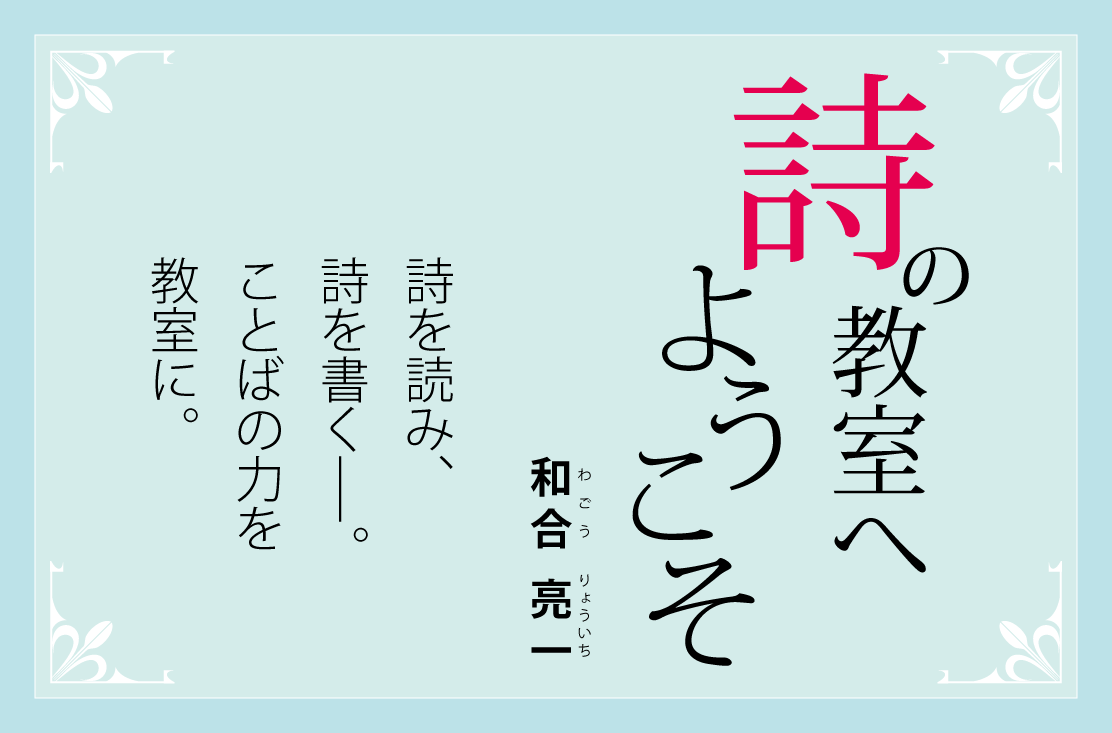
◆朗読との出会い
今回は、朗読の面白さについてお話をさせていただきます。
詩を書くことと朗読とは、大体同じ頃に始めました。
学生時代から演劇をやってきましたから、言葉を声にすることについてあまり抵抗はないほうでした。でも、本当の面白さに気づくのには、始めてからずいぶんと時間がかかったように思います。たどりつくまでには数々の失敗も経験してまいりました。
気がつけば30年ほども朗読の活動を続けてきたことになります…。このように書いていて、あらためて驚かされます。アナウンサーでもないし、プロの俳優でもない。自分なりの読み方であればいいということに気づいたとき、初めて肩の力が抜けて楽しむことができるようになった気がいたします。授業で生徒たちに範読をする時間を大切にしているのも、朗読の魅力をきちんと伝えたいという気持ちからです。
最初の経験は、ある美術館の企画展の展示室でした。20代の初め頃のことです。ありがたくも、展示された絵の前で朗読をする機会をいただきました。その日は日曜日の昼下がりということで、お客さんもたくさん入場していました。朗読の開始時間にはきちんと館内アナウンスが入り、しだいに人が集まってきました。ガチガチに緊張している私がいました。目の前の原稿から顔を上げられないぐらいになりながら、自作詩の朗読を終えて見渡してみると、集まってくれたり足を止めてくれたりしたお客さんのほとんどは、別のフロアへと消えてしまいました。
真っ青になりました。
ここで初めて、朗読の本当の難しさに直面したのです。それは、先に述べたように「自分なりの読み方」に全く気づいていないことによるものだと、ずいぶん後になって冷静に理解するに至ったのでした。このときは、すぐにすっかり自信喪失し、絶望しました。自作詩の朗読は二度とやるまいという誓いを心に立てることになりました。
そして、2年ほどの空白がありました。
しかし、どこか悔しさが胸のなかにあったのかもしれません。朗読をしていない間にも詩作は続けておりましたから、頭の片隅では自作詩の朗読の失敗のイメージがどこかに拭いきれずにあったのかもしれません。とにかく、このままで終わってしまうことは、表現者としての逃げに過ぎない、と歳月を経るうちに思い返しました。
チャンスがあれば、またどこかで自作詩の朗読に挑戦してみたい。その頃に親しく通うようになった、個人書店のマスターとそのような話をしているうちに、「それならばここでやってみては」というお誘いをいただいたのでした。
◆作品世界を楽しむということ
やがて毎月、3週目の土曜日の夕方に、自作詩の朗読会を開くことになりました。初めは椅子を並べて20人ぐらいで満員になるスペースに、お客さんの数は半分もいないぐらいでした。いつもマスターの尽力と励ましがあり、めげずにこつこつやり続けていくうちに、次第に人が増えてきて、顔なじみのお客さんもできてきました。終わってから朗読の感想を直接聞くことができるのが、自分にとっての貴重な勉強の場になりました。
そもそも、私はあがり性なところがあります(誰も信じてくれませんが)。緊張して何をしているのかわからないうちは、発信する側はもちろんですが、受け止める側も同じく、心の落ち着きどころを見つけることができません。何よりも、こちらが楽しんでいないと、受け手に本当の楽しさを伝えられるはずがありません。
これは、授業の場面でも全く同じかもしれません。指導する側が何よりも作品世界を楽しんでいなければ、生徒たちに伝わるはずがないというのが教師としての持論です。朗読会にしても、授業にしても、そうした余裕をもつことができるようになるには、ある意味で場数を踏むしかないと、その頃の私は直感していたのでしょう。お客さんを前にすることの意味を教わったのが毎月の朗読会でした。
この朗読会は、1年間ほど続けさせていただきました。今も思い起こしては懐かしくなります。
◆和合流朗読のポイント
朗読には、滑舌、抑揚、声の強弱や大小など技術的なポイントが多分にあります。
でも、それよりも大事なことがあるということをお伝えするのが本稿の目的なのですが、それでは物足りないかもしれませんので、ここで私なりのポイントを少しだけ述べさせていただきます。
まずは、声を明瞭に出すということは大切なことでありますが、それと同じくらいに間や静けさと対峙することも大事だということです。
緊張にただただ襲われていただけの時期は、詩の中の静かな部分で、緊張や焦りを大きく伝えてしまっていたように感じます。いつしか、こうした声を発していないときこそが重要だと感じ、静けさもきちんと聞かせようとしている自分に気づきました。つまり、沈黙の間とは、発声や呼吸の調整時間であり、音声と同じぐらいにその途切れ目が大事なのだと実感するようになりました。そこが声と心の拠りどころのようなものとなり、心の落ち着きを保つことができるようになるのだと、しだいにわかってきたのです。
次に、私の朗読の準備方法についてお伝えしましょう。テキストに事前に自分なりの線や文字で書き込みをすることの大切さです。
ファイルに綴じている昨年の私の朗読の台本のいくつかを、あらためて見直してみます。例えば、読みにくい単語は、線を引いたり、丸で囲んだりしています。また、「強」「弱」「大」「小」などの文字を実際に記しつつ、スピードやテンポ、声の強弱や大小、高低を記しています。「青空」、「寂しく」など、読むときの心のイメージも書いています。
こうしたコメントは、できるかぎりシンプルなほうがよいと思っています。声を発しているときに、ぱっと目に飛び込んでくるようにしておかないと、見落としたり読み間違えたり、朗読の妨げになったりする心配があるからです。
時折、「天」「地」「人」という言葉も書いています。「天」は上から降ってくるように、「地」は下を這うように、「人」はお客さんに語りかけるように…などというイメージで書き込みをしています。こんなふうに自分の好きな(勝手な)文字や記号を書き込むのがよいと思います。
読む前に書き込みをしてみると、テキストをどうとらえようとしているのか、自分の頭の中が見えてくる気がします。このように朗読のプランが先に見えていると、仮の全体像を描くことができます。
授業の中で、生徒たちにもこのような書き込みによる朗読の準備を少しでも説明してみると、取り組みが違ってくるように感じます。そして、声にしてみる機会を設けることにより、作品への親しみを増している姿がこちらに伝わってきます。
◆詩の朗読に見るお国柄

▲スロベニアの詩祭で朗読をする著者
少しだけ、海外での詩の朗読のフェスティバルに参加したときのことをお話しさせてください。
まず、ヨーロッパでは、オランダ、フランス、スロベニアの詩祭に参加させていただきました。母国語でという依頼があったので、日本語で朗読させていただいたり、たくさんの詩人たちの朗読に耳を傾けたりして肌で感じたのは、朗読への親しみがとても深いということです。抽象的な言い方をするならば、耳が朗読に開かれている、独特の澄んだ感覚をさまざまな場面で覚えました。
いろいろな詩人たちと語り合う機会をいただきましたが、そもそも自作、他作にかかわらず、作品の朗読はとても自然なことであるようです。例えば、作品を書き上げると、まずは家族や友人や仲間たちに、声に出して披露し、感想をもらうことにしているという話を幾人からも聞き、朗読という行為の敷居の低さを感じました。
アメリカでは、サンフランシスコなどで、同じく母国語でという依頼を受けて朗読させていただきました。真摯にまなざしと耳を向けている態度のなかにも、独特のノリのよさがありました。例えば、テンポがよくて気に入ったところがあると、客席から自然と掛け声があがったりして、こちらが驚かされてしまいました。なるほど、ラップなどの音楽文化のある国だと感じ入りました。
アジアでは、中国、台湾、シンガポール、韓国、インドネシアなどに行きました。どの国でも朗読について熱心なものを感じましたが、特にインドネシアは印象深いものでした。若者を中心にリーディングのイベントが盛んであり、夕方になるとカフェや公園などに仲間たちが集まり、輪になっている様子を目撃しました。私は、夜に特設の野外ステージに招かれましたが、驚くほどの聴衆(1000人以上)がいて、こちらは日本語で朗読をしているにもかかわらず、客席からの掛け声や手拍子などのリアクションが凄くて、圧倒されてしまい…いや、負けずになんとか頑張りました。
海外で味わった、それぞれの熱い空気感が、少しでも読者のみなさまに伝わっていればよいのですが…。それぞれに詩の朗読を心の底から楽しんで、それをその場で分かち合っていました。自分なりの読み方でよいということを前提として、詩や朗読がとても身近で自由なものとして、いつも傍らにある感じがします。幼い頃から家庭で、学校で、そして社交場で、作品について声に出すことをためらわない開かれた意識がある。私たちの家庭や学校教育の場において、大いに参考にしたいと、それぞれの国で直感できたのはよい体験でした。
東日本大震災から13年目の春を迎えました。
震災の少し後で落ち着きを取り戻した時に、ある先生から涙ながらにお話をいただいたことがあります。「教室に津波で家族や家を失った生徒があり、国語の授業でどうしても教科書に出てくる『海』や『波』という言葉を口に出せない感じがあった。この間、初めて、和合さんが書いた詩を生徒たちと朗読した。『海』や『波』を声にすることができた」、と。決して私の詩の力ではなく、朗読というものに内在している力なのだと実感しました。私も眼が潤みました。
元日から起こった能登半島地震の災害に心を痛めております。福島から祈り続けております。
『国語教室』第121号より転載
プロフィール
和合亮一(わごう りょういち)
福島県立福島北高等学校教諭。第一詩集にて、中原中也賞、第四詩集にて晩翠賞受賞。2011年の東日本大震災で被災した際、twitterで「詩の礫」を発表し話題に。詩集となり、フランスにて詩集賞受賞(日本人初)。2019年、詩集『QQQ』で萩原朔太郎賞受賞。校歌、合唱曲作詞多数。
一覧に戻る