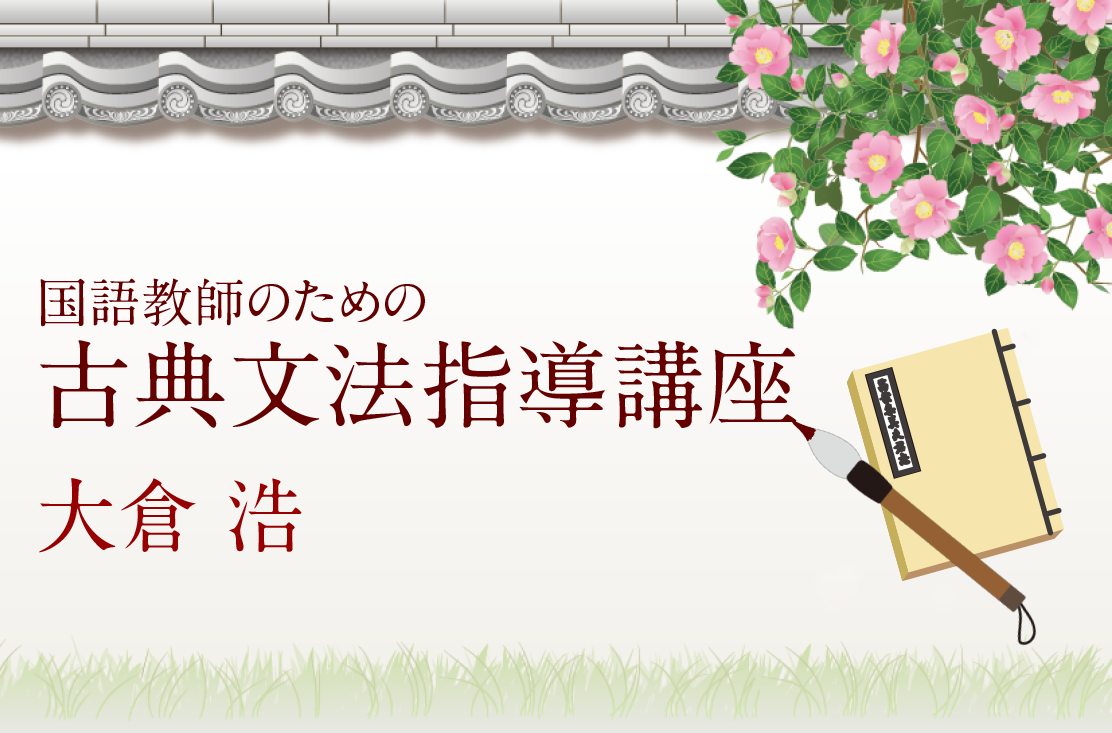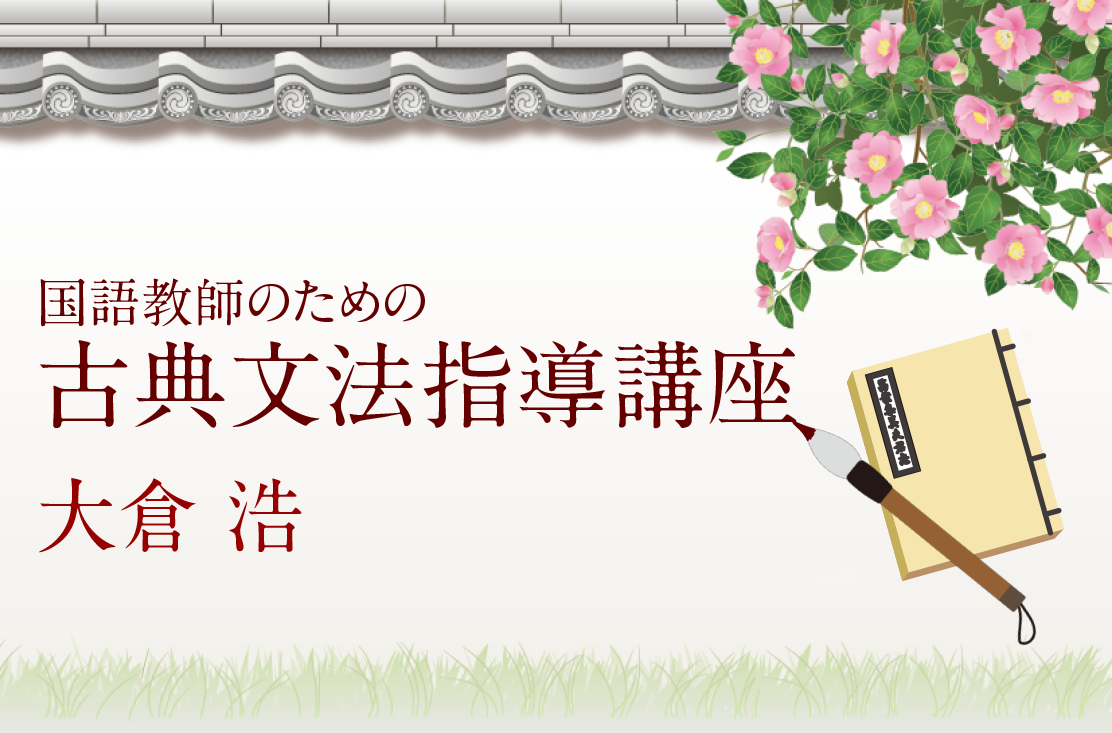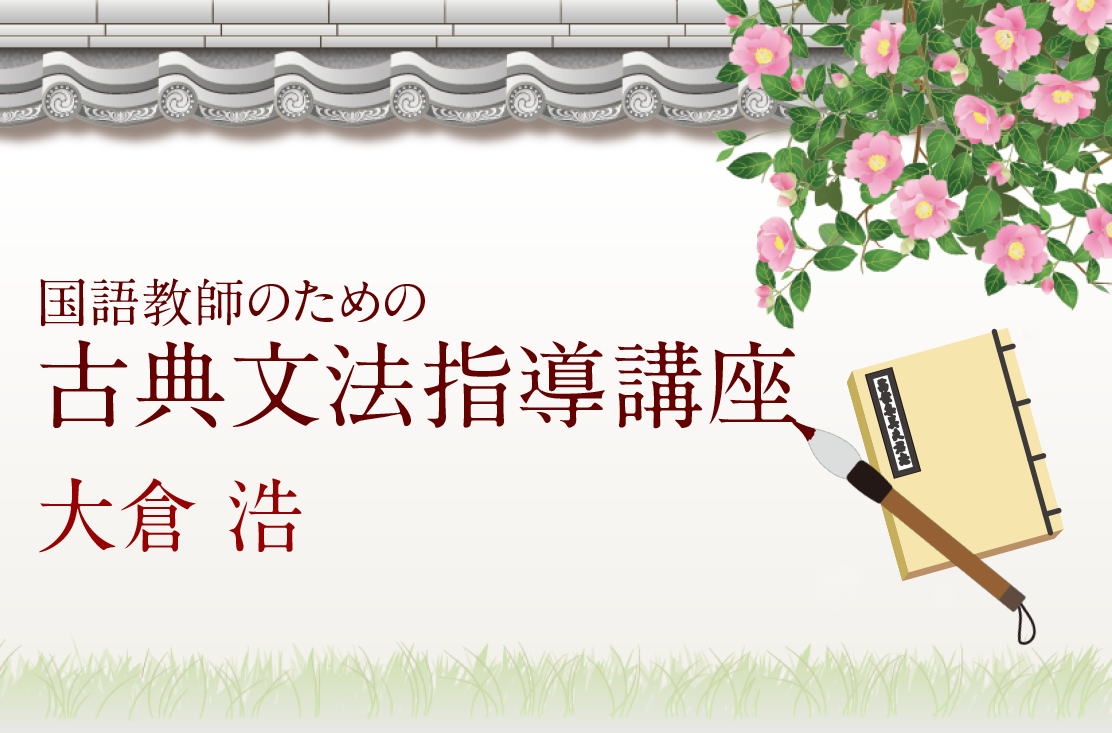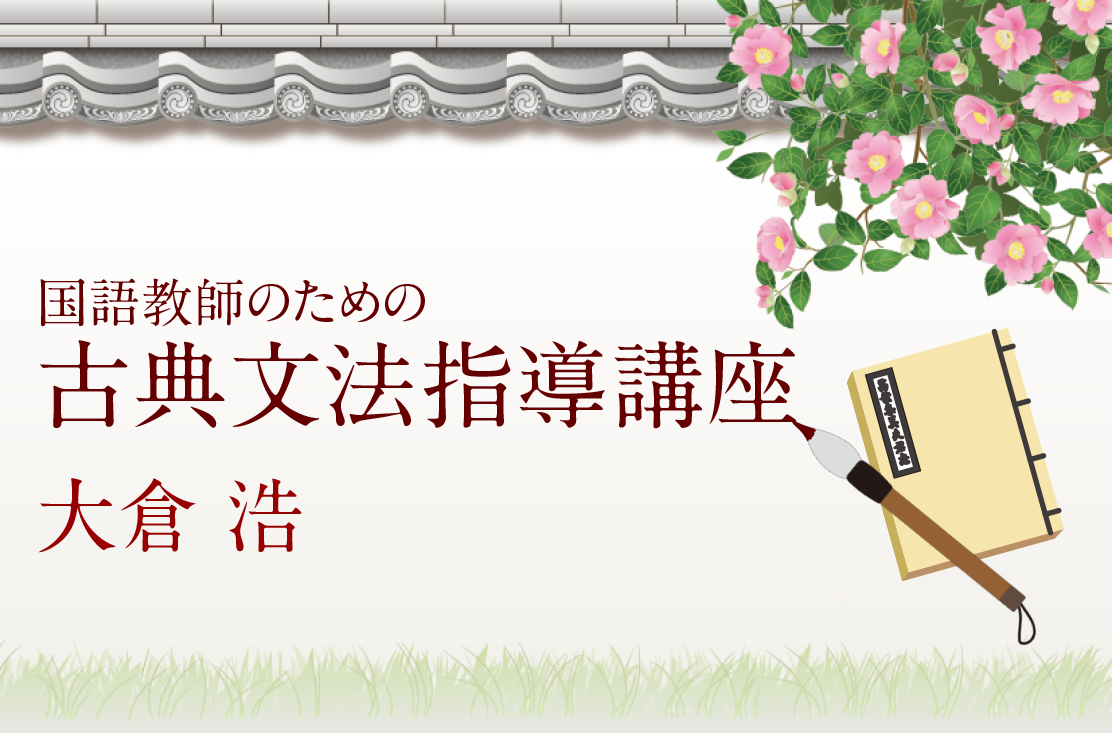国語教師のための古典文法指導講座
第4回 紫式部にファンレターを書こう①
大倉 浩
- 2025.08.01
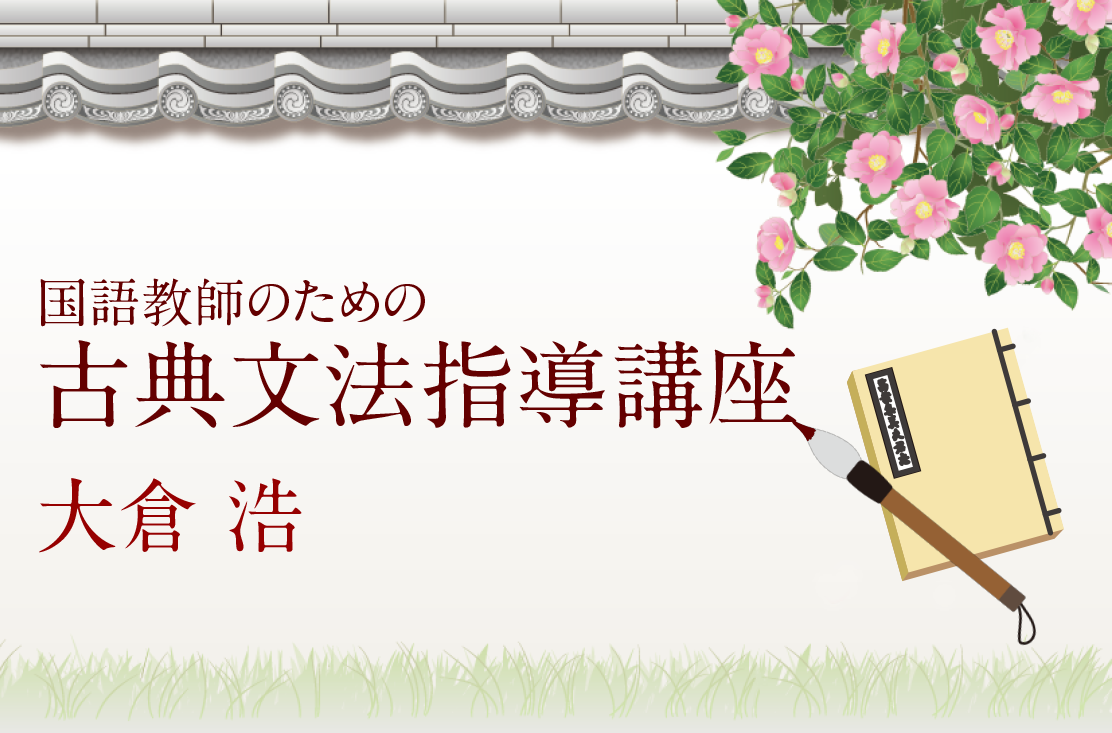
第三回では、紫式部にファンレターを書くという課題を出しました。今回はその続きです。
課題 紫式部の時代の手紙はどう書くのか。
実は、紫式部の本名も生没年も未詳です。漢学者藤原為時の娘で、夫藤原宣孝と死別し、一条帝の中宮である彰子に仕え『源氏物語』『紫式部日記』を残したことは知られています。しかし、出生や宮仕え後のことなどについて確実な記録は残されていないようです。とりあえずの宛先は、京都の内裏の「中宮彰子様方」にして、内容に取りかかりましょう。
ファンレターのような私的な手紙なら、当時は「消息」というべきでしょうが、手紙の作法は、互いの身分や内容、時代によっても違ってきます。古典の教科書では、かぐや姫が帝に書いたお別れの手紙の一節が『竹取物語』の中で採り上げられていると思います。
この国に生まれぬるとならば、嘆かせたてまつらぬほどまではべらむ。過ぎ別れぬること、かへすがへす本意なくこそおぼえはべれ。……
帝宛てなので敬語も多いのですが、現在の手紙で「です・ます」を使うように、文末に「はべり」が使われています。これは参考になります。他にも、時候の挨拶は? 頭語は「拝啓」でよいのか? など、作法についてはきりがありません。それはそれで興味深いのですが、この講座の目的である文法から少し離れてしまうので、川村裕子『王朝の恋の手紙たち』(角川選書)を参考にあげておきます。
さて文面です。まずは名前を名乗らなくてはなりません。前回の名前変換を使います。
私は東京都大修館高校教員の鈴木祐介です。
【古文訳】
われは武蔵の国大修館高校講師のすゞきのいうすけにてはべり。
「東京都」では紫式部にわからないでしょうから、教科書の古典地図や便覧を使って当時の地名に換えました。「です」にあたるのが「にてはべり」。断定の助動詞「なり」に「はべり」を接続させるには、古典文法の知識が必要です。「なり」の連用形「に」に接続助詞「て」を付けて「に・て・はべり」となります。そして、自分がファンであることを伝えなくてはいけません。例えば、
あなたの書いた「きりつぼ」を読みました。死んでしまう桐壺更衣がとてもかわいそうでした。
と感想を伝えるとすれば、さあどう訳しましょうか。
「英語に訳すほうが簡単だ」と思った方も多いかもしれません。それは、英語学習は英作文も勉強するのに、古文については、現代語訳という解釈しか勉強しないからです。逆方向の古文作文は勉強しないので、学んだはずの古典文法もうまく機能しないのです。何とももどかしい気分です。そこで、
課題 現代日本語を古語に訳してみよう。
英作文の際に助けになるのが和英辞典、日本語の単語を引くと、同じ意味の英語の単語や関係する表現を示してくれる辞書です。古文作文ですから、現代の日本語を引くと同じ意味の古語や表現が出てくる辞書、つまり「現古辞典」があると便利です。
しかし、古語を現代日本語で説明した「古語辞典」はたくさんあるのに、「現古辞典」はあまりありません。そのなかでは、歌人である芹生公男さんが編んだ『現代語古語類語辞典』(三省堂)が本格的です。もともとは作歌のために古語を整理することから生まれた辞書ですが、「あなた」を引くと、二ページにわたって時代別・身分関係別に、古語での第二人称代名詞が示してあります。ここではこの辞書を参考に「あなた」を「おもと」と訳してみます。ただ、こうして自立語を訳しても、文に仕上げるためには、やはり古典文法が必要になります。その話は次回。
『国語教室』第112号より転載
著者プロフィール
大倉浩(おおくら ひろし)
筑波大学名誉教授
→ 古典文法に関する質問をする
一覧に戻る