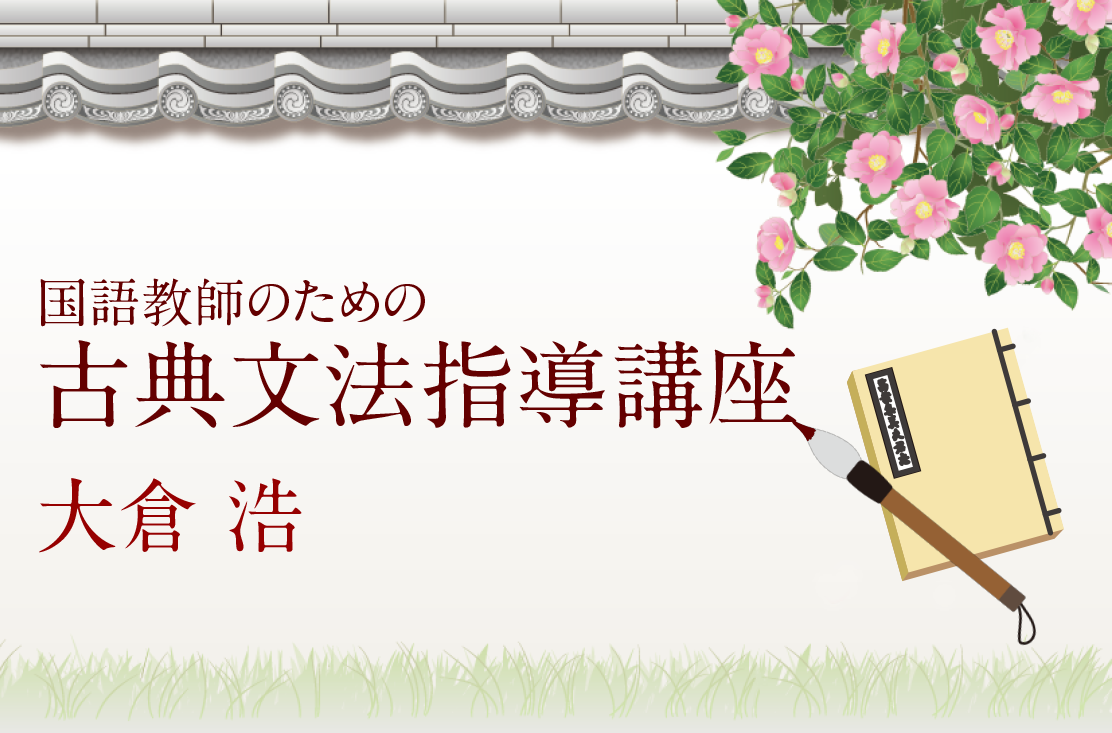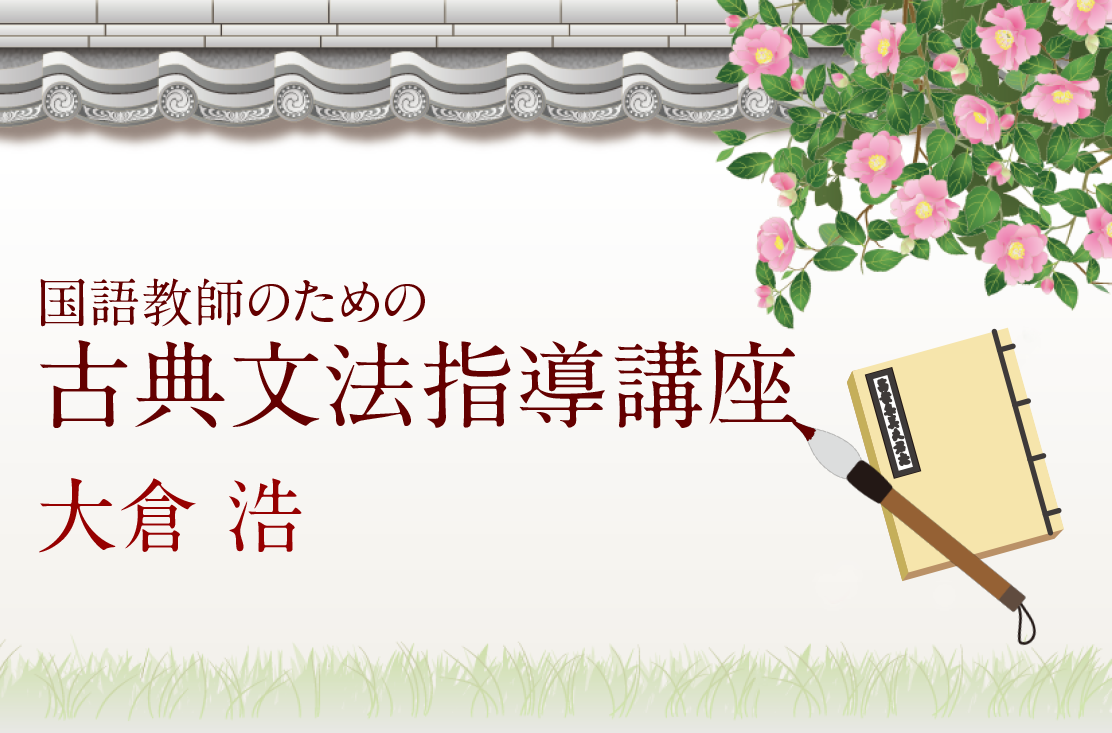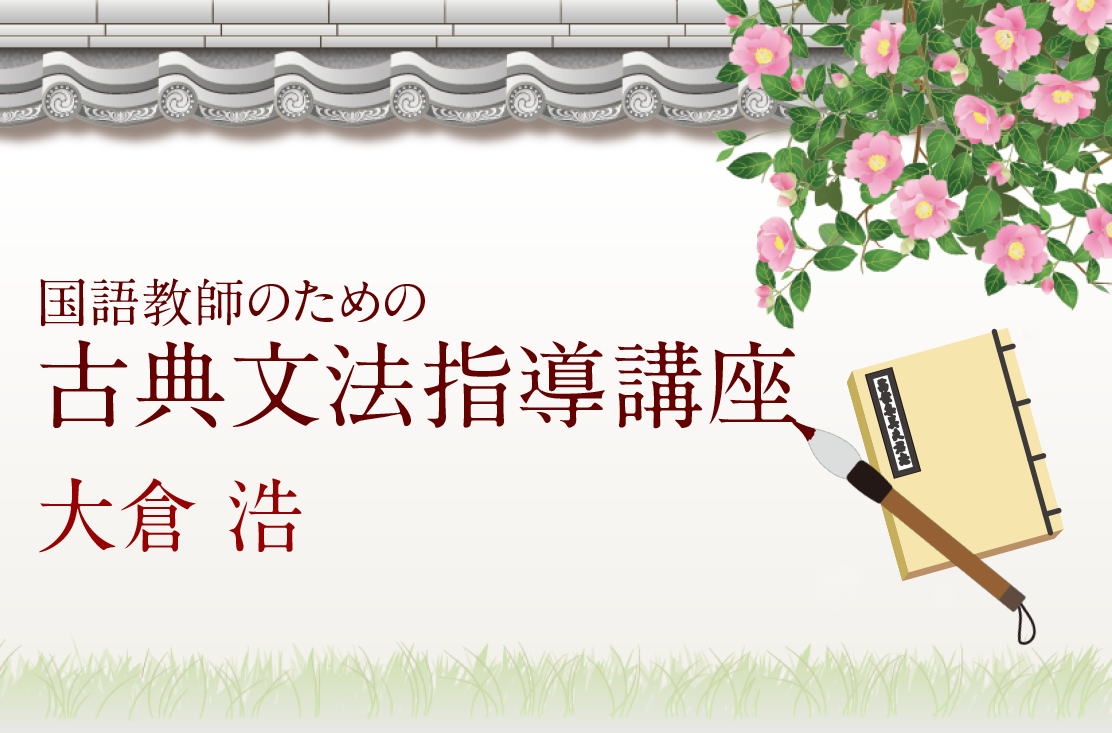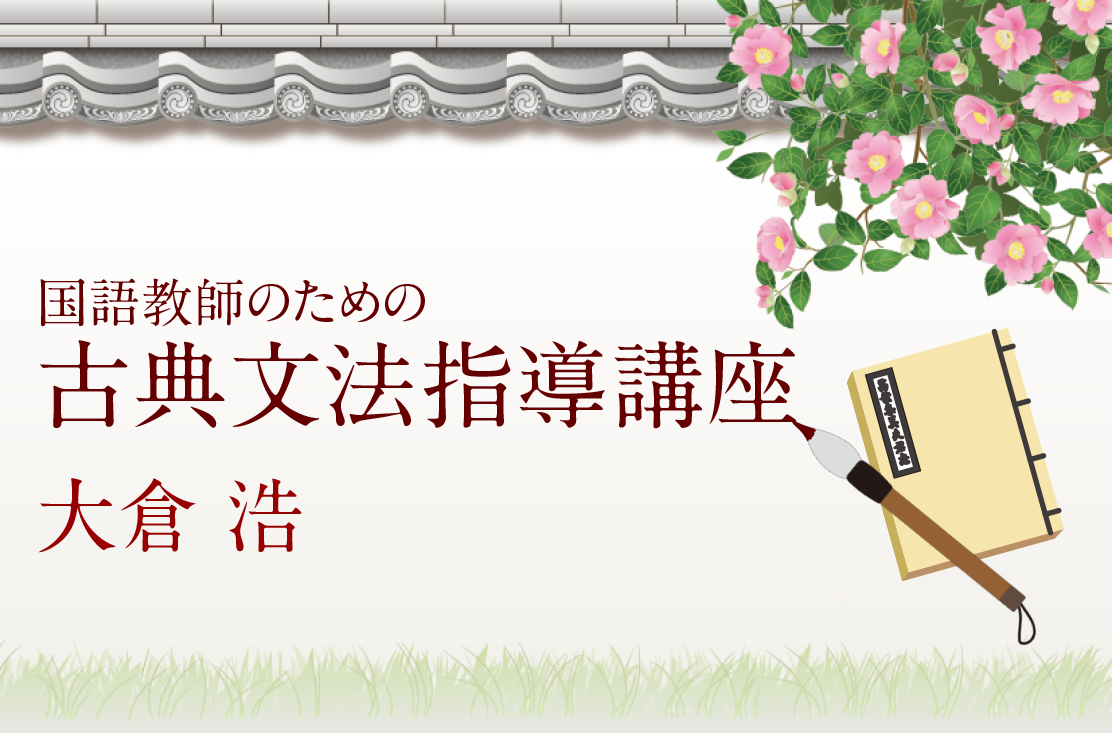国語教師のための古典文法指導講座
第5回 紫式部にファンレターを書こう②
大倉 浩
- 2025.08.04
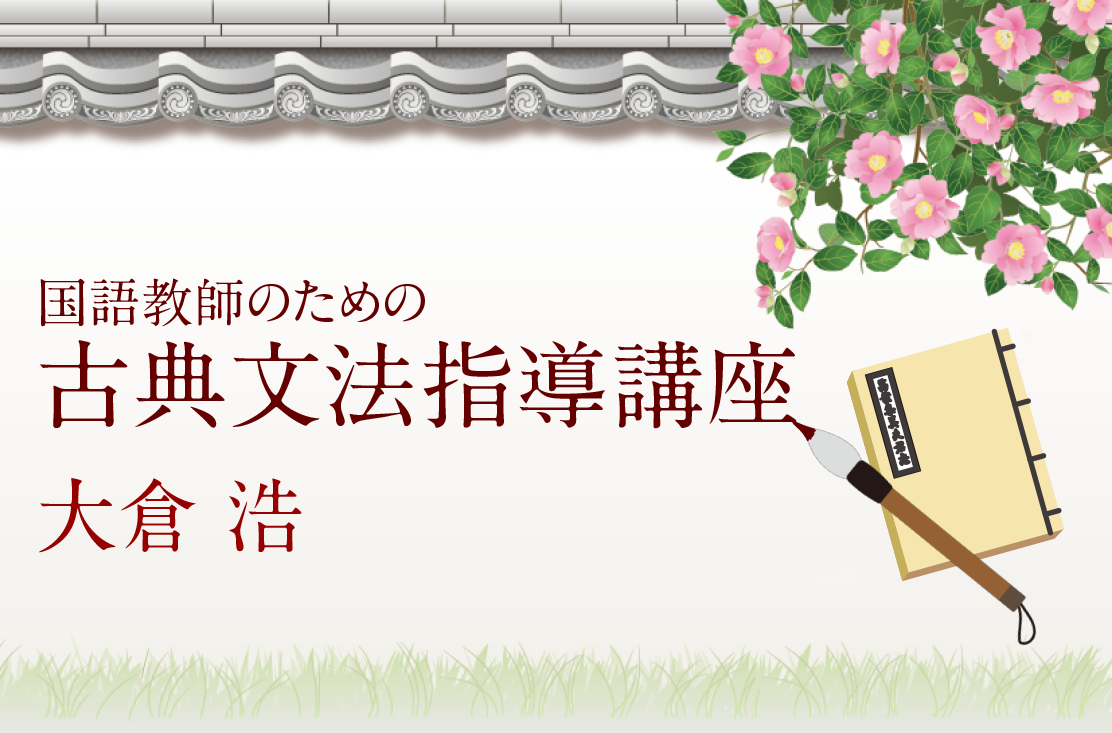
第四回では、紫式部へのファンレターを書き始めました。今回はその続きです。
あなたの書いた物語の「きりつぼ」を読みました。死んでしまう桐壺更衣がとてもかわいそうでした。
まずは日本語の「現古辞典」を使って
あなた→おもと
と訳してみたのが前回でした。同じく「現古辞典」を使って調べると、そのままの語も多いのですが、
(物語を)書く→ものす
死ぬ→なくなる
とても→いと
かわいそう→あはれなり
と、自立語には翻訳候補の単語が見つかります。ところが、「の・を」や「た」といった付属語(助詞・助動詞)も翻訳しなくてはいけないのですが、「現古辞典」は自立語が基本なので載っていません。さあどうしましょう。そこで古典文法の出番です。まず、国語の教科書や古語辞典の「助詞一覧表」「助動詞一覧表」を使って、現代語訳に「…ノ」や「…タ」とある語を探してみましょう。
「あなたの」の助詞「の」は、主語に付いていますから、古語でも格助詞「の」がそのまま使えそうです。「物語の」は連体「の」が、「『きりつぼ』を」は目的「を」が、そのまま使えそうです。
ところが、「書いた」と「読みました」の「た」は、助動詞「つ」「ぬ」「たり」「り」「き」「けり」と六種類も候補があります。現代語訳では「タ」一つであまり気にならなかった「完了」と「過去」の意味の違いを、はっきりさせなくては訳せませんね。そうした疑問を持ちながら、古典文法の副読本や古語辞典でこれら六種類の助動詞の意味を調べると、これまでモヤモヤしながらも「タ」で訳して済ましてきた、六種類の助動詞の違いが少しずつ見えてくるはずです。
まず「書いた」は、紫式部が過去に書いたというより、書き上げ完成させた(物語)という意味ですから、完了の意味がふさわしいでしょう。「たり」「り」は存続(テイル)の意味がもともとですから、「つ」か「ぬ」に絞られます。この二語について、副読本や古語辞典では、意志的動作(他動詞)に「つ」、自然的推移(自動詞)に「ぬ」、という違いが必ず説明されています。ここは、物語を書くという意志的動作ですから「つ」に絞られます。サ変動詞「ものす」の連用形に接続です。
いっぽうの「読みました」は、書き手が過去にしたことの報告ですから、過去の意味の「き」か「けり」ですね。これも、直接経験の「き」と、間接伝聞の「けり」というような違いが、副読本や古語辞典に説明されているので、ここは直接経験の「き」です。それぞれを、連体形、終止形に活用させて、
おもとのものしつる物語の「きりつぼ」を読みはべりき。
と古文訳ができました。
それにしても、助動詞の翻訳にこんなに手間がかかるのはなぜでしょう? それは、古語の助動詞で残っているものが少ないからです。もう一度「助動詞一覧表」を見てみると、約三十種の古語助動詞のうち、活用が違っても現在使われるのは十種ほど、残る二十種は残っていません。「完了」「過去」の助動詞でいえば、「たり」が「タ」のかたちで残りましたが、他の五種は衰退しています。残っていなければ私たちは現代語からの類推ができませんから、改めて古語として意味や活用を覚えなくては古文が読めないのです。
日本語も変化しますから、千年も経てば衰退して残らない語があって当然ですが、同じ付属語でも助詞を見てみると、約五十種のうち三十四種ほどは残っています。衰退したのは十六種ほど、三分の一です。くらべてみると、助動詞は大きく変化しています。このことを含めて、ファンレターの翻訳は続きます。
『国語教室』第113号より転載
著者プロフィール
大倉浩(おおくら ひろし)
筑波大学名誉教授
→ 古典文法に関する質問をする
一覧に戻る