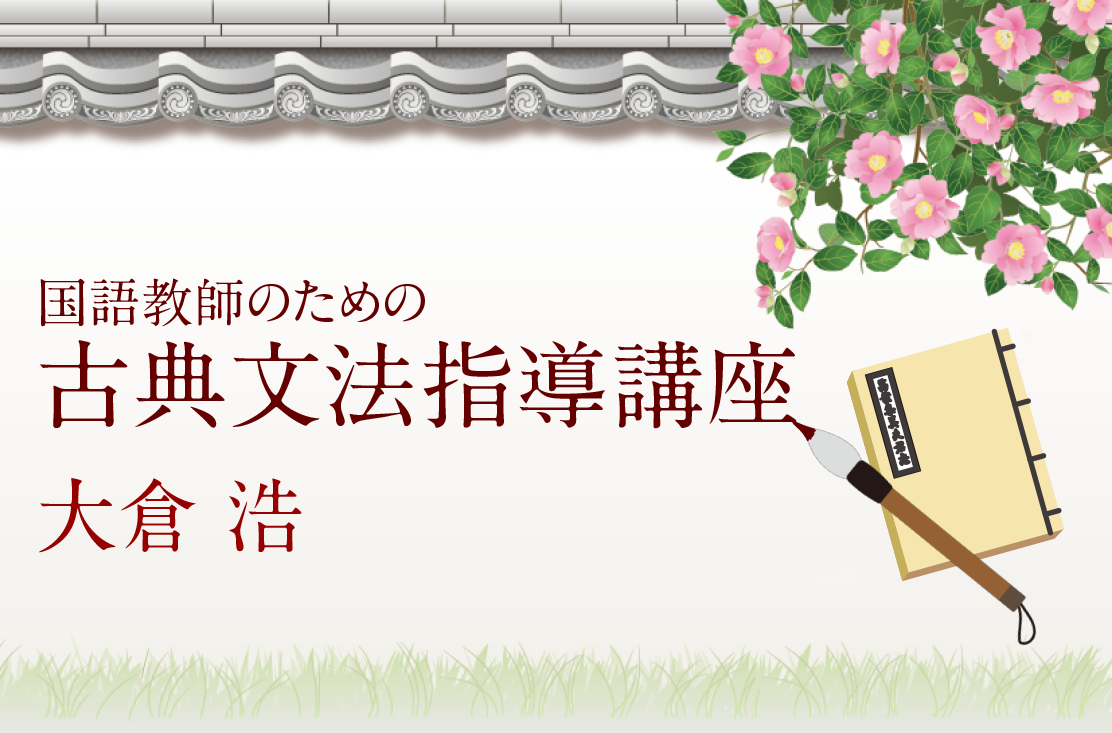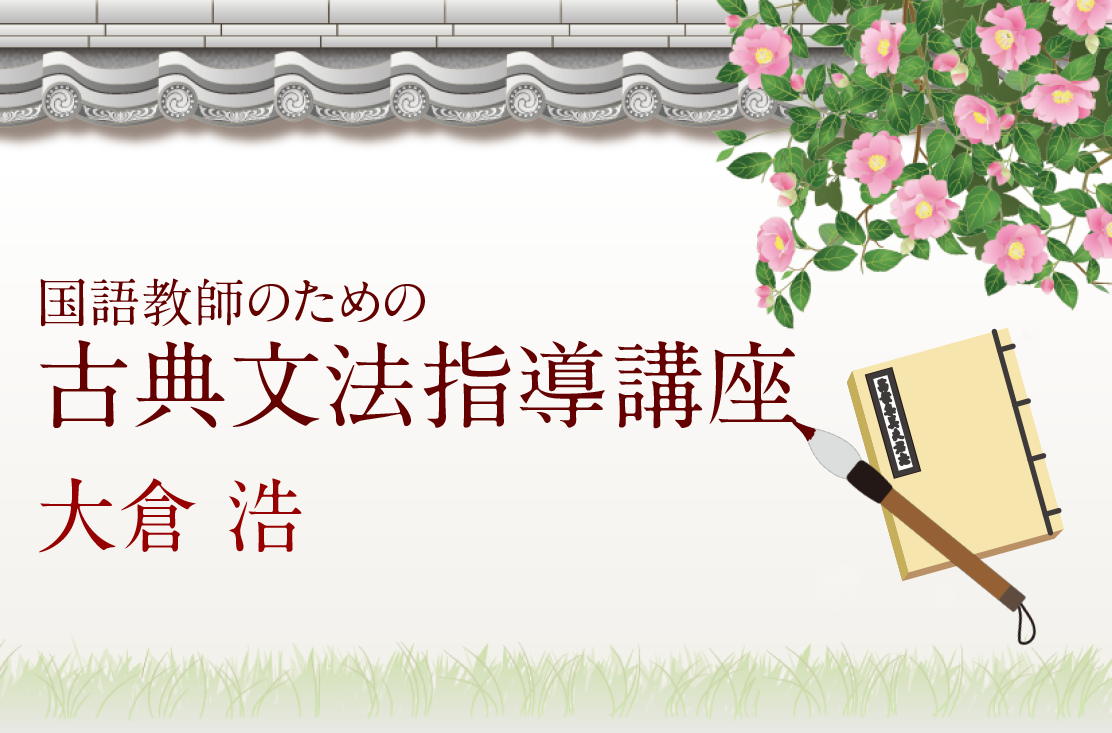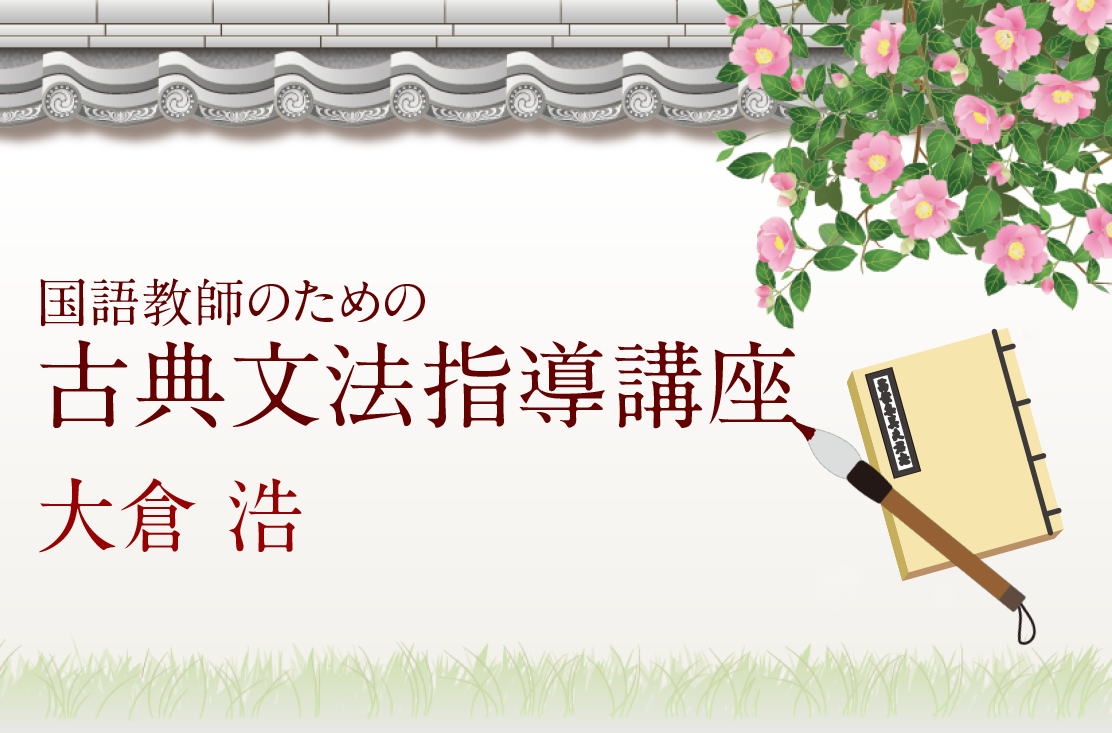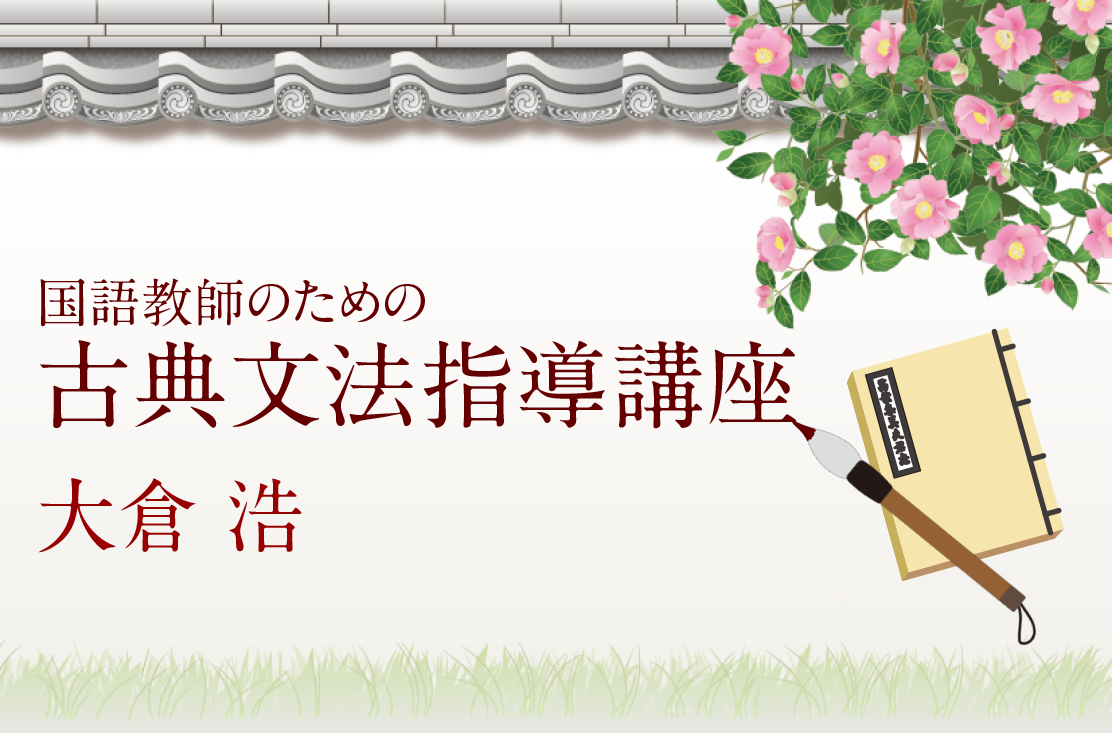国語教師のための古典文法指導講座
第6回 「ナ特」で納得! ――紫式部にファンレターを書こう③
大倉 浩
- 2025.08.06
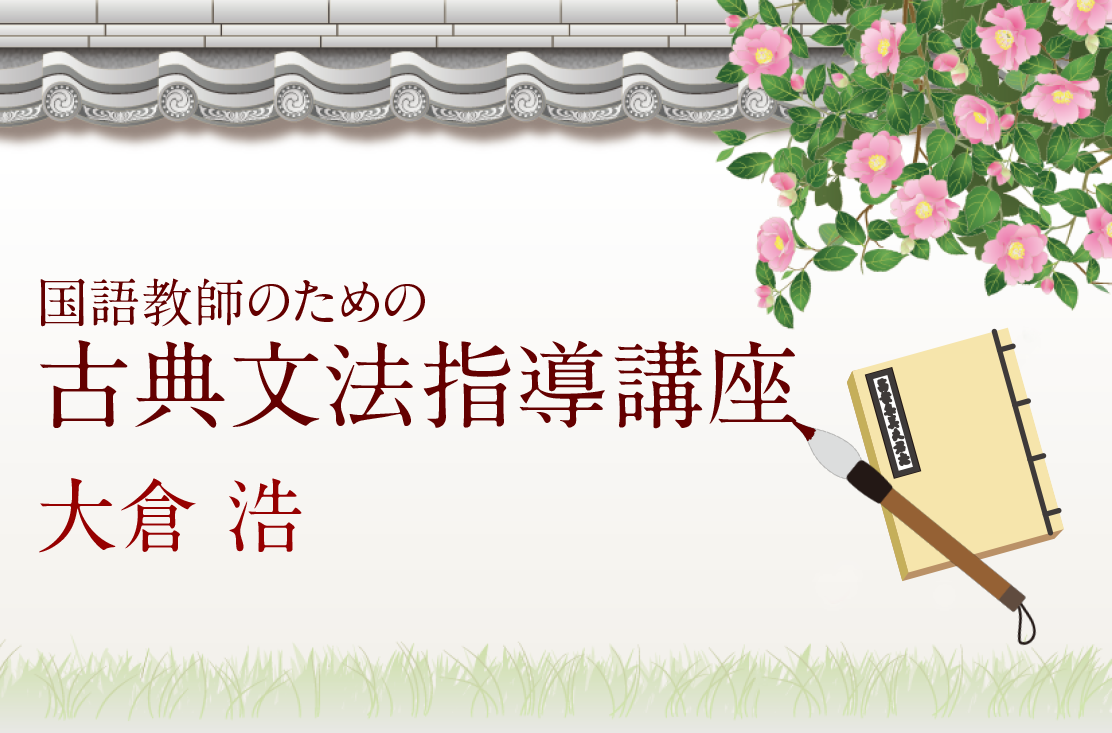
あなたの書いた物語の「きりつぼ」を読みました。死んでしまう桐壺更衣がとてもかわいそうでした。
前回の検討で、最初の文を
おもとのものしつる物語の「きりつぼ」を読みはべりき。
と書き換えました。現代語の「~た」の書き換えがポイントでした。今回は続く文を書き換えます。
死んでしまう桐壺更衣→死にぬる桐壺更衣
でいいでしょうか? 「死にぬる」という表現が、落ち着きません。「死ぬ」は不吉な言葉ですから、これまで参考にしてきた現古辞典でも、様々に言い換えた表現が時代ごとにあることがわかります。しかし今回は、この「死ぬ」という動詞にこだわってみます。
現代語に比べると、古語の動詞の活用は、9種類もあってパターンが複雑です。活用は品詞分解の基本でもあり、助詞や助動詞の接続を考える上でも重要となる古典文法の根幹の一つです。その中で「死ぬ」は、「 往ぬ」とペアで「ナ行変格活用(ナ変)」と呼ばれる、特別な活用をする動詞として分類されています。活用は
死(語幹) な に ぬ ぬる ぬれ ね
ですね。教室で先生は、「ナ変は『往ぬ』『死ぬ』の二語しかないから覚えておくように。」とあっさり言うだけで、生徒のほうはペットの犬が心配になったり、昔飼っていて亡くなった犬のことを思い出してしんみりしたりする(私もそうでした)ぐらいの記憶しか無いかもしれません。でも改めて考えると、ナ変ってそんなに「変」でしょうか?
古典文法が人気のない理由の一つに、その用語の難解さ・複雑さがあります。江戸時代の国学からの研究の伝統が背景にありますが、二十一世紀の子供たちには、英文法や、日本語教育で使う文法用語とのすりあわせが必要だと、私は思います。少なくとも「正格」活用と「変格」活用という用語は、あまり気持ちのよいものではありません。
「死ぬ」に戻ると、その活用は不規則で予測不能ではなく、「ナ・ニ・ヌと、四段活用かと思ったら、途中からヌル・ヌレと二段活用になって最後は四段のネに戻る」という、いわば四段活用と上二段活用の両面を持った「欲ばり」な活用をしているだけです。二語しかないといっても「死ぬ」はおそらく「死・往ぬ」(死の世界に往ってしまう)が語源でしょうから、もともとは「往ぬ」一語でしょう。さらに動詞の活用とア行カ行など五十音図の行との関係を眺めてみると、カ行には四段、上一段・上二段、下一段・下二段、カ変と様々の活用をする動詞があるのに、ナ行には上一段、下二段とナ変だけ、四段と上二段の動詞が無いのです。これは偶然ではなく、ナ変は、ナ行で四段と上二段を兼任する特別な動詞とも言えるのではないでしょうか。
何が特別なのかというと、ナ変と同じ活用を持つ助動詞があるのです。そうです、完了の「ぬ」です。助動詞「ぬ」は、語形(「往ぬ」の「い」が母音脱落した)からも、意味(「往ってしまう」→「自然にそうなってしまう」)からも、「往ぬ」に由来する助動詞と考えられます。助動詞として頻繁に現れる活用パターンであり、「往ぬ」という動詞自体も関西方言にも残っているように、基本的な意味の動詞であり、「死ぬ」も特別な動詞です。ナ変ではなく、ナ行特別活用動詞、「ナ特」と名付けたいくらいです。
この助動詞「ぬ」との関係については、副読本や古語辞典でも、平安時代には「往ぬ」「死ぬ」に「ぬ」が接続する例がないという事実を指摘しています。もともとの「往ぬ」が「往ってしまう」という完了の意味を持っているので、「ぬ」を付ける必要が無かったわけです。そこで、ファンレターの書き換えは、
死んでしまう桐壺更衣→死ぬる桐壺更衣
でよいことになります。ナ変以外の変格活用動詞にも、見直すべきことがありそうですが、それはまた次回に。
『国語教室』第114号より転載
著者プロフィール
大倉浩(おおくら ひろし)
筑波大学名誉教授
→ 古典文法に関する質問をする
一覧に戻る