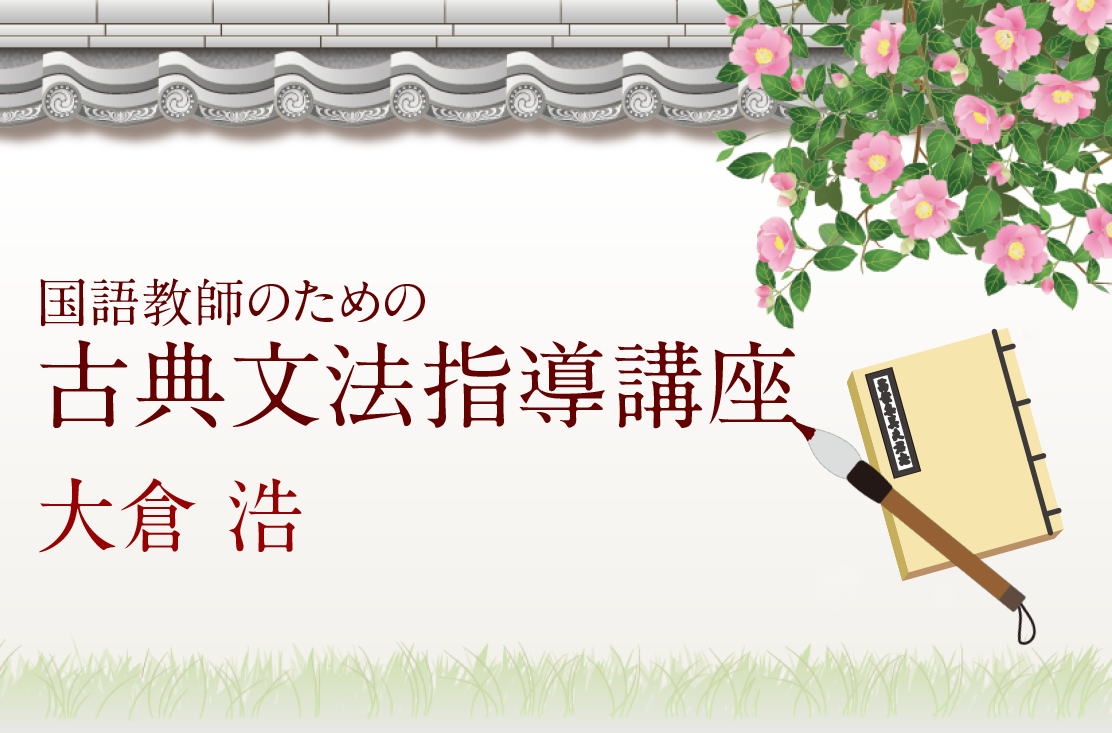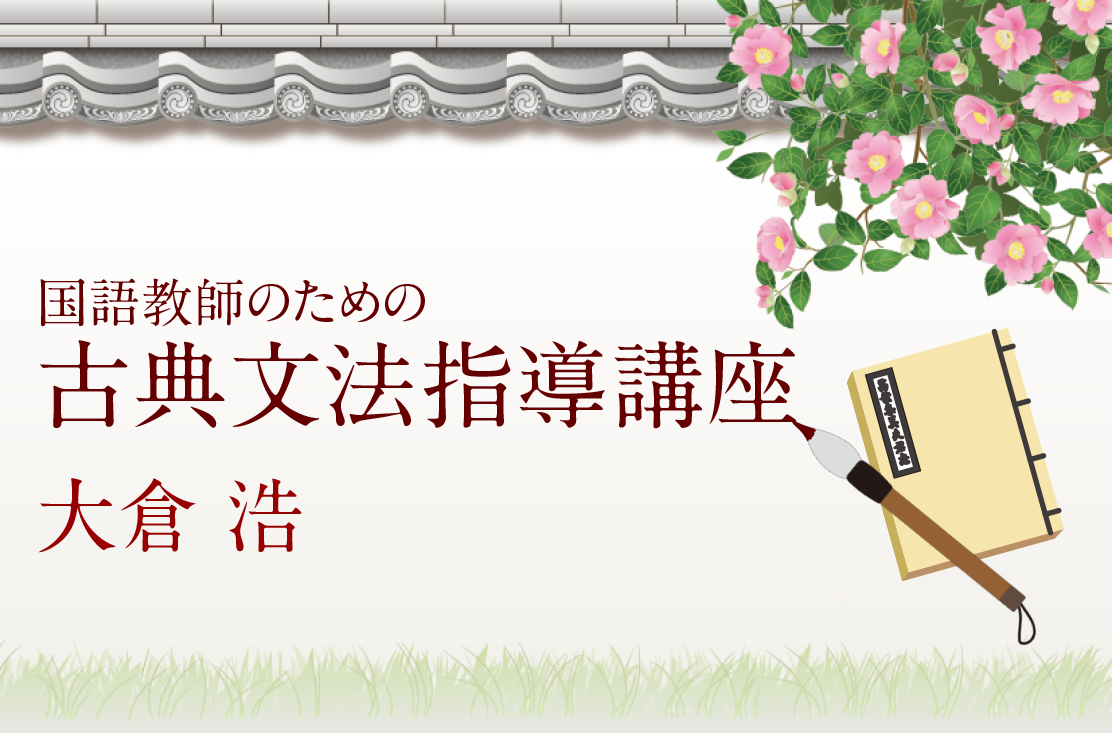国語教師のための古典文法指導講座
第7回 「サ変」も「ラ変」も変じゃない! ――紫式部にファンレターを書こう④
大倉 浩
- 2025.08.08
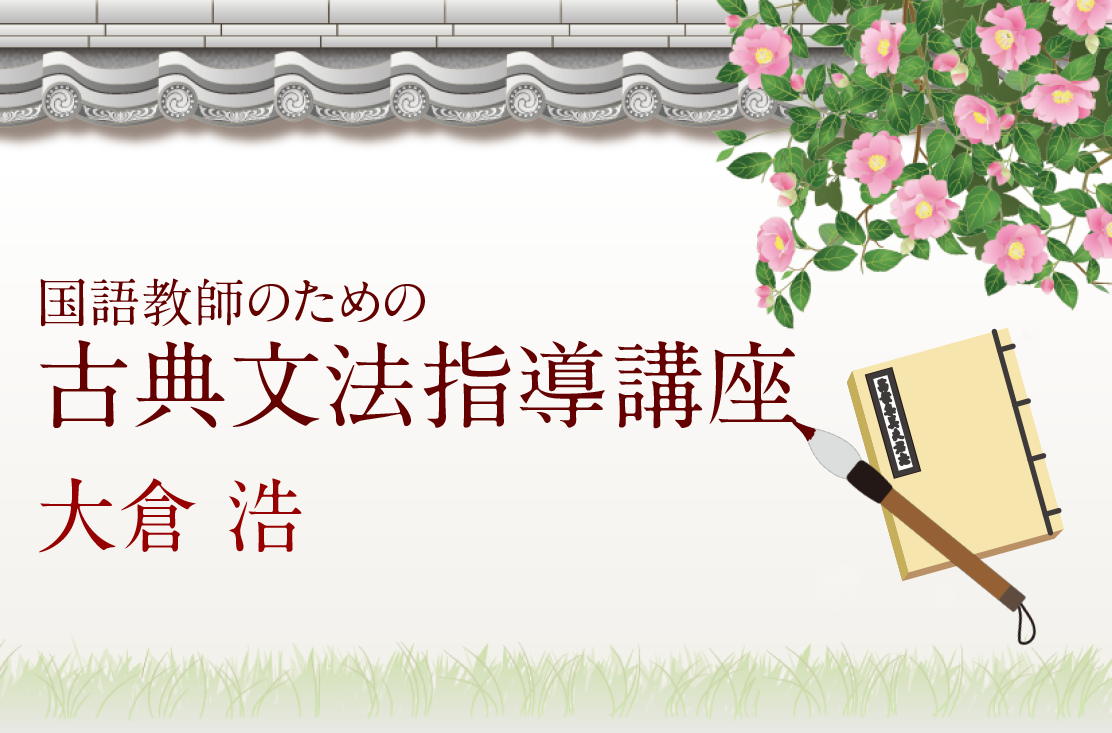
あなたの書いた物語の「きりつぼ」を読みました。死んでしまう桐壺更衣がとてもかわいそうでした。
前回の検討で、「死ぬ」という「ナ行変格活用動詞」について考えました。「ナ変」といっても不規則活用をしているわけではなく、四段と上二段を兼任する特別な活用であることを述べ、助動詞「ぬ」との関係にもふれました。今回はその流れで課題は一休みして、他の変格活用を見てみましょう。
兼任という見方をすると、「サ行変格活用」は
せ し す する すれ せよ
という活用変化ですから、連用形以外は下二段で活用しています。また、見方によっては未然形・命令形以外は上二段活用とも捉えることもできます。そこで、サ行に活用する古語動詞を調べてみると、四段と下二段はあるのですが、上二段活用の動詞がありません。つまり、中途半端な「サ変」活用があるために上二段活用が育たなかったと考えることもできそうなのです。サ変動詞は「す」「おはす」だけでなく、「具す」「物語す」「念ず」「御覧ず」など漢語と結びついて多くの動詞が存在しています。それらは、他の行でいえば上二段活用にあたる動詞活用グループだったとはいえないでしょうか。決して異質な動詞グループではなかったのです。
また、「ラ行変格活用」は
(あ:) ら り り る れ れ
という活用変化ですから、終止形以外は四段活用です。ラ行に活用する動詞は四段・上二段・下二段と揃っていますから、ラ変が何かの規則活用を兼任しているわけではないようです。そこで、改めて四段活用との違いを考えてみると、終止形が「あり」、イ段だということです。ラ変以外の動詞は全て終止形がウ段ですから、これは大きな違いです。では終止形がイ段になる用言はあるでしょうか? そうです、形容詞は「し」、形容動詞は「なり・たり」、いずれも終止形はイ段です。形容動詞についていえば、もともと「静かに・あり」「堂々と・あり」に由来するので当たり前かもしれませんが、形容詞と共通点があるというのが気になるのです。
改めてラ行変格活用動詞を眺めてみると、「あり」以外の三語も「をり(ゐ・あり)」「はべり(はひ・あり)」「いますがり(います・か・あり)」と「あり」が隠れています。そして、これらの動詞の意味は、「(主体が)存在している」ということで、他の多くの動詞が表すような、目に見える「動作・変化」とは大きく違うことがわかります。英語でも、存在を意味する動詞、be動詞は、格変化があったりと他の動詞とは文法的なふるまいが大きく違うことをご存じだと思います。単純に比較はできませんが、日本語の文法の歴史の中でも、このラ変の「あり」は様々な働きを持ち、多くの助動詞とも関わりを持つ、とても大きな存在なのです。
さらに形容詞の意味からも考えてみましょう。「赤し・暗し・うつくし・にくし・をかし……」これら形容詞は「動作・変化」ではなく、物事の「状態」や人間の「情意」を意味しています。ラ変の「あり」が表す「存在している」という意味と近いことがわかります。つまり、ラ行変格活用動詞は動詞と形容詞の境目の意味を持っているので、活用にも、終止形がイ段であるという形容詞的な特徴が混じっていると考えてはどうでしょうか。
今回サ変・ラ変について述べてきたことは、奈良時代以前、残された文献資料からは論証できない時代にかかわる日本語動詞についての推測に過ぎません。けれども、こうした推測によって、皆さんの古語動詞活用の見方が変わったり、なんだか面白くなったりすることが大事だと私は思います。
『国語教室』第115号より転載
著者プロフィール
大倉浩(おおくら ひろし)
筑波大学名誉教授
→ 古典文法に関する質問をする
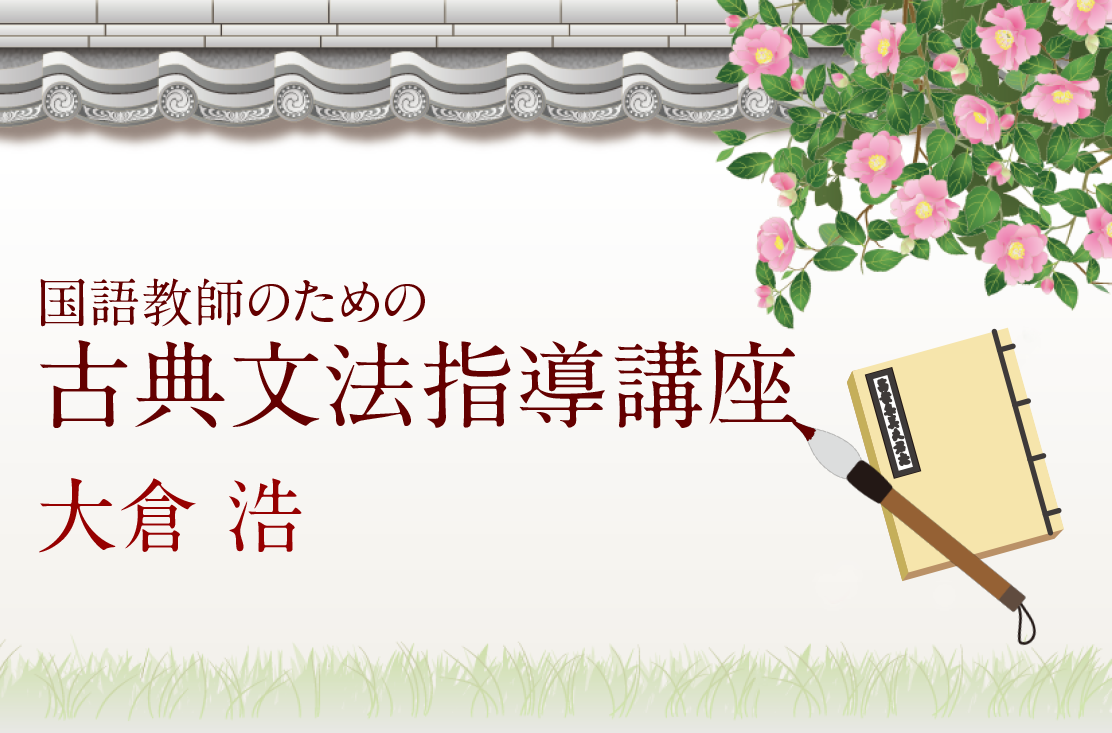
詳しくはこちら
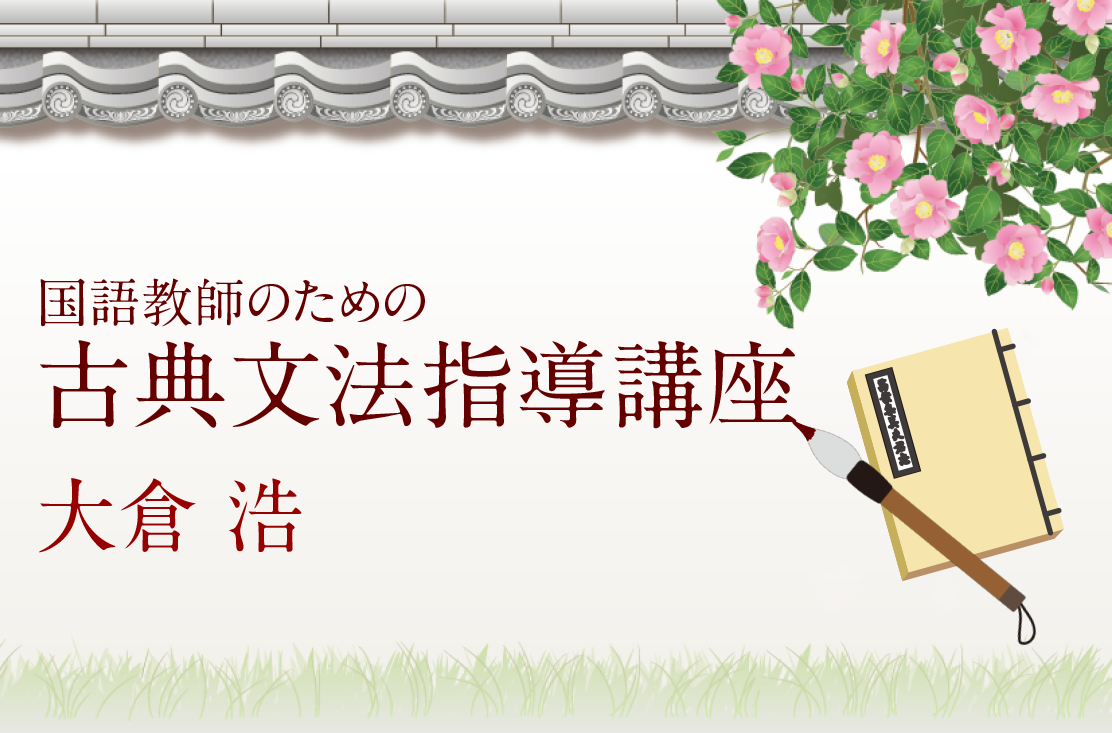
詳しくはこちら
一覧に戻る