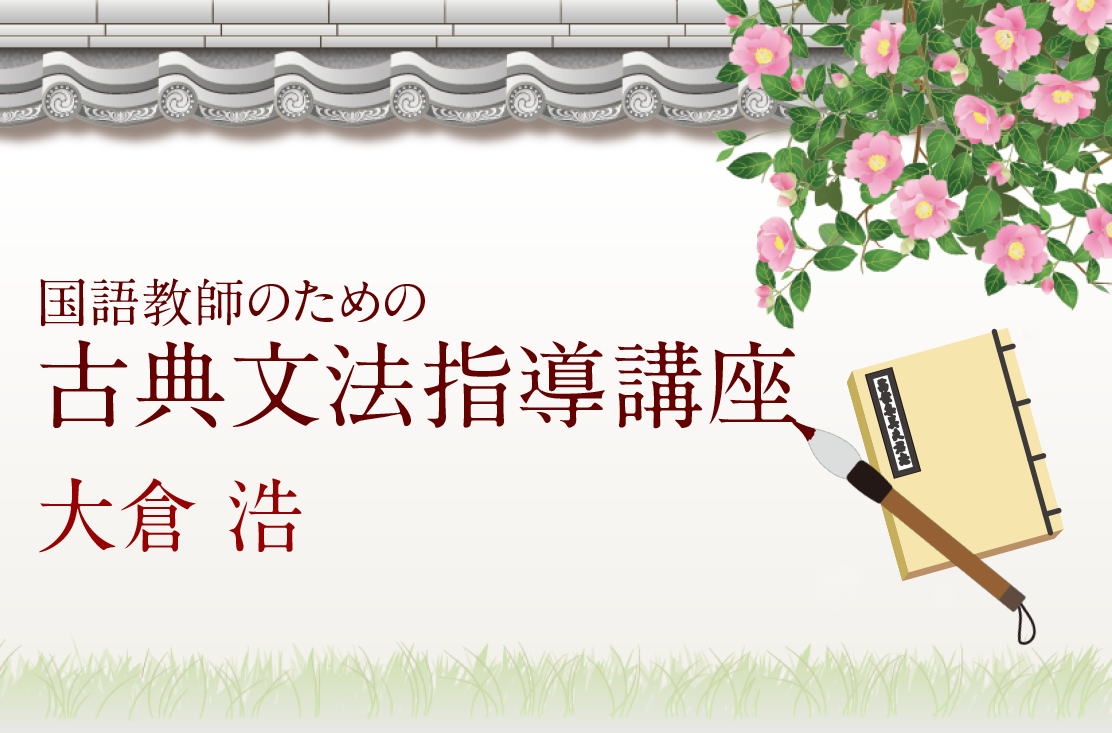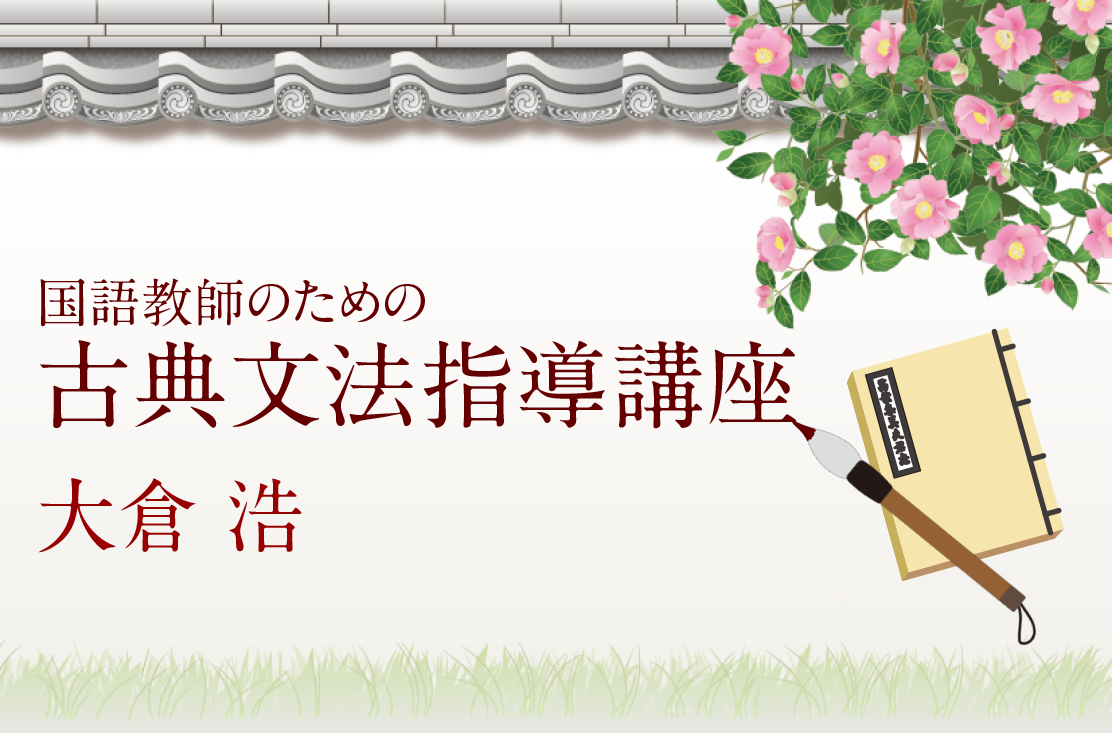国語教師のための古典文法指導講座
第8回 形容詞は「やばい」? ――紫式部にファンレターを書こう⑤
大倉 浩
- 2025.08.11
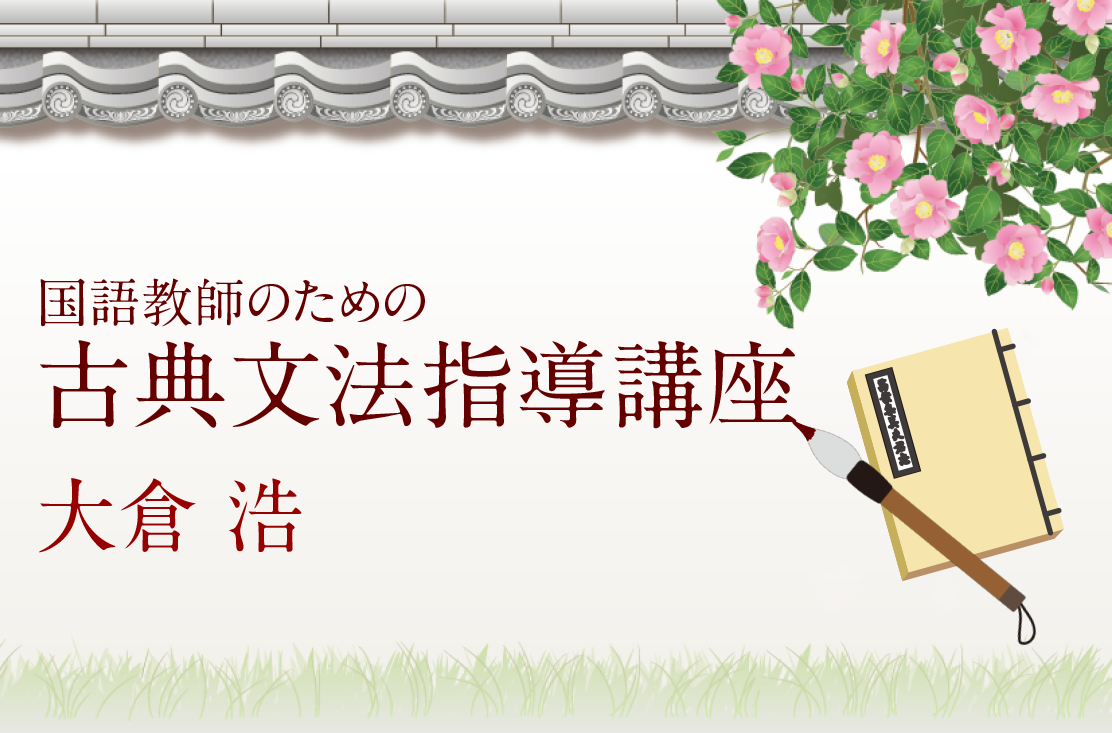
あなたの書いた物語の「きりつぼ」を読みました。死んでしまう桐壺更衣がとてもかわいそうでした。
紫式部に手紙を書くという課題のはずが、動詞活用の話にだいぶ寄り道してしまいました。まず、ここまでのミッションを完成させましょう。
おもとのものしつる物語「きりつぼ」を読みはべりき。死ぬる桐壺更衣ぞ、いとあはれにはべりける。
係り結び「ぞ…ける」を入れて強調してみましたが、今回は「かわいそう」→「あはれなり」という、形容詞・形容動詞の変化について述べます。
古語の動詞は活用が複雑でしたが、それに比べると形容詞はク活用とシク活用、形容動詞もナリ活用とタリ活用、ともに二種類ずつ、現代語ではそれぞれ一つの活用にまとまっていて単純です。それよりも、個々の語の意味が要注意です。課題の「あはれなり」の意味も、古語辞典では、
①しみじみと情趣を感じさせる。
②かわいい。いとしい。
③ありがたい。尊い。
④立派だ。見事だ。
⑤悲しい。さびしい。
のように幅広くたくさんあって、文脈や時代をよく確かめないと、うまく現代語訳できません。
他にも「をかし」「はづかし」「きよげなり」など、現代語訳がむずかしい形容詞・形容動詞がたくさんあります。教科書や参考書の重要古語のリストを見ると、ほぼ四分の一がこうした形容詞・形容動詞です。現代語との意味の違いやズレが大きいためです。でも、改めて考えてみると、どうして形容詞・形容動詞には、意味が変化している語が多いのでしょうか?
そもそも形容詞は、物事の様子・状態を表す語で、「嬉しい・悲しい」など、人間の気持ち・心の状態(「情意」と呼ぶ)を表す語群と、「大きい・早い」など、事物の性質や状態(「属性」と呼ぶ)を表す語群に大きく分かれます。形容動詞も活用パターンが異なるだけで、意味は同じく情意・属性に分かれます。
属性は、事物を見たり触ったりして感覚を共有できますが、情意は話者の心の中ですから、見たり触ったりできません。ことば(情意の形容詞)と表情、状況などで間接的に捉えるしかありません。千年も昔の日本人の心ですから、情意を表す形容詞という手がかりがあっても、我々が共有するのはなかなか難しいのです。書いた本人は、この形容詞が今の自分の気持ちにピッタリの意味だと思って使っても、読者が少し異なる理解をして使ってゆくと、千年もの時が経過していくうちに、最初の意味から拡張したり、真逆の意味に変わったりしてしまうのです。
そのうえ形容詞・形容動詞は、寿命が長くて、意味が変化しても現代まで生き残って使われるので、読者は混同しやすくなります。現代語の形容詞でも、もとは「危ない」の意味の俗語だった「やばい」が、程度の激しさ、想定外の高評価(「やばい! おいしい!」のように)を表す意味に変化してきています。
さらに、実はこの情意と属性という大きな意味の違いは、古語形容詞のシク活用とク活用との違いに対応しているようなのです。現代語で、終止形が「~しい」となるシク活用形容詞は、前述の「嬉し…」をはじめ「楽し・恥づかし・優し・をかし」など、情意の形容詞です。同様に「大し…」以外にも「暗し・黒し・遅し・良し」などはク活用で属性形容詞です。この区別は、平安時代でも例外や両面の意味を持つ形容詞もあり、整然と分かれているわけではありませんが、形容詞の原義を知る有力な手がかりになっています。
「ク活とシク活、ほとんど同じ活用をするなあ」と思いながら二つの形容詞活用を覚えた皆さんも、この違いを念頭に古語の形容詞の現代語訳を考えてみてください。「うつくし」が「かわいい」から「美的だ、きれいだ」に大きく意味が変わっているのも、シク活用の形容詞であることが関係しているのです。
『国語教室』第116号より転載
著者プロフィール
大倉浩(おおくら ひろし)
筑波大学名誉教授
→ 古典文法に関する質問をする
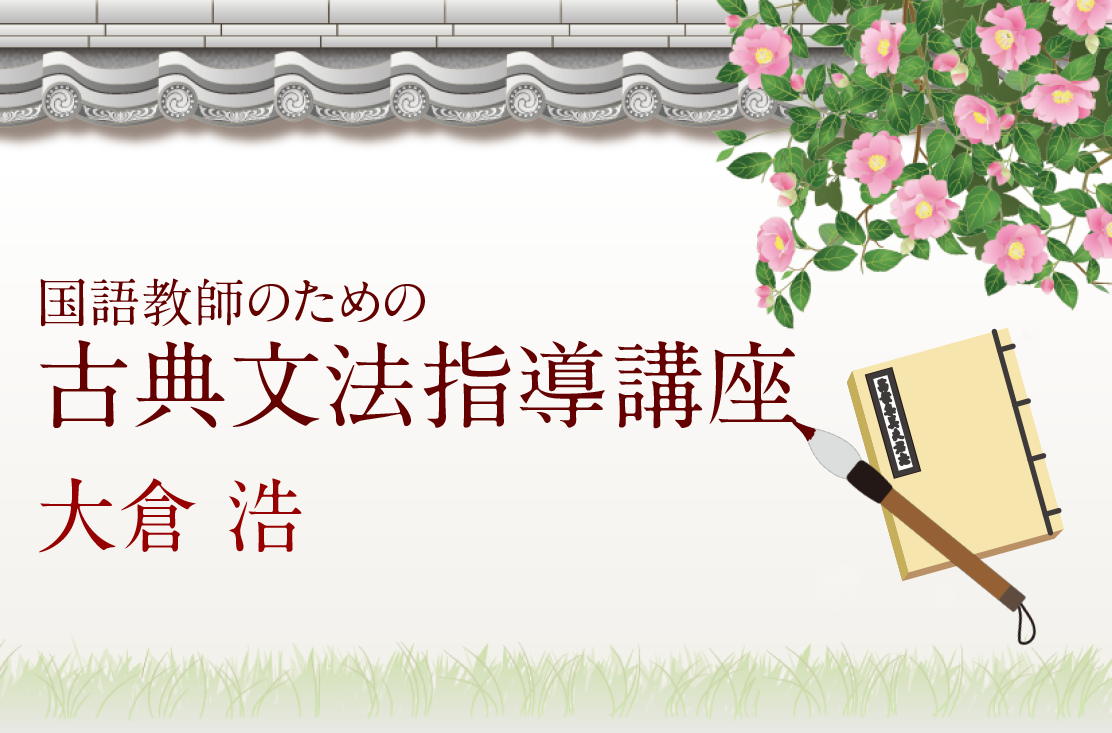
詳しくはこちら
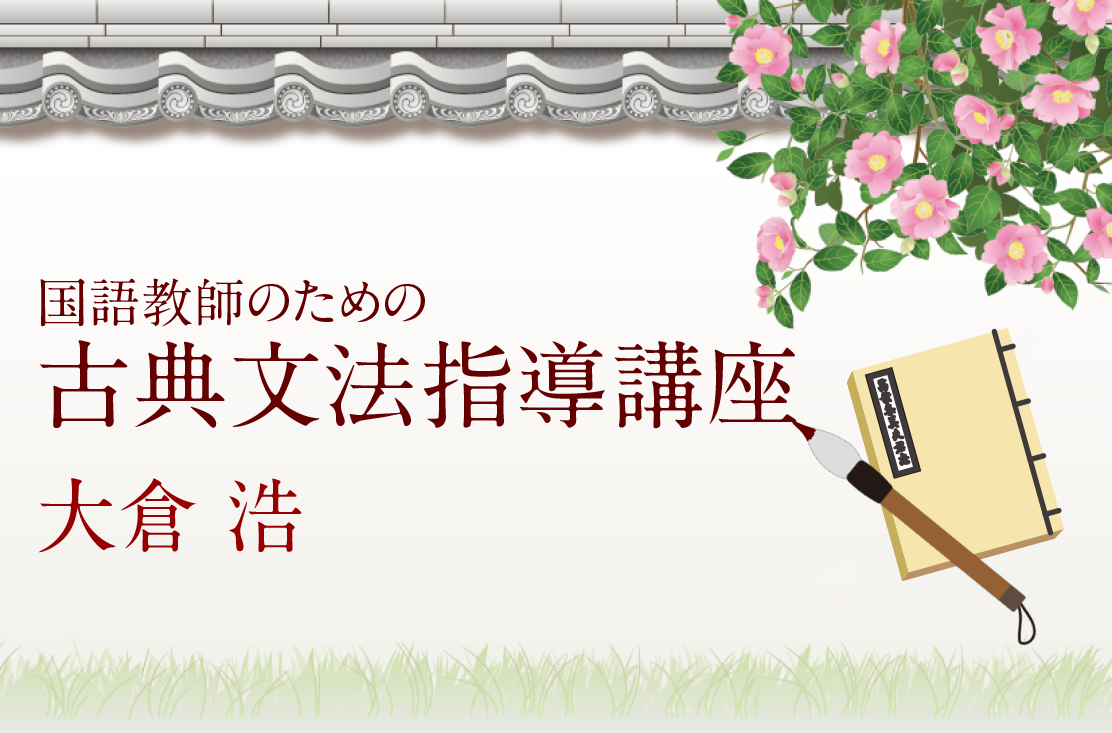
詳しくはこちら
一覧に戻る