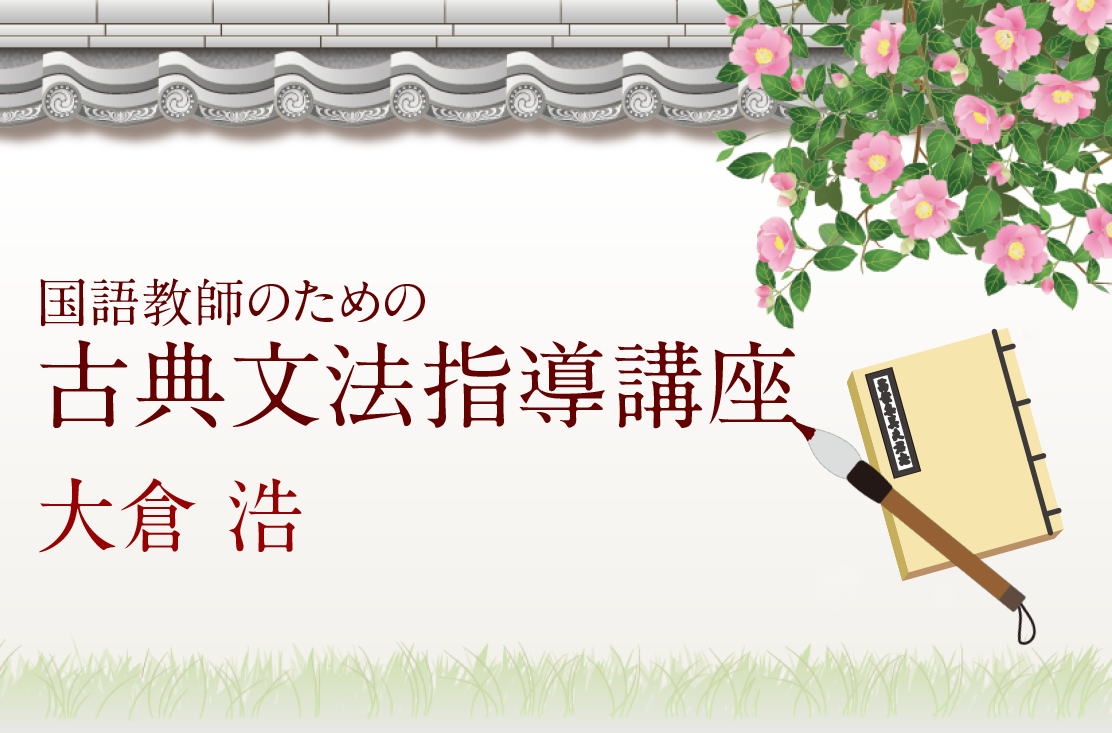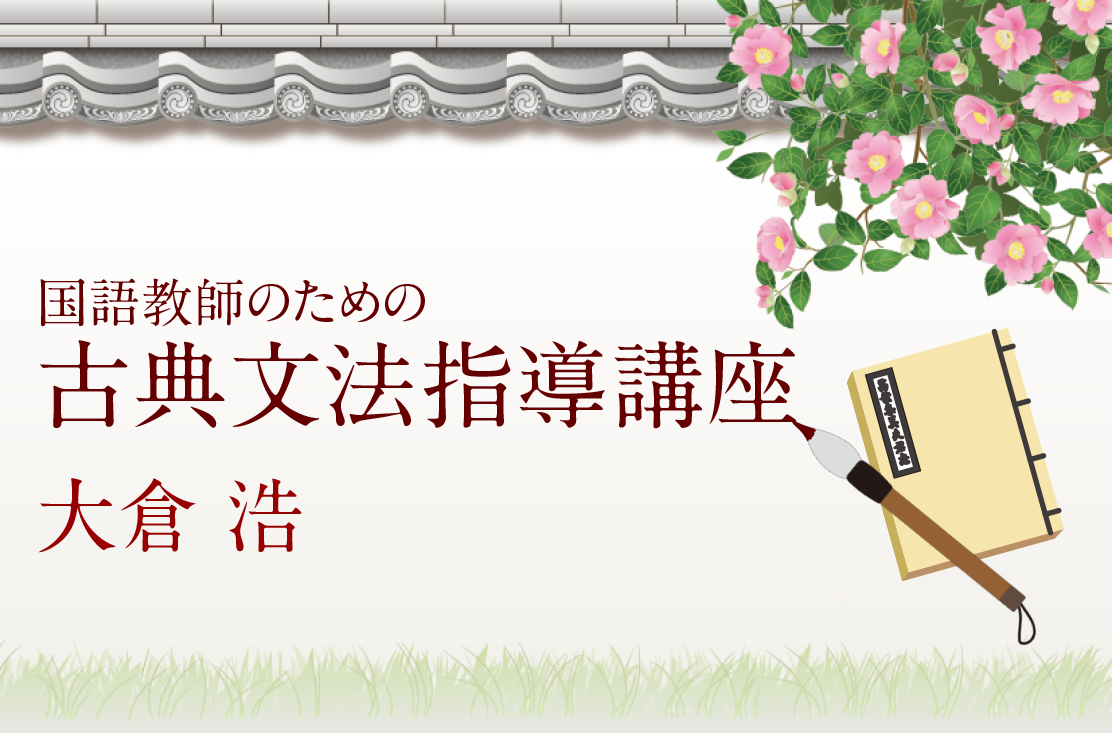国語教師のための古典文法指導講座
第9回 係り結びは「!」と「?」の気持ち――紫式部にファンレターを書こう⑥
大倉 浩
- 2025.08.13
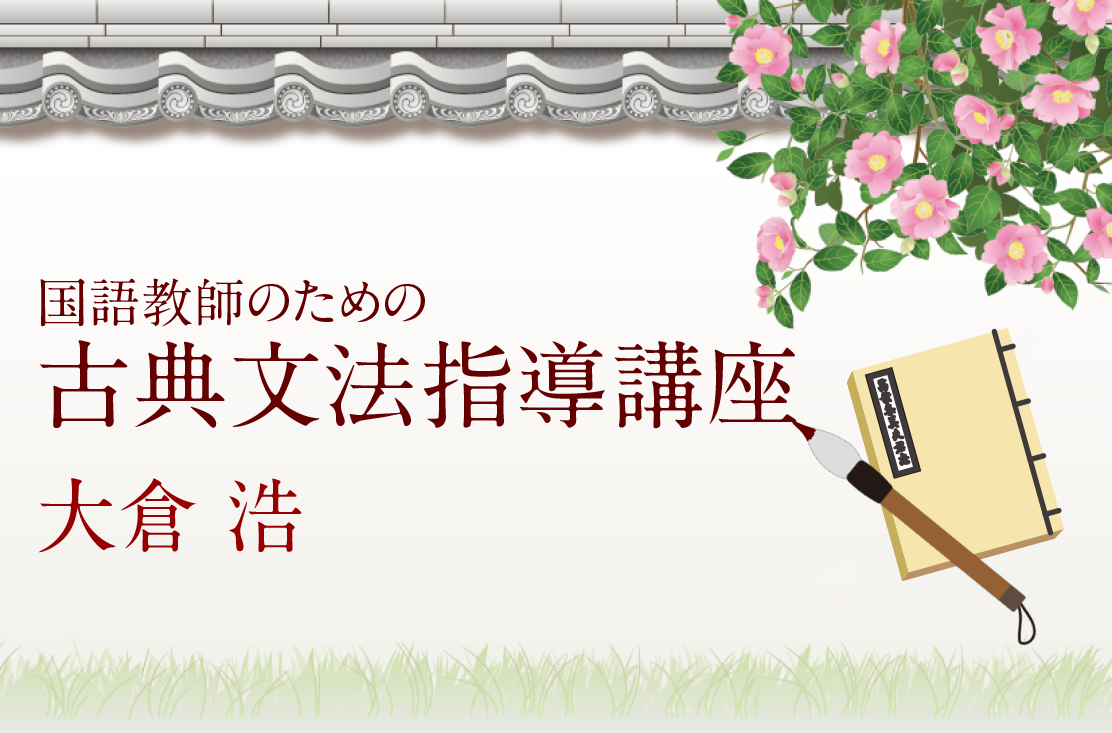
おもとのものしつる物語「きりつぼ」を読みはべりき。死ぬる桐壺更衣ぞ、いとあはれにはべりける。
今回は傍線部「ぞ…ける」のような係り結びについてあらためて考えてみます。
古典文法の必修事項「係り結び」ですが、
| 係り | はたらき | 結び | 例 |
|---|---|---|---|
| ぞ | 強調 | 連体形 | 都にぞ、行きける。 |
| なむ | 強調 | 都になむ、行きける。 | |
| や(やは) | 疑問・反語 | 都にや、行きける。 | |
| か(かは) | 疑問・反語 | いづこにか、行きける。 | |
| こそ | 強調 | 已然形 | 都にこそ、行きけれ。 |
のような説明が、どの古典の教科書にも出てきます。普通は終止形で結ぶ文が、これらの係りの助詞が現れると、連体形や已然形で結ぶという決まりが「係り結び」です。なぜ終止形ではなく連体形や已然形で結ぶかについては、いくつかの説はありますが、残念ながら古代日本語の資料的な制約もあって、定説はありません。まずは、「はたらき」(文に添える意味)が、なぜ「強調」と「疑問・反語」の二種類なのか? そのわけを考えてみましょう。
我々は文ということばの単位を使って、様々な情報をやりとりしています。もちろん、仕事から帰ってきたお父さんが、
「風呂、メシ」
と、二単語だけ発したとしても、お母さんは「まず風呂に入って、それからメシを食べるぞ」という意味であることをくみ取ることができますが、場面(文脈)は限定的です。普通は話し手(書き手)が、
「桜 の 花 が 咲い た。」
というように、単語を文法に従って組み合わせて、意味のまとまった文にして聞き手(読み手)に情報を伝えます。事実を淡々と伝える場合もあれば、
「とってもきれいな花が咲いたよ!」
と感動を込めて聞き手に訴えかける場合もあり、
「いつ何の花が咲いたのか?」
と聞き手に問いかけ答えを求める場合もあり、
「咲いた桜を見に来い!」
と聞き手に強制的に命令する場合まで、様々な表現を使って聞き手に文によって働きかけます。
「係り結び」が表す「強調」「疑問・反語」は、こうした聞き手へ向けた表現に関わるもので、主語と述語、修飾語と被修飾語のような、文の内部の構成に関わるものとは異なっていることが重要です。大雑把にいえば、我々が文章を書いている時、単なる「。」で結ぶのではなく、「!」や「?」を付けて相手に訴えたくなるような気持ち、あるいは、話している時に声に抑揚をつけたり強めたりする気持ちを、古語では「係り結び」などを使って表現しているということです。先ほどの感動を古語に書き換えれば、強調は
「いといみじき花ぞ咲きにける。」
という係り結びの文に、疑問は
「いつ何の花か咲きにける。」
という係り結びの文になるでしょう。
聞き手に対する働きかけがもっとも強い表現は、行為を要求する命令です。英語でも命令文という文型があるように、日本語でも命令専用の活用形、命令形がありますね。そして回答を要求する疑問文、感動を訴える感嘆文も、ともに聞き手に強く働きかける表現で、英語でも平叙文と文型が異なるように、日本語では、かつては「係り結び」が、現在では「か、ね、の、よ、ぞ」などの終助詞を結び(文末)に付けることで表現されているのです。活用表で見ると、働きかけが一番弱い結びである終止形と、最強の命令形の間に、「係り結び」の結びになる連体形や已然形があるのも興味深いですね。
実は「強調」と一括りにしていますが、「ぞ・なむ・こそ」、それぞれが持つ働きかけの気持ちには、時代や文体も含め差があります。「疑問・反語」の「や・か」にも問いかけ方や時代による差があります。次回はこうした違いを考えます。
『国語教室』第117号より転載
著者プロフィール
大倉浩(おおくら ひろし)
筑波大学名誉教授
→ 古典文法に関する質問をする
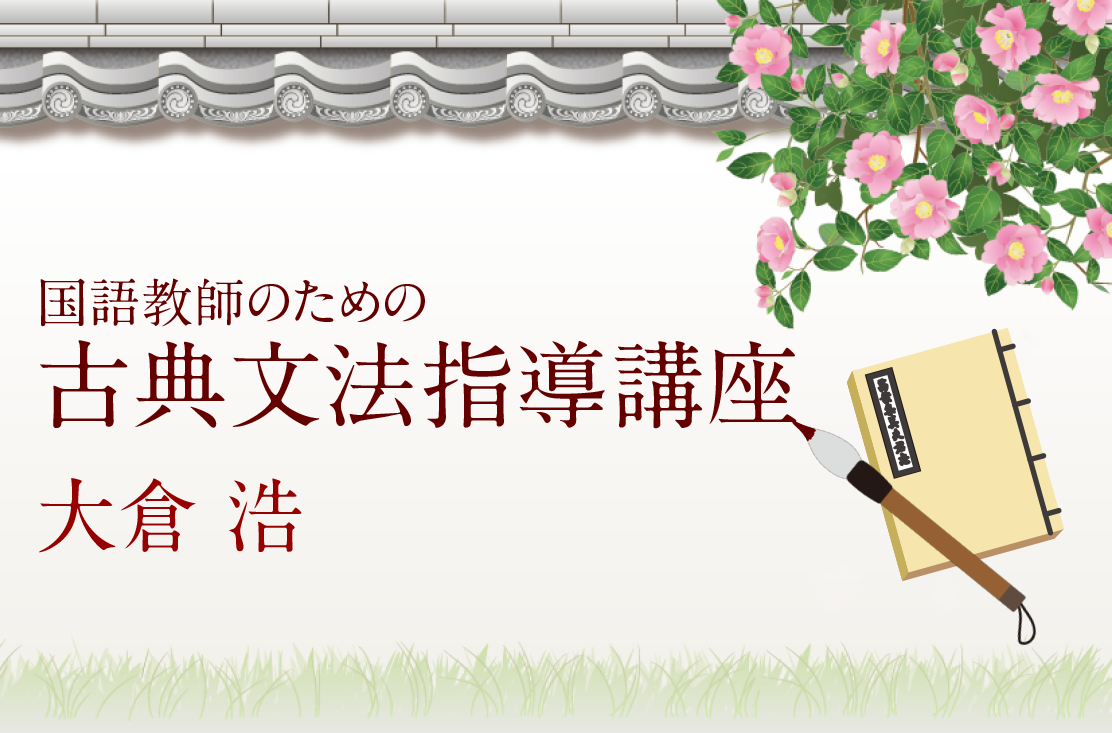
詳しくはこちら
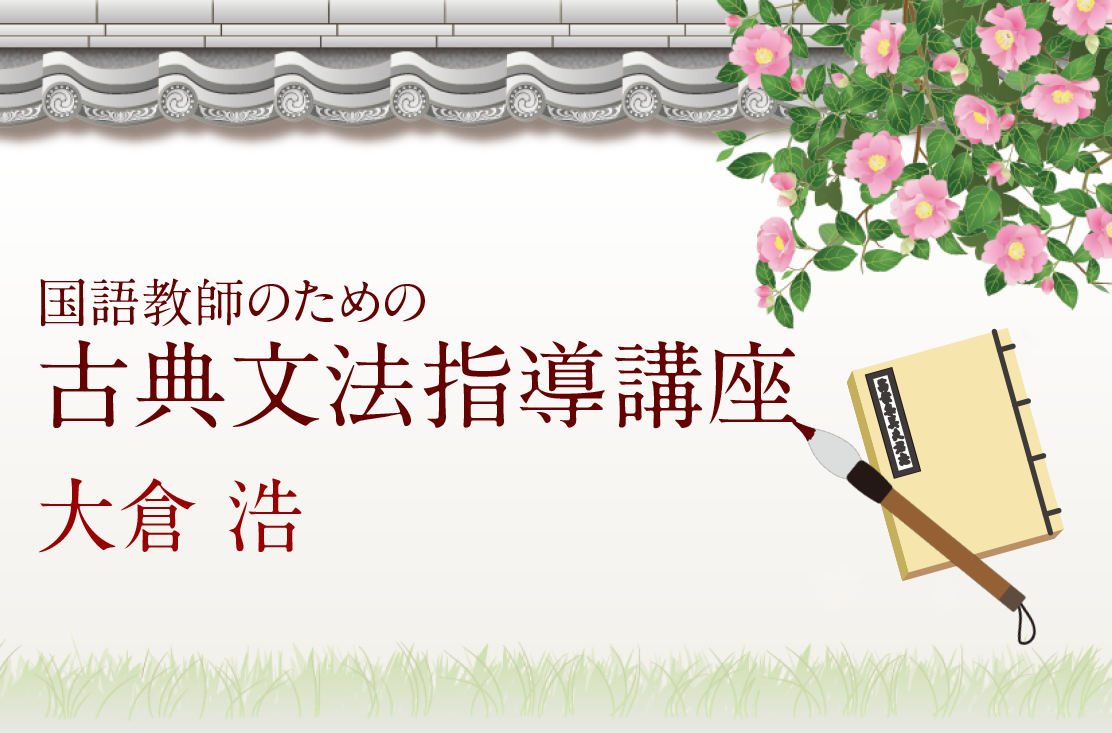
詳しくはこちら
一覧に戻る