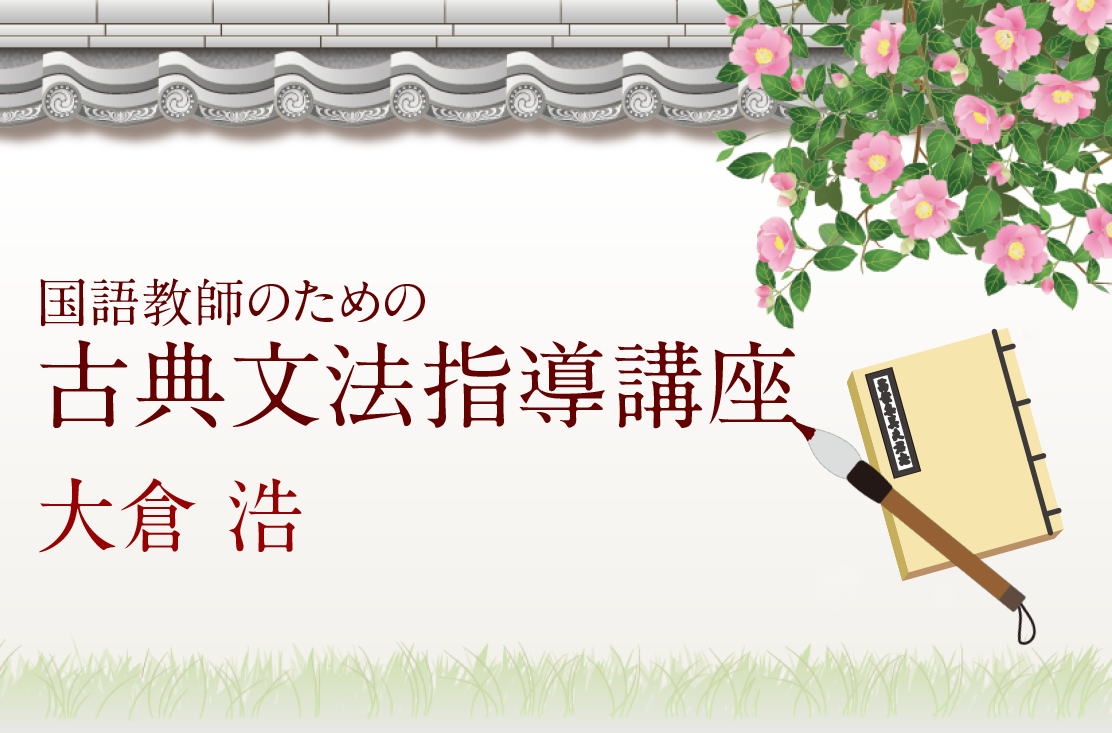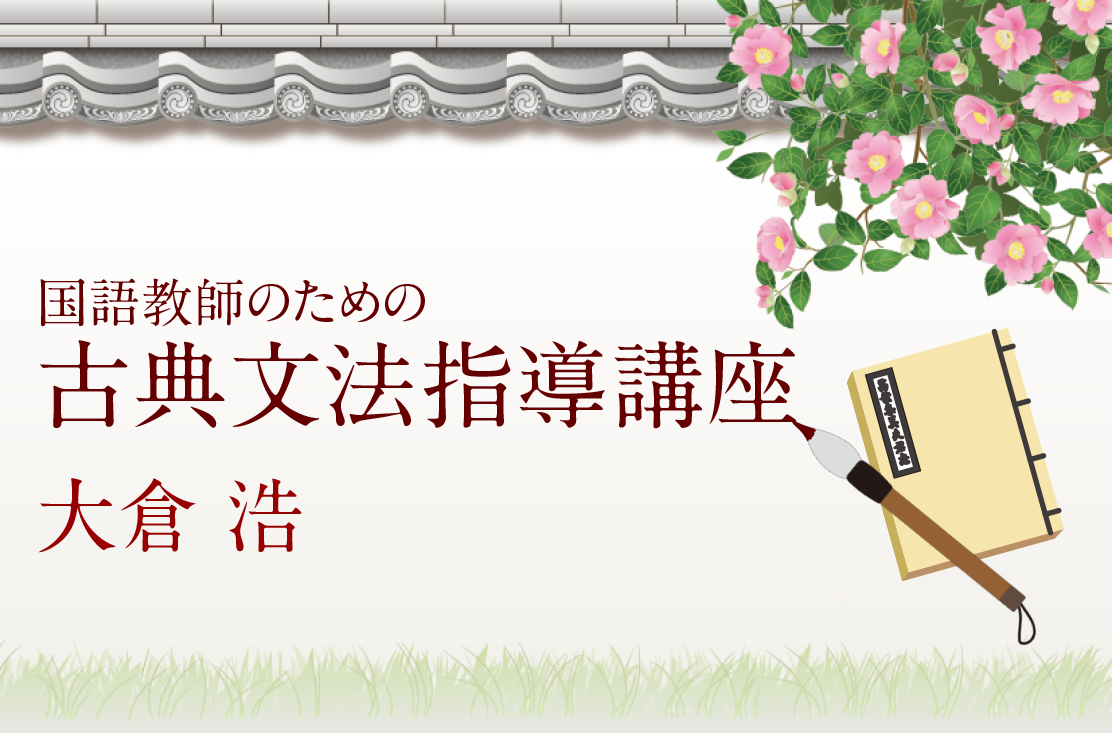国語教師のための古典文法指導講座
第10回 疑う「や?」と問いの「か?」――紫式部にファンレターを書こう⑦
大倉 浩
- 2025.08.15
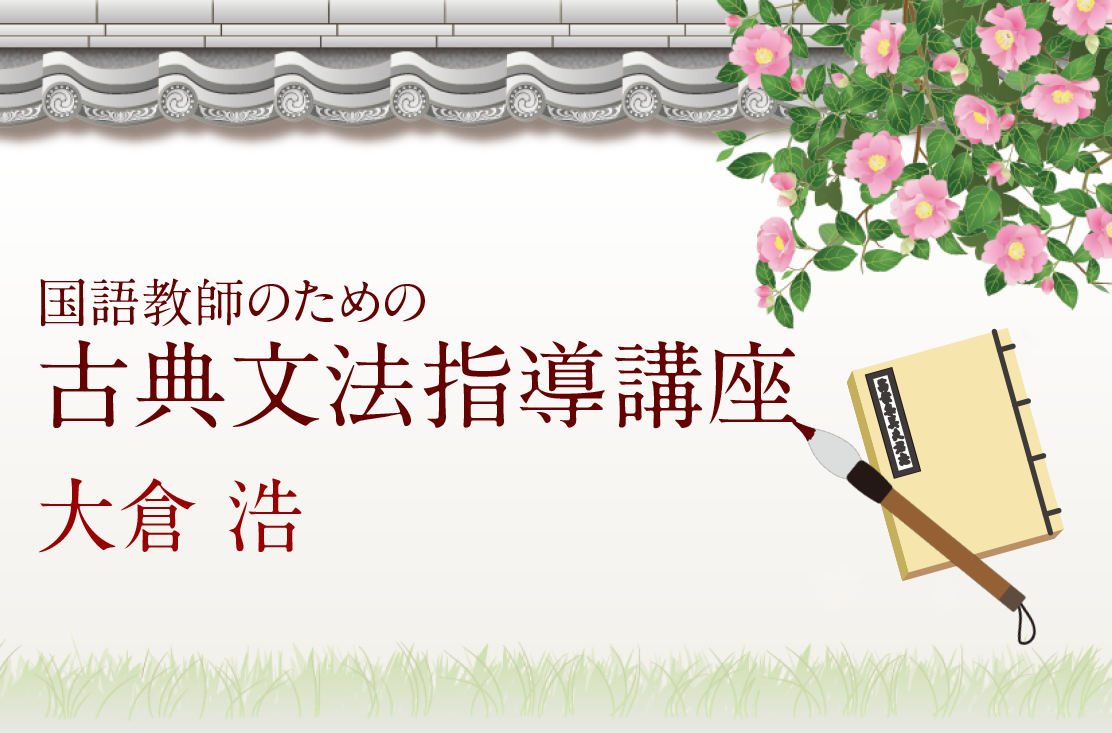
前回から「係り結び」を考えています。
| 係り | はたらき | 結び | 例 |
|---|---|---|---|
| ぞ | 強調 | 連体形 | 都にぞ、行きける。 |
| なむ | 強調 | 都になむ、行きける。 | |
| や(やは) | 疑問・反語 | 都にや、行きける。 | |
| か(かは) | 疑問・反語 | いづこにか、行きける。 | |
| こそ | 強調 | 已然形 | 都にこそ、行きけれ。 |
無関係に見える「強調」と「疑問」にも、聞き手への働きかけという点での共通点があることを述べました。では、個々の係助詞にはどのような違いがあるのか。今回は「疑問・反語」の「や」と「か」について考えてみます。
古語辞典や参考書、文法副読本には、「か」は「誰」「いかで」など疑問詞とともに用いられるが、「や」はこれら疑問詞とはあまり用いられない、という違いが説明されています(上の表の例文も、この違いを意識して書かれていたのです)。しかし、それ以上の違いについて触れているものはあまりありません。時代や文体によっても差が大きいからなのですが、ここでは、古文教材の中心である平安時代の物語や和歌での違いを主に考えてみます。
疑問詞とともに用いられない「や」の疑問文は、
都にや、行きける。(都に行ったのか?)
のようになるのですから、答える側は現代語でいえば、
はい、行きました。
とか、
いいえ、行きませんでした/田舎に行きました。
のように、肯定・否定で答えます。つまり、話し手が断定しきれない「疑い(都に行ったのかどうか)」を示して、相手の答えによって確認する表現です。それに対して、疑問詞をともなう「か」は、
いづくにか、行きける。(どこに行ったのか?)
のように話し手にとって不足している情報を「問い(どこか?)」として示します。答える側は、
都に行きました。
のように、不足部分の情報を補って提供してやることが答えになるわけです。
いきなりですが、英語の疑問文とその答えのパターンを思い出して下さい。英語では、
Q:Did you go to Kyoto? A:Yes, I did.
という、Yes/No の疑問文と
Q:Where did you go? A:I went to Kyoto.
という、WH の疑問文の二種類がありましたよね。もちろん古文と英語を単純に比較することはできませんが、疑問の表現には、求める答えの内容によって文法形式にも違いがあり、英語のYes/No疑問文とWH疑問文の違いのようなものが、日本語の古文では、係助詞の「や」と「か」の違いに現れているようなのです。つまり、「や」は、ことがらに対する話し手の疑いの気持ちの表明が元々の意味なので、その疑いを相手が肯定・否定するYes/No疑問文のみに使われ、いっぽうの「か」は、聞き手に呼びかけて問いかける意味が元々なので、Yes/No疑問文でもWH疑問文でも両方に使えるのではないかということです。
こうした解釈は、研究者の中でも意見が分かれており、定説とはなっていません。ただ、起源が同じと推定できる終助詞や間投助詞の「や」「か」の意味との関連を考えると、「疑い」の「や」と、「問い」の「か」という違いは妥当なものだと私は考えています。平安時代の和歌や物語など、情緒的な文章では、話し手の「疑い」と「問い」との表現の違いが重要だったでしょうから、使い分けがはっきりしていますが、記録や通信など実用的文章では、モヤモヤした「疑い」より、明確な「問い」が多く使われたものと考えられます。
歴史的には、平安時代には併用されていた疑問の係助詞「や」と「か」も、鎌倉時代以降には「か」の勢力が強まって終助詞化し、現代では主に「か」が、「疑い」も「問い」もともに示す疑問の意味の終助詞として使われています。
『国語教室』第118号より転載
著者プロフィール
大倉浩(おおくら ひろし)
筑波大学名誉教授
→ 古典文法に関する質問をする
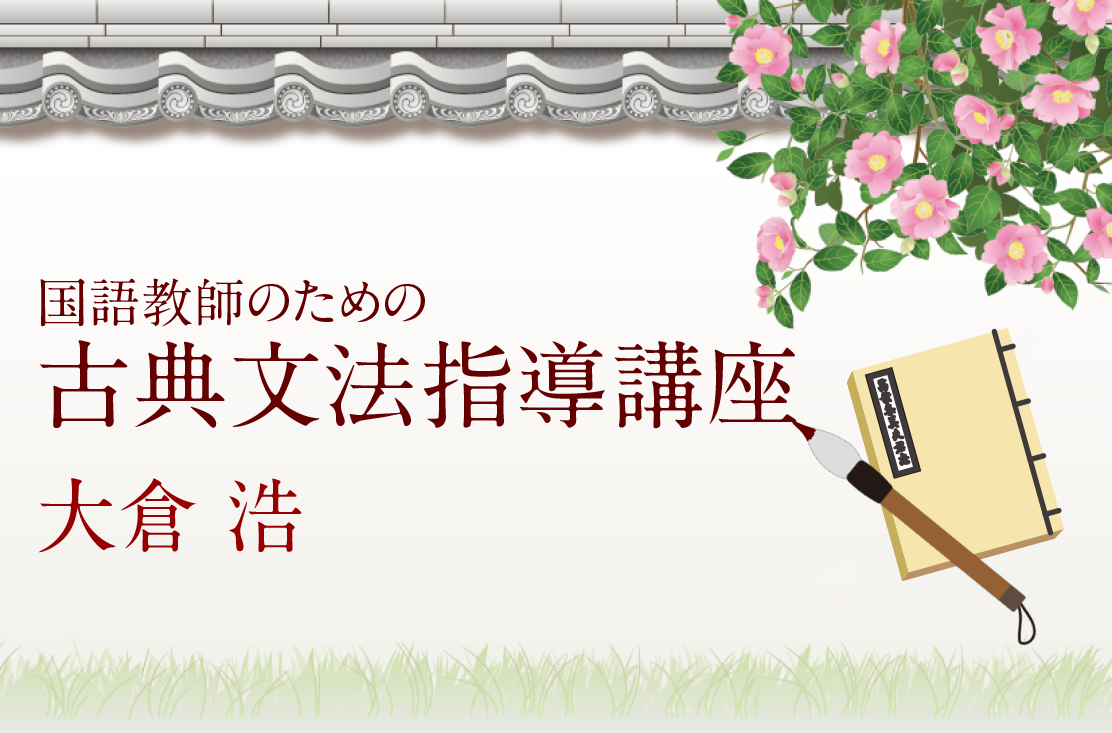
詳しくはこちら
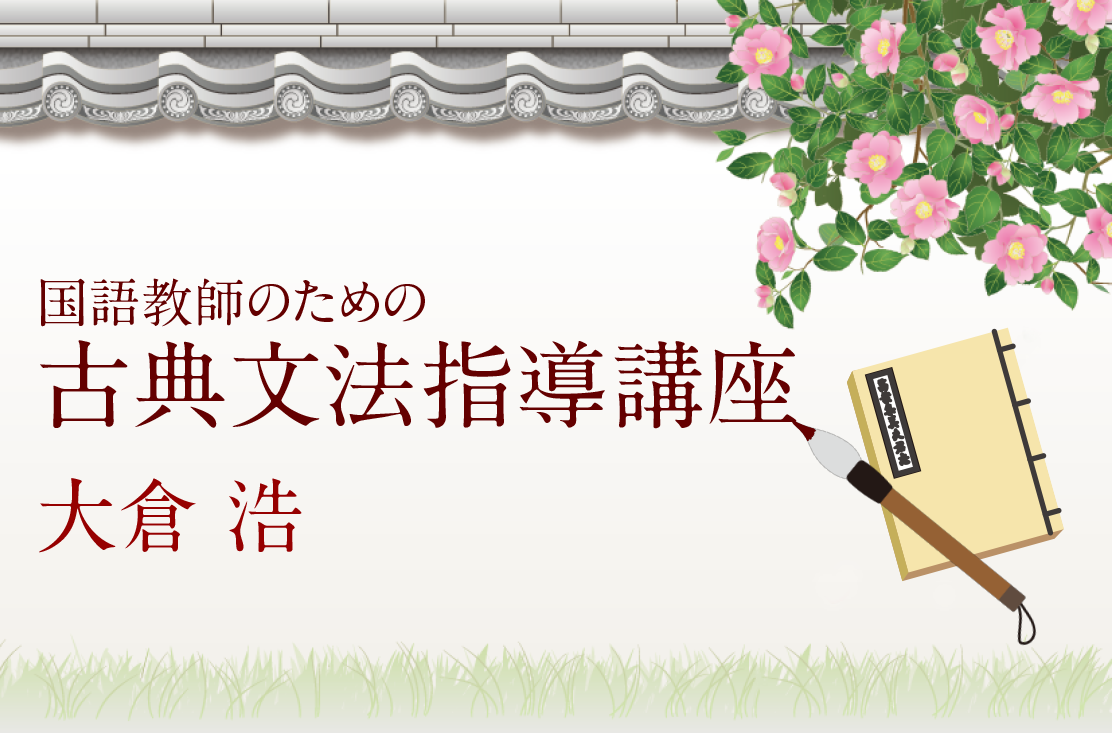
詳しくはこちら
一覧に戻る