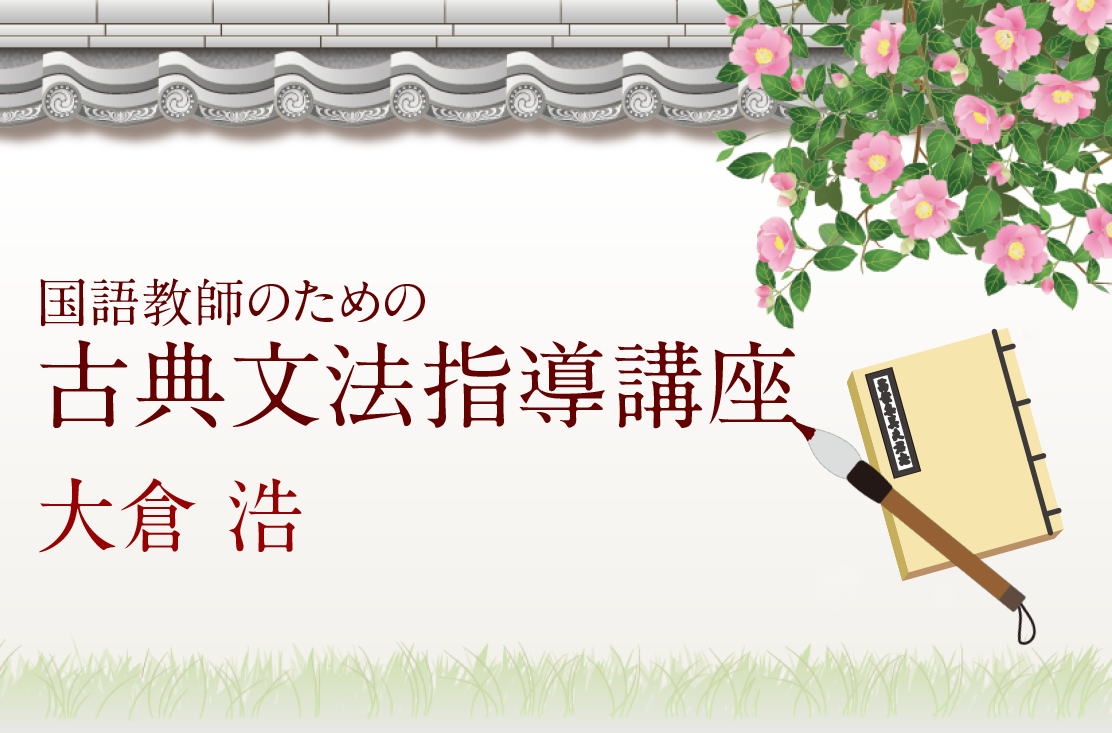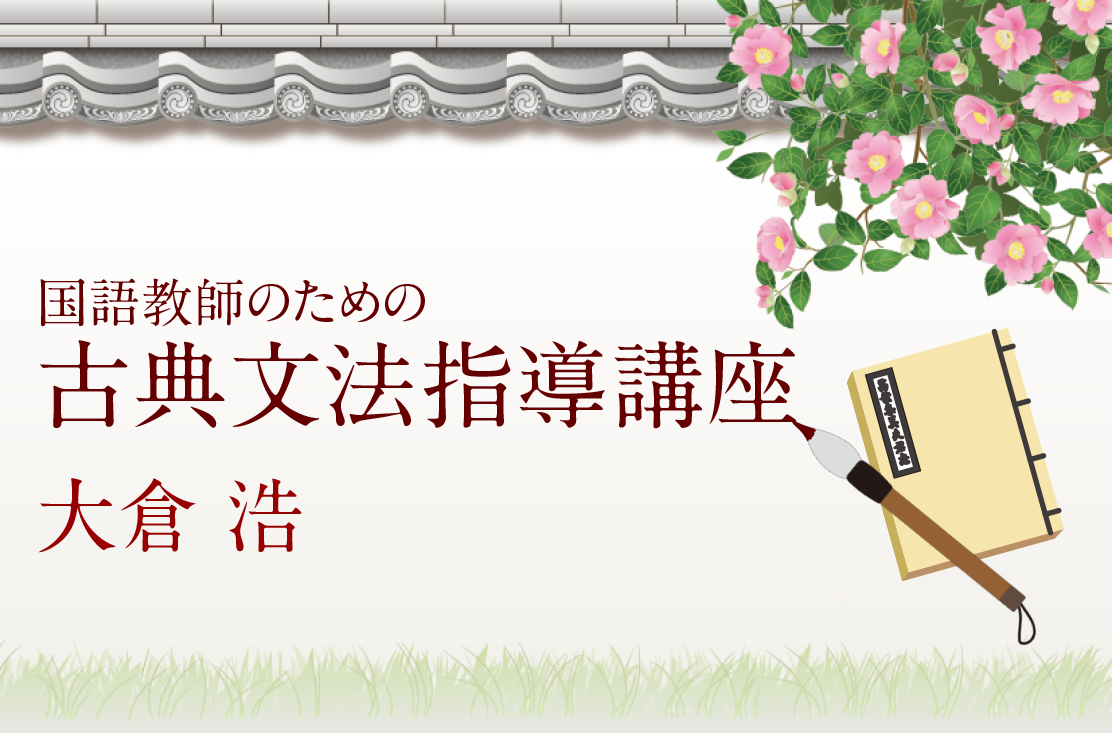国語教師のための古典文法指導講座
第11回 「ぞ」「なむ」「こそ」の違い――紫式部にファンレターを書こう⑧
大倉 浩
- 2025.08.18
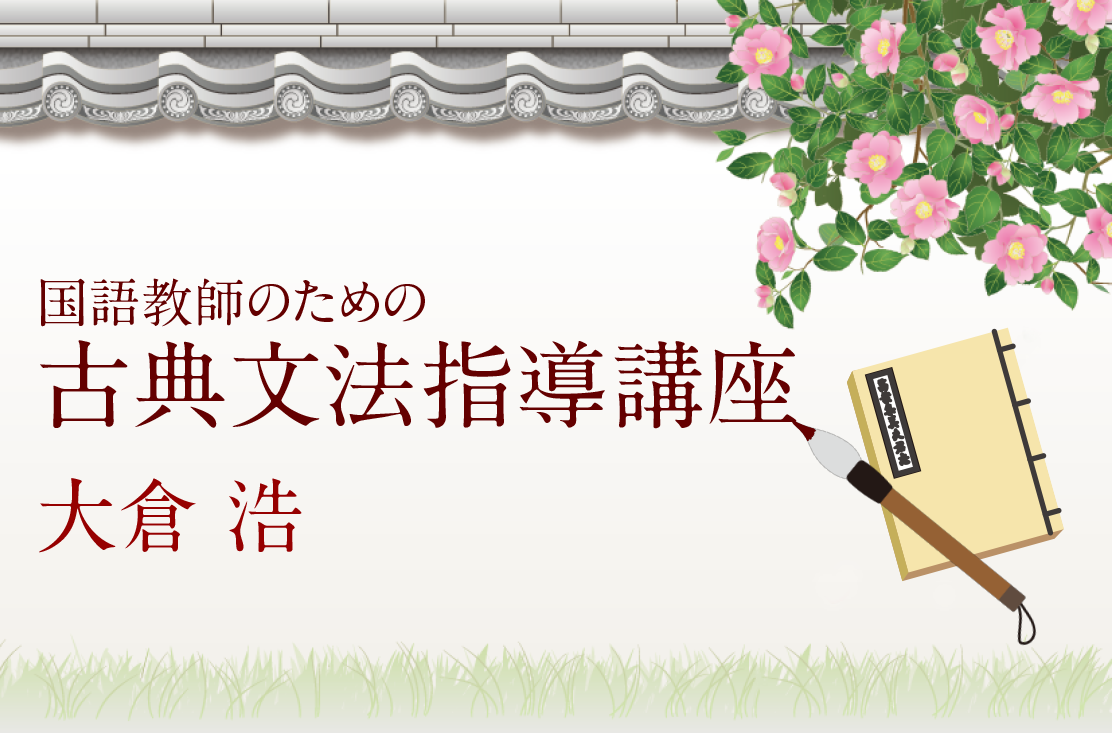
前回から引き続き、「係り結び」について考えます。今回は、強調と言われる「ぞ」「なむ」「こそ」の違いを考えてみます。
| 係り | はたらき | 結び | 例 |
|---|---|---|---|
| ぞ | 強調 | 連体形 | 都にぞ、行きける。 |
| なむ | 強調 | 都になむ、行きける。 | |
| や(やは) | 疑問・反語 | 都にや、行きける。 | |
| か(かは) | 疑問・反語 | いづこにか、行きける。 | |
| こそ | 強調 | 已然形 | 都にこそ、行きけれ。 |
この三語について、「こそ」が最も強調の勢いが強く、次いで「ぞ」、そして「なむ」が一番弱いというようなランク付けをしている古語辞典や副読本もあります。話し手(書き手)が、聞き手(読み手)に特に伝えたいこと(上表の例文で言えば「都に」の部分)を際立たせるのが強調だとすると、それに強弱の度合いがあるのでしょうか? 強調に度合いがあるとしても、前後の文脈が大きく関わり、助詞の違いだけでは説明できないと思います。それよりもこの三語については、由来や用いられる時期・ジャンルに違いがあることを、まずは確認すべきです。
最初に「ぞ」ですが、指示詞「其」に由来するという説があり、奈良時代の『万葉集』などでは、清音の「そ」としても用いられています。「それ、それだよ!」と指し示す働きが強調の助詞に変化したと想定するわけです。夕暮れの時分を「たそがれ時」とも言いますが、これは、周りが暗くて顔がよく見えない「誰そ彼」(誰だあの人は?)の時分、というのが語源で、清音の「そ」が残っている例です。平安時代には濁音「ぞ」となり、和歌から散文まで、ジャンルを問わず用いられました。鎌倉時代以降でも、前回の疑問の「か」「や」と同じく文末に移って終助詞化し、現代日本語でも、
今後のことは君に頼んだぞ。
というように、話し手から聞き手への強い働きかけの意味を残している、寿命の長い助詞です。
それに対して「なむ」は、平安時代の成立で、奈良時代には「なも」のかたちで宣命など散文文献に用例があるものの、和歌では、
いつはなも(奈毛)恋ひずありとはあらねどもうたてこのころ恋ししげしも (万葉、二八七七)
という一例があるだけです。語源も未詳です。平安時代に「なむ」となりますが、やはり会話文など散文にしか用いられず、和歌には用いられない係助詞でした。さらに鎌倉時代以降は、「ぞ」のように終助詞化することもなく(既に希望の終助詞「なむ」が存在していました)、衰退してしまいます。使われた時期やジャンルが限定的な係助詞なのです。
そして「こそ」ですが、こちらは指示詞「此其」が語源だという説があり、奈良時代から和歌にも散文にも用いられている点でも「ぞ」と似ていますが、
難波人葦火焚く屋の煤してあれど 己が妻こそ(許増)常めづらしき (万葉、二六五一)
のように、古くは形容詞の結びが已然形ではなく連体形になる例があり、こそ―已然形という「係り結び」の完成は平安時代であったことがわかります。また、「こそ」だけがなぜ已然形の結びとなるのかについても、残念ながら定説がありません。ただし奈良時代には、活用語の已然形が、接続助詞「ど・ども」などが無くてもそのままで逆接的な意味を表す働きがあったこと、「こそ」にも「…は…だけれども」という逆接の強調の含意が多いことから、「こそ」の係りと已然形の結びという関係が定着したのではないかとも考えられています。この係り結びの関係は室町末期まで維持されていて、その後、已然形結びは解消しましたが、現代日本語でも副助詞「こそ」として残っています。
古くからの「ぞ」と、新しい話し言葉の「なむ」、少しクセのある「こそ」、三種の係助詞がちょうど平安時代に共存していたわけです。次回は、この違いを踏まえて、改めて「強調」という働きを文章の中で考えてみましょう。
『国語教室』第119号より転載
著者プロフィール
大倉浩(おおくら ひろし)
筑波大学名誉教授
→ 古典文法に関する質問をする
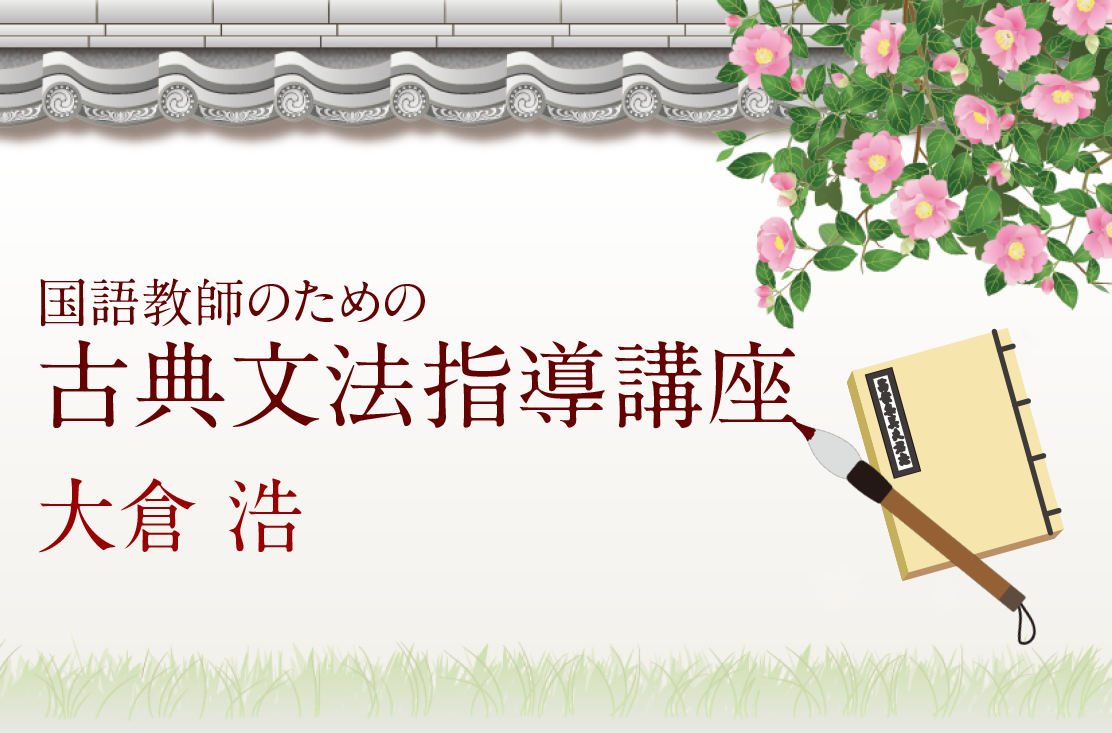
詳しくはこちら
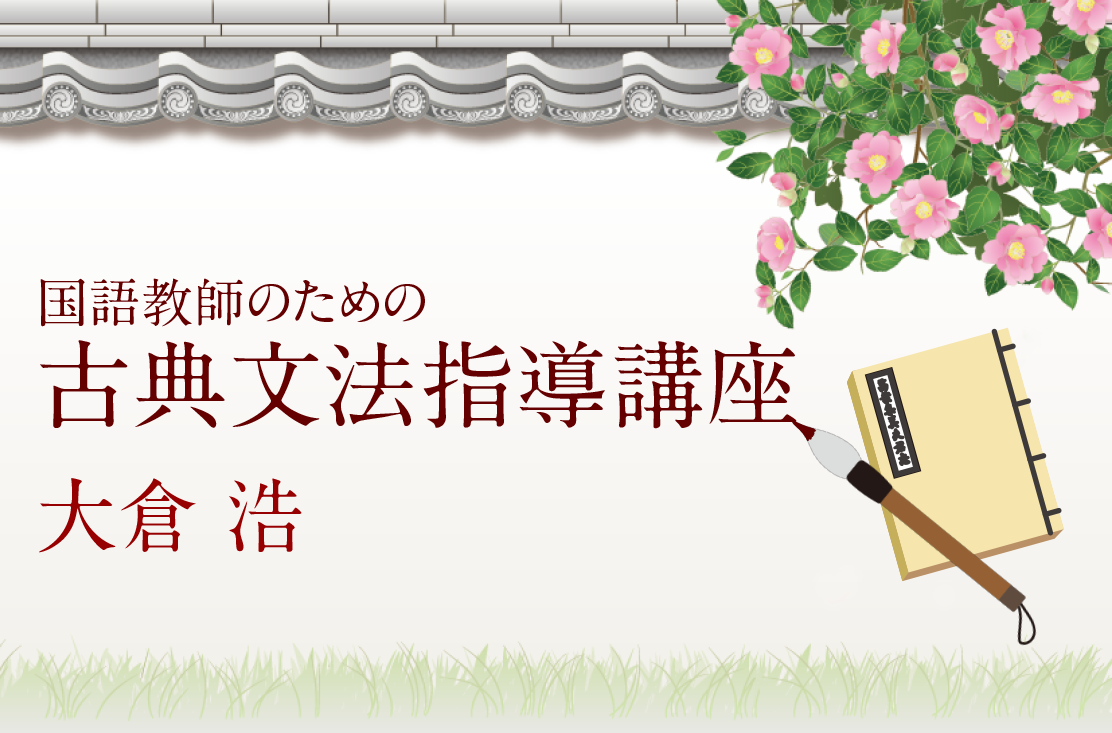
詳しくはこちら
一覧に戻る