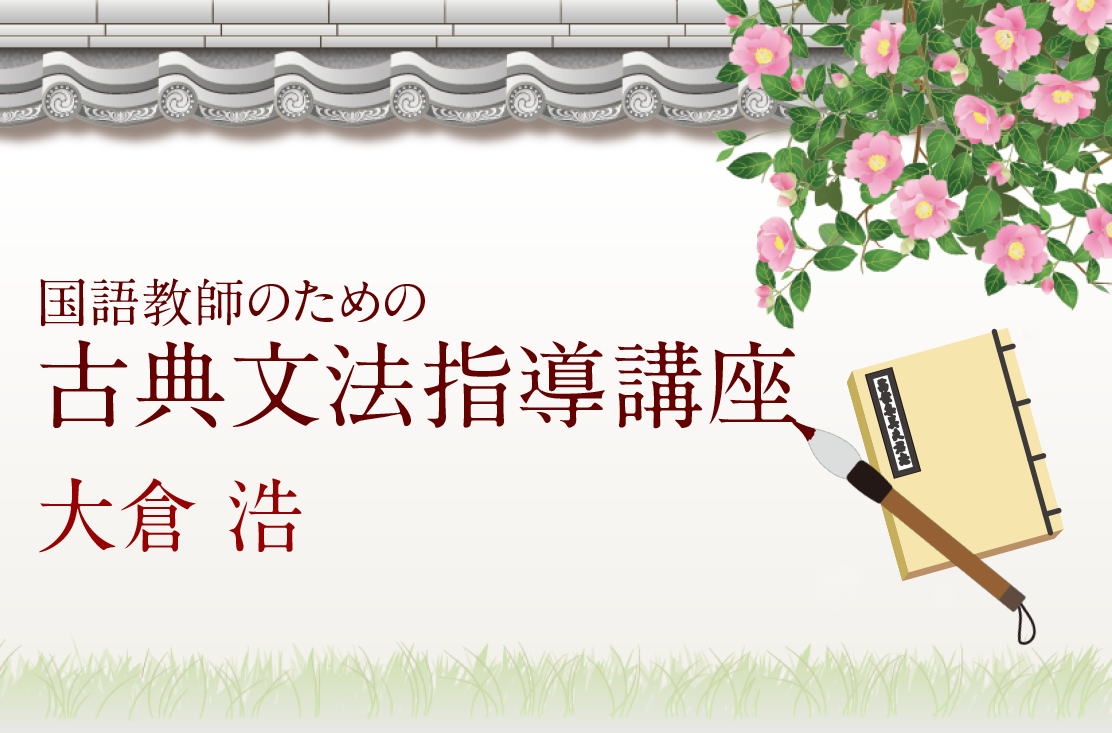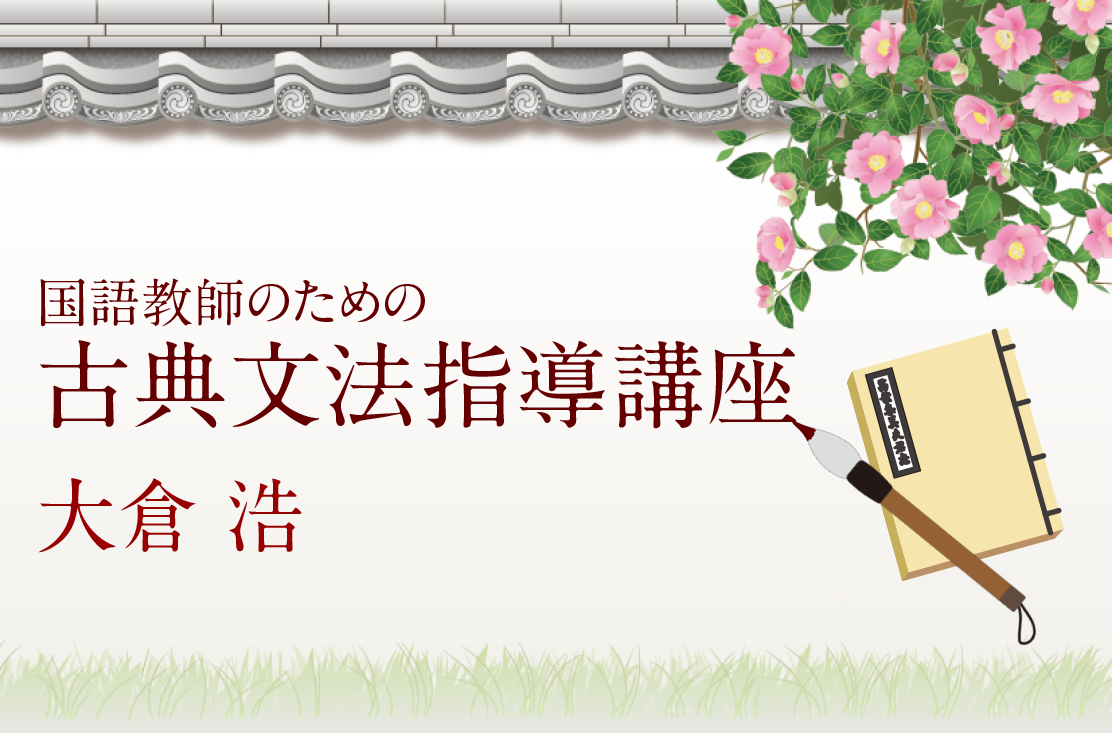国語教師のための古典文法指導講座
第12回 物語にメリハリを――紫式部にファンレターを書こう⑨
大倉 浩
- 2025.08.20
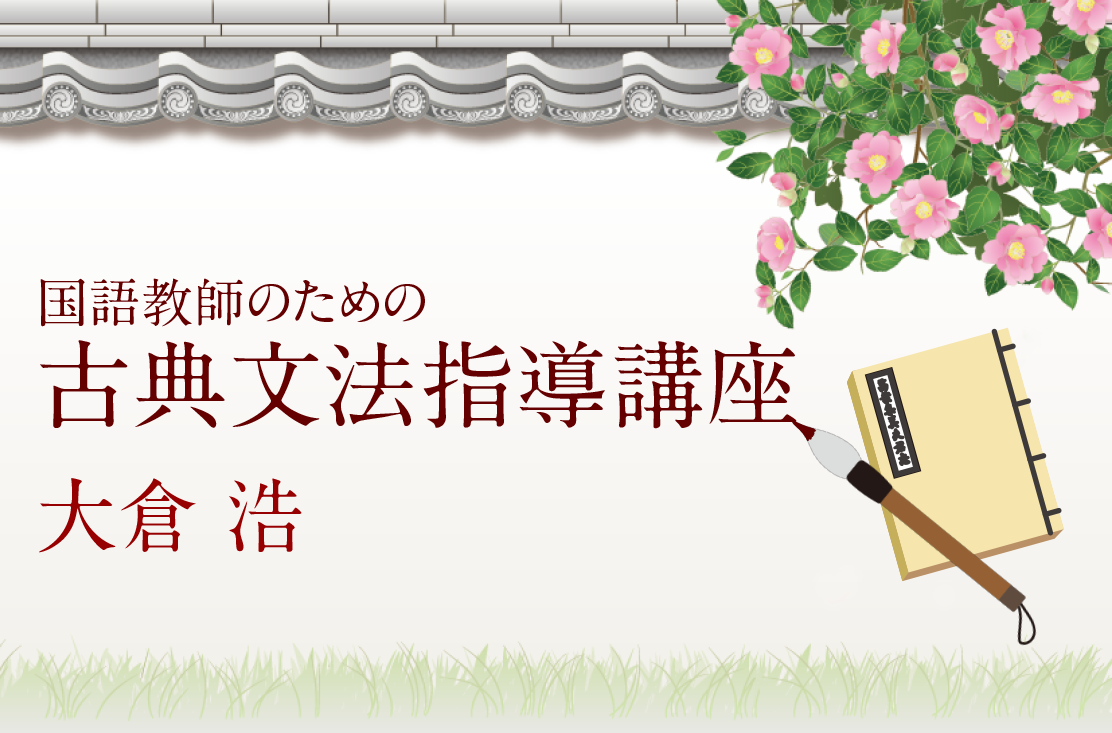
前回から係助詞「ぞ」「なむ」「こそ」についてお話ししていますが、改めてこれらの係助詞の働き、「強調」について考えてみましょう。
まず、「強調」を、話し手(書き手)が文の中で聞き手(読み手)に特に伝えたい語句を際立たせる働き、と規定しておきます。すると、
見渡せば柳桜をこきまぜて都ぞ春の錦なりける(古今集、春上、素性法師)
この和歌では、秋の錦(紅葉)ばかりでなく、春の柳の新緑や満開の桜に彩られた都そのものが「春の錦」であった、という発見を作者は強調して、「都ぞ」と係助詞を用いていると説明できます。
三十一文字と短い和歌(韻文)の中でも特にこの部分、というところを蛍光ペンでマークするように、係助詞「ぞ」が効果的に用いられていますが、ある程度の長さをもった散文、例えば物語では、係助詞はどのように用いられているでしょうか。「物語の祖」と言われる『竹取物語』の冒頭部分を見てみます。
今は昔、竹取の翁といふ者ありけり。野山にまじりて竹を取りつつ、よろづのことに使ひけり。名をば、さぬきのみやつことなむ言ひける。その竹の中に、元光る竹なむ一すぢありける。怪しがりて、寄りて見るに、筒の中光りたり。
いきなり係助詞で強調しているわけではなく、まず読み手に登場人物の生業を紹介したうえで、第三文「さてその名は…」、第四文「なんと光る竹が!」と、物語のヤマ場にさしかかると係助詞「なむ」が現れます。その後はしばらく係助詞は使用されず、姫を授かった翁たちの喜びと姫の成長が語られ、
秋田、なよ竹のかぐや姫と付けつ。このほど、三日、打ち上げ遊ぶ。よろづの遊びをぞしける。
と、冒頭の段の終わり、命名のエピソードで締めくくるところに「ぞ」が現れます。
係助詞については、その結びの部分を見つけることばかりに気を取られて、広く文章の中での位置など、注意したことはなかったのではないでしょうか。しかし、こうした視点で係助詞を探してみると、他の古文の文章でも、会話文にも使われていますが、地の文では、登場人物が和歌を詠む場面など物語のヤマ場(『伊勢物語』など)や、章段の最後などエピソードの切れ目(『今昔物語集』の「…となむ語り伝へたるとや。」という結びの表現もその例)に、多く係助詞が使われていることに気づくはずです。
現代でも、落語家や講談師、役者さんのナレーションなど、上手な語りを聞いていると、滑舌はもちろんですが、声の大きさ・速度・抑揚をコントロールして、その語りにメリハリをつけていることがわかります。「係り結び」は、聞き手を意識した「!」や「?」の気持ちの表現であると以前の回で述べましたが、物語の場合、古文では、強調の係助詞を使って語句や文を際立たせて前後の文や語句と差をつけることで、文章全体のメリハリやまとまりを生み出していることがわかります。一文の「係り」と「結び」だけで「係り結び」の働きは終わりではないのです。
こうした文章のメリハリやまとまりは、現代語では主として文頭の接続詞や副詞、書き言葉では段落分けによって示されています。(このコラムもいくつかの段落分けと、段落中の「さて、しかし、また、つまり、…」などの接続詞でメリハリをつけているつもりです。)
考えてみると、古典文法では「て・ば・が」など接続助詞がよく問題にされますが、接続詞についてはあまり触れることがありませんね。それは接続詞自体が当時の日本語の中で発達途上でもあったからなのですが、ここで述べたような古文の文章における係助詞の働きと、日本語の接続詞の発達との関連については、小松英雄先生の卓見(『日本語の歴史』二〇〇一年、笠間書院)がありますので、ご一読を強くお勧めします。
古文では、聞き手(読み手)に向けて物語ることと「係り結び」には、深い関係があったのです。
『国語教室』第120号より転載
著者プロフィール
大倉浩(おおくら ひろし)
筑波大学名誉教授
→ 古典文法に関する質問をする
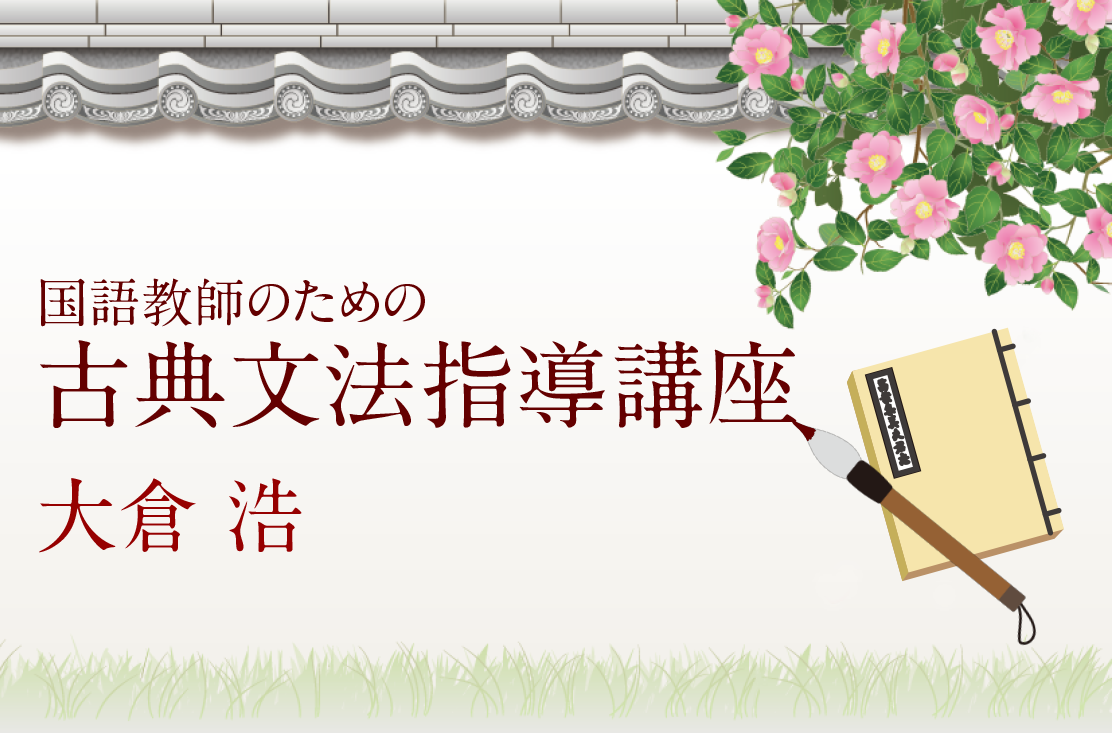
詳しくはこちら
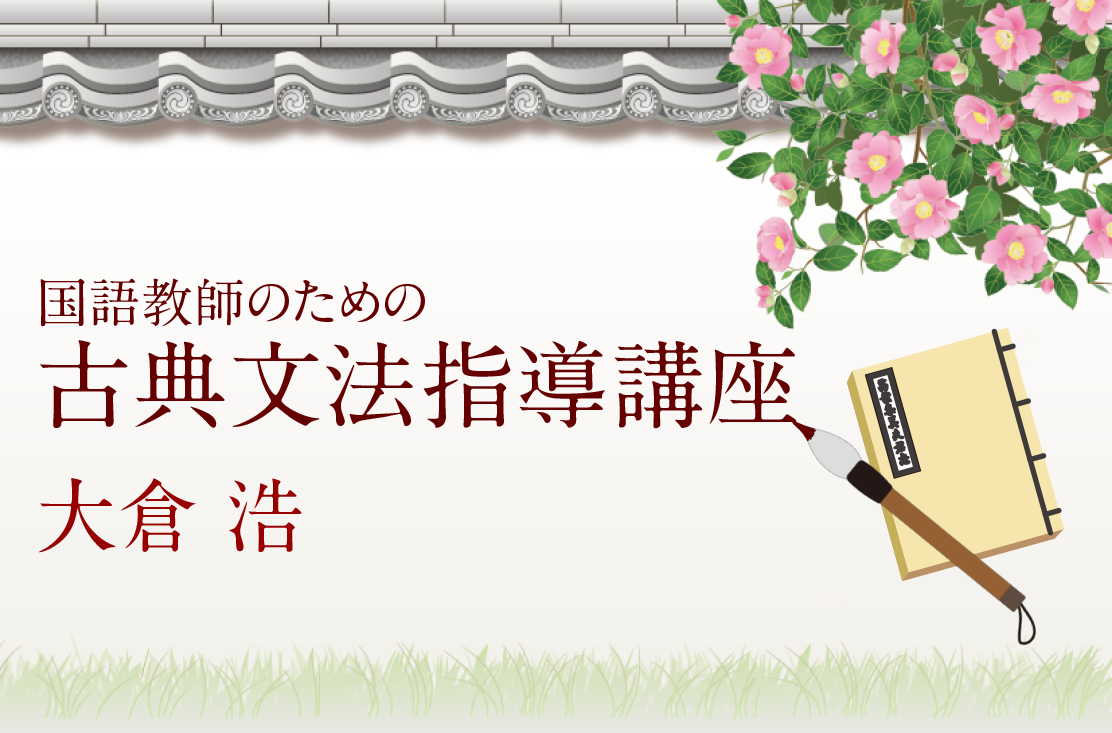
詳しくはこちら
一覧に戻る