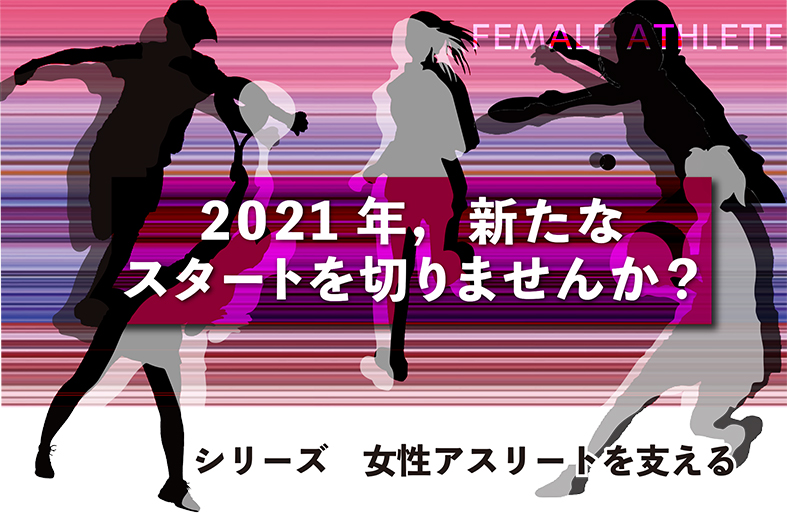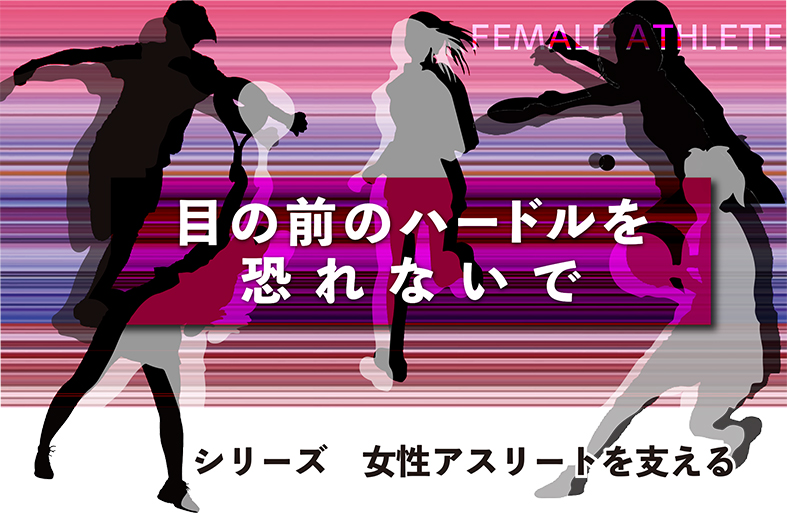「食べる」って大切だけど難しい!―女子アスリートの現場から―(後編)
鯉川なつえ(女性スポーツ研究センター副センター長,順天堂大学教授)

2023年4月24日に開催し,多くの方にご参加いただいたオンライン講座「女子アスリートの”強いカラダ”づくりに必要なこと,やるべきこと」(主催:日本スポーツ栄養協会,共催:女性スポーツ研究センター,(株)大修館書店)。
その一部を記事として再構成し,2回に分けてお届けしています(後編)。▶▶前編はこちら
今回お話しいただく方
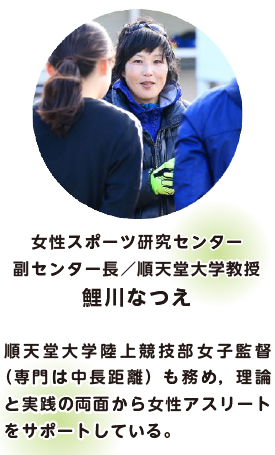
「LBMを増やす」をスタンダードに
体重がそんなに大事?
ここでは,持久系種目という観点から具体的な事例をお話します。
本学に入学してくる長距離の女子選手は,半数以上が無月経や貧血です。採血をしてみると,総蛋白やエネルギー不足の状態である場合が少なくありません。
そのような学生たちに,「目指す体重をどうやって決めているの?」と聞くと,一番多いのが「自己ベストが出た時の体重が自分のベスト体重」という答えです。
中には「監督に言われた体重が私のベスト体重」「憧れの選手と同じ体重を目指している」なんて言う子もいて,そこには身長や体組成なんて関係ないようなんです。よく考えるとおかしな話ですよね。
自分の体重に常に支配され,その増減に一喜一憂したり,あるいは,うまく走れなかった時に体重のせいだと考えたりする選手もいます。
これらは決して珍しいことではありません。そして残念ながらこの状況は、私が選手だった30年以上前と何ら変わらない問題でもあります。
陸上長距離でも「走る冷蔵庫」
世界の長距離レースを見てみると,トップランナーはがっちりして筋肉隆々。中でもリオ五輪(2016年)1万mに出場していたイギリス代表のある女子選手が強く印象に残っています。
なんと当時43歳のママさんランナー。しっかり食べて丈夫な体であれば,40歳を超えてもトラックでオリンピックの代表選手になれる可能性があるんですよね。
また,世界学生クロスカントリーにコーチとして帯同したときに見た優勝した選手は、長距離選手とは思えないようなしっかりした体格で,デコボコの砂地をガンガン走っていました。
こうしたことから,学生長距離選手も筋力アップが必須になっていることがわかります。
少し話は変わりますが,陸上長距離界では長い間,底の薄いシューズのほうが速く走れると考えられていました。
しかし底の厚いシューズの出現でその常識はあっという間に覆り,いまや厚底シューズのほうが速く走れることは周知の事実となりました。
シューズ問題同様,ランナーは体重が軽いほうが速く走れる,というのは過去の誤った認識であるということを,もっと多くの人に,早く気づいてもらいたいと思っています。
「食べた記録」が実るとき
私は長年,除脂肪体重(= LBM:Lean Body Mass)を重視しています。
LBMは体重から脂肪の重さを除いた数値なので,LBMが増えるということは,脂肪以外の筋肉,骨,内臓,血液などが増えるということ。
もうお気づきかもしれませんが,「体重が減った(増えた)」という理解は少し解像度が低くて,パフォーマンスや健康に重要な「筋肉や骨などが減った(増えた)かどうか」が大事なのです。
実際にLBMが低下してしまうと,貧血,無月経,疲労骨折などにつながる可能性が高まります。
したがって,体重ではなくLBMを見ることは,様々な女子アスリートの健康問題を解決するための大事なアイデアだと言えます。
ですから学生たちには「太るという考え方ではなく,『増やす』ことを意識しよう」といつも話しています。
去年、私の指導する2人のランナーが日本インカレで優勝し,学生日本一になりました。
試合で結果が出ると,ちゃんと食べてLBMを増やすことができていたからだと勇気づけられますが,彼女たちも例に漏れず,ジュニア時代にしっかり食べる習慣があったわけではありません。
4年生で見事に優勝したけれど,言いかえると4年間LBMを増やす努力をして,勝利に辿り着くのに4年もかかってしまったわけです。
嬉しい反面,強い体をつくる,取り戻すにはやはりそれくらいの時間がかかるんだとも感じています。
私のチームでは10年以上前からLBMを測定していて,『女性アスリートダイアリー』も使っています。
ダイアリーには食べたものを記録できるので,「食べ忘れ」や「ばっかり食べ」なども防止できます。
また,選手たちには,メモ欄に走った距離の累積を書くように伝えています。
そうすると,自分が何km走ったのかを把握したうえで,食事を考えることができる。そんなふうな使い方をしています。
持久系女子アスリートの世界では現在も,「痩せたら走れる」という幻想にコーチも選手も,場合によっては保護者も支配されていて,「食べる」という習慣が根付いていません。食事が大事だと頭では理解しているけれども,食べ方がわからない,あるいは行動に移せないという人がまだまだ多いということが,女子アスリートの大きな課題です。
今日のお話が皆さんにとって、少しでも「食べる」ことを考え直すきっかけとなれば嬉しいです。
オンライン講座ではこの他にも様々な議論(3名のトークセッション含む)があり,「食べる」ことの重要性をあらためて感じる内容ばかりでした。
鈴木先生,萩原さま,鯉川先生,そしてご参加いただいた皆様,誠にありがとうございました。
編集部がおすすめする「保体編集部オンライン」記事
▼シリーズ「女性アスリートを支える」(女性スポーツ研究センター 小笠原悦子先生,鯉川なつえ先生,桜間裕子先生)
▼思春期スポーツ選手の摂食障害―予防と早期発見(関口邦子先生 臨床心理士/公認心理師)
▼シリーズ「『書く』を語ろう」(法政大学 荒井弘和先生,女子バスケ 藤岡麻菜美選手,女性スポーツ研究センター 桜間裕子先生)

詳しくはこちら
一覧に戻る