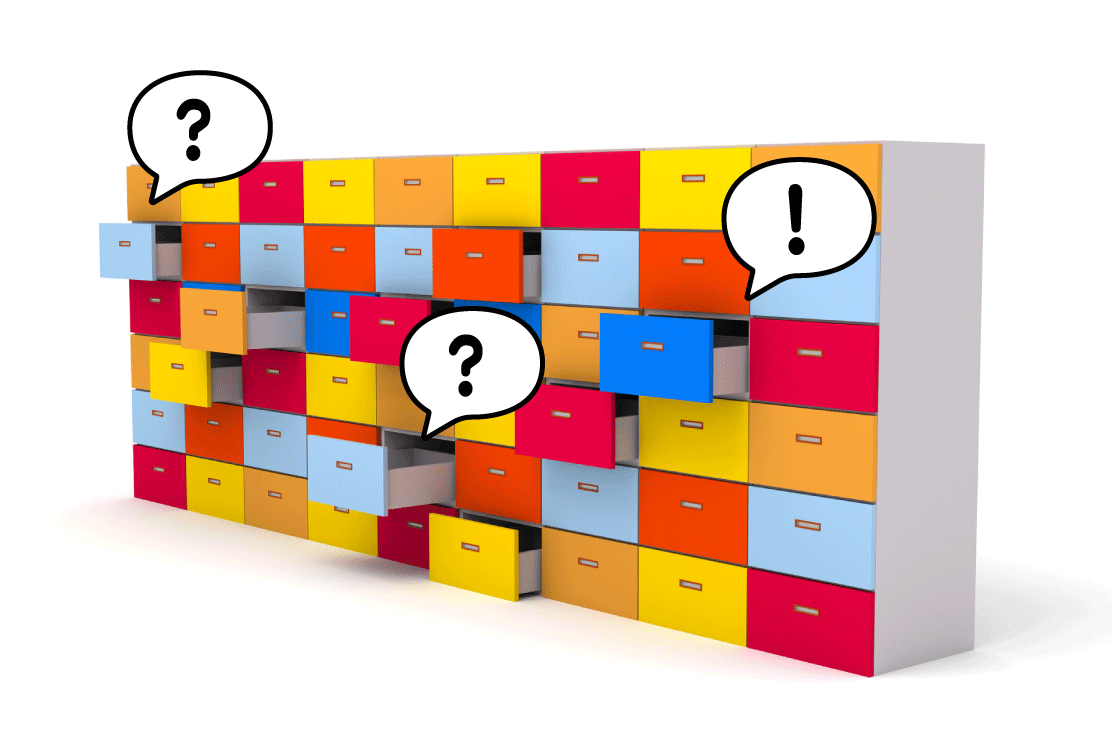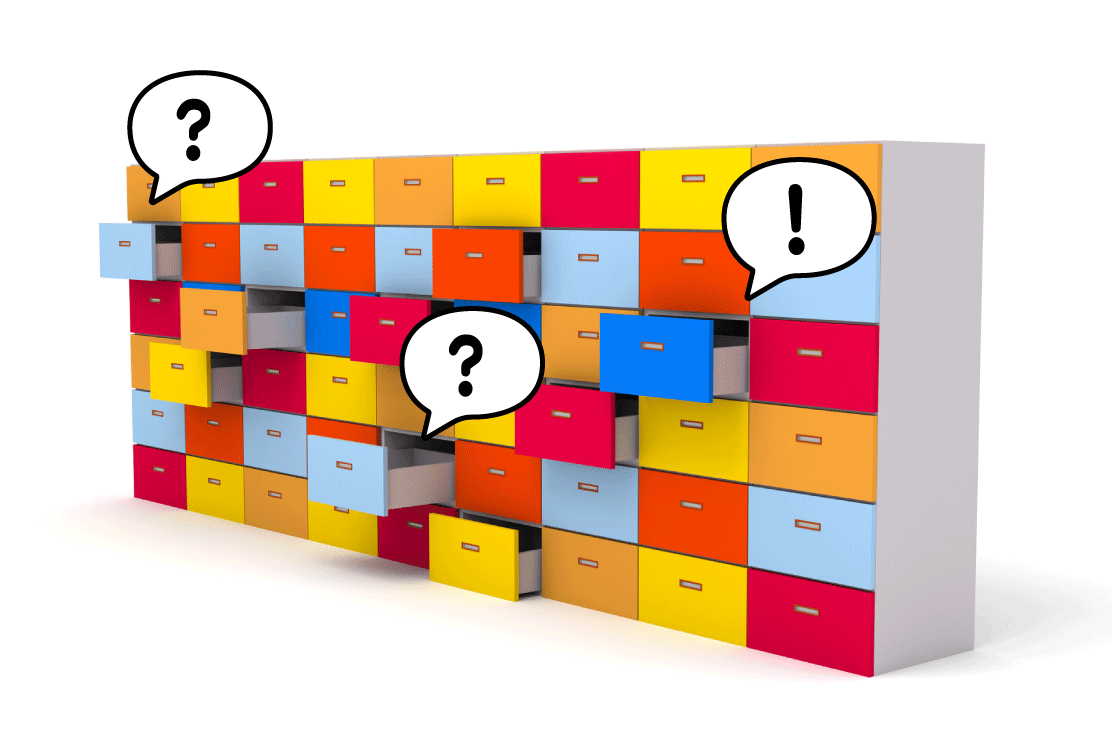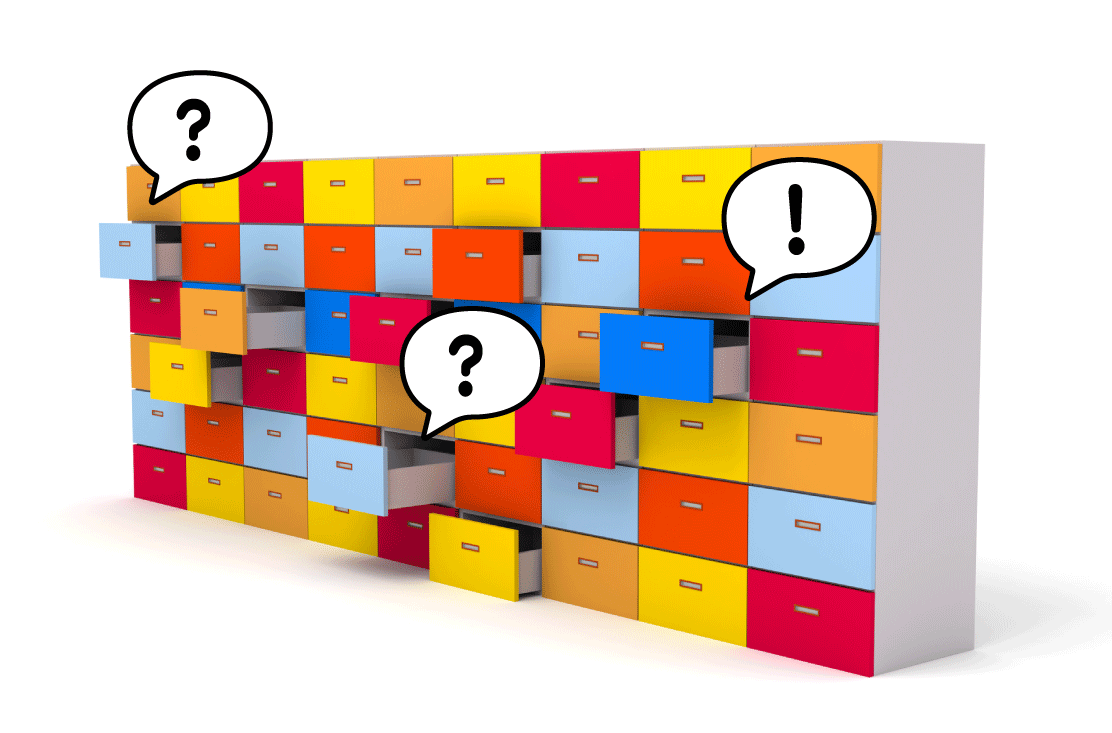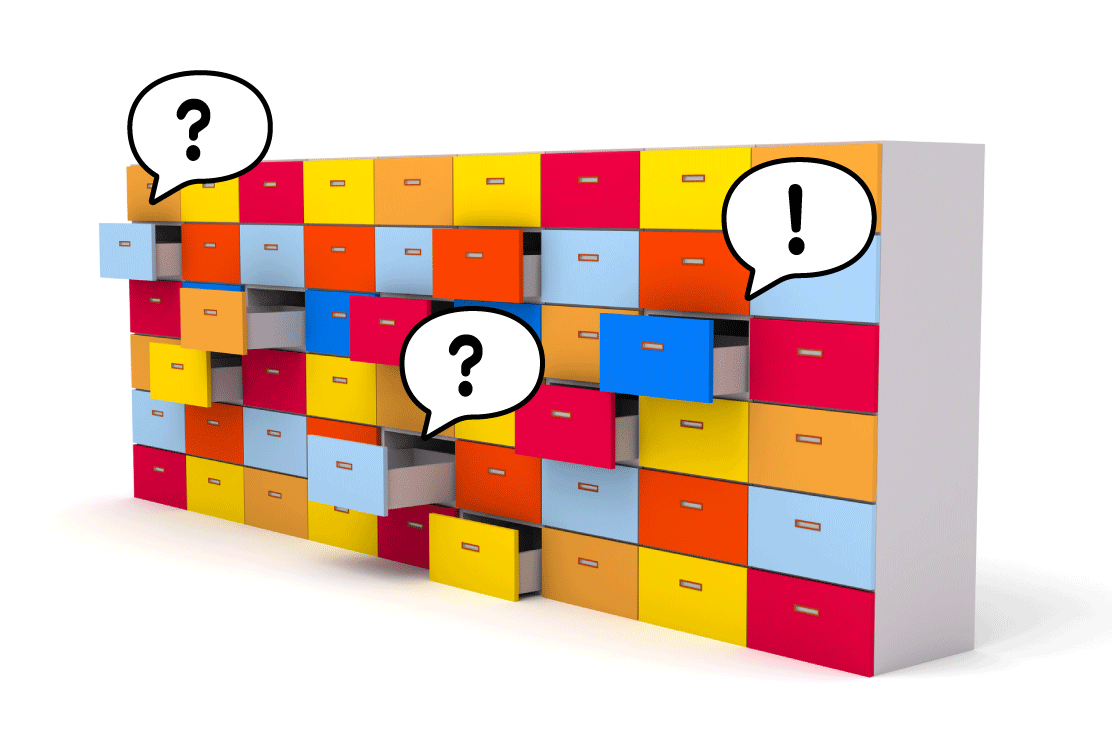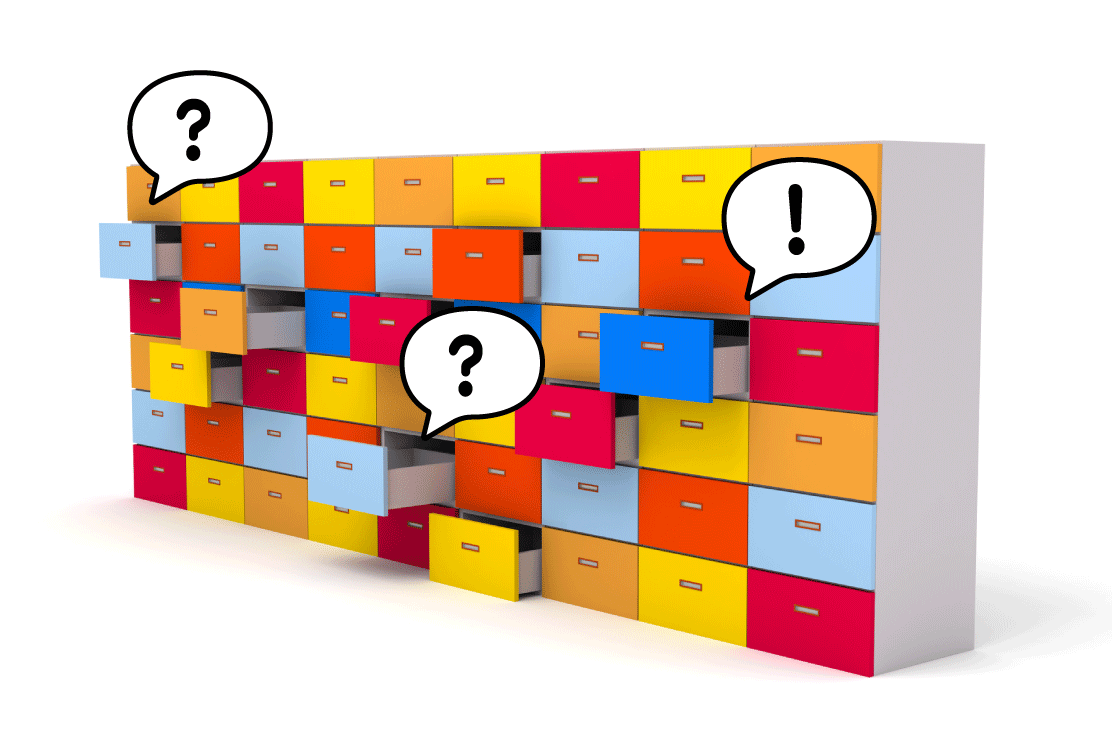コトバのひきだし ――ふさわしい日本語の選び方
第2回 いさめられても、叱らないで
関根健一
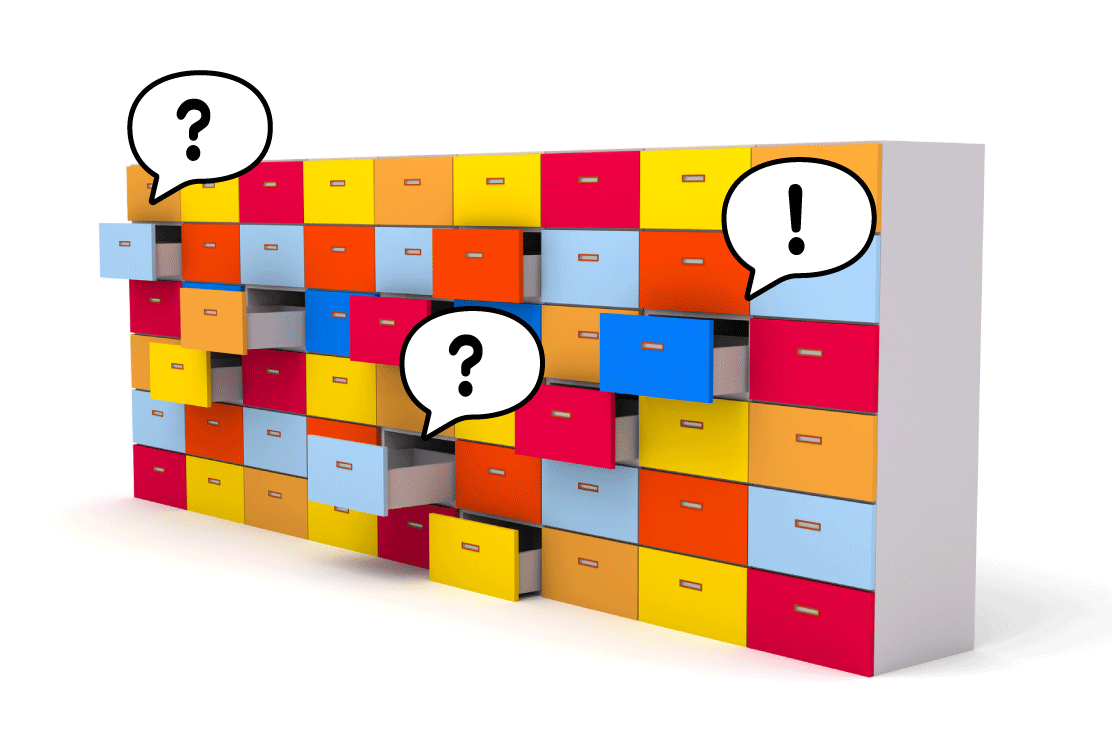
上司は部下をいさめてはいけません――最近の若者は傷つきやすいから、ではなく、「いさめる」は部下から上司へ向けられる行為だからです。
古くは「神のいさむる道」(伊勢物語)など、禁止を表す例もあり、この場合には「下から上へ」の方向性は含まれてはいません。ただ、指摘して改めさせる意味では、目上の人(上位者)の欠点・悪事を見かね、目下の人(下位者)が意を決して口を開くといったときに多く使われ、「諫」の字が当てられてきました。「家に諫(いさ)むる子あればその家必ず正し」(平家物語)は、父・平清盛の横暴な行動に苦悩する重盛を評した一節です。熟語「諫言(かんげん)」「諫死(かんし)」「諫止(かんし)」のイメージも相まって、「畏れ多いけれど勇気を出して」「不利益を被ることを恐れずに」といった熱い思いを感じるという人もいるのでは。最近のニュースでは「首相をいさめる議員がいないのは問題」「抗議の意味合いから辞任を決意した国防長官が大統領をいさめる」といった使用例がありました。
目下の人に向かって発するなら「叱る」です。「店長が働かない店員を~」「監督が練習しない選手を~」だったら、遠慮しないで叱りとばせばいいのです。「いやあ、このご時世、そうもいかないからなあ」――ごもっとも、「長」の肩書はあれど何の権威もない、部下の方が実力者、といった状況はありがちですね。「上から下をいさめる」用法の背景には、そんな実情があるのかもしれません。たいていの国語辞典は「多く(主に)目上の人に」としていて、目下にも用いることを許容する余地を残しています。とはいえ、あまり使用範囲を広げるのもいかがなものでしょうか。
*****
もっとも、「叱る」の威圧感も気になるところです。穏やかに注意するのであれば「たしなめる」ではどうですか。こんなことをしてはいけないよと教えておきたいときは「いましめる」がいいかもしれません。しでかしそうな失敗を予測して、前もって念を押しておくなら「釘を刺す」です。
となると、下位者から上位者に向かって言うときは、これらの表現はあまりふさわしくないということになります。「五歳児のチコちゃんに叱られちゃってさ」のような言い方が、何となくユーモラスに感じられるのは、本来の用法から少しずれているからなのでしょう。
*****
辞書を引いても、上下関係にかかわるかどうか、分かりにくいこともあります。ただ、「たしなめる」は「軽く叱る」と語釈を付けているものが多く、「叱る」の一種と解釈できます。『明鏡国語辞典 第二版』は「いましめる」について「生徒のいたずらを~」などの用例を挙げています。「乱暴な口を利いてたしなめられる」「他言するなと釘を刺す」(同)の用例からは、たしなめられ・釘を刺されているのは同輩以下であるのが、自然な情景として浮かんできませんか。
*****
「上から下へ」「下から上へ」の方向性が潜む言葉の存在は、かつて社会が厳格な上下関係に基づいて成り立っていたことの名残でしょうか。互いに配慮し合う平等な世の中になったのだから、そんな方向性など気にせず、自由に使えばいいようなものですが、長年にわたって染みついたニュアンスは簡単には落とせません。
文化庁の「国語に関する世論調査」(二〇一五年度)では、職場での挨拶として、年代によっては目上の人には「お疲れさま」、職階が下の人には「ご苦労さま」と使い分けている傾向もみられました。上か下か、気にする人は気にするのです。
年功序列制度が崩れ、働き方も多様化している今、上下関係が曖昧な組織も増えています。「意見を言う」「指摘する」など、上下に関係なく使える表現も工夫したいものです。
『国語教室』第110号(2019年4月)より
著者プロフィール

関根健一 (せきね けんいち)
日本新聞協会用語専門委員。元読売新聞東京本社編集委員。文化審議会国語分科会委員。大東文化大学非常勤講師。著書に『なぜなに日本語』(三省堂)、『ちびまる子ちゃんの似たもの漢字使い分け教室』『ちびまる子ちゃんの敬語教室』『ちびまる子ちゃんの春夏秋冬教室』(以上、集英社)、『上質な大人のための日本語』(PHP研究所)など。
一覧に戻る