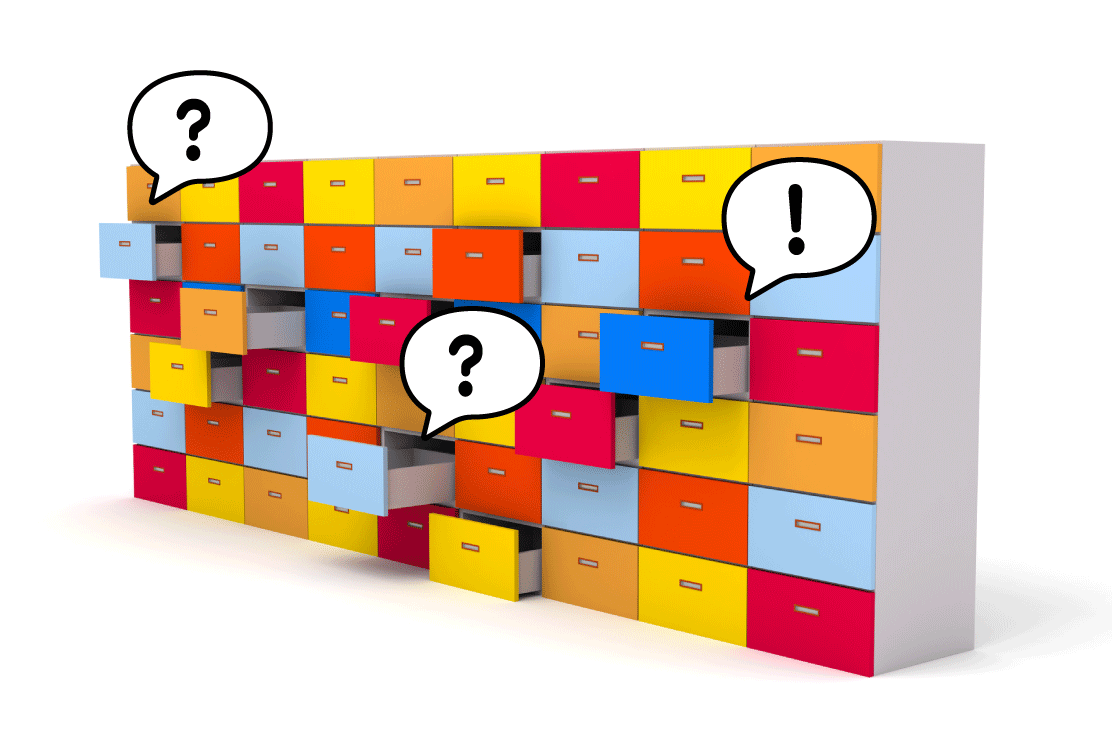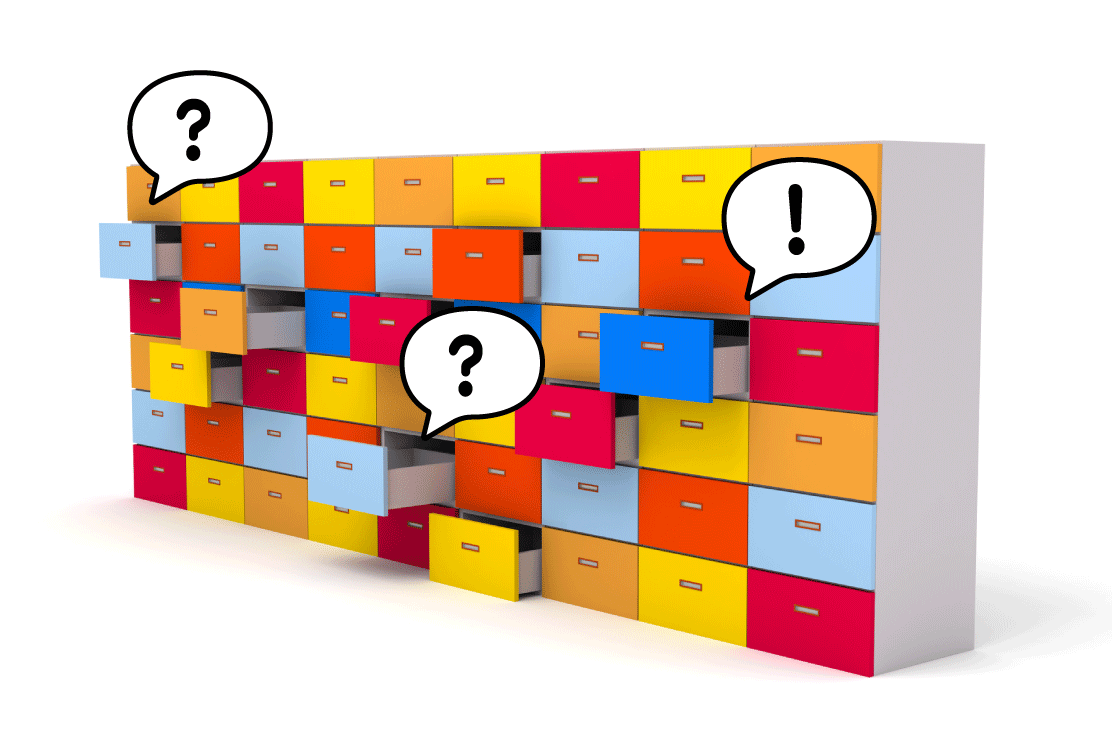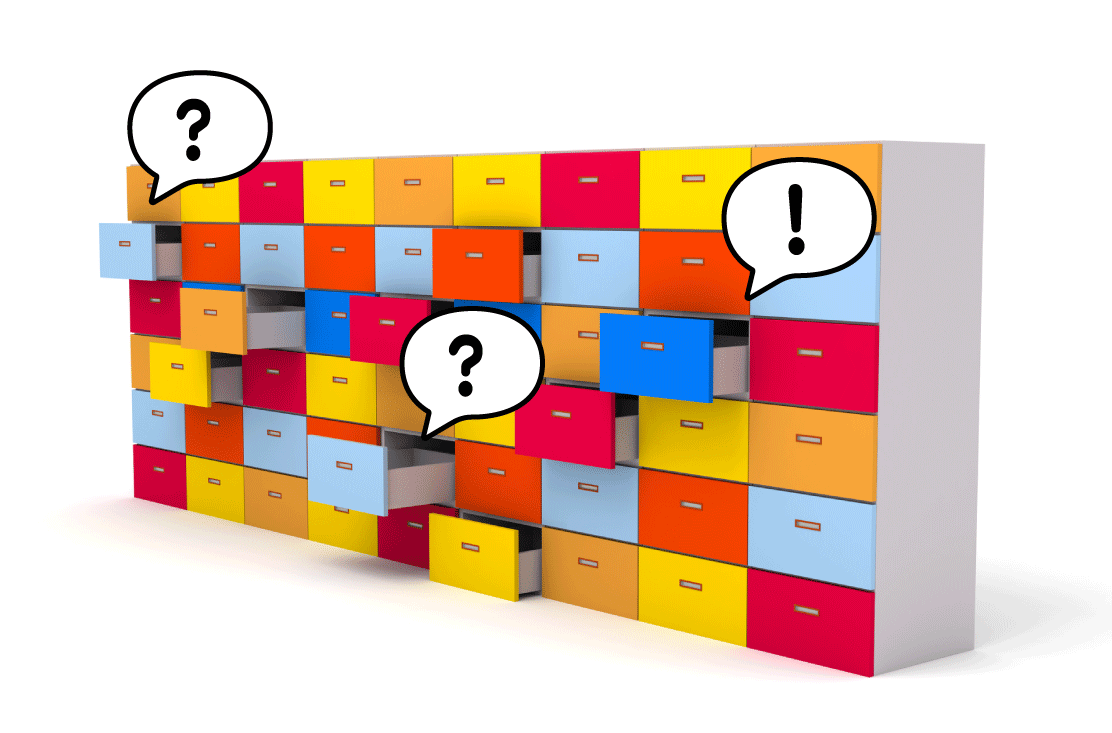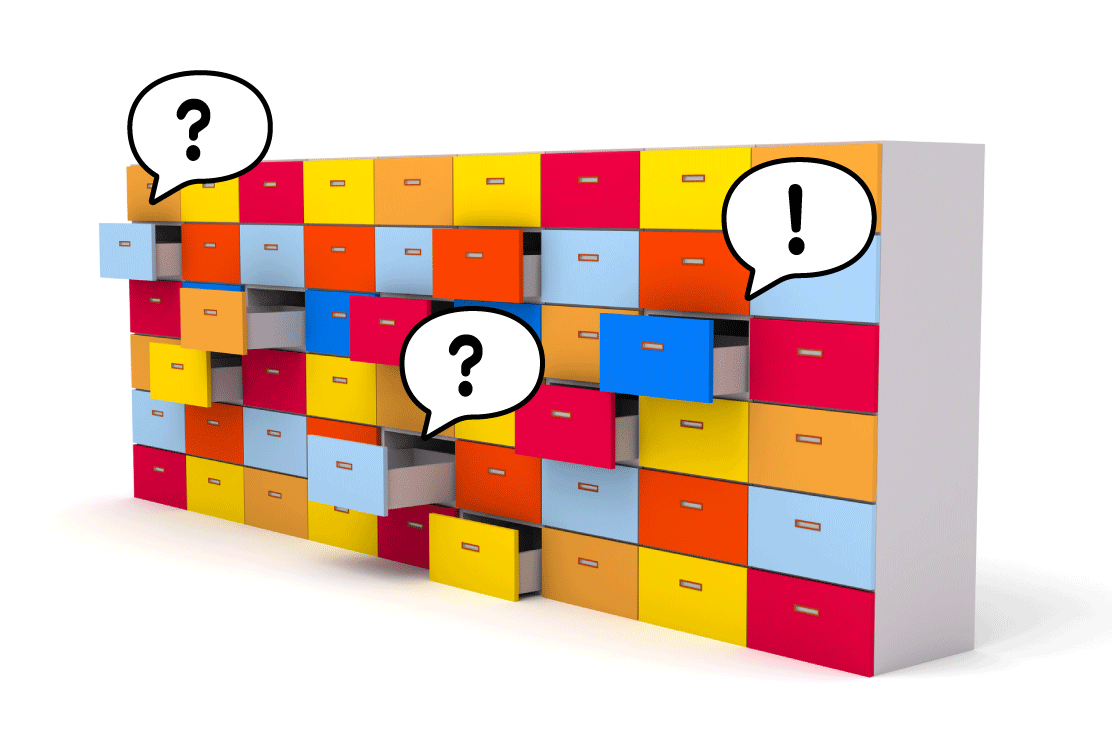コトバのひきだし ──ふさわしい日本語の選び方
第13回 「そうだ」の「だ」は要るそう……だ?
関根健一
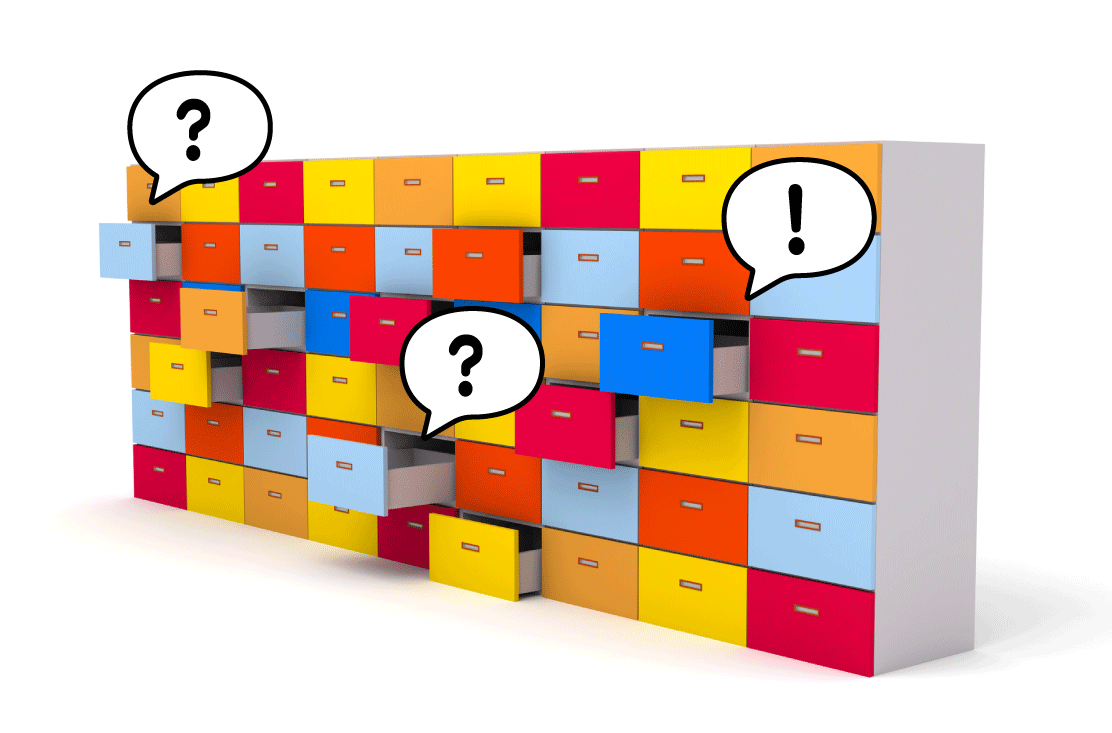
「平安時代を舞台にパリジェンヌがエイリアンと戦う青春ホラーヒューマンコメディー映画、絶賛公開中だってさ。おもしろいのかなあ」――と、友達から聞かれました。
人気イラストレーターが手掛けたポスターを見て波瀾万丈のストーリーやアクションシーンが期待できると思ったら、「おもしろそうだ」と答えるでしょう。雑誌の映画評で評論家が☆をたくさん付けていた情報を伝える場合は、「おもしろいそうだ」という答え方になります。
*****
同じ「そうだ」でも意味合いが違います。「おもしろそうだ」の「そうだ」は、自分で推測してそのように判断するときに使われる、様態の助動詞と呼ばれるものです。「おもしろいそうだ」の方は、誰かから伝え聞いた内容(伝聞)であることを表します。
様態の助動詞は「おもしろ(「おもしろい」の語幹)+そうだ」、伝聞の助動詞は「おもしろい(終止形)+そうだ」と、接続の形が違います。
雲が垂れ込めた空を見てつぶやくときは「降り(連用形)+そうだ(様態の助動詞)」、天気予報で聞いた情報を友人に伝えるなら「降る(終止形)+そうだ(伝聞の助動詞)」です。
*****
様態の「おもしろそうだ(です・である)」は、「おもしろそう」と、「だ・です・である」が省略されることがあります。特に話し言葉では、感情が高ぶったり、あわてたりしたときは、「おもしろそう!」「降りそう!」と思わず口に出てもおかしくありません。
それに対して、伝聞の「おもしろいそうだ」「降るそうだ」を、「おもしろいそう」「降るそう」と、「そう」で止めるのは中途半端で不自然な感じがあります。『明鏡国語辞典』も、伝聞の助動詞の場合、「『だ』や『です』を省略した形は標準的でない」と注記しています。
*****
ところが、最近では、テレビのナレーションなどで、伝聞なのに「だ(です・である)」を省いた形をよく耳にするようになりました。
「そうだ」の「だ」には、きっぱりと判断を示す働きがあります。濁音の響きが強いこともあって、柔らかく表現したい思いがあると、末尾は言いさすように「そう」と、終えたくなってしまうのかもしれません。
特に、「のだそうだ」と続く場合は、最後の「だ」が落ちやすいようです。「この店は100年前から続いているのだそう」「隣の町から毎日通い続けている常連客も多いのだそう」のような表現です。「のだ」に確認したり断定したりする気持ちがこもっているため、もう「だ」はこれで十分だ、といった気持ちが働くのでしょうか。
そもそも接続の形が異なり、「のだ」に続く「そうだ」は伝聞の意味になるのははっきりしていて、紛れることはないとはいえ、なんとなく落ち着かない感じがします。
*****
そうしなければならない、という意志や決意を示すとき「すぐに実行すべき」「優先してやるべき」などと表現することがあります。文末で言い切るとき(終止形)は「べし」なのですが、少々古めかしく、硬く感じられるせいか、文の末尾を「べき」で止めることが好まれるようです。ただ、「べき」は連体形ですから、「べきだ」(「べきである」「べきです」)と、続けるべきだ、と苦言を呈する人もいます。
「だ」の省略には、人に嫌われたくない、穏やかな関係を築きたいと思うあまり、きつく受け止められる言い方をできるだけ避けたいとする心理が潜んでいそう……だ、というのは考えすぎでしょうか。
『国語教室』第121号(2024年4月)より
著者プロフィール

関根健一 (せきね けんいち)
日本新聞協会用語専門委員。元読売新聞東京本社編集委員。大東文化大学非常勤講師。著書に『なぜなに日本語』『なぜなに日本語 もっと』(三省堂)、『ちびまる子ちゃんの敬語教室』(集英社)、『文章がフツーにうまくなる とっておきのことば術』『品格語辞典』『無礼語辞典』(大修館書店)など。『明鏡国語辞典 第三版』編集・執筆協力者。
一覧に戻る